
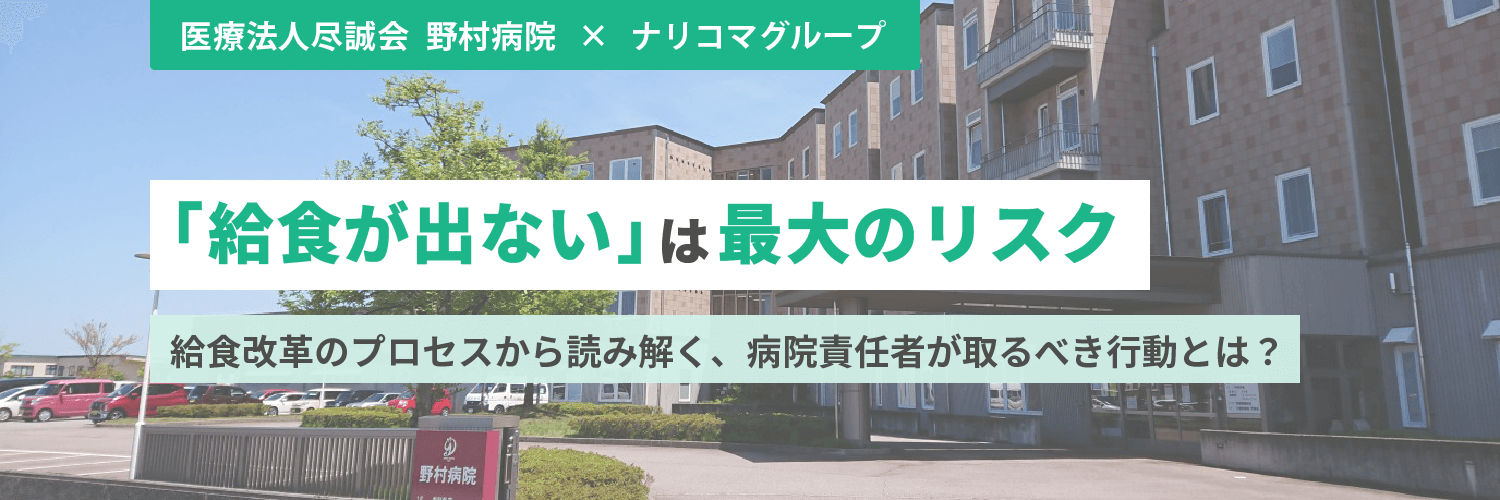
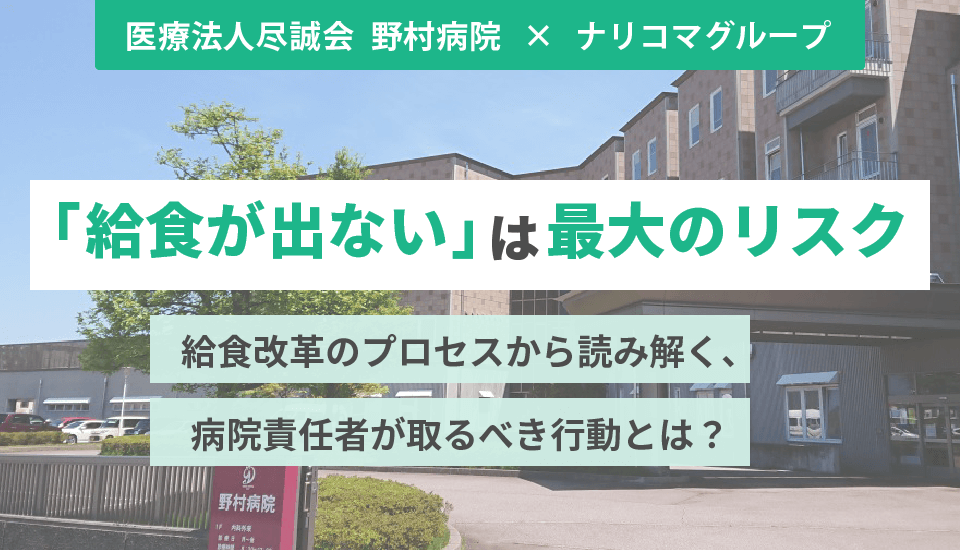
「求人を出しても本当に人が集まらない…」そんなお話を聞く機会が増えてきました。労働人口の減少や物価・人件費の高騰など、社会情勢の影響で「給食は手作りが当たり前」という時代が揺らぎ始めています。
「今は何とかなっているからまだ大丈夫」「委託会社に任せているから安心」と思っていても、いつその問題が降り掛かるかわからない状況です。病院にとって「給食が出ない」は致命的なこと。給食の提供を止めないためには、どのような行動を取ればいいのでしょうか?
今回、インタビューにご協力いただいたのは富山県の医療法人尽誠会 野村病院に勤務する経営企画室室長の桑原さま。他業種から野村病院に入職し、わずか4ヶ月で給食部門の改革に直面されました。
「給食のリスクヘッジはまず最初に取り組むべき」と語る桑原さま。5年以上も人が集まらない状況だった給食部門の課題をどのように解決したのか。
その時の状況やプロセスについて、桑原さまに直接お伺いしてきました。早期に課題に気づき、先々を見据えて給食改革をされた視点にはたくさんのヒントが詰まっていました。

医療法人尽誠会 野村病院
経営企画室室長 桑原さま
私が当院に入職して間もないころ、栄養部から相談がありました。「スタッフが病気で休んだので採用してください」と…。詳しく話を聞いてみるとすでに5年前〜10年前から人が集まらない状況が続いていたんです。特に過去数年間、募集をかけても応募が「ゼロ」という状況。
これまでと同じように募集を続けても、この問題は解決しない。採用ができないとなれば、今いる人数でできる方法を考えるしかないと思いました。
ちょうどそのころ、理事長から「クックチル」という言葉を耳にしていました。医療業界に来たばかりで当時はあまりピンときていませんでしたが、栄養部の人材問題を解決するヒントにならないか、検討することになりました。

業者を選定するにあたって「どこが地域的に強いのか」「機動力はどうか」「サプライチェーンがしっかりしてるか」みたいなことは、対外的な情報だけではわかりませんでした。どの会社も自分のところが最高と言いますからね。
だから、当時お付き合いのあった医療業界全般に目線を持っている方に、3社ほど紹介していただきました。
その中で、医療福祉に特化していて、確実に運営できる実績と周囲の施設が導入していたことからナリコマさんに決めました。実は気持ち即決でした。「継続」していくことに最大の不安を感じていたので、周辺施設が導入していたことによる流通に対する安心感、最低限、他施設と同等のクオリティが担保できるということは、ある意味リスクヘッジだと思っていたからです。
導入を進めるにあたって、事前に現場アンケートを取りました。現状のやるべきことを洗い出して「本当にやっていいのか?」という裏付けが欲しかったので。そこから正式にクックチル導入に向けたプロジェクトがスタートしました。あとは、現場が厨房の未来をどう考えているか、それが論点でした。
実はそこから、ナリコマさんの導入を決めたのが2週間だったんです。法人としての方針をある程度決めてしまう事がポイントで、「これについて建設的な意見を言ってほしい」という考え方で進めることです。そうでないとなかなか話が進まないですからね。
やはり不安の声はありましたね。普段から現場で患者さまに関わっているスタッフは、とても優しい方が多いんですよね。だからこそ、患者さまのためにも今まで通り原材料から作る方が「おいしく、温かみがあっていいんじゃないだろうか?」という漠然とした気持ちがあったと思います。
でも、そもそも今の体制で人員不足で「作る」こと自体ができなくなると、お食事も提供できなくなる。理想だけでは前に進まない、優しさはわかるけど、5年以上も人の悩みを持ち続けていたのなら発想を変えるしかないですよね。そこを現場に理解してもらうのに一番時間がかかりました。
現場の方は経験が体に染みついているので、ある意味自分の業務を可視化することが苦手な方が多いんですよね。だからこそ、ひとつひとつの工程をヒアリングしながら分解していきました。
「ものを切る時間は?刻む時間は?」「本当に刻まないといけないの?」「包丁を使うのをやめたらどうなる?」などを質問しながら整理するイメージですね。
調理するのに包丁を使わない、油を使わないなんて非常識すぎてなかなかそこから離れられないんですよね、それが前提になっているので。一度全部捨てて目の前で話を具体化させていくんです。そういうやり取りの中で現場にもわかってもらい、こちらも厨房のことを知っていくという感じですね。

そもそも私自身が厨房のことをあまり知らなかったので、実際に厨房のなかは結構見ました。
見る前は食洗器に入れてボタンを押すだけで洗浄ができるんじゃないか?というイメージを持っていました。でも実際は、食洗器に入れる前につけおきの時間が必要だったり、前洗いが必要だったりと、やはり現場を見ないとわからないことも多いじゃないですか。
そういうひとつひとつの工程がイメージの中に入ってくるんですよね。ここにこんな工程があるのかと。そういうことも含めて理解するために現場は結構見に行きました。
事務方は厨房のことを知らない人が多いと思いますよ。給食の現場を変えるというのは、やったこともないですし実務的なイメージも沸かないと思います。自分でゼロから知識を積み上げるのも難しい。そういう意味でいうとナリコマさんのコンサルには本当に助けられました。本当に全部お任せしました。
例えば、「栄養部の方がこんなことを言っておられます」という報告をナリコマさんの担当者から私が聞く。また、私(現場を知らない人)が言わなくてはならない事を伝えづらいことをナリコマさんから言ってもらうとか。本当にすごい通訳的な役割をしていただいたと思います。
導入前から導入後まで、全部で半年くらいかけてハンズオンでやっていただきました。本当に細かいところはノータッチでした。

ナリコマさんを導入したことで、当初「人が足りない」と言っていた栄養部から、栄養管理の前向きな言葉が出るようになったのは本当に大きいです。人の採用に気を使うのは管理栄養士の仕事じゃないですからね。そんな悩みをなくして本来の業務に注力できる環境をつくることができた、それが最大のメリットだと思います。
運営できているのは大前提で、「どうやって利用者の満足度を上げるのか」など前向きなことに時間を使うことは経営の観点でもとても重要なことです。
少ない人数で業務が回せるようになったのを見て、現場が十分な人員体制になっていることを自覚していくんです。
厨房には大ベテランのスタッフが数名いました。こういう業界の方は特に思うんですが、自分がいなかったら運営が成り立たないという使命感で仕事をされているんですよね。
ですが、クックチルを導入したことで、業務の内容や働く時間に大きな変化ができたんです。数多くあった工程が無くなった訳ですから当然ですよね。当院からお願いしてパートにきていただいた職員に、無理を言う必要がなくなる…お互いに肩の荷がおりたという感じでしょうか。
安定して厨房が回る様子を見て「この春でリタイアさせてもらっていいでしょうか?」という申し出もありました。全く違う運営となる訳で、いきなりガラッと人員を減らした体制に変えるつもりはありませんでした。しかしながらこういうことを通じて4ヶ月〜6ヶ月くらいかけて自然と適正な人数に落ち着いていきました。

かなり大きいです。私の考えとしては、赤字になろうと何になろうと、提供されるべきものが提供できないということは絶対避けたい。だからこそ、給食の安定化は一刻も早く手がけるべきだと思います。
特に厨房はひとり欠けても運営できない。厨房はチームでないと運営できないんです。いざ成り立たなくなったらそれを復元するためにものすごく時間がかかるその時間が一番大きなリスクだと考えています。なので、この病院にきて一番はじめの最重要任務が給食改革です。
判断が遅れるほど状況がよくなることはありません。今は大丈夫でも、朝4時半、大雪の時にも出勤しないといけない。こんな負担が大きい職種は、この先人が集まらないときが必ず来ると思います。待てば待つほど悪化するので、余力のあるうちに検討することをおすすめします。
現場の改革は給食部門だけでなく、あらゆるシーンで直面する機会があると思います。課題を特定し早期に動き、リスクヘッジをする。桑原さまのご決断力、現場とのコミュニケーションの取り方にはとても学びがありました。
我々ナリコマが提供しているサービスは、単なる現場の効率化だけではなく、管理栄養士の方々が本来の栄養管理業務に注力できる環境をつくることだと考えています。そうすることで、給食管理や栄養管理を通じて医療の質を高めるということにつながる。そういう思いでこれからも邁進してまいります。

ナリコマグループ
デジタルマーケティング室
山岡タケル

急性期病院
京都九条病院 さま
委託運営からナリコマのクックチルに切り替え、衛生管理を強化。パック済み食材で汚染リスクを減らし、多彩な献立も患者さまに好評です。調理作業は19名から11名に減少し、1日約40時間を削減。手厚いサポートで安定供給が可能となり、安心して食事提供ができています。

精神科病院
弓削病院 さま
病院の建て替えを機に、出産・育児後も働きやすい職場づくりとしてナリコマのクックチルを導入。アドバイザーの支援でシフトを整備し、5時半出勤が7時に短縮。未経験者の技術習得も3年から半年に。安定した厨房運営が可能となり、仕事に興味を持つ人も増えました。

慢性期病院
宝塚磯病院 さま
喫食数が減少しても、委託管理費は高額なままだったことから見直しを検討。味に対する不安もありましたが、試食したところ職員からも好評だったため導入を決断しました。人件費だけでなく、水光熱費の大幅削減にもつながっています。嚥下食の物性が安定しているのも魅力です。