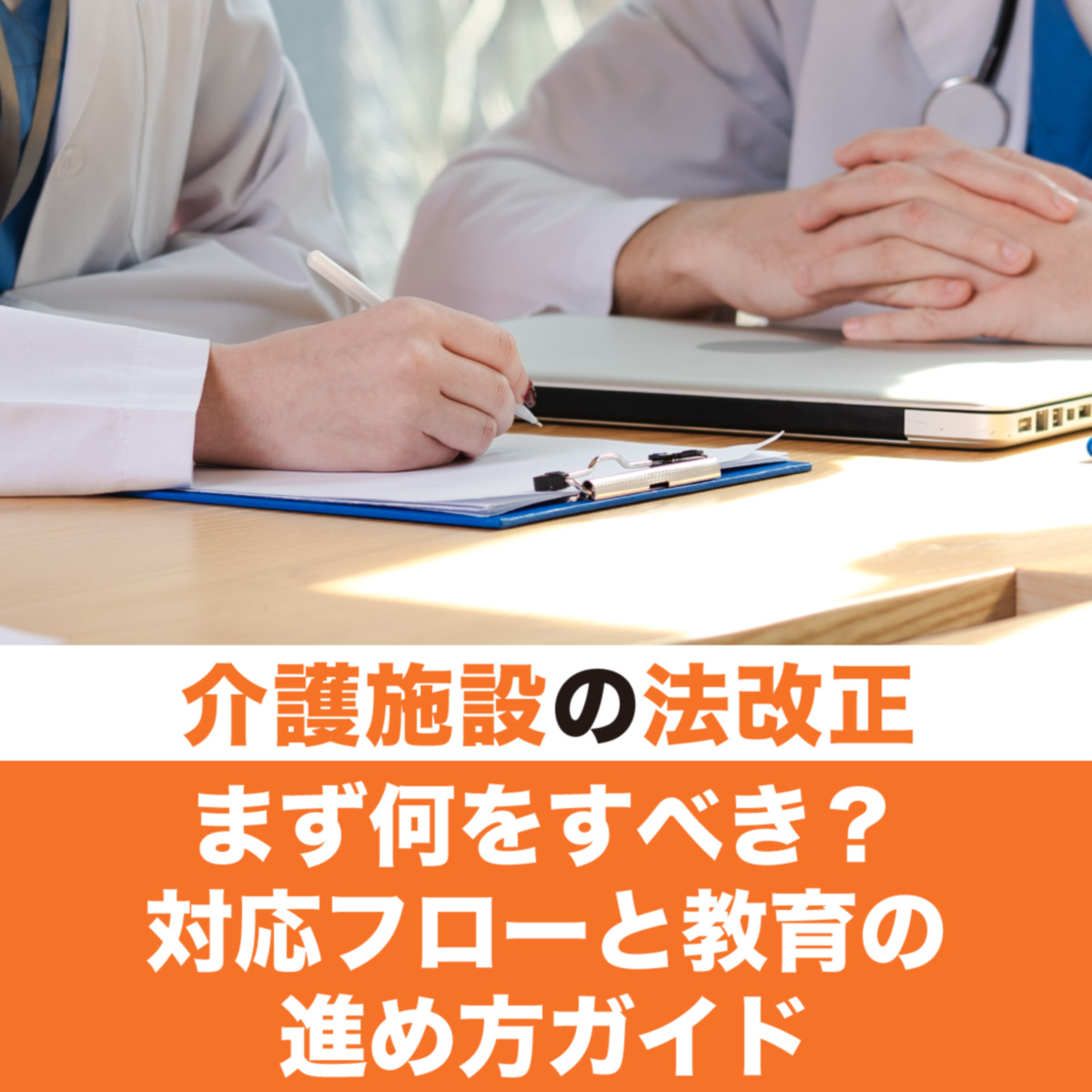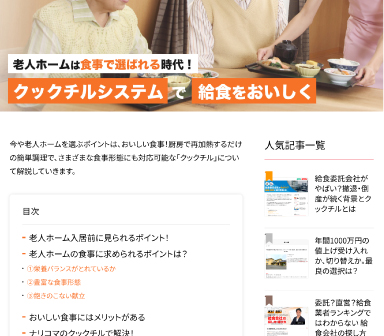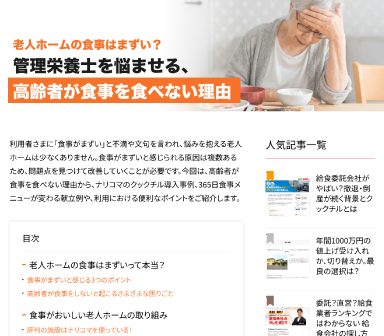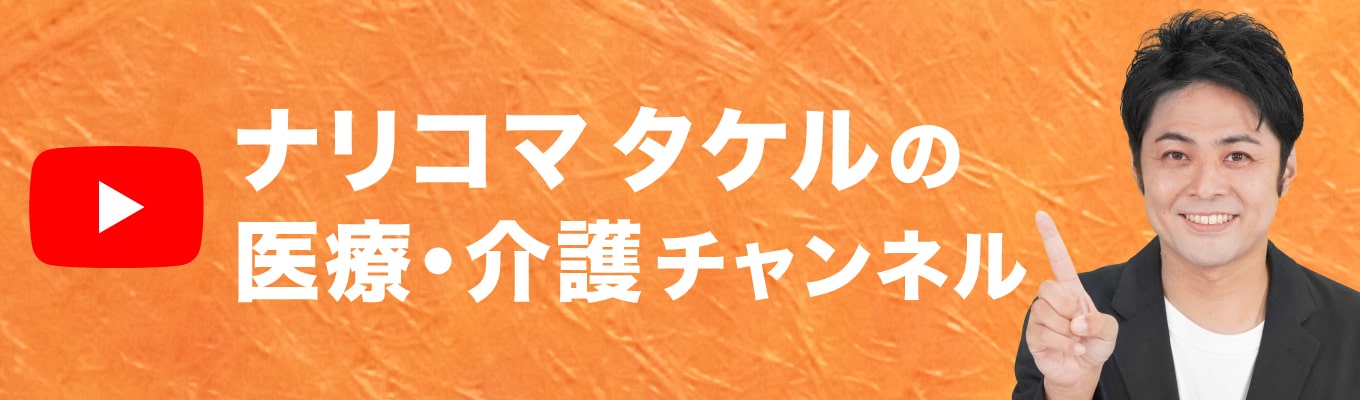介護施設の運営において、法改正への対応は避けては通れません。近年は高齢化社会の進行や働き方改革の影響により、介護保険制度や労働関連法の改正が相次いでいます。現場では「まず何から取り組めばいいのか分からない…」という声も少なくありません。
今回は、介護施設に関係する主な法改正のポイントをわかりやすく整理し、法改正の対応になにを優先したらいいのかや、対応をスムーズに進めるためのフロー、職員への伝え方をご紹介します。
目次
まず押さえたい!介護施設に関わる主な法改正のポイント
2025年には団塊の世代が後期高齢者になり、介護を必要とする人の数やニーズがますます増える日本。それによってさまざまな社会問題が懸念される「介護の2025年問題」に立ち向かうため、介護業界に関わる法律も見直しや改正が重ねられています。介護施設の運営や職員の働き方に大きく関わってくる、主な法改正についてまとめました。

2024年度以降の注目すべき改正事項
2024年度から施行・改定される法制度の中には、介護施設の運営や職員の働き方に大きな影響を与える内容が多く含まれています。ここでは、特に注目すべき2つの改正についてご紹介します。
1.育児・介護休業法等の改正
働く人がライフステージに合わせて仕事と家庭が両立できるよう、柔軟に働き続けられることを目的に、育児・介護休業法が改正されました。特に介護現場では、職員の離職を防ぎ、働き続けやすい環境づくりにもつながる制度変更となりました。
2025年4月1日に施行された改正内容は下記の通りです。
①子の看護休暇の見直し
これまでは病気の看病などが対象でしたが、予防接種や保育園・学校の行事の付き添いなどでも使えるようになりました。また、休暇を取れる子どもの年齢の範囲も広がります。
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
今までは「3歳未満の子ども」がいる職員だけが残業を免除されていましたが、今後は「小学校に入る前の子ども」がいる職員も対象になりました。
③テレワークの努力義務(育児・介護)
3歳未満の子を育てている職員や、家族を介護している職員について、自宅などで働けるようにする努力義務化されました。現場業務が中心の介護施設では難しい面もありますが、事務職など一部では検討が必要です。
④育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
これまでは、常時1,000人以上の職員がいる会社だけが対象でしたが、今後は300人以上の職員がいる施設や法人も、公表が義務になります。
⑤行動計画策定時の数値目標義務化
会社や施設が作る「行動計画」に、育休の取得状況や今後の目標などを示すことが義務となります。
⑥介護両立支援に関する義務の強化
以下の3点が新たに義務となりました。
- 介護に直面した職員への個別の周知・意向確認
- 介護制度に関する早期の情報提供
- 介護と仕事を両立しやすい雇用環境の整備
特に、職員が介護に直面したときの早期対応と柔軟な支援体制が求められるため、マニュアル整備や管理者向けの教育も重要です。
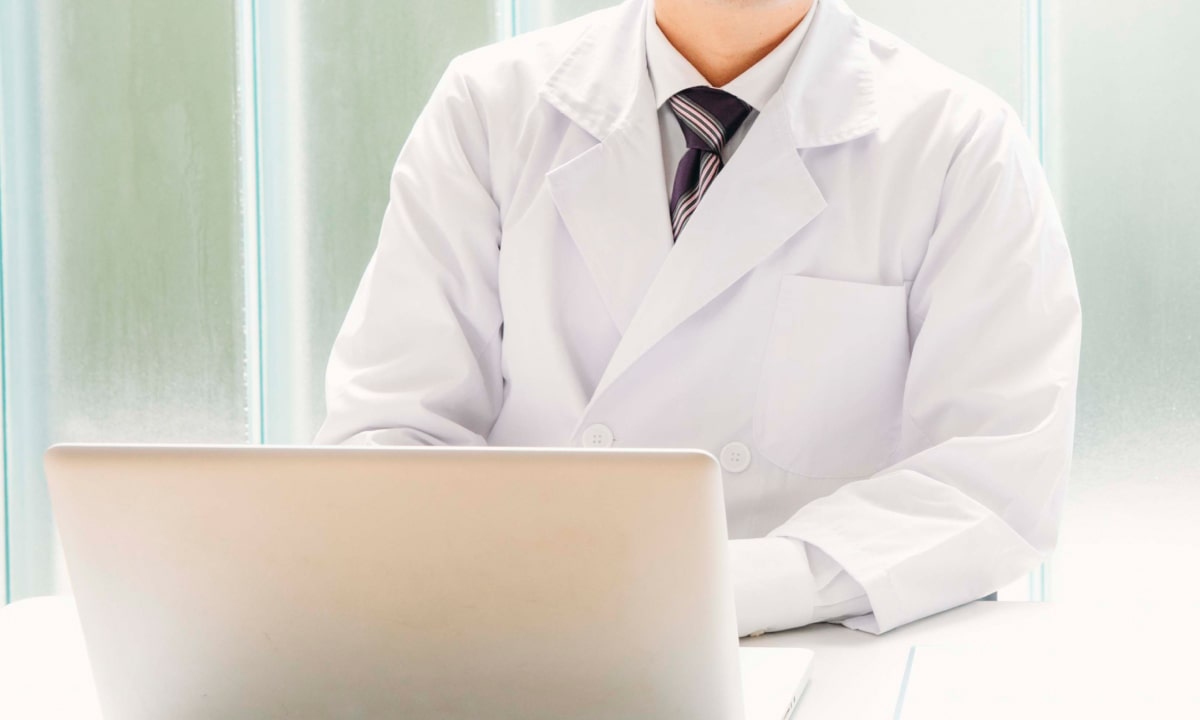
⑦介護休暇に関する労使協定の見直し
介護休暇について、職場での取り決めを見直す必要がある場合があります。あらためて施設内のルールを確認しておきましょう。
2025年10月1日に施行される改正内容は下記の通りとなり、働き方の柔軟性を高めるための施策がさらに追加されます。
⑧ 柔軟な働き方の実現に向けた措置の義務化
時差出勤、短時間勤務、テレワークの導入など、職員の生活に合わせた働き方ができるようにする制度を、職場として検討・整備していく必要があります。
⑨ 妊娠・出産の申し出への配慮義務
妊娠・出産を申し出た職員に対して、仕事と育児の両立ができるよう、今後の働き方について確認・配慮を行うことが必要です。妊娠・出産を理由とした退職を防ぐ体制づくりが重要になってきます。また、3歳になる前の子どもを育てる職員にも、本人の意向を確認して働きやすい環境を整備します。
2.介護保険制度改定
「介護保険制度」は、介護や支援が必要な高齢者を社会全体で支えるための仕組みで、要介護・要支援の認定を受けた方が介護サービスを利用できる制度です。2000年からおおよそ3年ごとに見直しが行われており、2024年(令和6年)にも改定が行われました。
2024年の改定では、高齢化の進行や人手不足などの課題に対応するため、「地域での支え合い」や「介護の質の向上」「持続可能な制度づくり」に重点が置かれるようになりました。

① 地域包括ケアシステムの深化・推進
自宅や地域で安心して暮らし続けられるよう、介護・医療・生活支援などが地域で連携してサポートする体制が重視され、「地域包括ケアシステム」の強化が図られました。
② 自立支援・重度化防止への取り組み強化
介護を必要とする方が、元気で自立した生活を取り戻せるよう、リハビリや口腔ケア、栄養管理などの取り組みが重視されています。
③ 働きやすい職場環境づくりの促進
介護職員の確保や定着を図るために、仕事の負担を減らす工夫や、職場環境の見直しが強く求められています。今回の改定では、ICT導入や業務効率化の推進、処遇改善加算の仕組みの見直しなどが強化されました。
④ 制度の持続可能性の確保
今後の高齢化の進展を見据え、制度そのものの安定性も重視されました。
介護を必要とする人が増える中で、限られた人材で制度を続けていくために、制度の再構築が進められています。
これらの改定は「働き方改革」の流れとも大きくつながっています。介護現場でも無理なく勤務ができる体制や、休みを取りやすくする工夫が必要です。短時間勤務や希望に応じたシフトを導入したり、ICTの活用による業務の効率化を行ったりするなど、職員が柔軟に働けるような対応が求められています。
対応の第一歩!優先順位をどうつけるか
複数の法改正が施行されると、何から手をつければよいのか分からなくなってしまうこともあるでしょう。限られた職員や時間の中で、効率よく対応を進めていくためにも、まずは対応すべき内容を「優先度」で分類することからはじめてみましょう。

未対応によって法的罰則や行政指導のあるものは最優先
法改正の内容によっては、未対応のままでいると法的なリスクや行政指導を受ける可能性があるものも。まずは法的罰則や行政指導のリスクがあるものを最優先に行いましょう。
優先対応が必要な例として、たとえば育児・介護休業法の場合、300人を超える事業所においては、育児休業の取得状況や、労働時間の状況の公表が義務化となりました。未対応の場合には報告義務違反とされる可能性もあるため、早めに体制を整えなくてはなりません。
また、家族の介護を担う職員に対しては、介護離職防止のための個別の周知・意向確認が義務となるため、両立支援制度についての対応漏れがないように努める必要があります。
現場目線で優先順位を整理する
次に「日々の現場業務に影響を与えるもの」を優先的に考えましょう。職員の安全や利用者の生活に関わる内容も、万が一の事故やトラブルを防ぐためには大切なことです。たとえば「BCP(業務継続計画)の整備義務」においては、災害や緊急時の対応を想定したマニュアルの整備や訓練が挙げられます。災害大国である日本だからこそ、職員や利用者の命を守るためにBCP対策は絶対に欠かせないもの。すぐに対応する必要があります。
さらに、介護報酬改定については「処遇改善加算」のルールが変わり、申請のための記録方法や人員配置の見直しが必要になります。放置すると、加算を受け取れなくなるリスクもあるため、このような場合も優先的に対応しなくてはなりません。
また、努力義務や制度準備にとどまっているものについては、計画的に備えればよいものとして、中長期でスケジュールを組んで準備をしたり、段階的に導入を検討しましょう。
たとえば、テレワーク対応や短時間勤務など、制度上は努力義務であっても、導入には就業規則の見直しや人員体制の再構築が必要となります。時間をかけつつ、段階的に進める計画を立てましょう。
施設内での対応フローを明確にする
複数の法改正に対応する場合に、施設全体でスムーズに動くためには、「誰が」「いつ」「何をするのか」といった対応フローをはっきりさせておきましょう。

法改正の対応フロー
1.改正内容の確認
厚生労働省や自治体などから発表される資料などから、どの法律がどのように変わるのかを確認しておきます。
2.関連業務の洗い出し
法改正によっての影響が、どんな業務や手続きにあるかを洗い出します。介護報酬の見直しであれば、記録の取り方や加算の算定方法、介護記録ソフトの設定などに対応しなければなりません。また、育児・介護休業法の改正であれば、「どの職員が対象になるのか」がわかるように対応する必要があります。
3.改定点に応じたマニュアル・ルール改訂
法改正によって影響を受ける業務が特定できたら、変更が必要なマニュアルや運用ルールを改定します。
4.職員説明と運用開始
マニュアル等が整ったら、職員への説明や研修を行いましょう。変更があると、最初はどうしても現場の負担になったり、混乱してしまいがちです。職員が納得して業務にあたれるように「なぜ変更が必要なのか」「どこを変更したか」をしっかり伝えます。
職員教育とチェックリストで対応の定着を図る
法改正については、職員教育で変更点や対応について周知を図ります。研修の際は、法改正による変更点が現場の業務にどう影響するかを意識した内容にすると、現場職員の理解度も高まります。
研修スタイルの例として
- Eラーニング:忙しい職員でも自分のペースで学べる。改正内容や制度の基本を効率よくインプットできる。
- OJT(現場指導):実務と結びつけながら、現場で必要な対応を身につける。
- 集合研修:チーム全体で課題を共有しながら、共通認識を持つ機会に。
内部研修の場合には、担当者が日常業務と兼務しているケースが多いため、研修準備の負担が大きくなってしまうことも。内容が偏ったり、研修の質にバラつきが出ることもあるため、外部研修を行うのもひとつの手です。外部講師による説明や、専門機関の教材を活用することで、より確かな知識の習得が期待できます。

チェックリストの活用で改正にも漏れなく対応
制度改正の対応は、関係する業務が多岐にわたります。漏れなく確実に対応するには、チェックリストなどで「見える化」することが大切です。
たとえば、以下のような項目を整理したリストを作成しておくと便利です。
- 対応が必要な改正項目
- 担当者
- 対応期限
- 実施状況(完了・未完了・確認中など)
チェック項目を具体化すると施設全体での進捗管理もしやすくなります。
法改正対応は「見える化」と「共有化」が大切
介護施設の法改正。一体どこから手をつけたらいいのか、混乱してしまうこともあるでしょう。複数の改正がある中、スムーズに対処するには、まずは対応すべき内容を整理して優先順位をはっきりさせることが第一です。必要な業務や手順をマニュアルやチェックリストで見える化し、「誰が」「いつ」「何をするのか」を全員で共有しましょう。職員一人ひとりが理解・納得できるような教育や情報共有の機会を設けることも、法改正対応の定着には欠かせません。

法改正は対応したらそれで終わりではありません。業務の中にしっかり根づかせ、これからの介護現場をより良くしていくことがゴールとなります。法改正に対して現場全体で取り組むことで、よりよい介護サービスの提供にもつながっていくでしょう。
その場でダウンロードできる
サービス資料
まずはどんなサービスかを知りたい!というあなたに、
その場でダウンロードできるナリコマの資料セットをご用意しています。
まずは情報収集したい方は是非ご活用ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。