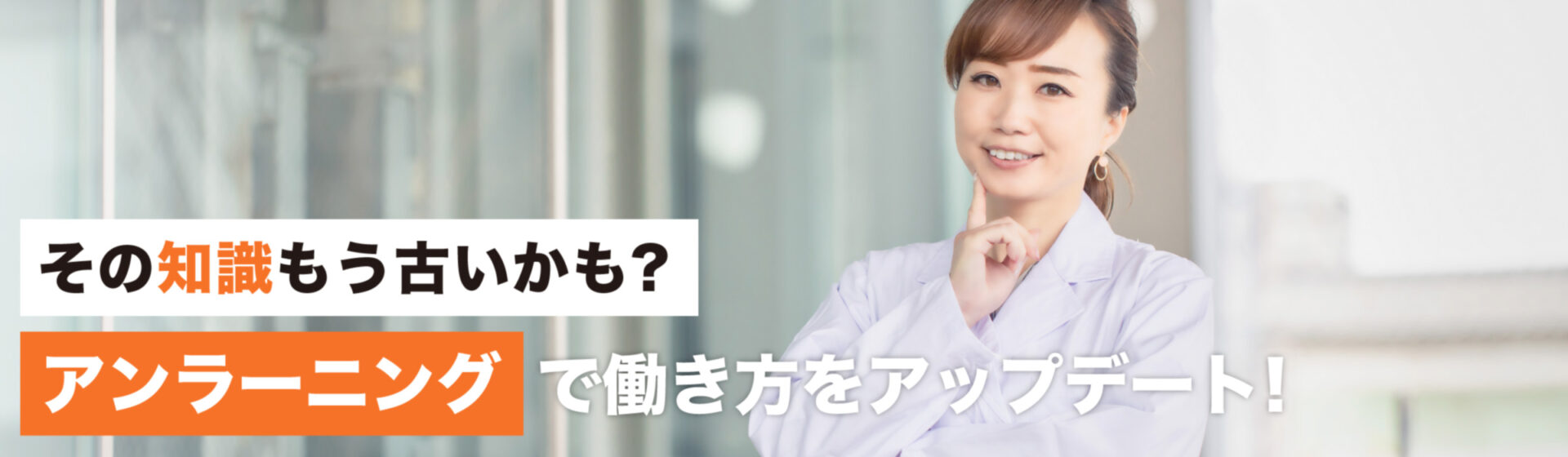今の働き方にモヤモヤしているなら、まずは「忘れること」からはじめてみませんか?
日々の業務に追われながら、「このやり方でいいのか?」「もっと柔軟に働けないのか?」などと感じたことはありませんか?これまで培ってきた経験や知識は、確かにあなたの武器ですが、それが時として変化を受け入れにくくする足枷になることもあります。変化の激しい今の時代に求められるのは、ただのスキルアップではなく、「一度手放す」という選択。そこで注目されているのが「アンラーニング」という考え方です。
今回はアンラーニングの意味や必要性をわかりやすく解説し、リスキリングとの違いやビジネススキルの向上に役立つ実践事例も紹介していきます。働き方やキャリアのあり方を見直したいと感じているあなたに、きっと役立つヒントが見つかるはずです。
アンラーニングってなに?その意味と必要性
働き方や価値観が大きく変わっている今、あらためて見直したいのが「これまでの当たり前」です。急速に変化する社会やビジネス環境に対応するため、今注目されている「アンラーニング(unlearning)」。アンラーニングとは、これまでの成功体験や慣習などを見直し、より柔軟な働き方や価値観へと自分をアップデートしていくための第一歩です。

アンラーニングとは
アンラーニングは、日本語で「学習棄却」や「学びほぐし」と訳されます。聞き慣れない言葉かもしれませんが、意味はとてもシンプルです。これまでの知識やスキルの中から、今の時代には合わなくなってしまったものを見直し、必要に応じて手放していくことを意味しています。
「手放す」と聞くと、これまでのすべてを忘れる必要がある気がしてしまいますが、そうではありません。大切なのは、過去のやり方に縛られすぎず「新しい考え方やスキルを柔軟に取り入れる」という姿勢なのです。「これは今の仕事には合わないかも」「もっと良い方法があるかも」と気づけることが、アンラーニングの第一歩になります。つまり、アンラーニングは「知識を完全に捨てる」というよりかは、必要なときに取り出せるように「一旦引き出しにしまう」ようなイメージです。状況に応じて、古い知識と新しい知識をうまく使い分けるのがアンラーニングなのです。
なぜ今アンラーニングが必要なのか
近年、ビジネスを取り巻く環境は急激に変化しています。デジタル技術の進化や働き方改革などで、これまで当たり前だった仕事の進め方がどんどん変化し、これまで通用していた仕事の進め方も見直しを迫られています。
かつては「正解」とされていたやり方が、今では時代遅れになることも珍しくありません。
こういった状況の中で求められるのが、「新しい知識や視点を柔軟に受け入れ、必要に応じて過去のやり方を見直す力」、アンラーニングの姿勢なのです。
アンラーニングは、個人だけでなく組織にとっても重要な意味を持っており、アンラーニングを積極的に進めることで、下記のような変化が期待できます。
- 新しいことに挑戦しやすくなり、成長につながる
- 仕事の進め方がスムーズになり、ムダが減る
- 変化にも前向きに対応できるチームや職場になる
変化の激しい時代だからこそ、過去の常識にとらわれず、新たなチャレンジを可能にするアンラーニングの姿勢が求められているのです。
アンラーニングとリスキリングの違いとは?
「アンラーニング」と「リスキリング」は、どちらも働き方やビジネスのあり方が大きく変わりつつある今、注目を集めている考え方です。自分のスキルや働き方をアップデートさせるためには、似ているようで異なるこの二つの考え方を正しく理解することが大変重要です。
リスキリング=新しい知識やスキルを身につけること
リスキリングとは「これからの仕事や環境の変化に適応するために、新しいスキルを身につけること」を指します。単なる学び直しではなく、ITスキルの習得など、「これからの仕事に必要とされる力」を学び直すイメージです。

経済産業省はリスキリングの定義として「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること(リスキリングとは DX時代の人材戦略と世界の潮流|経済産業省)」としています。
つまりリスキリングとは、「未来に向けた学び」を指しているのです。
アンラーニング=手放すことで広がる可能性
アンラーニングは、「アンラーニングってなに?その意味と必要性」でもご紹介した通り、これまでの経験や知識をいったん見直し、不要なものを手放すことを指します。過去には正解だった考え方ややり方も、今のビジネス環境では通用しないことがあります。知識をゼロにするわけではなく「これまでの当たり前」を見直して、考え方を柔軟に変えていくのがアンラーニングです。
アンラーニングとリスキリングはセットでより効果的に
スキルアップのためには「新しい知識を学べばいい」と考えてしまいがちですが、学んだスキルを存分に活かすためにはアンラーニングが必要となります。新しい知識を学ぶ意欲はあっても、過去のやり方に縛られていては、せっかくの学びをうまく活かせないことがあるためです。
順序としては、まずはアンラーニングによって思考を柔らかくし、その上でリスキリングに取り組むという流れが理想的でしょう。先に古い考えを手放すことで、新しい知識やスキルも効果的に取り入れることができます。
アンラーニングとリスキリング、2つのステップをセットで行うことで、環境の変化にも柔軟に対応できるようになります。
アンラーニングを実践するには?
アンラーニングは、ただ知識を忘れるというよりも、これまでの自分を見つめ直し、よりよい働き方にアップデートするために必要な手順です。しかし、実際なにから始めたら良いのか、戸惑ってしまう人も多いことでしょう。企業の中でアンラーニングを実践するためのステップをご紹介します。

まずは「気付くこと」から始めよう
アンラーニングの第一歩は、自分の考えや行動を客観的に見直すことです。「これは本当に今も効果的なやり方だろうか?」「自分の判断に思い込みはないか?」といった内省を常に行うだけで、今までの体制を変える一歩を踏み出せます。日々の業務の中でうまくいったことや失敗したことを書き出し「見える化」するのも有効で、今まで見えてこなかった自分の思い込みやクセなどにも目を向けることができるでしょう。
アンラーニングの核心|価値観の取捨選択
アンラーニングを実践するうえで、もっとも重要ともいえるのが「価値観の取捨選択」です。気付きを得たあとに、自分の中にある当たり前や正しさを見直し、いまの環境や目指す方針と合っているかを判断する必要があります。たとえば、「経験がすべて」「失敗はしてはいけない」「こうあるべき」といった考え方は、これまでの自分を支えてきた大切な考え方かもしれません。しかしそれらが現在の業務や組織にとって、本当にプラスになっているのかを振り返ってみると、意外にも「もう手放してもいいかも…」といった考え方が見つかることもあるのです。
価値観の取捨選択は一人だけで行うのは難しく、上司や同僚、部下との対話や研修、フィードバックによって、うまく進めることができます。他者からの視点によって、自分では意識していなかった「思い込み」や「固定観念」が浮かび上がることも少なくありません。
フィードバックの際、時には自分の弱さや未熟さに向き合う場面もあるかもしれませんが、それを変化のチャンスととらえ、モチベーションの維持や向上ができれば、アンラーニングによって大きな成長につながって行くでしょう。
試して学ぶ、行動から始まる実践
アンラーニングの対象が見えてきたら、いよいよ実際の行動に移す段階です。変革を行うことが怖いと感じる人もいるかもしれませんが、必要以上に構える必要はありません。まずは「ちょっと試してみようかな」くらいの気持ちで始めてみましょう。やってみてうまくいかなければ、元のやり方に戻せばいいのです。
今まで慣れ親しんだやり方を一度手放し、あえて違うやり方をしてみると、最初は不慣れで非効率に感じることもあるかもしれません。そうしたプロセスのなかにこそ、新たな気づきや予想もしなかったメリットが眠っていることもあります。試行錯誤のなかで、自分にとって本当に合った考え方や方法に出会えるかもしれません。
また、企業側は従業員が新しいことを学び、試すための「場」をつくることも非常に効果的です。異なる部署や職種との対話の場や、外部セミナーへの参加など、さまざまな交流を通じて、従業員の視野は大きく広がります。
そして何より大切なのは、「学び直し」を一時的なイベントで終わらせないことです。アンラーニングは一度で完了するものではなく、日々の実践の中で少しずつ積み重ねていくものです。変化することを前向きに捉え、チャレンジを楽しむ姿勢を持つことが、継続的な成長へとつながっていきます。
企業のアンラーニング実践事例
職場でのアンラーニングは、新しい技術や価値観、働き方を取り入れるうえでは欠かせません。いままでの成功体験や慣習にとらわれていては変化に対応できない時代に、実際にアンラーニングを取り入れて変革を成功させた事例を紹介します。

フィルムから化粧品へ・富士フイルムの事業転換
富士フイルムは、かつての主力事業であった写真フィルムが市場から消えつつあった中で、化粧品や医療、化学分野への大胆な転換を図りました。
これは単なる事業拡大ではありません。これまでに培ったフィルム技術の応用という発想を活かしながらも、写真フィルム中心の事業モデルを手放したことによるアンラーニングの成功例です。
価値観と組織文化の転換・とある社会福祉法人の再生
ある社会福祉法人では、介護報酬の引き下げや離職率の高まりによって経営が悪化し、従来の独裁的な体制からの脱却が求められていました。前理事長の退任によって旧体制の専制的な運営から転換し、「人間性の尊重」「自律型組織」を重視する新たな経営理念を掲げたことで、職員の意識が大きく変化することとなります。夜勤手当の増額やパート時給の底上げなど、報酬制度の見直しや業務改善も進み、職員が自ら課題を提起・解決する自律的な動きが広がりました。
価値観そのものを見直す、深いレベルでのアンラーニングが、組織全体の再生につながったケースです。
社内キャリアで新しい自分に出会う・ナリコマの社内公募制度

ナリコマでは、製造から配送、さらにはお客様への情報提供までを一貫して行う体制の中で、「社内公募制度」を導入しています。この制度は、あたかも社内で転職する感覚で、異なる職種や部署にチャレンジできる仕組みです。自ら希望して新たな業務に取り組むことで、新たな視点や気づきを得ています。
ナリコマが目指すのは、「主体的に考え、行動できる人材」の育成です。お客様、チーム、そして社会に対して自らの役割を考え、行動を起こすことのできる社員を増やしていくことが、組織全体の成長にもつながると捉えています。その実現に向けて、学びを義務ではなく意欲を後押しする仕組みとして、独自のe-ラーニングシステム「ナリトレ」を提供しています。場所や時間に縛られずに利用できるほか、大多数のコンテンツを社内で制作しているのが特長です。現場のリアルな課題や業務に即した内容が反映されており、実践的な学びにつながっています。
「まず自分が変わる」ことで、会社や自身の課題に対して主体的に考えることができる人材へ。ナリコマでは、社内公募制度とナリトレを通じて、前向きなアンラーニングを実現する環境づくりに取り組んでいます。
アンラーニングで働き方を見直して未来に備えよう
昨今のように変化の激しい時代には、これまでのやり方や考え方に固執せず、柔軟に見直していくことが求められます。アンラーニングはその第一歩として、「いったん手放す」ことで、新たな視点や価値観を受け入れやすくするためのきっかけになります。

こうした取り組みは、個人の成長だけでなく、チームや職場全体の働き方改革にもつながります。自分自身が変わろうとすることで、周囲にも前向きな変化を促すことができるためです。
また、これから必要になるスキルを学び直す「リスキリング」に取り組む際にも、いままでの当たり前を見直すことは欠かせません。未来に備えるためには、過去のやり方にとらわれすぎず、これからの働き方に合った「学び直し」の習慣を日々の中に取り入れていきたいものですね。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。