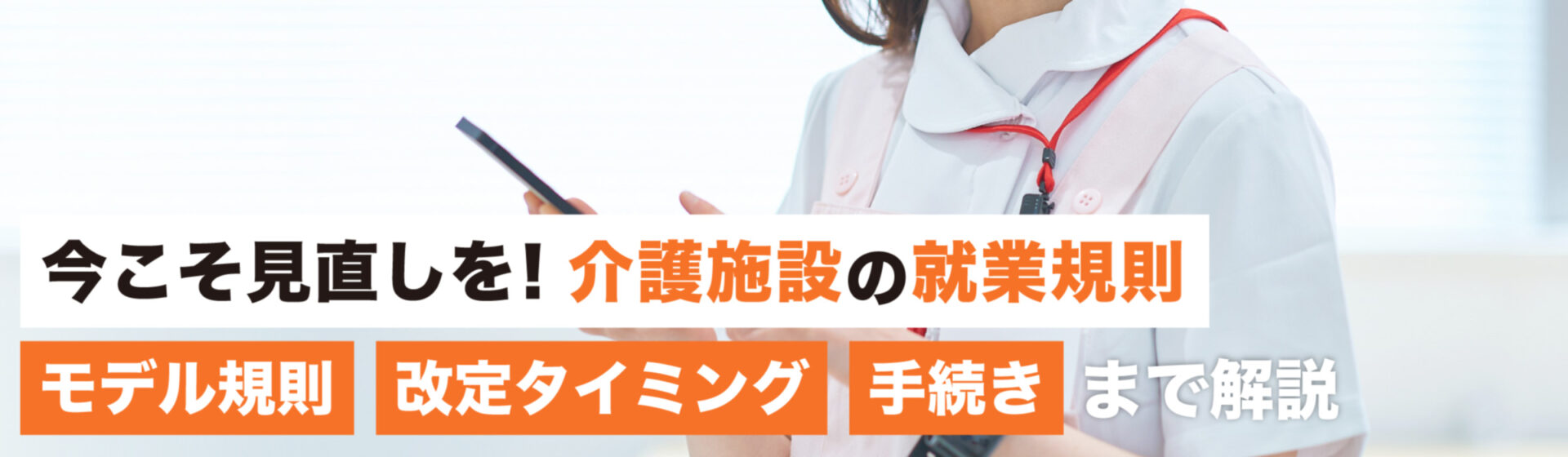介護業界では、法改正や制度の変更が続いています。その中で、介護施設の就業規則の見直しは、安心して働ける職場づくりに欠かせない取り組みの一つです。しかし「どのタイミングで改定すべきか」「どのような手続きが必要か」「何を基準に内容を整えるべきか」など、対応に悩む施設も多いのではないでしょうか。
今回は、厚生労働省が提示するモデル規則を参考にしながら、見直しに適した改定タイミングや具体的な手続きの進め方について、介護現場の視点からわかりやすく解説します。法令に沿った対応を進め、職員が安心して働ける職場をつくるために、今できることを一緒に確認していきましょう。
目次
なぜ介護施設の就業規則は見直しが必要なのか?
介護の現場では、働き方や法律がどんどん変わってきています。今の時代に合ったルールにしておくためにも、就業規則の見直しはとても大切です。

介護業界を取り巻く環境変化
介護業界では人手不足や職員の高齢化や、働き方の多様化など、現場を取り巻く環境が大きく変わってきています。さらに、働き方改革やそれに関連する法改正も続いているため、介護施設側は、より柔軟かつ公平な運用ルールの整備が必要です。
特に注目しておきたいのは、2025年4月1日から段階的に施行される育児・介護休業法の改正です。この改正では、育児や介護と仕事を両立しやすくするための制度が強化され、対象者の拡大や事業主に求められる措置の明確化などが進められます。そのため、育児介護休業規程を含む就業規則の見直しが求められます。
就業規則が古いと起こるリスク
就業規則が現状に合っていないまま放置されていると、さまざまなリスクが生じます。たとえば、適切な対応が取れなかったことで職員とのトラブルにつながったり、法改正に対応していない内容のままでは、行政指導の対象になったり、コンプライアンス違反として指摘される可能性もあります。曖昧なルールや時代に合っていない内容は、職員の不安や不信感にもつながりかねません。
就業規則の見直しに適したタイミングとは?
就業規則は状況に合わせて定期的に見直すことが大切です。特に、法律や施設内の運営が変わるタイミングでは、職員が安心して働けるために内容をアップデートしていきましょう。就業規則を見直す具体的なタイミングをまとめました。

法改正や制度変更があったとき
法律が変わった時には、施設のルールもそれに合わせる必要があります。たとえば、2025年4月改正の育児・介護休業法は、働く人が子育てや介護と両立しやすくなるような制度が追加されました。子どもの看護休暇が取れる対象年齢が未就学児から小学校3年生までに広がったり、休暇の理由に学級閉鎖や入学式・卒園式への参加も認められるようになるほか、残業免除の対象も3歳未満の子どもがいる職員から小学校入学前の子どもがいる従業員にまで拡大となりました。
加えて、労働基準法や介護保険法などの改正などもあり、度重なる法改正に対応するためには就業規則の見直しは必要不可欠です。
施設内のルールや運営体制が変わったとき
就業規則を見直すタイミングは法律の改正時だけでなく、施設の中で新しい制度や勤務形態を取り入れたときも該当します。たとえば、夜勤の体制を変えたり、短時間勤務やフレックスタイム制度を導入したりした時には、現場の運用に合わせて就業規則に反映させておくことが大切です。小さな変更だからといって後回しにせず、職員の戸惑いやトラブルを防ぐためにも早めの対応が必要です。安心・安全な施設運営のためにも、柔軟な対応を心がけましょう。
介護施設向けに参考にできる「モデル規則」とは?
「モデル規則」とは、最新の労働関係法令に基づいた就業規則の見本のようなものです。厚生労働省が作成しており、就業規則を初めて整備・見直しする際のテンプレートとして活用できます。施設のルールに合わせ、モデル規則を参考に調整していくことで、スムーズに規則の整備を進められます。

厚生労働省のモデル規則を活用するメリット
モデル規則には、就業規則を構成する基本的な項目が一通りそろっています。就業規則の改定に「何から手をつければいいかわからない」という場合でも、労働時間、休日・休暇、賃金、服務規律などが項目ごとに整理されているため、自施設に必要な部分を確認しながら編集ができます。
ただし、モデル規則はあくまでひな形です。そのままコピーして使うのではなく、施設の実情に合わせて労働時間や給与体系などの調整が必要です。また、厚生労働省の「就業規則作成支援ツール」を使えば、モデル規則の項目や作成上の注意を参考にしながら、入力フォームに必要事項を入力して、そのまま印刷・提出用の書類として活用できます。初めて就業規則の改定を行う施設にとっても心強いツールです。
介護施設ならではのカスタマイズポイント
介護施設では一般的な就業規則にプラスして、介護現場ならではの働き方ルールを取り入れたカスタマイズが必要です。たとえば、シフト勤務や夜勤手当の扱いについては、施設ごとに異なるため、きちんと定めておきましょう。さらに、職場の人間関係や心の健康を守るためにも、ハラスメント防止の方針やメンタルヘルス対策も就業規則に盛り込んでおくと安心です。最近では、職員のスキルアップやキャリア形成の支援として「リスキリング」を行う施設もあります。リスキリングや研修制度などの項目も記載しておくと、働きやすさや職員満足度の向上にもつながります。
就業規則を見直す際の手続きと注意点
就業規則を見直すときには、ただ内容を変えるだけでは不十分です。法律上のルールや必要な手続きをしっかり押さえておかないと、後から無効とされてしまうことも。就業規則の見直しから職員への周知までを、スムーズに進めるための流れと注意点を解説します。
見直しから改定完了までの基本の手順
就業規則を改定するときは、次のようなステップで進めるのが基本です。
1. 現在の就業規則を確認
2. 課題や見直しポイントを整理
3. 変更案の検討
4. 労働者代表への説明と意見の聴取
5. 就業規則変更届の作成
6. 労働基準監督署への届出
7. 従業員(職員)への周知
注意しておきたいのは「就業規則は会社の判断だけで自由に変更できるわけではない」という点です。労働基準法では、職員に不利益な変更を行う場合は、職員からの合意や変更内容が合理的であることが求められます。トラブル防止のためにも、現場の声を聞きながら丁寧に進めることが大切です。

労働基準監督署への届出
就業規則の見直し・変更が終わったら、労働基準法第89条に基づき、それを所轄の労働基準監督署に変更届を届け出ます。届出の際に必要な書類は、改定後の就業規則に加えて、労働組合などの労働者代表の意見書も必要です。
職員への周知徹底
就業規則は作成・届出しただけでは完了ではありません。職員への周知が法律で義務づけられており、これを怠ると無効になる可能性もあります。実際、過去の判例でも「周知されていなかった」として就業規則が認められなかったケースがあります。
下記のような方法で、確実に職員へ周知するようにしましょう。
① 社内掲示や常設の備え付け
職員がいつでも見られる場所に就業規則を掲示したり、閲覧できるファイルを置いておくとよいでしょう。「誰でも」「いつでも」確認できることが重要です。
② 書面で配布
印刷した就業規則を配布し、受け取ったことを確認します。配布記録を残しておくと安心です。
③ 電子データでの共有
社内ネットワークやクラウドなどに掲載し、職員がいつでも見られるようにします。ただし、アクセス方法が分かりにくいといった場合は、周知と認められないこともあるため、注意が必要です。
就業規則の見直しで安心して働ける環境づくりを

介護施設の就業規則は、定期的な見直しと法改正への対応がとても重要です。制度が変わり、働き方も多様化する今だからこそ、就業規則の定期的な見直しは避けて通れません。古いまま放置しておくのは、大切な職員や施設全体のリスクにつながってしまいます。
「どこから手をつければいいの?」と迷う時には、厚生労働省のモデル規則が心強い味方になります。しかし、モデル規則をそのまま使うのではなく、自分たちの施設に合った内容にしっかりとカスタマイズしてこそ、本当に使えるルールになるのです。就業規則を見直した時には、職員への周知徹底もお忘れなく。就業規則の見直しは、一つひとつ丁寧に進めていくことで、職員が胸を張って働ける職場づくりを叶えられるでしょう。
就業規則を整えることは、職場の未来を整えることといっても過言ではありません。今こそ、より良い職場環境づくりへの一歩を踏み出しましょう。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。