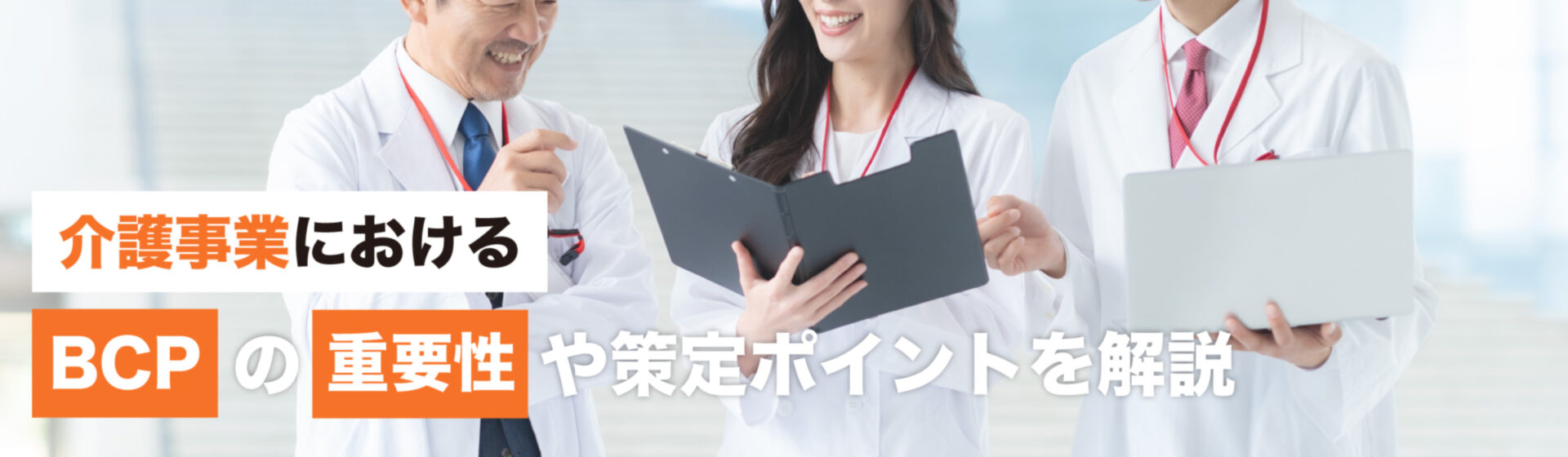近年、あらゆる事業において重要視されているBCP(事業継続計画)。今回の記事は、義務化された介護事業のBCPについて詳しくお届けします。介護施設・事業所におけるBCPの重要性や策定のポイントをお伝えするとともに、得られるメリットも解説。ぜひ最後までお読みください。
目次
介護事業に義務化されたBCPの重要性

BCP(事業継続計画)とは
BCPはBusiness Continuity Planの略。緊急時も業務を継続できるようにしたり、業務が中断してもできるだけ早期に復旧させたりすることを目的とした事業継続計画を指します。一般的な防災計画は、身の安全を確保したり、物的被害を抑えたりすることが主な目的です。つまり、BCPは防災計画がベースになっていますが、もう一歩踏み込んだ内容も盛り込まれています。
ここでいう緊急時というのは、自然災害やテロ、事故、感染症などによって大きな被害を受けた状況のこと。2024(令和6)年1月1日に発生した能登半島地震はまだ記憶に新しいところですが、日本は地震、津波、火山の噴火、台風、豪雨、豪雪といった自然災害が多発しています。こうした災害時は特に、少しでも早い復旧や復興が望まれるでしょう。だからこそ、BCPは非常に重要だと考えられるようになりました。
また、長期にわたって業務が中断されれば、顧客の信用を失うだけでなく、企業としての評価が下がってしまうかもしれません。BCPにはそのリスクを回避し、企業の価値を守るという役割もあります。
介護事業におけるBCP策定の義務化
介護事業においては、2021(令和3)年4月の介護報酬改定でBCP策定が義務化されました。前述したように、日本は自然災害が多く、いつ、どこで、誰が被害に遭ってもおかしくありません。とはいえ、介護施設・事業所の業務が滞ってしまうと、高齢者や要介護者の安全が脅かされる可能性があります。
BCP策定が義務化された背景の一つとして、高齢者や要介護者を支えるという社会的な役割があったでしょう。利用者はもちろんのこと、その家族にも安心してもらうためには、介護事業全体でBCPへの意識を強く持たなければならないのです。
ちなみに、策定が義務化された時点では即時対応する必要はなく、三年の経過措置期間が設けられていました。その期間が終了する2024(令和6)年4月に施行された介護報酬改定では、追加で一年の経過措置期間が設けられました。2025(令和7)年4月1日以降は、BCP未策定の介護施設・事業所すべてに介護報酬の減算措置をとることが決定しています。
介護事業におけるBCP策定のポイントとは?
介護施設・事業所におけるBCP策定の重要な目的は、緊急時に業務やサービスが継続されること。そして、もう一つ大事なのは、利用者と職員の安全がきちんと確保できることです。厚生労働省は感染症と自然災害、それぞれのパターンにあわせたガイドラインを公開しています。本項目は、そのガイドラインに従い、介護事業におけるBCP策定のポイントをまとめてみました。

BCP策定のポイント【感染症・自然災害共通】
◆情報収集と役割分担
緊急時に迅速な対応をとるためには、まず情報を集めて共有する必要があります。介護施設・事業所には自分で情報収集ができない高齢者も多いため、正確な情報を共有することで、安心感にもつながるでしょう。
一連の流れをスムーズにするには、意思決定を行う人だけでなく、各業務における担当者も細かく決めておくべきです。また、利用者の家族をはじめとする関係者への連絡先なども把握しておかなくてはなりません。
◆業務の優先順位
被害状況によっては、通常よりも職員が少なかったり、使える設備が限られたりすることも考えられます。緊急時に不要な業務は後回しにし、特に重要な業務を継続するよう、優先順位を決めておくことが大切です。
◆研修・訓練と計画の見直し
例えば、防災用品をせっかくそろえても、収納場所や使い方がわからなければまったく役に立たないでしょう。同様に、BCPは「策定したから終わり」というものではありません。まずは、緊急時に適切な行動ができるよう、職員全員に内容を知ってもらうことが重要です。日頃から研修や訓練を行っていれば、いざというときにBCPの効果が発揮されます。
また、時間が経てば施設内の事情が変わったり、新たな防災情報が追加されたりするかもしれません。常に最新の内容にしておくためにも、BCPは定期的に見直す必要があります。
BCP策定のポイント【感染症】
新型コロナウイルスなどの感染症は、建物や設備などに直接的な影響を及ぼすことはありません。BCPには感染拡大防止や人繰りへの対策を盛り込む必要があります。
◆感染者発生時の対応
感染症が流行しているときは、利用者だけでなく職員も感染の可能性があります。感染拡大を止めるためにも、事前に感染者発生時の対応を決めておくことが重要です。
◆人員確保の体制
感染者が職員だった場合、利用者の介護などに当たる人員が減ってしまいます。もちろん、感染者が増えてしまう可能性もあるでしょう。関連施設や事業所から職員を回してもらう、自治体に応援を要請するなど、人員確保のためにどうするか決めておく必要があります。
BCP策定のポイント【自然災害】
自然災害は、立地などによって被害状況が異なります。建物や設備が壊れたり、崖崩れや倒木などで道路が寸断されたりすることもあるでしょう。また、職員自身が無事でも、通勤手段を失う可能性もあります。BCPには、こうしたさまざまな状況への対策を入れなくてはなりません。
◆平時と災害発生時に分けた対策
平時におけるポイントは、事前の備えです。地震などで倒れやすい機器や什器を固定したり、パソコンなどに含まれるデータのバックアップをとったりすることが対策となります。
災害発生時のポイントは、利用者と職員の安全確保のために建物や設備などの被害状況を把握すること。その上で復旧に向けてどのように行動するのか、ルールを決めておきます。また、出勤できない職員がいるときの対応も考える必要があるでしょう。
BCP策定は介護事業にとってのメリットが大きい
介護施設・事業所でBCPの策定をすると、主要な業務やサービスが継続できること以外にも次のようなメリットがあります。

①利用者や職員の安全が保たれ、信頼感も高まる
安全配慮義務を果たし、その場にいる全員の命を守ることにつながります。また、利用者と職員だけでなく、関係者や取引先、地域における信頼感も高まります。
②業務改善のきっかけになる
BCP策定にはまず、事業全体の見直しが必要です。これまで気付かなかった、もしくは未対応だった改善点が洗い出され、より働きやすくなるかもしれません。職員の離職を防ぐ効果も期待できます。
③ワクチンの特定接種対象になる
新型インフルエンザ等対策特別措置法の第28条に従い、特定接種対象事業者として認められます。優先的なワクチン接種によって安全性が高くなり、職員や利用者にも安心感が生まれます。
④税制優遇や補助金、融資などが受けられる
2025(令和7)年3月31日までにBCP策定を完了すれば、中小企業防災・減災投資促進税制に従って特別償却18%の税制措置が受けられます。また、BCP実践促進助成金などの補助金を受け取れる可能性もあります。低金利で融資を受けられる場合もあるため、資金面での不安も軽減されるでしょう。
介護事業のBCPにも貢献!ナリコマの献立サービス

ナリコマでは、介護事業のBCPにも貢献できる献立サービスをご提案しております。災害などが起きても、安全が確認できれば自社配送センターから完全調理済み食品をお届け。非常食はソフト食、ミキサー食、ゼリー食もご用意しております。緊急時に安心の献立サービスをお探しの際には、ぜひ一度ナリコマにご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
コストに関する記事一覧
-

介護職員のキャリア研修を考える!未経験スタートや管理職向けなど目的別の設計方法
介護職員のキャリア研修に取り組むことで、個々の職員のスキルアップを促し施設全体の質を高めることができます。この記事では、介護職の仕事を未経験からスタートした場合の一般的なキャリアアップの流れや、介護福祉士からのキャリアアップ、リーダー育成や管理職向け研修などに注目し、キャリア研修の設計や導入のコツを解説します。介護職員のキャリアアップや幹部研修を検討している施設の担当者さまはぜひご参考ください。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。 -

ニュークックチルの初期コストを抑えたい!導入補助金や助成金、支援制度の有無をチェック
近年の日本は少子高齢化と物価高騰が急速に進んでおり、あらゆる業界で人手不足の解消やコスト管理の難しさが課題となっています。病院や介護福祉施設の給食を提供する厨房も、同様の影響を受けている現場の一つ。長時間労働や職員の高齢化、給食運営コストのアンバランスなど、いろいろな問題が生じているのです。
ニュークックチルは、そんな病院や介護福祉施設での導入が増えている新調理方式。今回の記事はニュークックチルのコスト面に注目します。導入補助金や助成金などの支援制度についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
人材不足に関する記事一覧
-

給食業界の今後はどうなる?人手不足がもたらす変化と解決策
今、給食業界では人手不足が大きな課題となっています。給食業界を取り巻く環境は人手不足に加えて、給食コストの上昇などで大きく揺れています。
今回は、給食業界が人手不足を解消するための解決策や、データから読み取れる給食業界の今後についても解説します。 -

栄養士の仕事で大変なことは?病院、介護施設別に公開!
病院や介護施設などで提供される食事において、栄養士の存在はとても重要です。本記事では、栄養士がどんな仕事をしているのか詳しくご紹介しましょう。病院や介護施設で働いていて大変なことも、それぞれお伝えします。
「キツい」「つらい」といったイメージが付きやすい理由を考察し、栄養士に向いている人の特徴やよくある話、働き方を改善するポイントなども併せて解説。ぜひ最後までお読みください。 -

クックチルとニュークックチルの違いは?メリットデメリットを解説!
入院患者を受け入れる医療施設、高齢者をサポートする介護施設などでは、毎日何かしらの食事を提供しています。提供方法はいろいろありますが、今回取り上げるのはクックチルとニュークックチル。この二つは医療施設や介護施設の給食現場などで重宝されている業務用の調理システムです。
本記事ではクックチルとニュークックチルの違いがわかるよう、メリットやデメリットを解説。ニュークックチルシステムの導入時に欠かせない再加熱機器(再加熱カート、リヒート)についても、詳しくお伝えします。