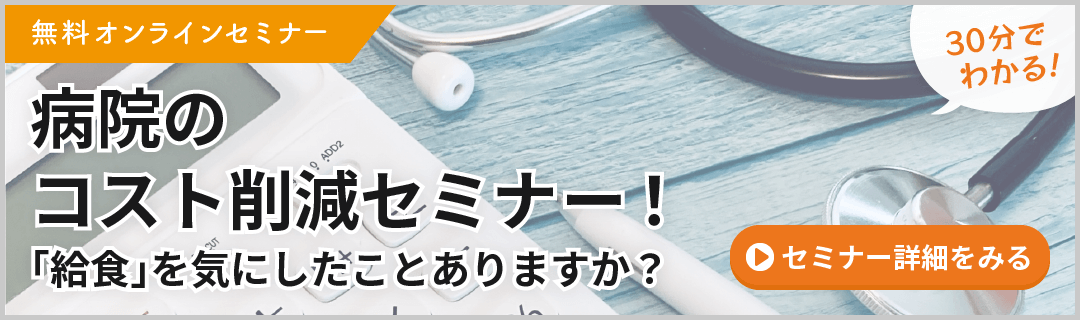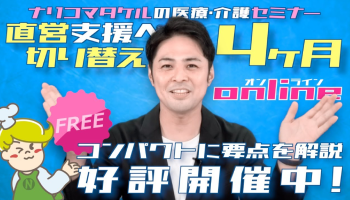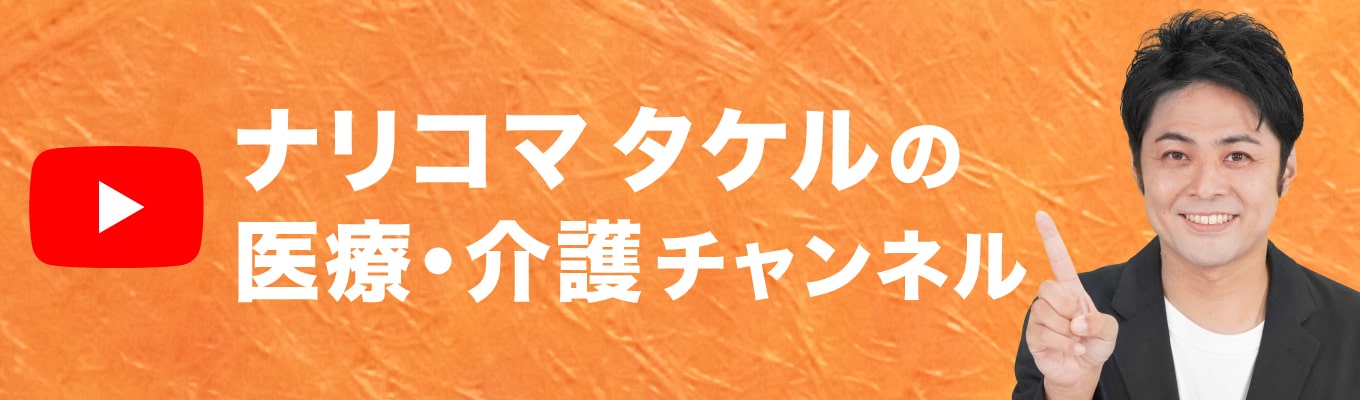「育成就労制度」は、2024年に創設され3年以内に施行される制度です。この記事では、旧制度である「技能実習制度」の概要や課題を振り返りながら、制度変更によりどう変わるのかを、育成就労制度の特徴や受け入れ企業の実務のポイントも押さえながら解説します。
目次
育成就労制度が生まれた背景について
2024年に公布された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」により、技能実習制度を発展的に解消する形で「育成就労制度」が創設されることとなりました。ここではまず、旧制度となる「技能実習制度」のあゆみと現在までの課題について解説します。

技能実習制度とは?
日本では、国内の技術や知識を開発途上国等へ伝えることや、開発途上国等の経済発展に向けた人材を育てることなどを目的に、1993年に外国人技能実習制度が創設されました。外国人技能実習制度は、1960年代の後半頃に海外で行われていた現地法人などによる社員教育のための研修が注目され誕生した背景があります。
さらに、外国人の技能実習の適正な実施と技能実習生の保護などを目的に、技能実習の基本理念などを定めた「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律」が2017年に施行され、技能実習法として知られると共に新しい技能実習制度として発展してきました。技能実習制度には、外国人の技能実習生が、自国で身に付けるのが難しい技能等を日本で修得できるメリットがあります。主な目的が技能の修得と上達にあるため、技能実習は日本における労働力の需給の調整の手段にしてはいけないという理念が定められています。
技能実習法によって新しく技能実習3号が設けられ、技能実習の最長期間が3年間から5年間に引き延ばされたほか、技能実習生の人数枠を約2倍まで増加することが認められるなど、より充実した環境が意識されました。2007年から2024年までの間に、一時減少したものの技能実習生は大幅に増加し、2024年末には過去最多の456,595人となっています。
旧制度の問題点について
外国人技能実習生が、より良い環境で技術を身に付けられるための環境作りが意識されていたものの、実際の状況が理念とかけ離れているケースもありました。技能実習制度で定められた本来の目的と異なっていたり、厳しい就業環境で技能実習生の権利が保護されていなかったりと、技能実習制度には複数の課題と問題点が認識されています。こうした環境でとくに問題視された事柄の一つが、技能実習生の失踪です。技能実習生の失踪は一時的に減少したものの年々増加し、2023年には過去最高となる9,753人となりました。

失踪の原因としては、やむを得ない事情がある場合を除いて転籍が認められないといった、技能実習制度の環境が考えられています。原則として転籍は不可となり、こうした制限がある中で職場環境のトラブルや人権侵害などがあり、失踪につながっていると想定されます。
「やむを得ない事情」には、暴行やハラスメントなどの人権侵害行為や悪質な法令違反・契約違反行為などを受けている、などの場合が当てはまるため、こうしたトラブルがある場合は転籍が可能です。そのため近年では、こうした内容を技能実習生にわかりやすく伝えることや、転籍手続き中の技能実習生に対して在留管理制度上の措置を設けるなど、さまざまな改善が行われています。しかし技能実習制度では、本人の意向によって転籍することは不可能です。
技能実習制度と育成就労制度の主な違いと特徴
ここでは、旧制度となる技能実習制度と比較した、育成就労制度の特徴について解説します。
育成就労制度の目的
旧制度となる技能実習制度との大きな違いは、目的が異なることです。技能実習制度が、開発途上国等への国内の技術・知識の移転や経済発展に向けた人材育成への協力であったのに対して、育成就労制度は、日本国内のための人材育成や人材確保が主な目的になっています。
現在、日本では人手不足が深刻化し、外国人を受け入れて就労してもらうことは必須となり、さらに国際的な人材獲得競争も激しくなっています。そのため、外国人にとって働きたいと思える国や制度を目指すことに目的も変化してきました。そのうえで、日本における経済の重要な担い手として、長期にわたって産業を支えてくれる人材育成が目指されています。
在留期間と内容の変化
技能実習制度では、特定技能1号の段階に進むまでに、技能実習1号・技能実習2号・技能実習3号のステップがあり、最長で5年の在留期間が設けられています。育成就労制度では、これらの期間は育成就労としての一つの期間となり、在留期間は原則3年と定められています。
旧制度では不一致だった対象となる職種や分野についても、育成就労から特定技能1号に進むうえで対象となる職種や分野は原則として一致させるため、キャリアアップの道筋が明確化されるようになりました。旧制度で原則だった実習終了後の帰国についても、育成就労制度では長期に渡って日本で産業を支えてもらえるよう、外国人が地域に根付いて共生できる内容に見直されています。

本人の意向による転籍が可能
旧制度の課題や問題点として挙げられていた転籍の制限が、育成就労制度では緩和されたことも大きな特徴です。先述した「やむを得ない事情」による転籍のほかにも、転籍先の業務が転籍元と同一の業務区分であることや、規定の業務期間を満たしていること、技能や日本語力が一定水準以上であることなどの、一定の要件を満たせば本人の意向によっても転籍が認められることになりました。
日本語能力が必須
技能実習制度では、受け入れの際の日本語の語学力について、一般的に入国後に日本語教育の講習を受けるといったシステムでしたが、育成就労制度では、就労開始前に下記の日本語能力試験の合格や講習の受講が必要となります。
- 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格
- 上記に相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講
日本語能力A1とは、よく使用される日常的表現などが理解できて使えることや、はっきりとゆっくりわかりやすく話してもらえれば簡単なやり取りをすることができるといった、基礎段階のレベルです。また、日本語の語学レベルについては、旧制度も参考に、産業分野ごとにより高い水準を可能にすることも視野に入れて検討されています。
受け入れ企業の対応や実務のポイントとは?

育成就労制度は、公布日から起算して3年以内に施行されるため、2027年中までには施行される予定です。育成就労外国人の受け入れを行う場合は、それまでに知識を蓄えておきましょう。下記のような、受け入れ企業に設けられた要件などを確認しておくと役立ちます。
- 産業分野が育成就労産業分野に当てはまるかどうか確認する
- 受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制等の要件を確認する
- 受入れ対象分野別の協議会への加入等の要件を確認する
すでに技能実習生を受け入れている場合は?
育成就労制度の施行日の時点ですでに技能実習生を受け入れている場合は、認定された計画に基づいて引き続き技能実習を続けることができます。技能実習3号への移行については、範囲が限定される場合があるため規定を確認しましょう。技能実習生として受け入れる場合には技能実習制度のルールが適用されるため、技能実習から育成就労に移行することは不可能です。
育成就労制度のより良い受け入れ企業を目指そう
育成就労制度の受け入れ企業となることで、長期的な雇用が期待できる人材を採用することができます。育成就労外国人には一定の日本語力が求められるため、旧制度と比較してコミュニケーションが取りやすい可能性もあるでしょう。育成就労制度においても受け入れ企業の優遇措置が検討されているため、育成就労外国人が働きやすい環境を整え、日本語や技能の試験合格に向けたサポートを行うことは企業全体のメリットにつながります。
ナリコマでは施設運営における外国人材の活用のご相談を承っております

ナリコマでは、病院や介護施設に特化した厨房運営のサポートを行っており、ニュークックチルシステムによる早朝や遅番の無人化など、人手不足の課題解決に役立つサービスを提供しています。また、ナリコマは「登録支援機関」の認定を取得しており、育成就労の先に続く特定技能外国人の受け入れに関するサポートも行っています。
介護職では多くの施設様が導入している外国人材ですが、厨房職での検討も増えてきています。人手不足や外国人の受け入れにお悩みを抱えている施設さまは、ぜひお気軽にご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。
コストに関する記事一覧
-

ニュークックチルに必要な再加熱機器とは?スチームコンベクション・再加熱ワゴン・マイクロ波加熱装置を紹介
病院や介護施設で導入が進むニュークックチル。効率的な調理体制を整えるために欠かせないのが「再加熱機器」です。でも実際、どんな機器を用意すればいいの?と悩まれる方も多いはず。
調理を前日に終えておける仕組みは魅力ですが、食事を提供する直前に安全かつおいしく仕上げるためには、専用の再加熱機器が必要になります。
ただ、再加熱機器といっても「スチームコンベクション」「再加熱ワゴン」「マイクロ波加熱装置」など種類はさまざま。それぞれ仕組みや特徴が異なり、自施設の配膳スタイルや厨房動線によって、適した機器は変わってきます。
今回は、ニュークックチルを運用するために必要な再加熱機器と、その違いや導入時のポイントを解説します。 -

ニュークックチルの初期コストを抑えたい!導入補助金や助成金、支援制度の有無をチェック
近年の日本は少子高齢化と物価高騰が急速に進んでおり、あらゆる業界で人手不足の解消やコスト管理の難しさが課題となっています。病院や介護福祉施設の給食を提供する厨房も、同様の影響を受けている現場の一つ。長時間労働や職員の高齢化、給食運営コストのアンバランスなど、いろいろな問題が生じているのです。
ニュークックチルは、そんな病院や介護福祉施設での導入が増えている新調理方式。今回の記事はニュークックチルのコスト面に注目します。導入補助金や助成金などの支援制度についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。 -

今後どうなる?給食業界の課題と将来性を詳しく解説
給食は、保育所や学校、病院、老人ホームといったさまざまな施設で提供されています。施設を利用する人々にとって、給食は健やかな生活を送るために欠かせないものでしょう。ところが、その一方で、現在の給食業界は大きな課題をいくつも抱えています。
今回の記事で取り上げるテーマは、給食業界の将来性。近年における業界の動向や解決すべき課題を挙げ、今後の展望について解説します。ぜひ、最後までお読みになってください。