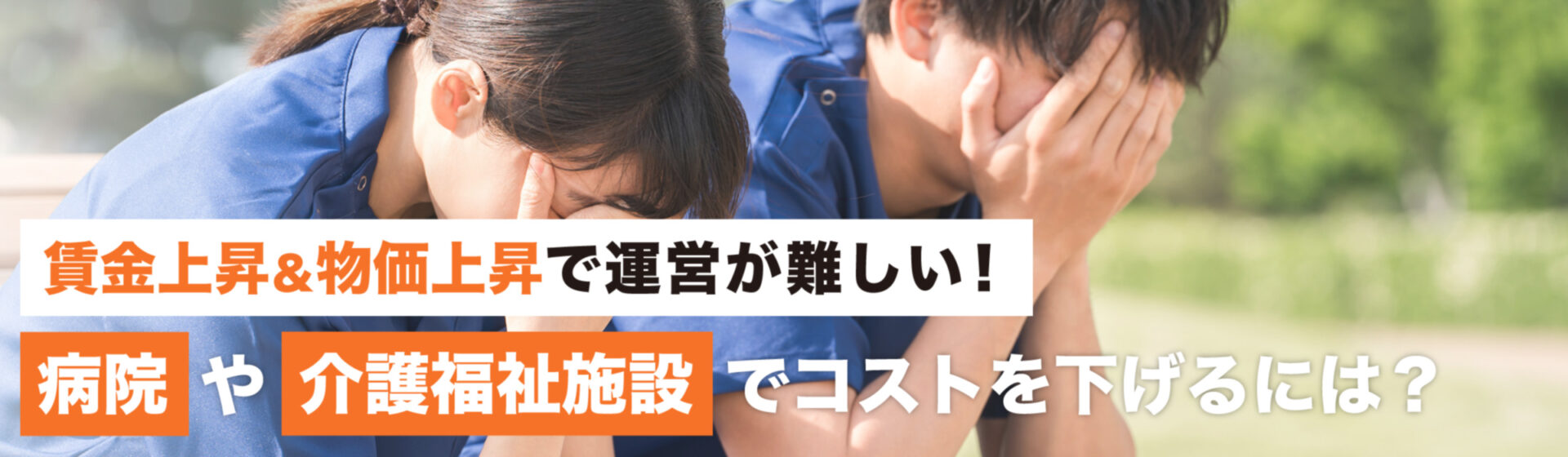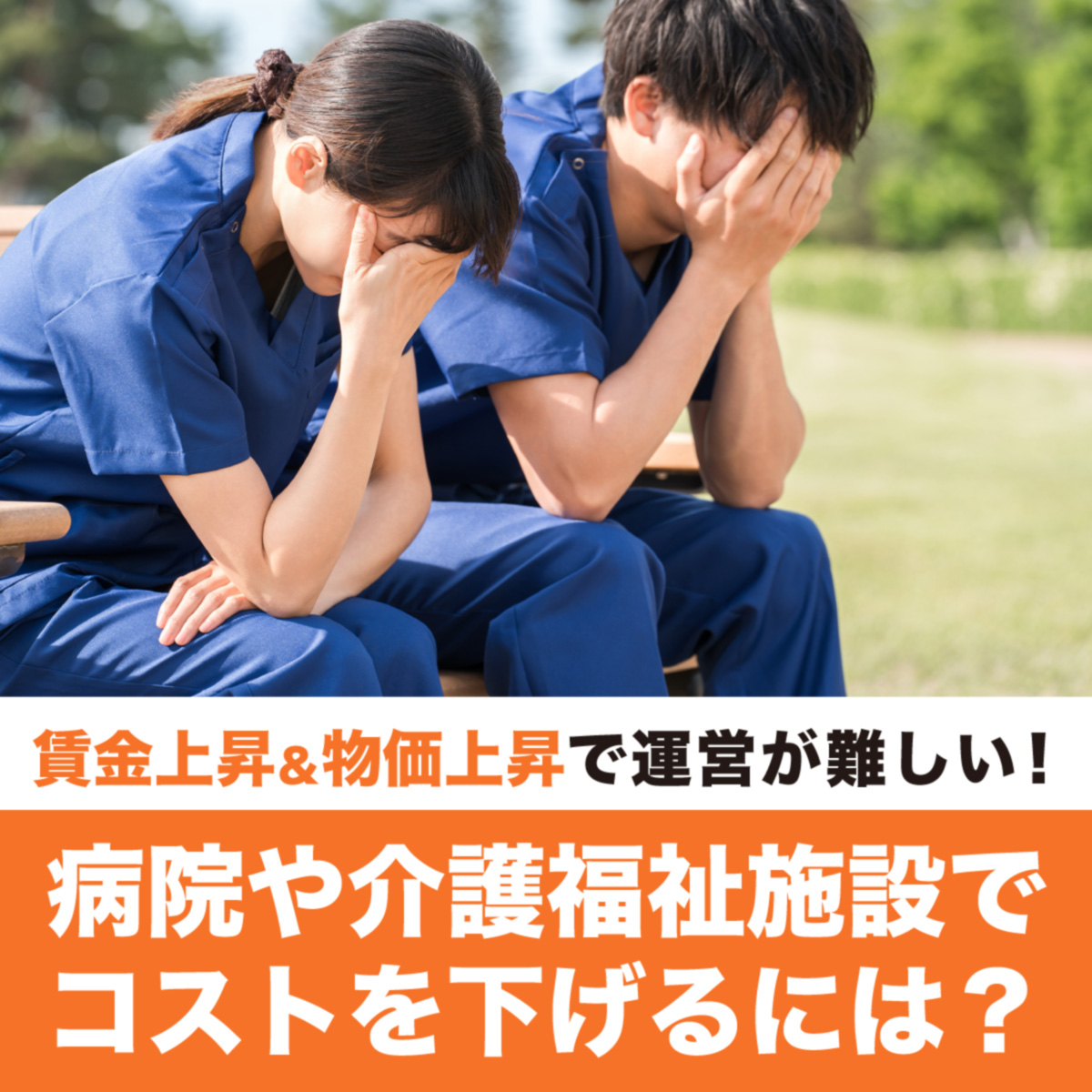近年では急速に物価上昇が進んでいますが、同時に、各業界では賃上げの動きもみられるようになっています。病院や介護福祉施設はかねてから運営が難しく、赤字になりやすいといわれてきました。しかし、賃金上昇や物価上昇の影響は大きく、依然として厳しい状況は続いているようです。
本記事では、賃金上昇と物価上昇が進む現状を解説し、病院や介護福祉施設が直面している赤字問題やコスト削減のポイントなどについてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
目次
賃金上昇と物価上昇が進む現状
はじめに、賃金上昇と物価上昇が進む現状を詳しくみていきましょう。

33年ぶり!2024年の平均賃上げ率が5%台へ
政府は以前より経済界に対して賃上げを要請してきましたが、1991年以降の平均賃上げ率は長らく低水準が続いていました。2020年には新型コロナウイルスが世界各地で蔓延。感染対策のため経済活動が鈍化し、賃金上昇への道のりはさらに険しくなりました。しかし、2024年には状況が大きく変化。33年ぶりに平均賃上げ率が5%台を記録したのです。こうした賃金上昇の流れには、次のような背景があります。
賃金上昇の背景①賃上げ促進税制の導入
2022年4月1日、政府は賃上げ促進税制を導入しました。その内容を簡単に説明すると「青色申告書を提出する企業・個人事業主が従業員の賃金を上げた場合、税額控除が適用される」という制度。導入当初は資本金や従業員数が多い大企業向け、それ以外に該当する中小企業向けの二つに区分されました。
令和6 (2024)年度税制改正では、大企業と中小企業の中間に当たる中堅企業の枠を新たに設けており、より活用しやすい環境が整えられています。税額控除が適用されるには、制度内で定められた基準をクリアしなければなりません。とはいえ、税金面で優遇されるメリットは大きく、賃金上昇のきっかけになったと考えられます。
賃金上昇の背景②人手不足の慢性化
総務省統計局が公開している「労働力調査(2024年平均結果)」では、全体の就業率が前年より増加しているものの、製造業、農業・林業、建設業などは減少傾向にあり、業界によって差が出ているようです。
現在の日本は少子化が進み、今後は高齢者が増加していくとみられています。つまり、将来的に若い労働者人口は減るということ。このままでは、どの業界も人手不足の慢性化は避けられません。賃上げを実施する企業が増えたのは、人手確保のためともいえるでしょう。
賃金上昇の背景③物価上昇への対策
物価上昇の傾向が強まったのは、新型コロナウイルスが大流行した2020年ごろから。先に述べた通り、経済活動が鈍化したことで需要と供給のバランスも崩れてしまったのです。2022年にはロシアのウクライナ侵攻がはじまり、エネルギー価格や原材料費などが高騰。さらに円安も続いており、輸入品の価格は大きく上昇しています。
株式会社帝国データバンクが実施した「2024年度の賃金動向に関する企業の意識調査」では、企業が賃金を見直した理由が挙げられています。その結果によると、人手不足を補うことと従業員の生活を支えることに続き、物価上昇も大きなきっかけになっているようです。
病院や介護福祉施設が赤字になる理由
本項目では、独立行政法人福祉医療機構が公開しているデータをもとに、近年における病院や介護福祉施設の赤字問題を解説します。

病院や医療法人の赤字について
一般病院や病院主体の医療法人では、新型コロナウイルスの影響で2020年度の赤字率が増加。2021年度と2022年度はコロナ関連の補助金があったため、赤字率はいったん減少傾向になりました。しかし、補助金の縮小・終了が決定した2023年度の赤字率は、2020年以前を上回る結果に。数値上では一般病院が51.0%、病院主体の医療法人が42.8%となっています。
このように赤字が多くなる要因の一つは、二年ごとに行われる診療報酬改定。人件費や設備費など、あらゆる費用が高騰しているにもかかわらず、医療行為で得られる収益は減っているのです。さらに、少子高齢化によって在宅医療が増えたり、外来・入院患者の数が減ったりしていることも厳しい経営状況の要因となっています。
介護福祉施設の赤字について
社会福祉法人全体を対象とした2023年度の赤字率は、前年度の35.3%より少ない30.5%。介護主体の社会福祉法人のみで集計された赤字率は2022年度が46.6%、2023年度が40.0%となっています。ちなみに、特別養護老人ホームのみを集計した赤字率も減少傾向。従来型・ユニット型それぞれの数値は2022年度が47.8%・34.4%、2023年度が41.7%・30.0%となっています。
一見すると赤字率は減少しており、経営状況が改善されているような印象を受けるかもしれませんが、実は2022年における介護事業所の倒産は前年比76.5%に増加していました。倒産の主な要因は物価上昇や人手不足のほか、実際にかかるコストに対して介護報酬改定が間に合っていないという状況もあるようです。
一方、倒産を免れた事業所や施設は、政府による介護職員処遇改善支援補助金や福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金、電気・ガス価格激変緩和対策事業などの恩恵があったと考えられます。しかしながら、赤字率は高水準で推移しているのです。今後も賃金上昇や物価上昇が続くのであれば、さまざまな課題が生まれ、経営もますます難しくなるといえるでしょう。
給食運営の見直しはコスト削減になる?
前述したように、病院や介護福祉施設の赤字率は高水準のまま推移しています。一般企業のケースなら、「コストが増えた分は価格転嫁して赤字を回避する」という対策を取ることができるでしょう。ところが、病院や介護福祉施設が受け取る報酬のほとんどは公定価格に当たるため、価格転嫁ができないのです。そのため、経営状況を安定させるには各コストの見直しが必須となります。

医薬・材料費は一般的な消耗品のほか、レントゲンフィルムや聴診器など医療行為に必要なものも含まれています。コスト削減のポイントになり得ますが、医療や介護の質を落とさないことが重要です。また、機器や設備、メンテナンスなどの費用を含む減価償却費も同様のことがいえます。人件費は職員のモチベーション低下につながるため、基本的には削減対象外と考えるべきでしょう。
現実的におすすめできる見直しのポイントは、外部委託費やその他の諸費用。清掃・給食・警備・検査など幅広い業務を外部に委託している場合は、見直せるポイントが多いといえます。その他の諸費用は車両・機器等のレンタル費、通信費、広告費など多岐にわたりますが、少しずつでもコストを抑えられる可能性が高いでしょう。
その中でも、給食は直営や委託、配食サービスなど、運営方法の選択肢が多い部門です。病院や介護福祉施設の規模や方針にあわせて最適化することで、大幅なコスト削減ができるかもしれません。
コスト削減の実績あり!ナリコマの直営支援型厨房運営

ナリコマでは、完全調理済み食品をお届けするクックチル方式の献立サービスをご提案しております。一般病院や介護福祉施設には365日日替わりの「すこやか」が最適。栄養バランスがきちんと計算されており、介護食もミキサー食・ゼリー食・ソフト食をご用意しております。再加熱と簡単な仕上げのみで提供できるため、直営でも厨房職員の負担を減らせるのが魅力。業務の効率化だけでなく、コスト削減の実績も多数ございます。給食運営の見直しをお考えの際には、ぜひ一度ナリコマにご相談ください。
コストや人員配置の
シミュレーションをしませんか?
導入前から導入後まで常にお客さまに寄り添うナリコマだからこそ、厨房の視察をしたうえでの最適解をご提案。
食材費、人件費、消耗品費などのコストだけでなく、導入後の人員削減について個別でシミュレーションいたします。
スムーズな導入には早めのシミュレーションがカギとなります。
まずはお問い合わせください。
こちらもおすすめ
委託に関する記事一覧
-
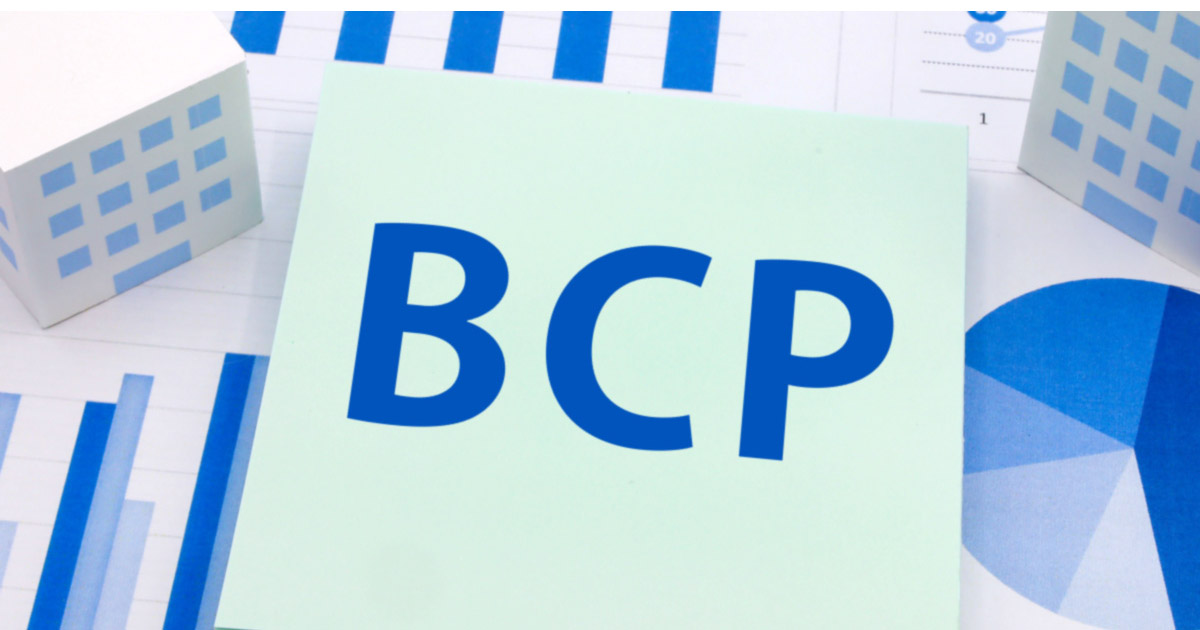
災害と介護研修の取り組み方とは?BCP研修や防災訓練など災害対応教育を強化しよう
災害と介護研修について日頃から考え、対策を練っておくことはとても重要です。この記事では、災害対応教育の重要性を法定研修と共に振り返りながら、介護施設や事業所が行うべきBCP研修や、防災訓練に取り組む際のポイント、給食提供に関する厨房のBCP対策について解説します。
-

介護福祉教育研修制度でスキルアップ!実務者研修や認知症ケア研修等のサポートや実施のコツ
介護福祉教育研修制度の充実は、個々のスタッフのスキルアップを促し、より高度なサービスを提供できる施設運営にも役立ちます。この記事では、介護福祉士になるために必要な研修や、実務者研修の資格講座内容などを改めて振り返りながら、介護資格取得支援制度への取り組みや認知症ケア研修等の法定研修のサポートや実施のコツを解説します。
-

介護施設に適した食事の提供体制とは?外部委託の選定ポイントも紹介
日本は65歳以上の高齢者人口が年々増加しており、2043年には3,953万人でピークを迎えるといわれています。一方、2024年10月1日時点で1億2380万人余の総人口は減少していく見込み。今後は高齢化率が上昇し、2070年には2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になると推測されています。
こうした背景から、近年では介護福祉サービスの需要が高まっています。今回お届けする記事のテーマは、そんな高齢者ケアの拠点となる介護施設の食事。食事の重要性や提供体制について解説し、外部委託業者の選定ポイントなどもあわせてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
コストに関する記事一覧
-

老人ホームの厨房管理費を削減したい!効率の良い厨房運営のコツとは?
物価が上昇している近年、食材費の値上げに伴い給食委託会社の利用料も値上げすることがありますが、食材費だけでなく厨房管理費の値上げも同じく打診される場合があります。こうした給食委託会社からの値上げ要求に対して、厨房管理費が値上げする理由等の疑問などと共に厨房運営でお悩みの施設さまもいらっしゃることでしょう。
この記事では、給食委託会社の料金形態から、厨房管理費が高騰する理由などについて詳しく解説します。老人ホームなどの介護施設の厨房管理費を削減し、より効率の良い厨房運営に切り替えるコツをご紹介しますのでぜひご参考ください。 -

給食業務を委託すると食材費はどうなる?物価高騰を上手に乗り切る方法とは
近年、給食業界はよりいっそう厳しい状況にあるといわれています。その主な要因の一つとされているのが、急速に進む物価高騰です。今回は、そんな物価高騰に対して給食業務をどのように行っていくべきか考えてみましょう。
キーワードは、委託給食と食材費。給食業務の委託サービスについて詳しく紹介し、委託にした場合の食材費がどうなるのか解説します。記事後半では食材費削減のアイデアもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。 -

安い給食委託会社のメリットとデメリットとは
給食コストの上昇は業界全体の課題となっています。少しでも給食コストを抑えるために安い給食委託会社に切り替えを検討している方必見! 安い給食委託会社のコストダウンの仕組みについても紹介しています。