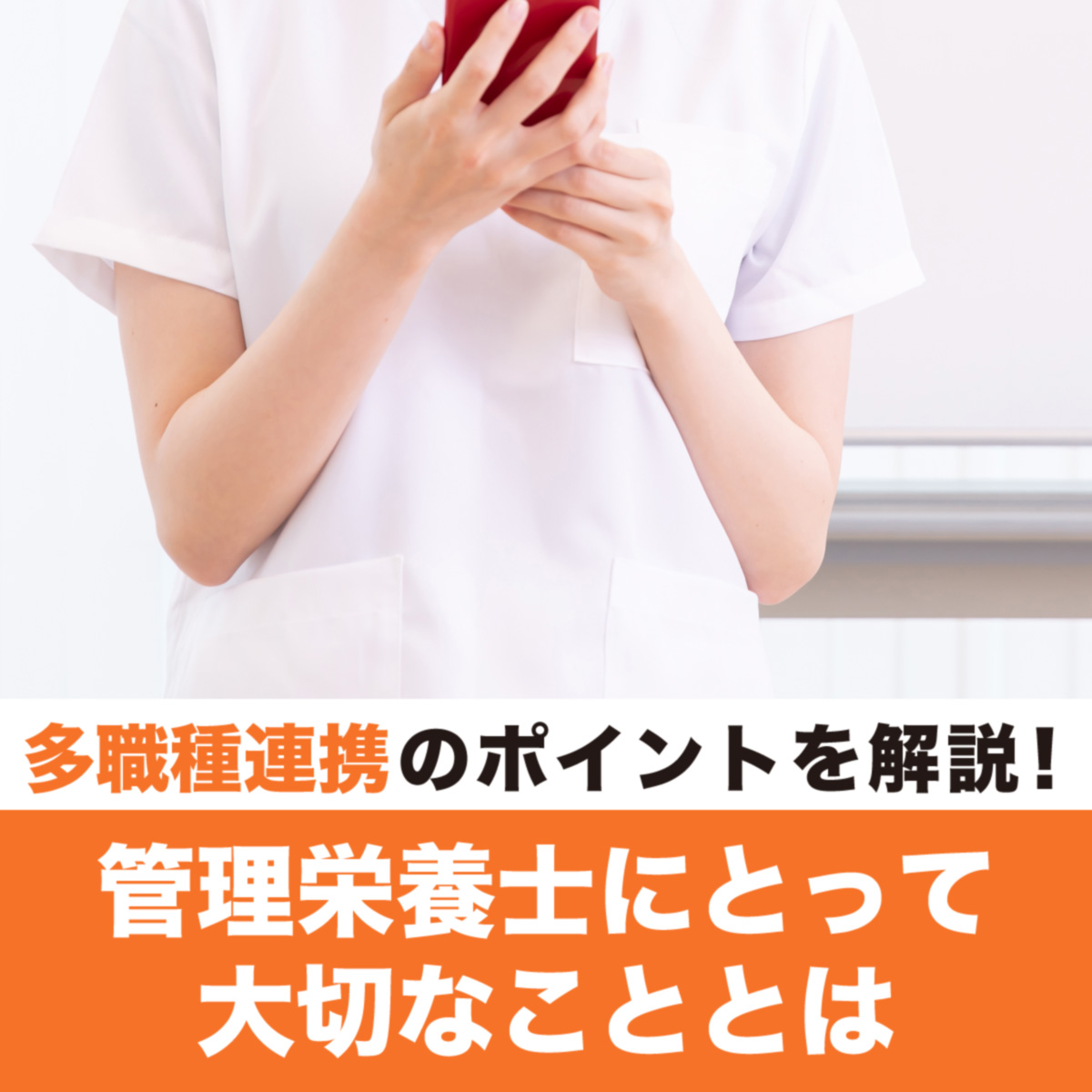多職種連携は、主に医療・介護福祉業界で重視されている取り組みのこと。業務を円滑に進め、患者や利用者をケアする上でとても大切なことだと考えられています。本記事では病院や介護福祉施設で働く管理栄養士に焦点を当て、多職種連携について詳しくお届け。多職種連携の概要や必要性をお伝えし、その中で管理栄養士がどのような役割を担っているのか解説します。
目次
なぜ多職種連携が必要?

多職種連携とは
多職種連携(IPW:Interprofessional Work)は、「複数の専門家が集まり、共通の目標に向けて連携すること」を意味しています。冒頭でお伝えした通り、医療・介護福祉業界では特に大切なこととしての認識が強くなっています。場合によっては、医療・介護福祉以外の専門家が加わることもあるようです。
日本において多職種連携が注目されはじめたのは2000年ごろとのこと。高齢化社会が急速に進む現在は、医療・介護福祉関連のニーズが高まったこともあり、スムーズに連携を行うための教育プログラム(IPE:Interprofessional Education)も充実してきました。
厚生労働省は、医療や介護が必要になった高齢者が住み慣れた地域で自立して生活できるよう、2025年までに地域包括ケアシステムの構築を目指しています。実は、この地域包括ケアシステムにおいても多職種連携が重視されているのです。
多職種連携の必要性
病院や介護福祉施設は、さまざまな職種の専門家が在籍する場所。具体的には医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、管理栄養士、ケアマネジャー、生活相談員といった人たちが働いています。では、なぜ医療・介護福祉業界において多職種連携が必要とされているのでしょうか?
例えば、病院では患者ごとに治療内容が細かく決められています。個人で抱えている疾患が違うのであれば、それは当然のことでしょう。はじめに患者と向き合って診断を下す医師はもちろん、その後のいろいろなケアをする看護師、処方された薬の確認や調合をする薬剤師、リハビリメニューを調整する理学療法士など、患者一人に対して何人もの専門家が関わり、情報を共有しながら最適な治療体制を整えているのです。こうした取り組みはまさに多職種連携の代表例であり、チーム医療と呼ばれることもあります。
介護福祉施設でも同様に、利用者一人ひとりの健康状態や事情が異なります。だからこそ、職員同士の情報共有は必須。高齢者なら咀嚼・嚥下機能や認知機能が低下していたり、日常的な動作に不安があったりする人もいて、個別で対応しなくてはならないこともあるでしょう。障がい者であれば、どのような不自由があり、どうサポートするのがいいのかという情報がとても重要です。
こうした事情を踏まえると、病院も介護福祉施設も、患者や利用者にとって最善のケアをするためには多職種連携が欠かせません。もし連携ができていなければ、患者の状態が悪化したり、利用者がケガをしたりといったトラブルにつながってしまう可能性もあるのです。多職種連携は医療・介護福祉において生産性・質の向上というメリットをもたらしますが、それだけでなく、結果的に患者や利用者の満足度アップにも貢献しているといえるのではないでしょうか。
多職種連携における管理栄養士の役割
本項目では、病院や介護福祉施設で働く管理栄養士に焦点を当てます。各施設での多職種連携において、管理栄養士がどのような役割を担っているのか詳しくみてみましょう。

病院で働く管理栄養士の役割
病院で働く管理栄養士の多くは、チーム医療の一員として業務を行います。環境は病院によって異なりますが、連携をとるべき職種が医師や看護師だけでなく、かなり多いケースもあるようです。管理栄養士の主な役割は、患者を対象とした食事提供と栄養管理。食事は医療の一環として扱われ、栄養状態の改善によって回復を図る目的があります。
病院の診療科目や規模にかかわらず、食事の区分は大きく分けて一般食と特別治療食の二つ。一般食は栄養面で特別な制限がない患者向けで、常食のほかに、軟菜食やおかゆ、流動食なども含まれます。一方の特別治療食は、疾患にあわせてさまざまな調整が必要な患者向け。治療内容にあわせて摂取カロリー、塩分、たんぱく質、脂質などを調整するほか、嚥下訓練中の患者にはゼリー食やペースト食を提供することもあります。
管理栄養士は、診断を下した医師の指示に沿って献立を作成。看護師が記入するカルテで食事の摂取状況などを確認するだけでなく、病棟の患者と面談する場合もあります。間違いが起こらないようにするのはもちろん、状況が変われば食事内容や栄養バランスも見直すことになるので、周りとの連携は迅速かつ確実に行わなければなりません。
介護福祉施設で働く管理栄養士の役割
介護福祉施設で働く管理栄養士は、利用者である高齢者や障がい者を対象に業務を行います。病院と同様、主な役割は食事提供と栄養管理。介護福祉士や看護師などと連携し、利用者それぞれの栄養ケア計画を立て、献立作成を進めます。介護福祉施設での食事は、病院のように医療の一環として扱われるわけではありません。健康維持に必要な栄養をとってもらったり、毎日過ごす中で楽しみを感じてもらったりする意味合いが強くなります。
基本となる食事の種類は、食に関する問題がない人向けの常食と、咀嚼・嚥下機能が低下している人向けの介護食。治療中の疾患がある人には、医療機関からの情報をもとに摂取カロリーや栄養成分などを調整した献立を作成します。介護食は「ユニバーサルデザインフード」の区分1〜4、もしくは「スマイルケア食」の赤0〜2・黄色2〜5・青に該当するもの。それぞれ、かみやすさや飲み込みやすさの目安に従って分類されています。
管理栄養士はこうした介護食の基準も考慮していますが、食事介助を担当する職員から「食べにくそう」「あまり好みではなさそう」といった意見を聞けば、献立内容を再検討する必要もあります。利用者に充実した時間を過ごしてもらうために、管理栄養士は周りと密に連携し、臨機応変な対応をしなければならないのです。
多職種連携をする管理栄養士にとって大切なこと

多職種連携をする管理栄養士にとって、大切なことがいくつかあります。最も重要なのはコミュニケーション。相手がどんな職種でも、きちんと話せる関係でなければ、うまく連携ができません。まずは意識的に挨拶をするだけでも、相手に歩み寄る姿勢が伝わるでしょう。
また、ほかの職種に対する理解も大切なことの一つ。専門外の職種について完璧に理解している人はあまり多くないかもしれません。相手がどんな仕事をしているのか、どんなことで苦労しているのか、いろいろと知っていくと日頃のコミュニケーションもスムーズになるはずです。
そして、管理栄養士の立場で意見を述べる際には、異なる職種の人が理解しやすいように伝えることも大事。質問されたら丁寧に説明し、反対に相手の話でわからないことがあれば、まとめて質問するように心がけましょう。
栄養管理をしっかりサポート!ナリコマの献立サービス
病院や介護福祉施設で働く管理栄養士は、自身の幅広い業務に加え、多職種連携をうまく機能させなくてはなりません。ナリコマでは、そんな管理栄養士の業務負担を軽減する献立サービスをご提案しております。

病院や介護福祉施設におすすめしたいのは、栄養バランスのとれた365日日替わりの献立をお届けする「すこやか」です。もちろん、介護食や治療食への展開も可能。ご利用中の施設さまからは、日々の業務を効率化できるとの声もいただいております。ご興味がありましたら、ぜひ一度ナリコマにご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
委託に関する記事一覧
-
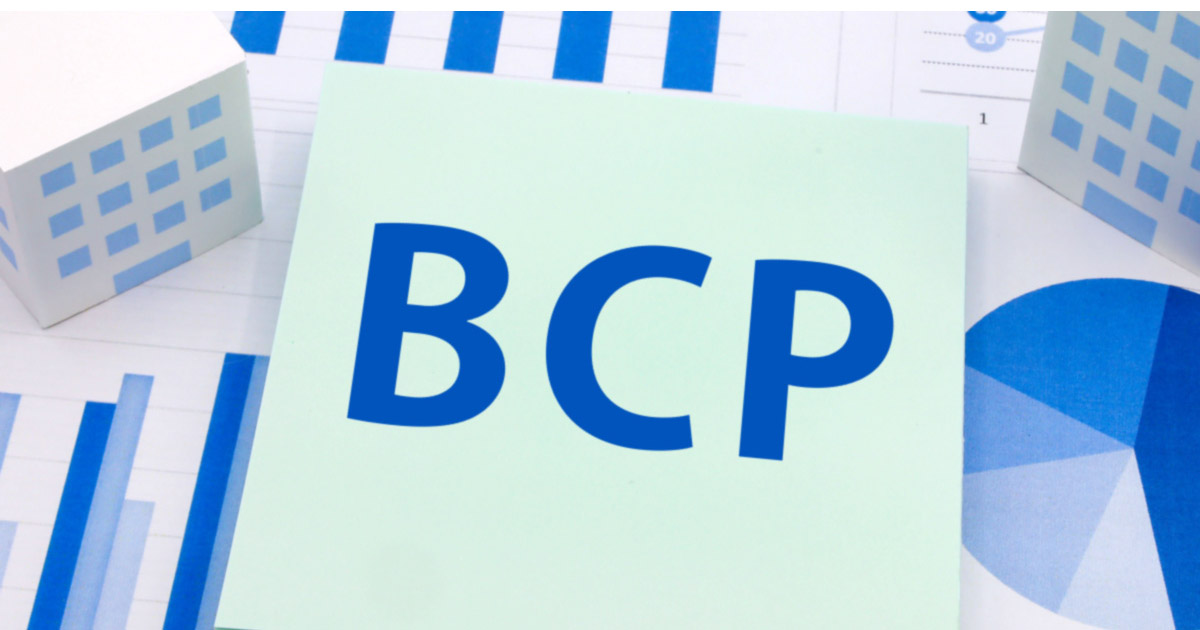
災害と介護研修の取り組み方とは?BCP研修や防災訓練など災害対応教育を強化しよう
災害と介護研修について日頃から考え、対策を練っておくことはとても重要です。この記事では、災害対応教育の重要性を法定研修と共に振り返りながら、介護施設や事業所が行うべきBCP研修や、防災訓練に取り組む際のポイント、給食提供に関する厨房のBCP対策について解説します。
-

介護福祉教育研修制度でスキルアップ!実務者研修や認知症ケア研修等のサポートや実施のコツ
介護福祉教育研修制度の充実は、個々のスタッフのスキルアップを促し、より高度なサービスを提供できる施設運営にも役立ちます。この記事では、介護福祉士になるために必要な研修や、実務者研修の資格講座内容などを改めて振り返りながら、介護資格取得支援制度への取り組みや認知症ケア研修等の法定研修のサポートや実施のコツを解説します。
-

介護施設に適した食事の提供体制とは?外部委託の選定ポイントも紹介
日本は65歳以上の高齢者人口が年々増加しており、2043年には3,953万人でピークを迎えるといわれています。一方、2024年10月1日時点で1億2380万人余の総人口は減少していく見込み。今後は高齢化率が上昇し、2070年には2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になると推測されています。
こうした背景から、近年では介護福祉サービスの需要が高まっています。今回お届けする記事のテーマは、そんな高齢者ケアの拠点となる介護施設の食事。食事の重要性や提供体制について解説し、外部委託業者の選定ポイントなどもあわせてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
人材不足に関する記事一覧
-

その知識もう古いかも?アンラーニングで働き方をアップデート!
今の働き方にモヤモヤしているなら、まずは「忘れること」からはじめてみませんか?
日々の業務に追われながら、「このやり方でいいのか?」「もっと柔軟に働けないのか?」などと感じたことはありませんか?これまで培ってきた経験や知識は、確かにあなたの武器ですが、それが時として変化を受け入れにくくする足枷になることもあります。変化の激しい今の時代に求められるのは、ただのスキルアップではなく、「一度手放す」という選択。そこで注目されているのが「アンラーニング」という考え方です。
今回はアンラーニングの意味や必要性をわかりやすく解説し、リスキリングとの違いやビジネススキルの向上に役立つ実践事例も紹介していきます。働き方やキャリアのあり方を見直したいと感じているあなたに、きっと役立つヒントが見つかるはずです。 -

今後どうなる?給食業界の課題と将来性を詳しく解説
給食は、保育所や学校、病院、老人ホームといったさまざまな施設で提供されています。施設を利用する人々にとって、給食は健やかな生活を送るために欠かせないものでしょう。ところが、その一方で、現在の給食業界は大きな課題をいくつも抱えています。
今回の記事で取り上げるテーマは、給食業界の将来性。近年における業界の動向や解決すべき課題を挙げ、今後の展望について解説します。ぜひ、最後までお読みになってください。
-

育成就労制度とは?技能実習制度の制度変更による違いや特徴を解説
「育成就労制度」は、2024年に創設され3年以内に施行される制度です。この記事では、旧制度である「技能実習制度」の概要や課題を振り返りながら、制度変更によりどう変わるのかを、育成就労制度の特徴や受け入れ企業の実務のポイントも押さえながら解説します。