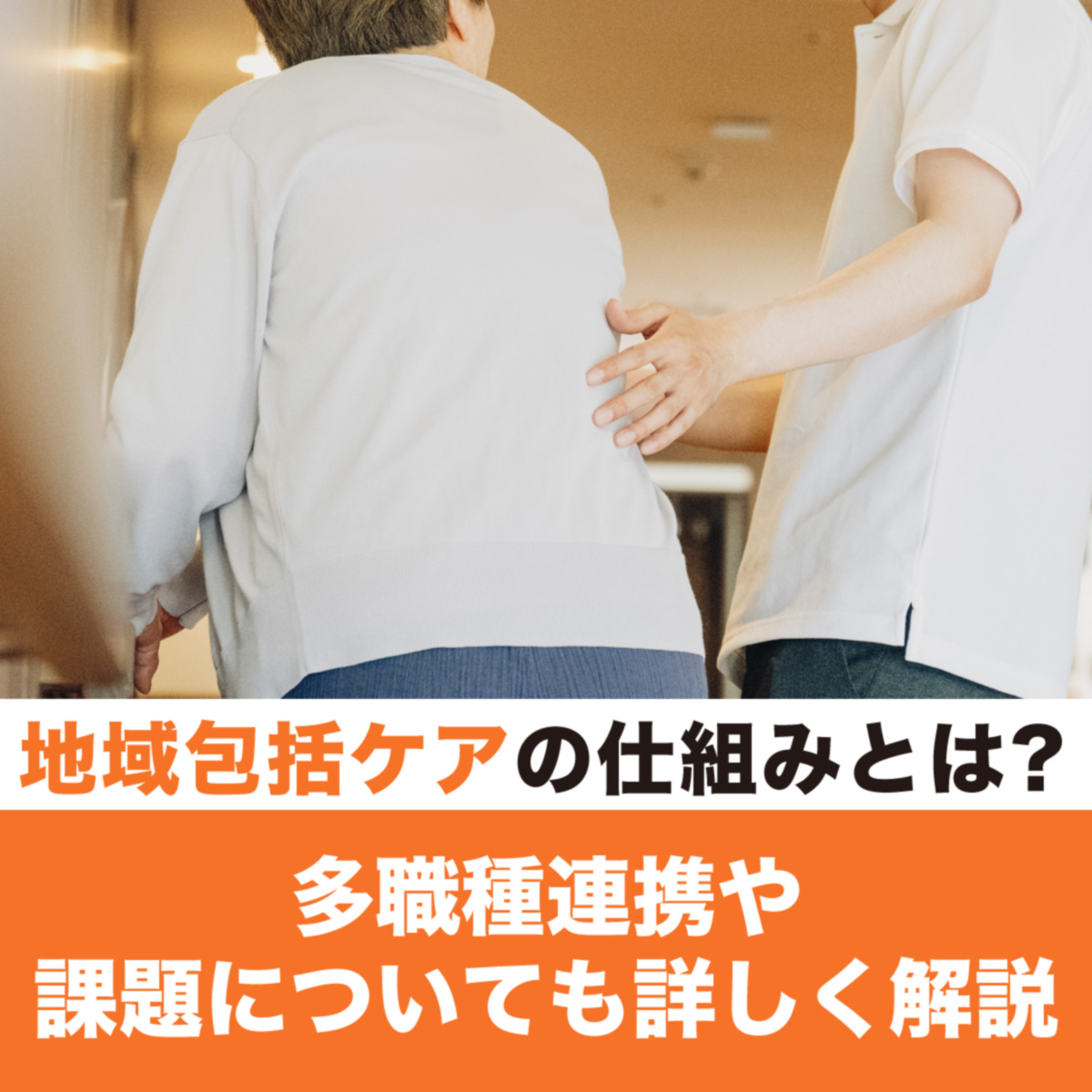日本は将来的に高齢者が激増するといわれています。そんな高齢化社会を支える医療・介護・福祉のあり方として推進されているのが「地域包括ケア」というシステムです。本記事では、地域包括ケアの基本的な仕組みについて詳しくお伝えします。また、その中で重要視される多職種連携や、今後の課題や対策についても解説。ぜひ最後までお読みください。
目次
地域包括ケアとは

冒頭で少しお伝えしましたが、日本は高齢化社会が急速に進んでいます。内閣府が公表した「令和6年版 高齢社会白書」によると、令和5(2023)年10月1日時点における65歳以上の人口は総人口の29.1%。この割合は今後も増加し、令和22(2040)年には34.8%、令和52(2070)年には38.7%になるとみられています。その一方、出生数は減少しており、高齢化と同時に少子化も進んでいるのが現状です。
ところが、このままでは人手不足の深刻化、社会保障制度の破綻、単身高齢者の孤立といった重大な問題が生じるといわれています。特に、高齢者からのニーズが高い医療・介護・福祉業界は、従来通りの対応ができなくなる可能性も指摘されています。そういった問題に対処するために厚生労働省が医療・介護・福祉のあり方を見直し、新たに提唱したのが地域包括ケアなのです。
地域包括ケアで求められているのは、「医療や介護が必要な状態になっても、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した生活を続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制」です。これを実現するため、自治体、病院、介護福祉施設などが連携するシステムの構築が必要とされています。
ただし、そのシステムをうまく機能させるには、次に挙げる「自助」「互助」「共助」「公助」も重要です。
・自助:高齢者が自発的に生活を管理し、問題を解決すること
・互助:家族や友人、趣味の仲間などでお互いに助け合うこと
・共助:介護保険や年金など、被保険者が費用を負担する社会保障制度のこと
・公助:公金によって賄われる福祉事業や生活支援のこと
上記からわかるように、多角的な視点でサポートを行うのが地域包括ケアの基本となります。
高齢者の希望を叶える役割も
内閣府が実施した「令和2年度 第9回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果」では、「身体機能が低下して車いすや介助者が必要になった場合、自宅に留まりたいか、どこかへ引っ越したいか」という問いかけがありました。
60歳以上の調査対象者1,367人の回答を見ると、「現在のまま、自宅に留まりたい」が37.5%、「改築の上、自宅に留まりたい」が21.6%。全体のうち60%近くが自宅で過ごすことを希望しています。地域包括ケアには、こうした高齢者の希望も叶える役割もあるのです。
地域包括ケアを支える5つの柱
地域包括ケアを支える柱となるのは「介護」「医療」「予防」「住まい」「生活支援」という5つの要素です。これらが相互的に関わり、適切な連携をとることで、高齢者の健やかな生活をサポートできるようになります。各要素について、もう少し詳しくみていきましょう。

①介護
「介護」には2種類のサービスがあります。一つは、自宅で過ごす高齢者を支援する訪問看護や訪問介護などの在宅系介護サービス。もう一つは、特別養護老人ホームや介護療養型医療施設、小規模多機能型居宅介護などの施設・居住系介護サービスです。高齢者の状態や環境にあわせてサービスを選び、利用することができます。
②医療
「医療」は、普段の健康管理から緊急時の診察までカバーします。日常的な診察を行うかかりつけ医や地域の連携病院、急な疾患や大怪我などの診察を行う急性期病院、リハビリテーション専門の病院などがあります。各医療機関の連携がとれていれば、在宅と入院の切り替えもスムーズです。
③予防
「予防」は、要介護状態にならないための対策をとり、健やかな心身を維持することが目的です。自治体などが運営する介護予防サービスのほか、ボランティア団体による見守り活動なども含まれます。高齢者自身が地域交流・社会参加に加わることも予防の一環として考えられており、要介護者の支援を手伝うケースもあります。
④住まい
「住まい」には自宅以外に介護サービスを提供する施設なども含まれ、高齢者が生活するスペース全体を指します。プライバシーや尊厳を守りつつ、本人の希望や経済力に適合した住まいを確保することが重要です。賃貸契約を行う場合は、保証人の手配や各種手続きも支援します。
⑤生活支援
「生活支援」は、要介護と認定された高齢者の生活に対する支援を指します。専門的な知識は不要ですが、高齢者が安心・安全に過ごせるよう、買い物支援や見守りをすることが大切です。自治体やNPO法人はもちろん、ボランティア団体や地域住民も取り組みやすい部分だといえます。
地域包括ケアにおける多職種連携の重要性
多職種連携は、医療・介護・福祉など分野の異なる専門職が協力体制を築くことです。専門的な知識やスキルを発揮しながら連携をとることで、業務全体の効率がアップ。さらに、医療や介護、各種サービスの質を向上させる目的があります。

高齢者を多角的にサポートする地域包括ケアのシステムでは、この多職種連携が特に重要と考えられています。連携がスムーズになれば、良質かつ適切なケアができるのはもちろん、高齢者やその家族に安心感を与えるというメリットもあるのです。
また、医療・介護・福祉関連の業務に携わる人たちにとっても、プラスになることがあります。自分にはなじみがない職種の人とコミュニケーションをとったり、意見交換を行ったりすることで、新たな成長が期待できるでしょう。
地域包括ケアの課題と対策
最後に、地域包括ケアにおける今後の課題と対策をまとめました。

課題①地域包括ケアの認知度が低い
現在、地域包括ケアの認知度は決して高いとはいえません。システムをしっかりと機能させるには、医療・介護・福祉関係の従事者以外に、地域住民の理解や協力も必要でしょう。つまり、地域包括ケアの仕組みを国民全員が知ることで、よりいっそう機能しやすくなるということ。正しく理解してもらうためにも、運用元である自治体や関連施設などが率先して広めていくことが重要なのです。
課題②地域による格差が生じやすい
地域包括ケアのシステムを運用するのは自治体です。だからこそ、自治体によっては財源が確保できなかったり、サポート体制が十分に整わなかったりすることもあります。この場合、高齢者とその家族がより快適に暮らせる地域へ移住する可能性があり、急激に過疎化する地域が出てくるかもしれません。対策として、公的支援の範囲拡大、民間企業との連携などが考えられます。また、システム運用の参考になるよう、自治体同士で取り組みの事例を共有することも大切です。
課題③連携のための人材が足りない
地域包括ケアのシステムには、各分野の垣根を越え、連携しやすい体制を整える人材が必要です。しかし、医療・介護・福祉の現場はもともと人手が集まりにくい傾向にあります。積極的に採用や育成を進めていくのはもちろん、高齢者を再雇用して人材不足を解消するのも対策の一つです。高齢者の雇用は、前述した介護予防の効果も期待できます。
栄養管理も簡単!ナリコマの献立サービス

ナリコマでは、地域包括ケアの一端を担う病院や介護福祉施設に最適な献立サービスを提供しています。時間のかかる献立作成や栄養管理も含まれており、専門のアドバイザーが幅広くサポート。再加熱と簡単な盛り付けだけで提供できるクックチル方式のため、人手不足でお悩みの現場にもおすすめです。詳細は、お気軽にナリコマへお問い合わせください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
委託に関する記事一覧
-
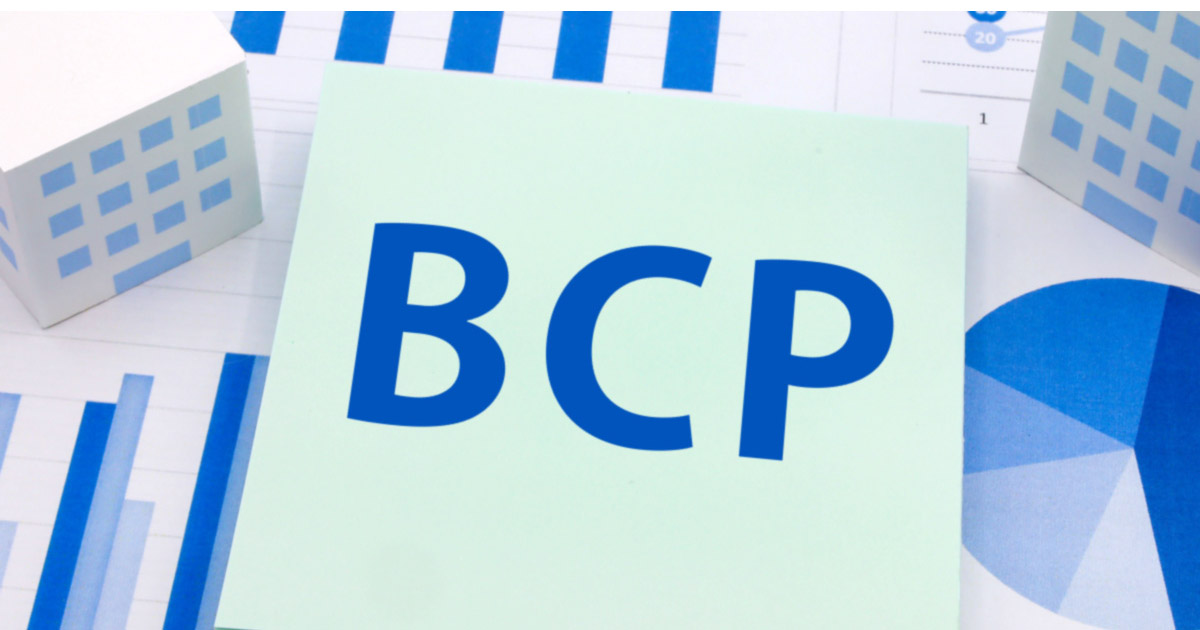
災害と介護研修の取り組み方とは?BCP研修や防災訓練など災害対応教育を強化しよう
災害と介護研修について日頃から考え、対策を練っておくことはとても重要です。この記事では、災害対応教育の重要性を法定研修と共に振り返りながら、介護施設や事業所が行うべきBCP研修や、防災訓練に取り組む際のポイント、給食提供に関する厨房のBCP対策について解説します。
-

介護福祉教育研修制度でスキルアップ!実務者研修や認知症ケア研修等のサポートや実施のコツ
介護福祉教育研修制度の充実は、個々のスタッフのスキルアップを促し、より高度なサービスを提供できる施設運営にも役立ちます。この記事では、介護福祉士になるために必要な研修や、実務者研修の資格講座内容などを改めて振り返りながら、介護資格取得支援制度への取り組みや認知症ケア研修等の法定研修のサポートや実施のコツを解説します。
-

介護施設に適した食事の提供体制とは?外部委託の選定ポイントも紹介
日本は65歳以上の高齢者人口が年々増加しており、2043年には3,953万人でピークを迎えるといわれています。一方、2024年10月1日時点で1億2380万人余の総人口は減少していく見込み。今後は高齢化率が上昇し、2070年には2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になると推測されています。
こうした背景から、近年では介護福祉サービスの需要が高まっています。今回お届けする記事のテーマは、そんな高齢者ケアの拠点となる介護施設の食事。食事の重要性や提供体制について解説し、外部委託業者の選定ポイントなどもあわせてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
人材不足に関する記事一覧
-

給食委託費に含まれるものとは?直営と委託の違いやコスト削減のコツを解説
厨房運営で大きな課題となるのがコスト問題です。直営から委託に切り替えただけでは上手く改善できないケースも見られ、解決が難しい問題となっています。給食委託費としてくくられるコストには、様々な費用が含まれています。そこで今回は、給食運営の直営と委託の違いを改めて振り返りながら、給食委託費に含まれるものの内訳や給食委託費を削減する見直しのポイント、さらなるコスト削減に向けて給食運営をもっとシンプルにするコツを解説します。
-

介護施設の法改正|まず何をすべき?対応フローと教育の進め方ガイド
介護施設の運営において、法改正への対応は避けては通れません。近年は高齢化社会の進行や働き方改革の影響により、介護保険制度や労働関連法の改正が相次いでいます。現場では「まず何から取り組めばいいのか分からない…」という声も少なくありません。
今回は、介護施設に関係する主な法改正のポイントをわかりやすく整理し、法改正の対応になにを優先したらいいのかや、対応をスムーズに進めるためのフロー、職員への伝え方をご紹介します。 -

法改正で改革が進む医療現場!課題多き厨房業務の負担軽減策とは
医療現場はこれまでも数多くの課題と向き合ってきましたが、今後はさらに過酷な状況となる可能性が指摘されています。本記事では近年における医療現場の状況を解説し、政府が推進する医療制度改革の一部をご紹介。また、病院の業務改善において注目される厨房にも焦点を当て、課題や負担軽減策などをまとめてお伝えします。ぜひ最後までお読みください。