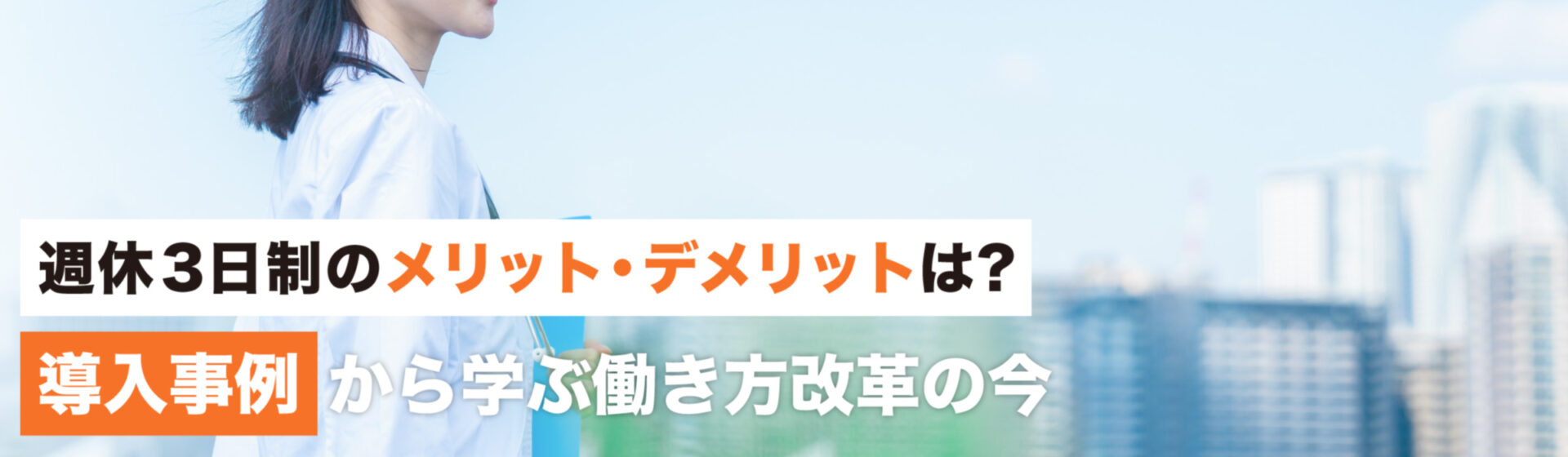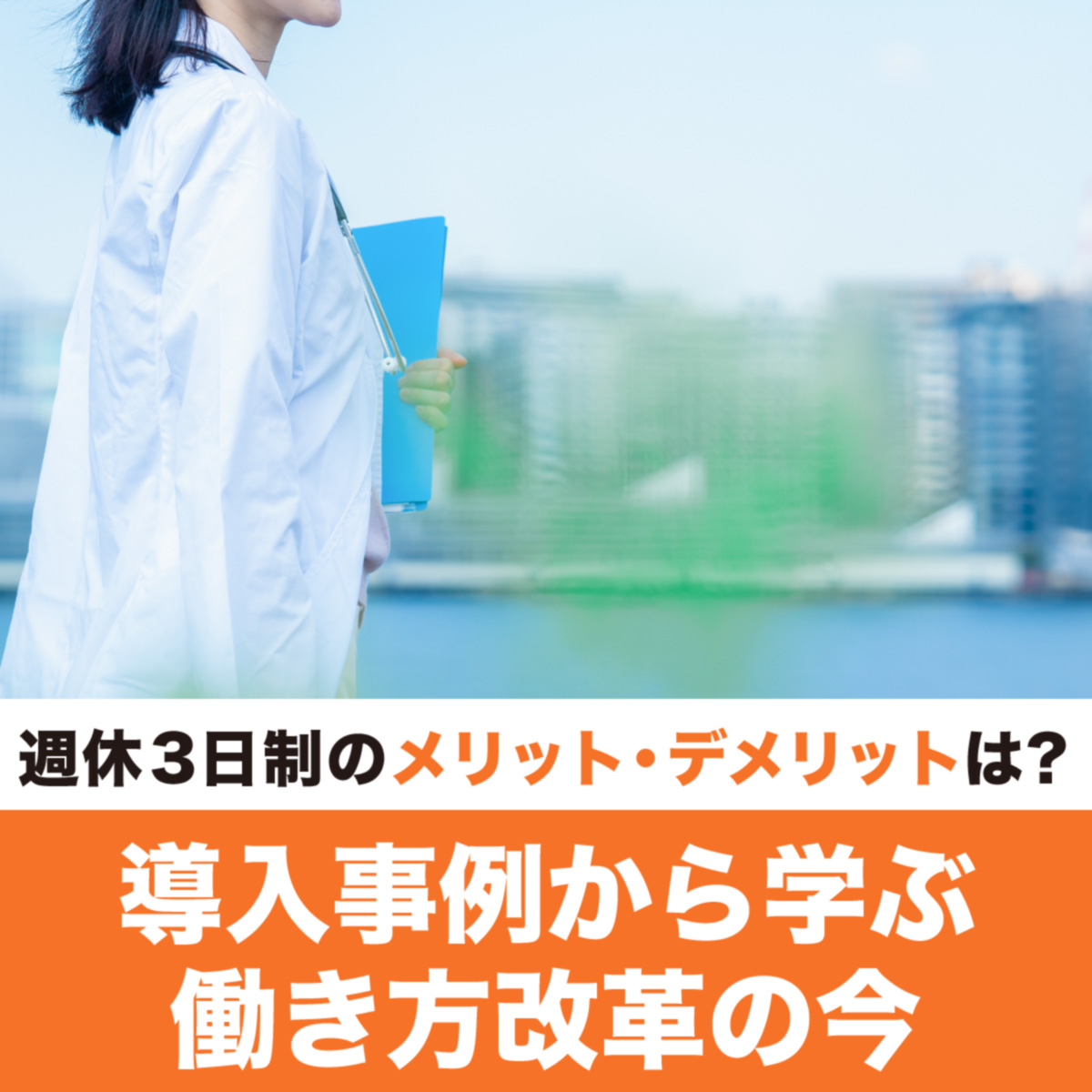週休3日制とは、週に4日間勤務し3日間を休日とする働き方です。「経済財政運営と改革の基本方針」においても、選択的週休3日制の導入と普及の促進が明記されました。週休3日制は従来の週休2日制とくらべると、働く人のライフスタイルに寄り添った柔軟な制度として注目されています。2025年からは東京都も独自に導入を開始し、子育てや介護といった個別の事情を抱える職員でも働き続けられるよう、働き方の選択肢を増やす取り組みが進められています。
今回は、週休3日制の基本から導入のポイント、現場でのメリット・デメリットまで詳しく解説します。
目次
週休3日制とは?新しい働き方が注目される理由

週休3日制には 次の3種類があります。
・労働時間・給与を維持する「総労働時間維持型」
・労働時間・給与を削減する「給与減額型」
・労働時間は削減・給与は維持する「給与維持型」
週休3日制は企業側にとっても、悩みのタネである離職防止や人材確保にも有効な手段とされており、今後さらに広がっていく可能性があります。週休3日制のメリットとデメリットにはどんなものがあるか、一緒に確認していきましょう。
週休3日制のメリット
労働者側のメリット
週に1日多くの休みを確保できるため、心身のリフレッシュがしやすくなります。仕事とプライベートの両立ができ、内閣府が掲げる「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」の実現もしやすくなるでしょう。
また、空いた時間を使って資格取得や学び直し(リスキリング)に取り組むこともできるため、キャリアアップの後押しにもつながっています。週休3日制によって生まれた時間を有効に使い、仕事に対するモチベーションを維持できます。
企業側のメリット
柔軟な働き方を導入することで、子育て世代や副業希望者など、多様な人材を受け入れやすくなります。業務の効率化を進めるきっかけにもなり、生産性の向上につながるケースもあります。また、従業員満足度の向上は定着率の改善を後押ししてくれるでしょう。
週休3日制のデメリット
労働者側のデメリット
週の勤務日数が減るために、給与が減額されてしまう場合があります。また、短い勤務日数の中で業務をこなす必要があるため、1日の作業量が増してしまうことも考えられます。勤怠管理も複雑となり、導入時には混乱することも。
ただし、企業によっては「給与はそのままで週休3日制」を実現している例もあります。詳しくは企業事例の項でお伝えしますが、社内制度によってはこうした懸念を払拭することも可能です。
企業側のデメリット
人員配置やシフト調整が難しくなることが大きな課題となります。特に、サービス業や医療・介護業界など、常に人手が必要な職場の場合、週休3日制に対応するための業務見直しやICT導入が必要です。また、週休3日制を円滑に機能させるためには、導入前の準備と定期的な見直しも欠かせません。
週休3日制の企業事例
実際に週休3日制を導入している企業や自治体の事例を見ると、その運用方法や目的はさまざまです。ここでは、民間企業の代表例であるZOZO、国家・地方公務員の取り組み、そして介護・医療業界での導入事例を紹介します。

週休3日制導入企業の取り組み事例
ZOZO
ファッション通販大手のZOZOでは、2021年から一部部署で「給与が減らない週休3日制」を導入しています。出勤日の労働時間を1日10時間に延ばすことで、週の総労働時間は週休2日制と同じ。半年ごとに利用申告ができ、誰でも自由に選択可能です。
また、制度を選ぶ社員とそうでない社員が混在しても業務に支障が出ないよう、勤務日程の共有や、休日中の業務連絡を避けるなど、柔軟に運用されています。
公務員の場合
国家公務員
政府は働き方改革の一環として、国家公務員にも選択的週休3日制の導入を進めています。従来は育児や介護をしている職員に限定されていた制度でしたが、見直しにより誰でも利用できるようになりました。条件は、週の総労働時間を維持すること。出勤日の労働時間を延ばすことで、1日多くの休みを取得できる形です。
地方公務員
朝日新聞の調査によると、47都道府県のうち、週休3日制をすでに導入しているのは茨城県・千葉県・兵庫県・大阪府・奈良県の5府県。さらに、岩手県・秋田県・群馬県・埼玉県・長野県・鳥取県では導入準備が進められており、東京都は2025年4月から、宮城県は2025年度中、愛知県は2026年1月から導入予定です。全国で16都府県が週休3日制の実現に向けて動いており、地方自治体でも柔軟な働き方への意識が高まっています。
介護・医療業界での事例
介護保険サービスや障害福祉サービスを提供する企業でも、週休3日制の導入が進んでいます。宮城県のある介護事業所では、2017年から働き方改革に着手し、2022年より選択的週休3日制を導入しました。この制度は、総労働時間と給与を維持する形で運用されており、従業員は希望に応じていつでも勤務体系を変更できます。
この事業所では、全体の約8割の職員が週休3日制を選択しており、制度の定着度も高いのが特徴です。さらに、ICT化の推進により、記録書類の手書き作業をなくし、見守り機器の導入によって業務負担も軽減。こうした取り組みは、職員の働きやすさを高めるだけでなく、利用者へのサービスの質の向上にもつながっています。
週休3日制の導入方法と注意点

週休3日制は、柔軟な働き方を実現する手段の一つですが、導入には段階的な準備と明確な目的設定が求められます。厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」によると、週休3日以上を導入済みの企業の割合は7.5%にとどまっており、実際の導入は慎重に進める必要があります。
福島県が発行した「週休3日制導入の手引き」では、介護施設における週休3日制の導入について、下記のように示しています。
自施設が導入に適しているかを確認する
・正職員の比率が高い
・施設規模が大きい(ある程度の職員数がいる)
・夜勤や短時間勤務のある職員が、週5日勤務を基本としている
・介護主任やユニットリーダーなどリーダー的職員が導入に前向き
これらの条件が揃っていれば、制度導入に向けた下地は十分といえるでしょう。
導入目的を明確にする
人材確保や離職防止、職員のワークライフバランス向上など、週休3日制の導入によって解決したい課題を明確にしておきます。
スタッフへのアンケート調査
職員の中に制度導入に消極的な人がいないか、実施前にアンケート等で意見を把握しておくことが重要です。消極的なスタッフには面談を行うなど、現場の声を取り入れながら進めます。
業務プログラムの見直し
週の勤務日数が減っても業務が滞らないよう、業務の整理・分担を見直す必要があります。ICTの導入も効率化に役立ちます。
給食業務の場合には、クックチル(完全調理済み食品)などを活用することで、業務の負担軽減に役立ちます。
モデルシフトの作成
制度導入後の働き方をシミュレーションするため、仮のシフト表を作成し、課題を事前に把握しておきます。
対象職員との面談・説明
対象となる職員には、制度の概要、メリット・デメリットを個別に説明し、納得したうえで導入できるように配慮します。
就業規則と給与体系の変更
制度導入には、就業規則の変更が必須です。特に該当職員の給与体系も見直す必要があります。
週休3日制には「週休3日制とは?新しい働き方が注目される理由」の項目で説明したように3タイプがありますが、どの型を採用するか決める必要があります。たとえば、総労働時間維持型では1日の労働時間が法定の8時間を超えてしまうため、フレックスタイム制などの適用が不可欠となり、就業規則等の変更も必要です。
また、注意点として、給付金や保険料への影響も考慮しなくてはならないことが挙げられます。賃金が下がる形で制度を導入する場合、毎月支払う雇用保険料や、失業時の求職者給付、育児・介護休業給付金などが減額されるケースもあります。導入前に、制度変更がもたらす影響を確認、周知しておくことが大切です。
クックチルで働き方改革をサポート
週休3日制の導入にあたっては、就業規則の見直しやシフト調整、業務の再編成など、多くの準備が必要です。特に介護や給食の現場では、「職員が減っても業務を回せる仕組みづくり」がカギとなります。

そこで注目したいのが、ナリコマのクックチルです。
調理の負担を大幅に減らせるクックチルは、厨房業務の省力化に直結し、人手不足の現場でも品の高い食事提供を実現します。さらに、調理時間の分散や業務の効率化によって、シフトの柔軟化が進みやすくなり、週休3日制のような新しい働き方への移行も現実的になるでしょう。
週休3日制を進めたいけれど、「人手が足りない」「今の業務体制では難しい」とお悩みの施設こそ、まずはクックチルの導入から始めてみませんか?
週休3日制を「理想」で終わらせないために、今こそ、現場の仕組みそのものを見直すチャンスです。働き方改革は、待っていても始まりません。
週休3日制の実現を、クックチルでサポート。
現場のゆとりと、スタッフの働きやすさを両立する取り組みをぜひご検討ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
委託に関する記事一覧
-

介護施設に適した食事の提供体制とは?外部委託の選定ポイントも紹介
日本は65歳以上の高齢者人口が年々増加しており、2043年には3,953万人でピークを迎えるといわれています。一方、2024年10月1日時点で1億2380万人余の総人口は減少していく見込み。今後は高齢化率が上昇し、2070年には2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になると推測されています。
こうした背景から、近年では介護福祉サービスの需要が高まっています。今回お届けする記事のテーマは、そんな高齢者ケアの拠点となる介護施設の食事。食事の重要性や提供体制について解説し、外部委託業者の選定ポイントなどもあわせてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。 -

給食委託会社切り替え時に必要なものって?
施設給食に対する悩みが増えてきたら、それは給食委託会社の切り替え時かもしれません。
委託会社切り替えのメリットやデメリット、次の給食会社を選ぶ際に確認しておきたいポイントもご紹介!
給食委託会社以外の運営方式「直営支援方式」についても解説しています。 -

介護福祉教育研修制度でスキルアップ!実務者研修や認知症ケア研修等のサポートや実施のコツ
介護福祉教育研修制度の充実は、個々のスタッフのスキルアップを促し、より高度なサービスを提供できる施設運営にも役立ちます。この記事では、介護福祉士になるために必要な研修や、実務者研修の資格講座内容などを改めて振り返りながら、介護資格取得支援制度への取り組みや認知症ケア研修等の法定研修のサポートや実施のコツを解説します。