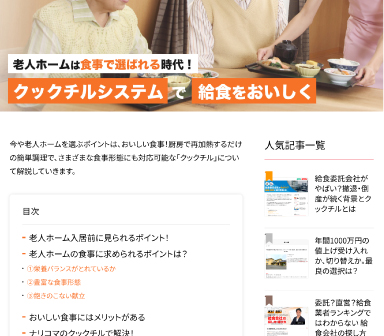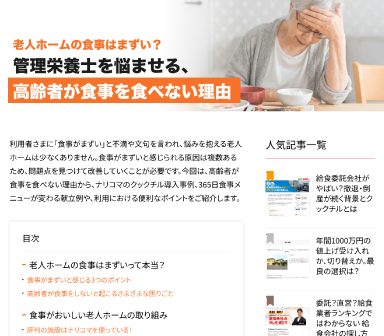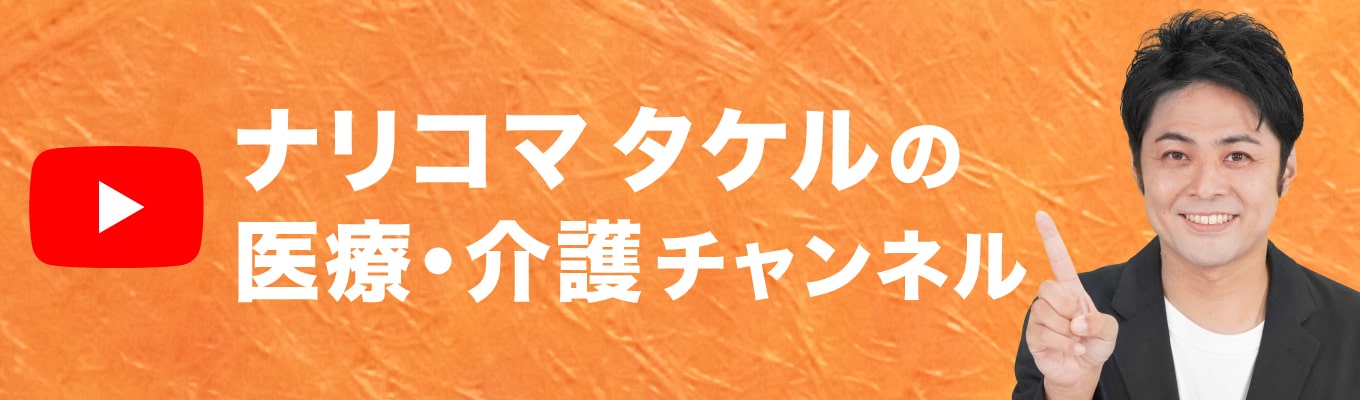現在、給食委託は病院や学校などをはじめとする多くの施設で利用されています。
特別養護老人ホーム(以下、特養)もそのうちの一つで、超高齢社会が進む近年は需要が増加。今回の記事は、そんな特養の給食委託についてお届けします。
特養に最適な給食委託会社の選び方をポイント別に解説。
後半では、給食委託以外の選択肢についてもお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、ご参考になさってください。
目次
特養の給食では何が求められるか
特養は在宅生活が難しい高齢者向けの介護施設で、正式名称を介護老人福祉施設といいます。原則として要介護3以上の認定を受けた高齢者が対象。入浴や食事といった日常生活に関する介護のほか、健康管理や機能訓練なども行っています。ちなみに、“特別”が付かない養護老人ホームは身体的に自立した高齢者が対象。環境的・経済的に在宅生活が難しくなった高齢者の支援を行っています。特養と養護老人ホームは一見似ているようで、実は目的が大きく異なるのです。
先にお伝えしたように、特養には要介護3以上=中度〜重度の介護を必要としている高齢者が集まっています。何らかの疾患を抱えている場合もあり、身体的機能は個人差が大きいでしょう。食事に関することでいうと「大きなものは食べにくい」「歯がなくてしっかりかめない」「水も飲み込みにくい」など、嚥下機能が低下している方も少なくありません。

つまり、特養の給食は個別の細かい事情に合わせて提供する必要があるのです。献立作成では、栄養価やカロリーへの配慮が欠かせないでしょう。さらに、介護食としての食形態(ミキサー食など)を増やし、食材の下ごしらえや調理の仕方も考えなくてはなりせん。しかし、現実にはこうした業務に手が回らない特養もあります。そこで注目されているのが給食委託なのです。次の項目では、給食委託会社の選び方を詳しく見ていきましょう。
給食委託会社を選ぶためのポイント

特養で給食委託会社を利用する際、何を重視すればいいのか、成功事例から考察した選び方のポイントをまとめました。
①高度な品質・衛生管理
多くの人が口にする給食において、品質の安定や安全性の確保は最も重要といえる部分です。厚生労働省は、食品等事業者に対しHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を義務付けています。
また、給食の品質を安定させるため委託に切り替える特養もあります。品質・衛生管理の方法については、事前に確認しておくと安心できるでしょう。
②柔軟性のあるコミュニケーション
先に述べたように、特養で過ごす高齢者の健康状態はさまざまであり、給食も個別の事情に合わせなくてはなりません。長い目で見ると、企業や担当者との信頼関係が築けることはとても重要。「厨房運営の悩みを聞き、コスト削減を実現するための提案をしてくれた」という事例もあります。些細なことでも親身になってくれる企業は、トラブルなどが生じたときも頼れる存在になりそうです。
③給食の味やバリエーションへのこだわり
ある特養の事例では「おいしいだけでなく、献立の種類も多いので高齢者の方々に喜ばれる」という声がありました。特養で豊かな生活を送ってもらうためにも、味やバリエーションにこだわった給食を提供している点は重要といえるでしょう。
④コストパフォーマンスの良さ
給食のおいしさと価格のバランスがとれていることも重要です。いくら給食の質が良くても、価格が高くて経営を圧迫するようでは本末転倒。長くお付き合いしていけるように、コストパフォーマンスも納得した上で選びましょう。
⑤サービスやサポート体制の有無
給食委託に付随するサービスやサポート体制は、企業によってさまざまです。緊急時のサポートが受けやすいことを重視し、施設の近くにある給食委託会社を選んだ事例もあります。日本では災害も多いため、非常食などの物資までカバーしてくれるのであれば、より心強いでしょう。
特養における食事の多様性

特養で提供される食事は、主に嚥下機能が弱った高齢者向けであることを前提とし、常食より食べやすいように調理するのが基本です。では、その食事内容と食形態について詳しく解説します。
ユニバーサルデザインフードの区分に沿った食事内容
日本介護食品協議会が制定したユニバーサルデザインフード(UDF)の区分は、食事内容の基準となります。各区分について、ご飯に置き換えたイメージと共に解説していきましょう。
区分①容易にかめる:普通のご飯〜やわらかご飯
ほぼ常食と同じものが食べられる人向けの区分。かむ力はありますが、かたい食材や大きな食材がやや食べづらく、飲み込む力は問題ないレベルです。食事によっては、わずかなとろみを付けることもあります。
区分②歯ぐきでつぶせる:やわらかご飯〜全粥
かたい食材や大きな食材が食べづらく、飲み込む力が少し弱っている人向けの区分。区分①に比べて食材は小さく、やわらかく調理します。とろみもやや濃厚で、とんかつソース程度です。
区分③舌でつぶせる:全粥
細かくやわらかな食材なら食べられる人向けの区分。水やお茶などが飲みづらいと感じることがあるレベルです。区分②よりも食材本来の形がわかりにくくなり、とろみはケチャップ程度になります。
区分④かまなくてよい:ペースト粥
大きさにかかわらず固形物が食べづらく、飲み込みづらい人向けの区分。水やお茶なども飲みづらいレベルです。とろみは強くなり、マヨネーズ程度のこともあります。
食形態の種類
特養では、ユニバーサルデザインフードの区分に加え、以下のような食形態を採用しています。
ソフト食や軟菜食
食材をやわらかくなるまで長時間煮込んだり、ゆでたりした食事のこと。舌でつぶせる程度が目安で、中期の離乳食に相当します。食材の見た目は常食と大きく変わらない場合も。
きざみ食
食材を5mm〜1cm程度に刻んだ食事のこと。主に、かむ力が弱っている場合に適しています。食材の見た目は変わりますが、味は大きく変わりません。
ミキサー食
調理済みの食材をミキサーにかけ、液体状にした食事のこと。かむ力も飲み込む力も弱っている場合に適しています。飲み込みづらいときは、とろみを追加。食材の見た目が完全に変わるため、彩りや味のバリエーションにも配慮する必要があります。
流動食
スープや果汁、重湯など、最初から液体状になっている食事のこと。手術後や体調不良などで食事ができない人向けのため、個別で栄養バランスやカロリーが調整されることもあります。
特養の食事では、このような細かい配慮や対応が求められるのです。改めて、給食委託会社の選び方が重要であることがお分かりいただけるでしょう。
給食委託以外の選択肢はある?
特養における給食の提供方法は、給食委託以外にも直営給食と配食サービスがあります。それぞれ詳しくご説明しましょう。
選択肢①直営給食
施設内に厨房などの給食設備を配置。栄養士や調理師などを直接雇用し、給食運営を行います。喫食者の声が聞きやすくなる一方、給食を担当するスタッフの業務量は増えがちに。また、食材は必要量のみ仕入れるため、選び方によってはコストが高くなるかもしれません。
選択肢②配食サービス
調理済みのお弁当やお惣菜を冷蔵・冷凍、レトルトパックなどで配達してもらうサービス。施設は設備費や人件費などが大きく削減できます。サービスによっては少数から注文でき、急な変更やキャンセルも可能です。
特養の給食委託でお悩みなら、ナリコマへお問い合わせください
今回は、特養における給食委託会社の選び方などを中心にお届けしました。最後の項目で給食委託以外の選択肢についてお伝えしましたが、ナリコマでは医療/介護福祉施設に向けて委託、直営、配食サービスのメリットを取り入れた“直営支援型”の厨房運営をご提案しております。
お届けする食事は栄養バランスがよく、バリエーションも豊富です。再加熱すれば提供可能なクックチルのため、現場では業務の効率化、労働環境の改善につながったというお声をいただいています。ほかにも、シフト管理や帳票作成などの厨房業務をしっかりサポート。給食のことでお悩みの際には、ぜひ一度ナリコマへお問い合わせください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
委託に関する記事一覧
-
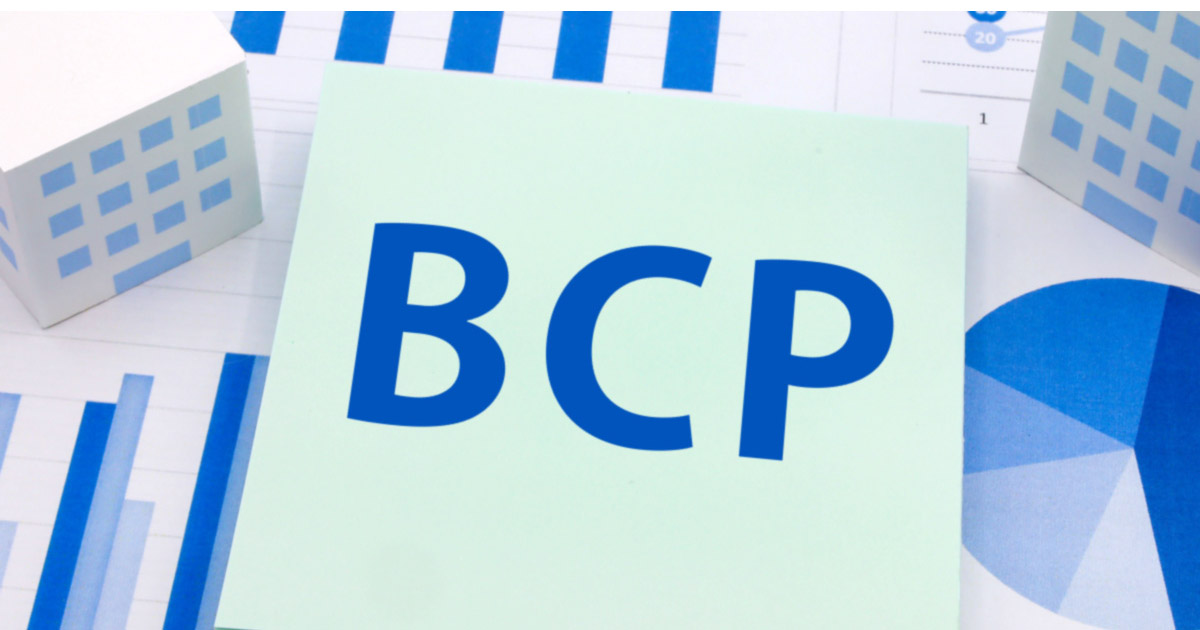
災害と介護研修の取り組み方とは?BCP研修や防災訓練など災害対応教育を強化しよう
災害と介護研修について日頃から考え、対策を練っておくことはとても重要です。この記事では、災害対応教育の重要性を法定研修と共に振り返りながら、介護施設や事業所が行うべきBCP研修や、防災訓練に取り組む際のポイント、給食提供に関する厨房のBCP対策について解説します。
-

介護福祉教育研修制度でスキルアップ!実務者研修や認知症ケア研修等のサポートや実施のコツ
介護福祉教育研修制度の充実は、個々のスタッフのスキルアップを促し、より高度なサービスを提供できる施設運営にも役立ちます。この記事では、介護福祉士になるために必要な研修や、実務者研修の資格講座内容などを改めて振り返りながら、介護資格取得支援制度への取り組みや認知症ケア研修等の法定研修のサポートや実施のコツを解説します。
-

介護施設に適した食事の提供体制とは?外部委託の選定ポイントも紹介
日本は65歳以上の高齢者人口が年々増加しており、2043年には3,953万人でピークを迎えるといわれています。一方、2024年10月1日時点で1億2380万人余の総人口は減少していく見込み。今後は高齢化率が上昇し、2070年には2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になると推測されています。
こうした背景から、近年では介護福祉サービスの需要が高まっています。今回お届けする記事のテーマは、そんな高齢者ケアの拠点となる介護施設の食事。食事の重要性や提供体制について解説し、外部委託業者の選定ポイントなどもあわせてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
人材不足に関する記事一覧
-

これから採用すべきは「未経験者」!?厨房で即戦力を育てるヒント
病院や介護施設などでは、厨房の人手不足の悩みが深刻化しています。問題が解決しない背景には、募集をかけても調理員の応募がない、という実態もあるようです。未経験でも勤務可能な調理員は一見応募のハードルが低いように思えますが、なぜ応募が少ないのでしょうか?
この記事では、調理員が集まらない理由から、未経験者にとって厨房業務がつらく感じる理由、未経験者が活躍できる厨房にするための解決策とクックチルの特長について解説します。 -

介護施設の法改正|まず何をすべき?対応フローと教育の進め方ガイド
介護施設の運営において、法改正への対応は避けては通れません。近年は高齢化社会の進行や働き方改革の影響により、介護保険制度や労働関連法の改正が相次いでいます。現場では「まず何から取り組めばいいのか分からない…」という声も少なくありません。
今回は、介護施設に関係する主な法改正のポイントをわかりやすく整理し、法改正の対応になにを優先したらいいのかや、対応をスムーズに進めるためのフロー、職員への伝え方をご紹介します。 -

給食業界の現状!早期改善が求められる課題3つ
給食は保育所や学校、病院、介護・福祉施設、社員食堂など、いろいろな場所で人々のお腹を満たし、健康を支えています。しかし、その給食を提供する側に目を向けると、いくつかの課題が浮き彫りに。近年、給食業界は厳しい状況にあると指摘されており、早めの対策が必要といわれているのです。
本記事では、給食業界が抱える複数の課題から、特に重視すべき3つをピックアップ。課題の内容とともに、その要因や改善のポイントも詳しくお伝えします。