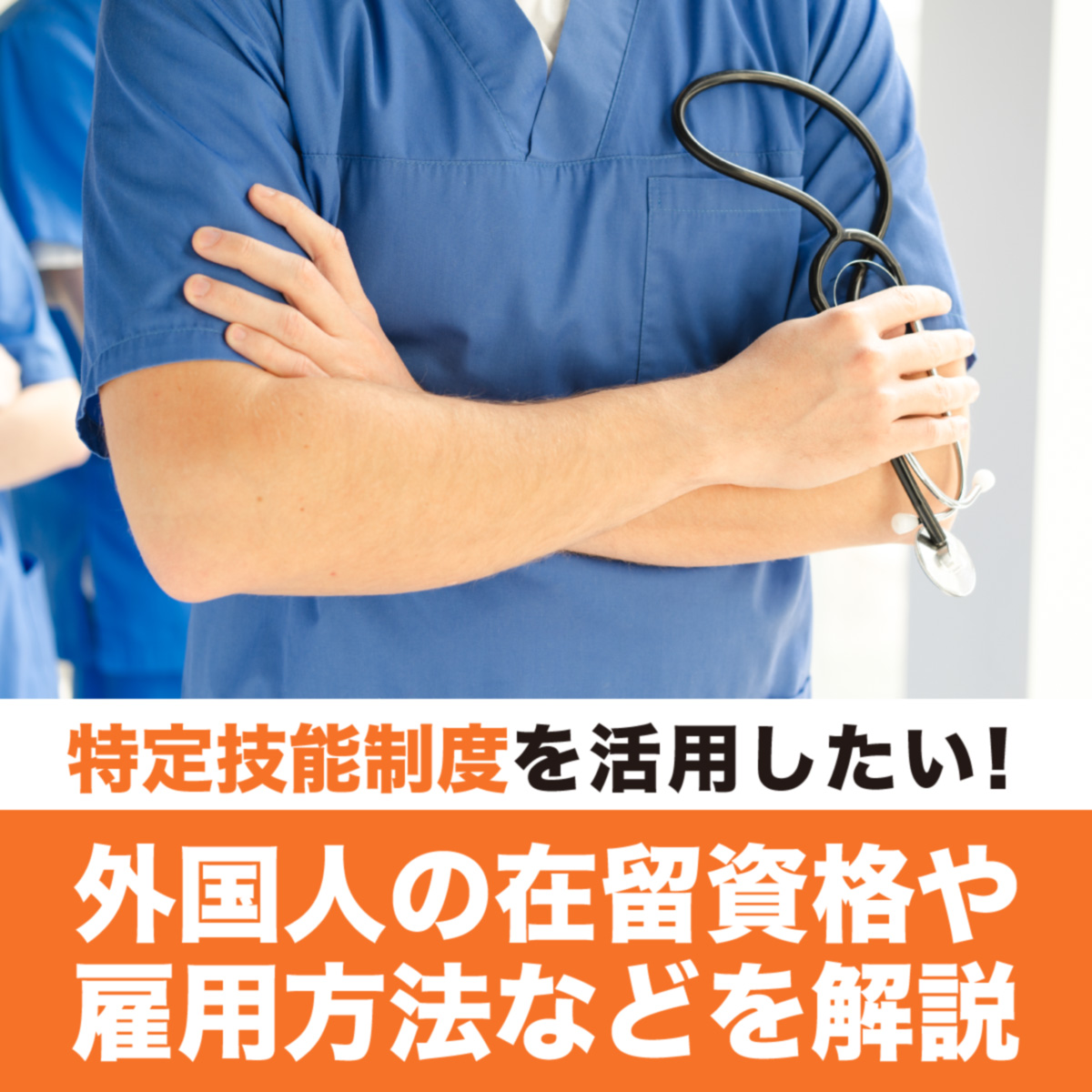近年の人手不足の課題解決の一つとして、特定技能制度が注目されています。この記事では、特定技能制度による在留資格「特定技能」の概要から、産業分野一覧、試験等の詳細や資格取得までの流れ、雇用方法などをわかりやすく解説します。病院や介護施設の厨房業務の人手不足にお悩みの施設さまはぜひご参考ください。
目次
特定技能制度とは?
特定技能制度は、国内での人材確保が難しい産業分野で、一定の専門性や技術があり即戦力となる外国人の就労を受け入れる制度です。2018年に成立した改正出入国管理法により「特定技能」が在留資格となり、2019年から受け入れが始まりました。外国人の在留資格には、教授や芸術、高度専門職、医療、介護など、複数の資格がありますが、特定技能はその中の一つです。

特定技能の種類
特定技能には、知識や技能のレベルの違いによる特定技能1号と特定技能2号の種類があります。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能の在留資格を持つ外国人の数は年々増加しており、2024年12月末の時点で、特定技能1号在留外国人数の合計は283,634人、特定技能2号在留外国人数の合計は832人、となっています。国籍ではいずれもベトナムが最も多く、特定技能1号が約47%、特定技能2号が約67%を占めています。
特定技能の産業分野一覧
特定技能では、特定技能外国人を受け入れる分野として産業分野が指定され、特定技能1号は16分野、特定技能2号は11分野に区分されています。この特定産業分野は、分野によって所管省庁が異なり、厚生労働省・経済産業省・国土交通省・農林水産省が個々に管理しており、分野ごとに運用方針や運用要領、評価試験、実施機関などが定められています。
下記は特定産業分野の一覧です。
|
分野 |
所管省庁 |
特定技能2号に該当するもの |
|
介護 |
厚生労働省 |
|
|
ビルクリーニング |
厚生労働省 |
〇 |
|
工業製品製造業 |
経済産業省 |
〇(一部業務区分が対象) |
|
建設 |
国土交通省 |
〇 |
|
造船・舶用工業 |
国土交通省 |
〇 |
|
自動車整備 |
国土交通省 |
〇 |
|
航空 |
国土交通省 |
〇 |
|
宿泊 |
国土交通省 |
〇 |
|
自動車運送業 |
国土交通省 |
|
|
鉄道 |
国土交通省 |
|
|
農業 |
農林水産省 |
〇 |
|
漁業 |
農林水産省 |
〇 |
|
飲食料品製造業 |
農林水産省 |
〇 |
|
外食業 |
農林水産省 |
〇 |
|
林業 |
農林水産省 |
|
|
木材産業 |
農林水産省 |
上記の中で介護の分野は特定技能2号が設けられていませんが、在留資格には別に「介護」があります。介護福祉士の資格取得により「介護」の在留資格に変更することが可能です。
特定技能1号と特定技能2号の違いと試験

特定技能1号と特定技能2号では、在留期間や永住権の取得、日本語能力基準など、さまざまな違いがあります。詳細は下記の主な違いをまとめた表をご参考ください。
|
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
|
在留期間 |
更新上限5年 (1年・6ヶ月・4ヶ月ごとに更新) |
更新上限なし (3年・1年・6ヶ月ごとに更新) |
|
永住権の取得 |
不可 |
条件を満たせば可能 |
|
日本語能力基準 |
日本語能力試験(JLPT)N4以上 |
・日本語能力試験のN3レベル以上 または ・国際交流基金日本語基礎テストのA2レベル以上 |
|
技能基準 |
試験等で確認 (※技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除) |
試験等で確認 |
|
外国人支援 |
受入れ企業、登録機関により支援 |
支援は不要 |
|
家族の帯同 |
不可 |
条件を満たせば可能 |
特定技能2号になると、在留期間の更新回数に制限がなくなることや、条件を満たせば配偶者や子供の帯同が可能になるなど、特定技能1号のときよりも日本で暮らしやすくなります。
特定技能の資格取得の流れ
特定技能の前段階として、技能実習制度による技能実習1号と技能実習2号、場合によって技能実習3号のステップがあります。ただし、技能実習制度は旧制度となり、2027年中までに育成就労制度が施行されるため、技能実習1号・2号・3号の期間は原則3年間の育成就労期間に変更となります。
育成就労制度の場合、まず就労開始までに、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格か、これに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講が必要です。また、育成就労から特定技能1号に進む過程でも、技能試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)や、日本語能力試験(日本語能力試験N4等の日本語能力A2相当以上の試験)の合格を要件とする方針があります。特定技能2号に進む過程でも、同様に技能試験や日本語能力試験があり、ステップごとに試験が設けられる予定です。
特定技能1号には、技能実習または育成就労のステップを踏む以外に、試験ルートで資格を取得することも可能です。そのため、外国人が日本国外で試験を受けて特定技能1号の取得の条件をもって入国することもできます。
特定技能外国人の雇用方法
特定技能外国人を雇用するためには、受入れ機関(特定技能所属機関)として基準に適合している必要があります。受入れ機関としての義務もあるため、それぞれよく把握しておきましょう。例えば、基準と義務には下記のような内容があります。
外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 労働法令違反がないなど適切な機関であること
- 外国人を支援する体制があり、適切な支援計画があること
受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する
- 外国人への支援を適切に実施する
- 出入国在留管理庁への各種届出を行う
外国人との雇用契約は受入れ機関が結びますが、支援については、登録支援機関に委託することもできます。また適切な雇用契約については、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることなどが含まれます。義務を怠ると、外国人を受け入れられなくなり、出入国在留管理庁からの指導や改善命令等を受けることがあるため注意しましょう。

特定技能外国人の雇用までの流れ
特定技能の資格を持つ外国人を募集する際には、人材紹介を行う登録支援機関を利用するとスムーズに求職者情報を得られることがあります。例えば、登録支援機関に問い合わせると、登録支援機関が海外人材紹介会社と求人情報のやり取りを行い、求職者情報を伝えてくれます。働いてもらえる特定技能外国人が見つかった際は、面接や雇用契約の締結に進み、就労のための環境作りを行う流れです。具体的には、下記のステップとなります。
1. 面接、雇用契約の締結
2. 事前ガイダンスの実施
3. 在留資格認定証明書の申請
4. 地方出入国在留管理局(入管)審査
5. 在留資格認定証明書、在留カードの交付
6. 就業開始
就業開始後も、各種届出を定期的または随時提出する必要があるため、忘れずに行いましょう。例えば、特定技能外国人の労働日数・労働時間数・給与の支給額・昇給率などの年度平均を記載した「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」を1年に1回提出します。また、雇用契約や氏名、住所などに変化があった際や、雇用後に1か月活動ができない事情が生じた場合などにも届出が必要です。
病院や介護施設の厨房で活躍する特定技能

病院や介護施設の厨房業務には、特定技能の「外食業」の分野が当てはまります。外食業分野は、先述した出入国在留管理庁による2024年12月末の特定技能1号・2号の在留外国人数においても、特定技能1号が27,759人、特定技能2号が105人と比較的活躍している人数の多い分野です。病院や介護施設の厨房業務でも、近年特定技能1号の受け入れが加速しています。試験に合格した技能を持つ特定技能外国人に厨房業務の即戦力として活躍してもらいながら、人手不足の課題解決につなげることができるでしょう。
ナリコマは「登録支援機関」の認定を取得しています!

ナリコマには、特定技能外国人の受け入れ実績が豊富にあるため、経験を活かしてご要望に沿った登録支援機関をご紹介することができます。また、ナリコマも「登録支援機関」の認定を取得しているため、厨房運営の支援を踏まえながら、幅広いサポートが可能です。厨房の人手不足や特定技能外国人の雇用にお悩みの施設さまは、ぜひ一度ご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
委託に関する記事一覧
-
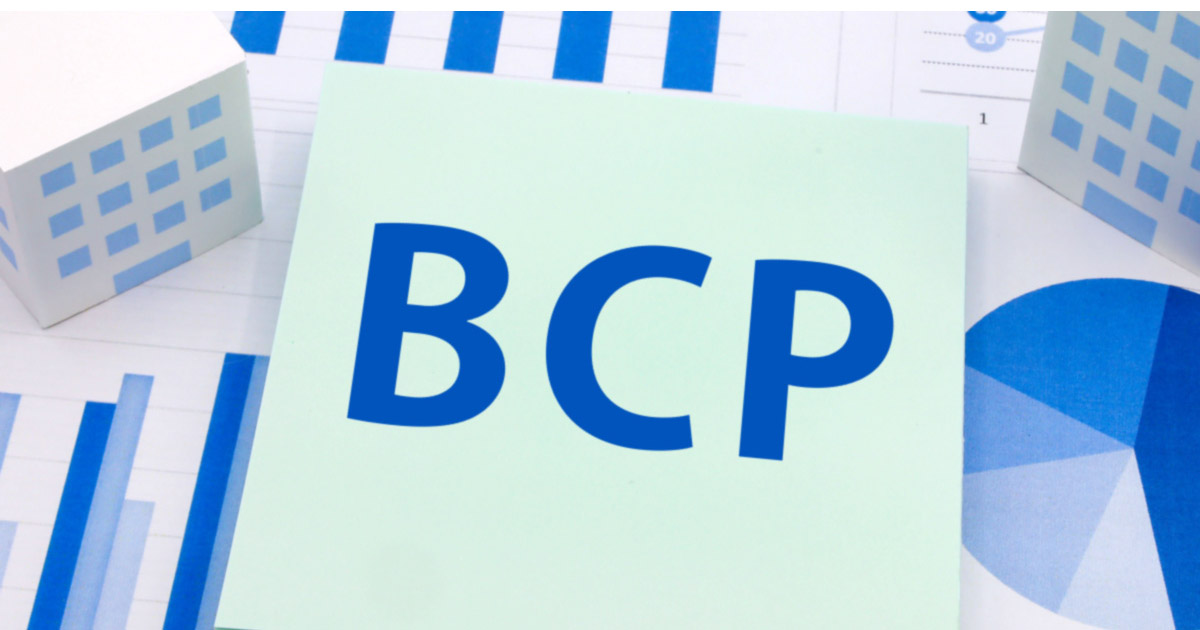
災害と介護研修の取り組み方とは?BCP研修や防災訓練など災害対応教育を強化しよう
災害と介護研修について日頃から考え、対策を練っておくことはとても重要です。この記事では、災害対応教育の重要性を法定研修と共に振り返りながら、介護施設や事業所が行うべきBCP研修や、防災訓練に取り組む際のポイント、給食提供に関する厨房のBCP対策について解説します。
-

介護福祉教育研修制度でスキルアップ!実務者研修や認知症ケア研修等のサポートや実施のコツ
介護福祉教育研修制度の充実は、個々のスタッフのスキルアップを促し、より高度なサービスを提供できる施設運営にも役立ちます。この記事では、介護福祉士になるために必要な研修や、実務者研修の資格講座内容などを改めて振り返りながら、介護資格取得支援制度への取り組みや認知症ケア研修等の法定研修のサポートや実施のコツを解説します。
-

介護施設に適した食事の提供体制とは?外部委託の選定ポイントも紹介
日本は65歳以上の高齢者人口が年々増加しており、2043年には3,953万人でピークを迎えるといわれています。一方、2024年10月1日時点で1億2380万人余の総人口は減少していく見込み。今後は高齢化率が上昇し、2070年には2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になると推測されています。
こうした背景から、近年では介護福祉サービスの需要が高まっています。今回お届けする記事のテーマは、そんな高齢者ケアの拠点となる介護施設の食事。食事の重要性や提供体制について解説し、外部委託業者の選定ポイントなどもあわせてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
人材不足に関する記事一覧
-

これから採用すべきは「未経験者」!?厨房で即戦力を育てるヒント
病院や介護施設などでは、厨房の人手不足の悩みが深刻化しています。問題が解決しない背景には、募集をかけても調理員の応募がない、という実態もあるようです。未経験でも勤務可能な調理員は一見応募のハードルが低いように思えますが、なぜ応募が少ないのでしょうか?
この記事では、調理員が集まらない理由から、未経験者にとって厨房業務がつらく感じる理由、未経験者が活躍できる厨房にするための解決策とクックチルの特長について解説します。 -

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

栄養士の仕事で大変なことは?病院、介護施設別に公開!
病院や介護施設などで提供される食事において、栄養士の存在はとても重要です。本記事では、栄養士がどんな仕事をしているのか詳しくご紹介しましょう。病院や介護施設で働いていて大変なことも、それぞれお伝えします。
「キツい」「つらい」といったイメージが付きやすい理由を考察し、栄養士に向いている人の特徴やよくある話、働き方を改善するポイントなども併せて解説。ぜひ最後までお読みください。