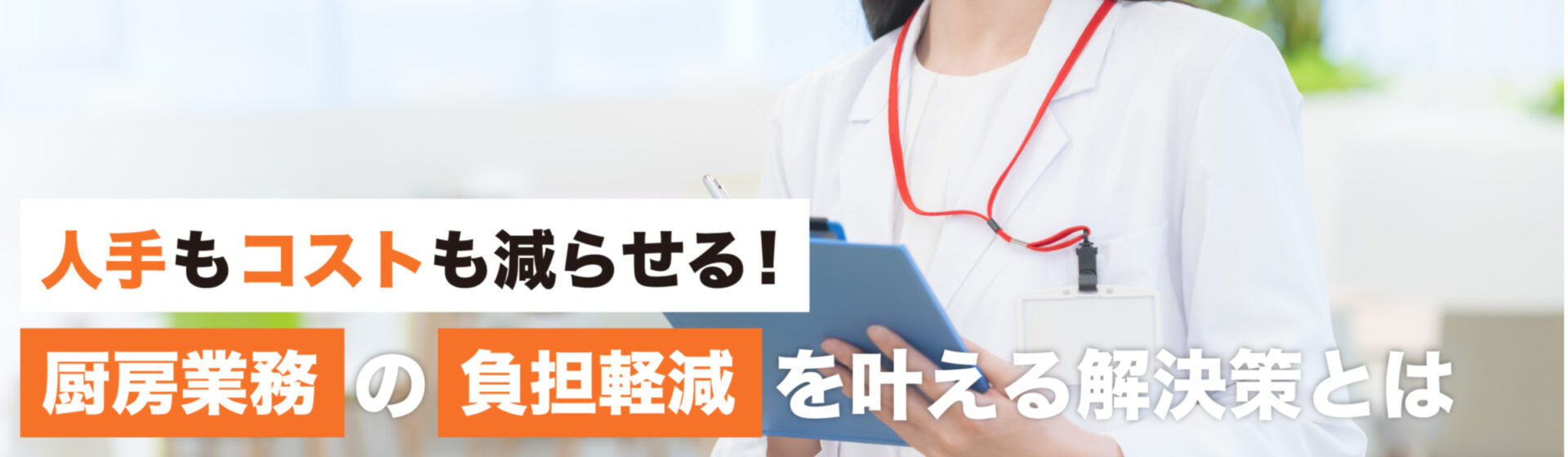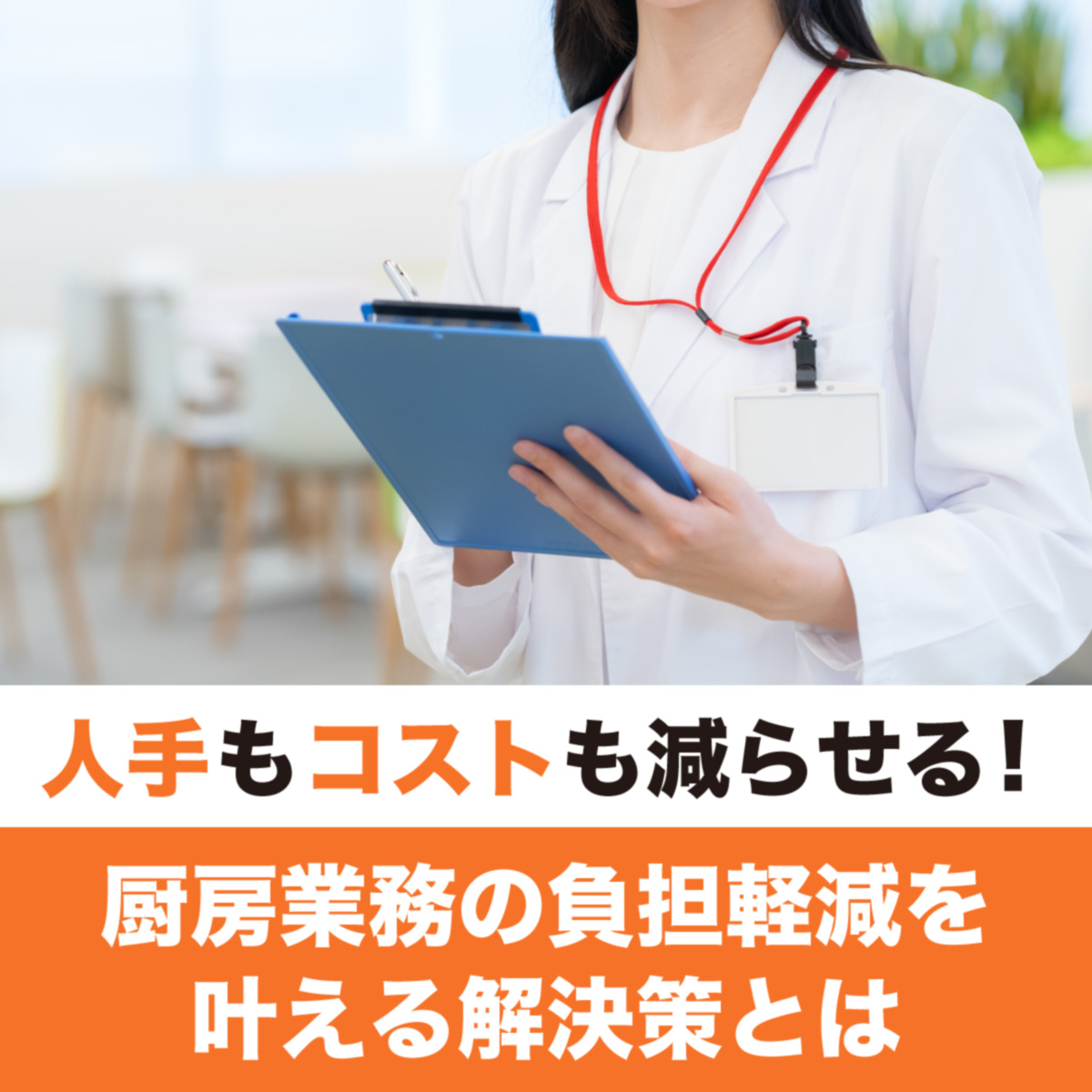調理スタッフの確保が難しくなっている今、厨房の現場では「いかに負担を減らすか」が大きな課題になっています。人が集まりにくい理由のひとつは、作業の多さや大変さ。こうした働きにくさが、職員の離職や採用の難しさにもつながっています。だからこそ今、厨房業務を見直して、負担を減らす工夫が必要なのです。単に効率を上げるだけでなく、「人が働き続けやすい職場」をつくることがゴールです。
この記事では、業務の効率化やICT導入、外注の活用など、厨房省人化に向けた具体策をご紹介。ナリコマのクックチルを活用した、人手不足への対応例も合わせてお伝えします。
目次
人手も時間も足りない…施設厨房現場が抱える課題
高齢化の進行とともに、施設での食事提供ニーズは増え続けています。しかし、厨房の現場では、人手も時間も足りず、業務負担の重さが大きな課題となっています。

人手不足が常態化する施設厨房の現実
2025年には、団塊の世代がすべて75歳以上となり、介護を必要とする高齢者が一気に増えると見込まれています。この「介護の2025年問題」により、施設全体の業務量はさらに増加すると考えられていますが、施設厨房の現場は人手不足が続いており、調理スタッフの確保に苦労している施設も多く見られます。
厨房の仕事は体力的な負担が大きく、早朝やシフト勤務が避けられないなど、働くうえでのハードルが多い現場です。人手不足に陥る理由として、業務の大変さに対して待遇が見合わないと感じる方も多く、定着しにくい状況が続いていることが挙げられます。さらに、仕事のやり方が共有されておらず、限られた人に頼りきりになっている現場も多かったり、ベテラン職員の退職が重なったりすることで、人材の定着がますます難しくなっているのです。
求人を出しても人が集まらず、ようやく採用できてもすぐに辞めてしまう。その結果、限られたスタッフに業務が集中し、さらに負担が大きくなるという悪循環が生まれています。
負のスパイラル?業務負担増加が離職を呼ぶ
人手不足が続く厨房では、職員一人ひとりの業務量が増えてしまいがちです。朝早くからの出勤、限られた人数での調理・盛り付け・洗浄といった作業をこなしながら、献立の作成や発注、衛生管理まで担うなど、その業務範囲は多岐にわたります。本来は分担すべき作業が少人数に集中することで、負担が大きくなり、心身の疲れがたまりやすくなってしまうことも。その結果「もう続けられない」と感じて離職するケースも少なくありません。
こうした負のスパイラルを断ち切るためにも、厨房全体の業務を見直し「人に頼らず回せる仕組みづくり」が必要です。介護業界全体の人手不足を食い止めるために、厨房での負担軽減が大きなカギになっているのです。
厨房業務の負担軽減のためにできること
人手不足の中でも安定した食事提供を続けるためには「今ある職員数でどう回すか」を考えながら、作業の効率化や外部の力も上手に取り入れていくことが求められています。
作業工程の見直しと効率化
厨房業務の負担を軽くするには、まず毎日の作業を見直すことが効果的です。調理や盛り付け、配膳、片付けと、日々の厨房業務にはたくさんの工程がありますが、その中にはほんの少し工夫すればラクになるポイントが意外と多くあるものです。たとえば、作業動線にムダがあったり、手順が人によってバラバラになっていたりすることもあります。見直しが必要な部分を洗い出して、作業の順番や配置を変えることで、厨房業務の負担はぐっと軽くなるでしょう。
また、毎日繰り返す定型業務は、マニュアルを整えて誰でも同じようにできる状態にしておくと、職員間での作業のばらつきも減ります。小さな見直しの積み重ねが、厨房の忙しさを和らげ、働きやすい厨房づくりにもつながっていくのです。
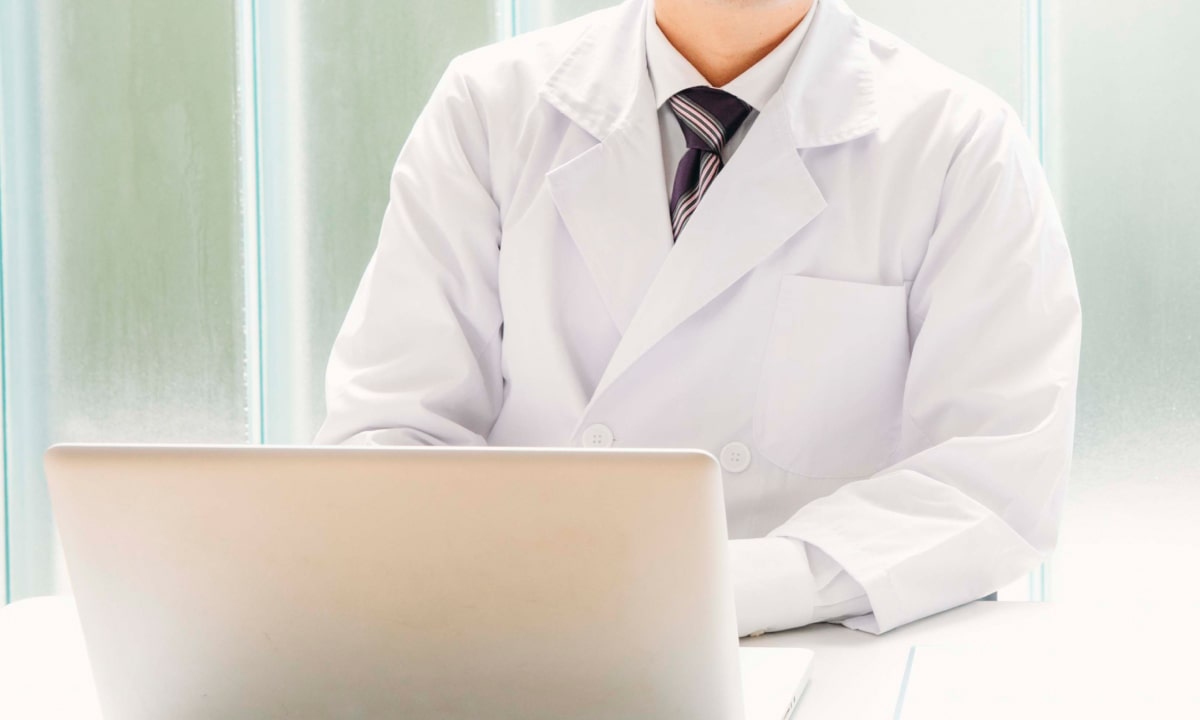
ICTで厨房をもっと効率的に
厨房業務の中には、調理以外にも多くの事務作業が発生します。
たとえば、献立に応じた食数管理や食材の発注、帳票の作成など、手間のかかる業務が毎日のように発生します。こうした作業をすべて手書きで行っていると、時間も人手も取られ、ミスが起きやすくなる原因にもなります。近年では、食数管理や発注をデジタルで行えるシステムを導入する施設が増えてきました。ICTを活用すれば、これらの煩雑な業務を効率化でき、厨房職員の負担軽減につながります。
操作がシンプルなものを選べば、特別なスキルがなくても使いこなせるため、現場への導入もスムーズです。手書きで行っていた業務をデジタル化することで、作業時間の短縮や入力ミスの軽減が期待できます。
厨房業務の一部を外注でカバー|省人化に向けた第一歩
人手不足が続く中「厨房のすべてを自施設でまわすのは限界に近いかも…」といった現場も少なくないでしょう。そんな時には、厨房業務の一部を「外注」でカバーするという方法もひとつの手です。
たとえば、献立作成や調理を外部の給食サービスに委託すれば、現場での負担は大きく軽減されるでしょう。そのほかにも、再加熱だけで提供できる「完全調理済み食品(クックチル)」を活用すれば、調理工程そのものを省くことができ、少人数でも無理なく運営できます。調理の手がかからなくなる分、他の業務に人員を回したり、限られた人数でもシフトを組みやすくなったりと、人員確保にも余裕が生まれます。
さらに、厨房コンサルのような外部の専門家に依頼すれば、作業動線や人員配置など、業務の見直しを行い、現場に合った改善提案を受けることも可能です。「どこを変えれば楽になるか」が見えるだけでも、大きな一歩になります。外注は「全部任せる」のではなく、必要な部分を必要なタイミングで任せる柔軟な手段なのです。人手不足の今こそ、こうした選択肢を前向きに活用していきたいですね。
クックチル導入で“人手”と“業務”をWで削減|ナリコマでできる負担軽減対策
人手不足の今だからこそ、導入のハードルが低く、すぐに効果が出る方法を選びたいとお考えの方もいるでしょう。その対策のひとつがナリコマのクックチルです。ただの調理済み食品ではない、現場目線の仕組みをご紹介します。
クックチルとは?
クックチルとは、加熱調理した食品を急速冷却し、提供時に再加熱して出せる調理済み食品のことです。「調理」と「提供」のタイミングを分けられるため、厨房のピークタイムにも余裕が生まれ、人手が少ない現場でも無理なく対応できます。
ナリコマのクックチルは、全国6か所にあるセントラルキッチンでHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を徹底して調理・製造されています。あたためるだけで美味しく提供できる一方で、食事としての満足感にも妥協しないのがナリコマの強みです。調理の手間を省きながらも「美味しさ」「安全」「効率化」のすべてを兼ね揃えています。

ナリコマのクックチルが選ばれる理由
ナリコマのクックチルが多くの施設に選ばれているのは、調理の手間を減らすだけでなく、日々の厨房業務を少しでも軽くできるよう、現場目線の工夫が込められているからかもしれません。クックチルでは、チルド状態の料理が届き、再加熱と盛り付けを施設内で行います。盛り付け作業も簡単にでき、調理経験が少ないスタッフでも安心して作業可能です。
さらに業務の負担を抑えたい施設には、「ニュークックチル」という選択肢も。ニュークックチルは、チルド状態の料理を専用の食器に盛り付けて加熱機器にセットする方式です。あらかじめセットしておけば、設定時間に合わせて自動で加熱が始まり、そのまま提供できます。メイン作業は盛り付け作業となるため、提供直前の手間を減らし、少人数でもスムーズな給食提供が可能です。
また、ナリコマは嚥下食や制限食などの対応力にも強みがあり、通常食と同じ献立で形態だけを変えて提供できます。献立調整にかかる負担が減ることで、厨房全体の作業も安定します。人員の確保が難しい施設には、求人支援などのサポート体制も充実。「食事だけでなく、厨房全体の運営まで支えてくれる」という安心感も、ナリコマが選ばれている理由のひとつです。
ナリコマを導入した施設の事例やインタビューも掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。
ナリコマなら厨房運営のスペシャリストが味方に

食事の準備だけでなく、厨房全体の運営も見直していきたい。そんなときには、ナリコマが心強いパートナーになります。ナリコマでは、単にクックチルを納品するだけでなく、施設の厨房運営に精通した担当者が、状況に応じた改善提案も行います。たとえば、食数や職員体制をふまえたシフトの見直しや、無理のない導線づくり、人員配置の工夫などのオペレーションの見直しなど、日々の業務の中で見直せそうなポイントを一緒に探しながら、負担を減らしていきます。
また、「採用が難しくて現場が回らない」「求人を出しても応募がない」といったお悩みにも、求人支援や人材確保に向けたサポートで対応可能です。ナリコマは、調理の効率化だけにとどまらず、現場がより安定して回るよう、人と業務の両面から支える姿勢を大切にしています。
ナリコマ独自のシステムで厨房業務をサポート
ナリコマではクックチルの導入にあわせて、日々の業務を支えるための独自システムも提供しています。発注や検品、食数変更、帳票の作成などもできるだけシンプルに行えるよう設計されています。なかでも帳票管理は、最小限の入力で必要な書類が自動で整うため、日々の記録や報告作業の負担もぐっと軽減できます。
このシステムはナリコマが自社で開発しており、わからないことがあればすぐに問い合わせができ、解決までの対応もスムーズです。導入後もナリコマはしっかりと寄り添います。厨房業務の効率化は、調理だけでなくこうした間接業務の負担を減らすことでも実現できるでしょう。
厨房業務の負担軽減で人も時間も守る現場へ

厨房業務の負担は、現場で働く人の心身に大きな影響を与えるだけでなく、サービスの質や人材の定着にも関わるものです。人手不足は仕方ないこと、とあきらめず、効率化・外注・ICTの導入など、できるところから一歩ずつ見直すことが、無理なく働き続けられる現場づくりにつながります。
なかでもクックチルの活用は、調理の手間や負担を減らすだけでなく、厨房省人化を進める手段としても注目されています。これからの施設給食において、多くの現場で取り入れられていくことでしょう。ナリコマでは、厨房運営のパートナーとして、施設ごとに異なる課題に寄り添いながら、最適な改善策をご提案しています。人も時間も守れる厨房づくりを、ナリコマと一緒に始めてみませんか?
厨房業務の負担軽減についてお考えの場合には、ぜひ一度ナリコマへご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。
コストに関する記事一覧
-

ニュークックチルは省エネに効果あり?エネルギー効率や環境負荷について詳しく解説
環境問題への対策は世界各国で行われており、日本でもさまざまな取り組みが実施されています。ガスや電気といったエネルギーは、産業から家庭まで幅広く必要とされるもの。近年では、環境負荷軽減を考慮した多種多様な省エネ機器も登場しています。今回の記事は、厨房における省エネ対策をクローズアップ。需要が高まっている新調理方式、ニュークックチルを運用する際のエネルギー効率や環境負荷について詳しくお伝えします。
-

ニュークックチルの運用を安定化!機器メンテナンスの重要性を解説
近年の日本は高齢化が急速に進んでおり、医療や介護福祉サービスの需要も増加傾向にあります。病院や特別養護老人ホームなどにおいて欠かせないものといえば、毎日の食事です。ニュークックチルは厨房業務の業務効率化や負担軽減に有効であることから、人手不足や負担増加に悩む医療・介護福祉業界でも注目を集めています。今回の記事は、ニュークックチルの運用に欠かせない厨房機器とメンテナンスについて解説。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
-

ちゃんと食べていても体重が減っていく?高齢者の食事は少量高栄養で!
高齢者になると健康上の問題が目立つようになります。当然個人差はありますが、健康状態を左右する食事の困りごとはいち早く解決したいものでしょう。「若い頃と同じように食べられなくなった」「食欲がなくなってきた」といった声は、いつの時代も聞こえてきます。
本記事で取り上げるのは、しっかり食べているのに体重が減るという「やせ(低体重)」の問題。高齢者の体重減少を引き起こす理由や具体的な原因を解説し、「やせ」の危険性についてもお伝えします。
また、そんな高齢者の食生活をサポートする少量高栄養の介護食・給食についても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。