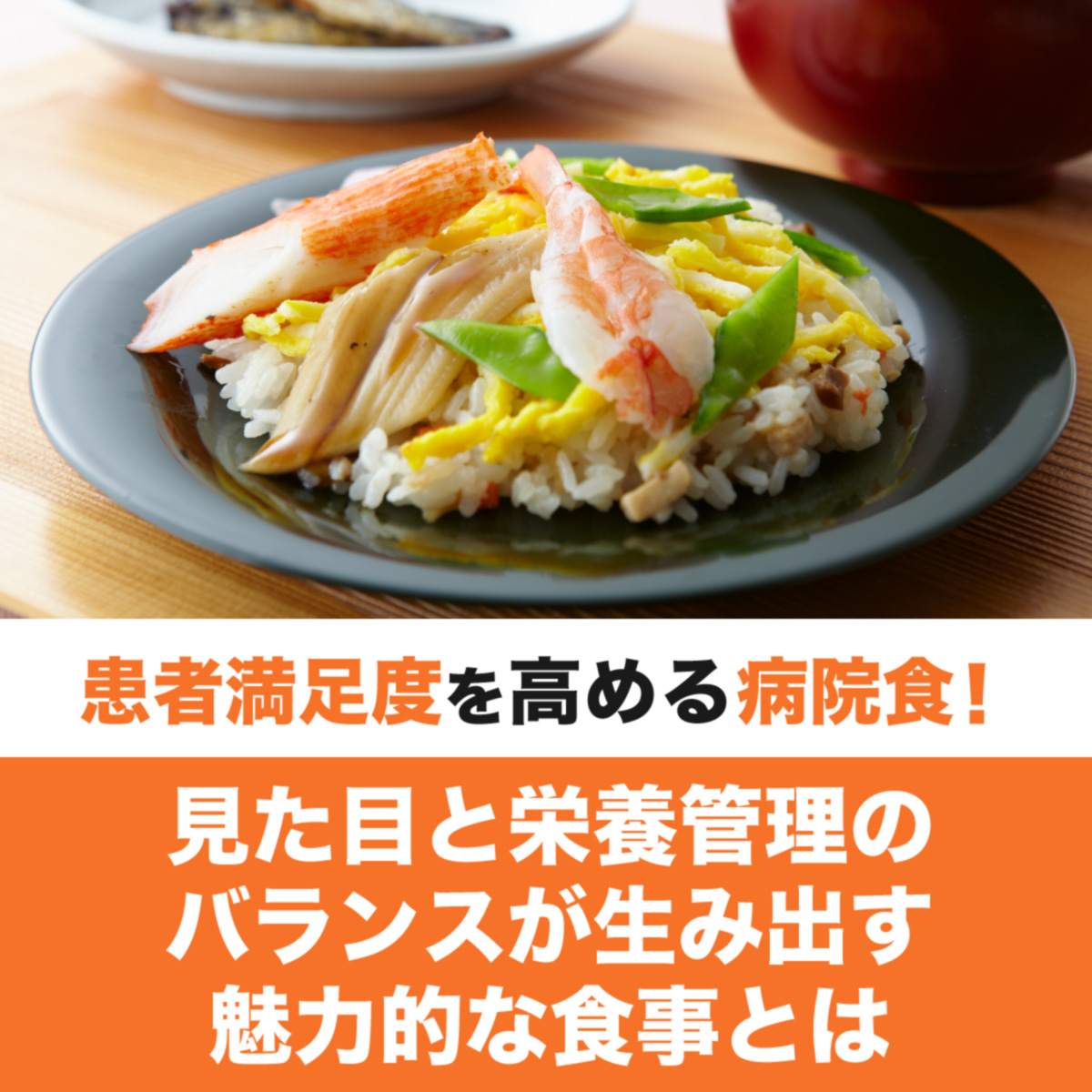「量が少ない」「おいしくない」などのイメージを持たれてしまいがちな病院食。もう栄養バランスのみを重視した病院食の提供をする時代は終わろうとしています。
昨今では、病院食が持つ力に注目されるようになり、「おいしい病院食」を提供する病院が増えてきました。病院食がおいしくなれば、食事だけでなく病院に対する満足度の向上にもつながります。
おいしい病院食の提供のために、私たちが今できることには何があるのでしょうか。
目次
おいしい病院食は治療効果につながっている

病院食は単なる栄養補給ではなく、医師や管理栄養士が患者一人ひとりの病状や体調に応じて設計した、治療のベースとなるものです。消化器系の病気を抱える患者には胃腸に優しい食事、心臓疾患の患者には減塩や脂肪を抑えた食事が提供されるなど、病院食一つとっても、細やかな配慮がされているのです。
適切な栄養摂取によって回復がスムーズに進むだけでなく、体力や免疫力を維持するうえでも病院食はとても重要なものですから、食べやすさも考慮しなくてはなりません。
病院食がおいしいことは患者さんの心にも大きな影響を与えます。おいしい食事は患者の「食べたい」気持ちを引き出します。さらに必要な栄養をしっかりと摂取する意欲が湧き、満足感を得られることで入院生活や治療へのストレス軽減にもつながります。治療やリハビリ病院食は栄養面だけでなく、心の健康を支える役割も担っているのです。
おいしい病院食の提供は、単なるサービスではありません。患者さんの健康を取り戻すための土台を築く、重要な医療行為の一つなのです。
病院食を楽しんでもらうためには
病院食を楽しんでもらうためには、おいしさや栄養バランスの追求だけでなく、多職種の視点を取り入れたチーム医療が欠かせません。患者一人ひとりに寄り添い、満足度の高い食事を提供するための具体的な取り組みをご紹介します。
栄養バランスとおいしさの両立
病院食は栄養管理が基本ですが、おいしさも同時に追求することで患者さんの満足度を向上させることができます。
国立循環器病研究センター(大阪府)は、おいしい減塩食を追求し「塩をかるく使っておいしさを引き出す」という方法で注目を集めています。「病院食はおいしくない」といったイメージ払拭のため、管理栄養士や調理師が試行錯誤を重ねて生まれた「かるしおレシピ」で、減塩もおいしさも兼ね備えた病院食の提供を行っています。退院した患者からの熱い要望を受けて、減塩した日替わり弁当の監修や、減塩レシピ本の発行がされるようになりました。
このように、制限食でもだしや香辛料を活用して風味を高めたり、旬の食材を取り入れることで季節感を楽しめる工夫をするなど、栄養バランスとおいしさの両立のための工夫が大切です。

患者とスタッフの声を反映する
病院食はチーム医療の一環であり、多職種の連携が重要とされています。おいしい病院食提供のために、患者の声を聞きながら「どんな味付けなら食べやすいか」「苦手な食材は何か」などの要望を把握することも、満足度を高めるカギとなります。
病院食に関わるスタッフだけでなく、看護師をはじめ、理学療法士などのリハビリスタッフ、介護士など、患者さんに日々関わる職種の意見も大切です。「食事形態が適しているか」「食事摂取量は低下していないか」など、多職種の視点を反映させることで患者に適した食事形態への変更も臨機応変に対応できるため、患者がより食事を楽しめるように心を配る必要があります。
食事提供時の工夫
おいしい病院食を提供するためには、提供時の配慮も大切です。温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たく出すなど、食事は一番おいしい状態で提供したいものです。
また、見た目から食事を楽しむことも、病院食をよりおいしく感じさせるためには必要なエッセンスです。人がおいしさを感じるのは、味覚よりも視覚からの情報の方が割合が多いと言われているため、食事のおいしさは見た目で大きく左右されると言っても過言ではありません。
盛り付けを工夫したり提供する食器を変えてみるなど、いつもの病院食にちょっとした変化を加えてみるのもいいでしょう。
食事満足度向上のために
おいしい病院食の提供によって満足度を高めるためには、さまざまな課題への対応が必要です。病院給食には限られた予算の中で質を保ちながら、効率よく提供するための工夫が求められています。
病院食を取り巻く現状と課題
病院給食の現場では、食材費の高騰や最低賃金の引き上げに伴う人件費の上昇、そして衛生基準の厳格化といった問題に直面しています。これらにより、病院の収支は圧迫され、給食の質を維持するのが難しくなっているのが現状です。
また、2024年度の診療報酬改定により、食事療養基準額が30円引き上げられましたが、これは現場の負担を軽減するには決して十分とは言えません。
さらに、この改定後にも物価は高騰を続けており、2025年度よりさらに20円引き上げられる見込みとなりましたが、厳しい状況を打破できるかどうかは、効率的な調理方法やスタッフの工夫が欠かせないでしょう。

業務の効率化を図る
食材費や人件費の増加に対応するためには、少人数でも効率よく調理できるシステムや機器を導入するなど、調理方法の見直しが必要です。完全調理済み食品や冷凍食品などの院外調理品をうまく活用すれば、調理にかかる負担を減らしながら、品質も高く安定した食事の提供が可能になります。
患者満足度向上のカギを握るナリコマのクックチル
病院食を取り巻く課題も鑑みると、満足度向上のためにはおいしい病院食の提供と同時に、調理作業の効率化も両立させる必要があります。効率化しつつも、味や見た目、温度管理に十分な配慮を行うには、院外調理品を導入することもひとつの方法です。ナリコマでは全国の医療施設や福祉施設向けの完全調理済み食品(クックチル)を提供しています。
クックチルとは
クックチルとは、調理後に急速冷却を行い、食事の美味しさや栄養価をそのまま保つ調理システムです。全国6ヵ所のセントラルキッチンでHACCPの理念に基づいた衛生管理のもと製造されているため、安全性を確保しながらも高品質な食事を提供できます。
また、ナリコマのクックチルには365日日替わり献立の「すこやか」と、急性期・回復期病院向け28日サイクル献立の「やすらぎ」の2つのパターンがあります。ナリコマでは食べる楽しみや喜びを大切にした食事作りを心がけているため、食材本来の香りやおいしさを引き出しながら、こだわり抜いた食事づくりをしています。
和食から洋食まで多種多様な献立を用意しているほか、季節の行事食や郷土料理を提供したり、食事に楽しみを感じられるように工夫しています。

スタッフの負担軽減も可能
食事の提供時には、届いたクックチル食品を厨房で再加熱し盛り付けるだけなので、調理スタッフの負担軽減や業務のスムーズ化につながります。少ない人員でも食事の提供が可能となり、人材不足や運営コストの削減に悩む現場にもおすすめです。
ナリコマは食事を通して患者の「おいしい」の笑顔を引き出しながら、病院運営の効率化を同時にサポートします。
食事満足度向上のためにナリコマがしっかりサポート!
毎日の食事が充実することは、入院患者さんにとって大きな喜びです。おいしい病院食によって食事の満足度が上がれば、回復への意欲や心のゆとりにもつながります。クックチルをはじめとした完全調理済み食品を活用し、「おいしい」を実感できる体制を整えることで、病院全体の信頼性アップにも貢献できるでしょう。

食事提供の面でのお悩みや改善したい点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。ナリコマは調理品の提供だけでなく、経験豊富なスタッフが現場の課題を洗い出し、解決策をご提案いたします。病院食の質向上と併せて、厨房運営に関するサポートも行います。
おいしい病院食の提供、ひいては満足度の向上のためには院外調理品の導入がカギを握っていると言っても過言ではありません。おいしい病院食の提供実現のために、ナリコマが精一杯サポート致します!
コストや人員配置の
シミュレーションをしませんか?
導入前から導入後まで常にお客さまに寄り添うナリコマだからこそ、厨房の視察をしたうえでの最適解をご提案。
食材費、人件費、消耗品費などのコストだけでなく、導入後の人員削減について個別でシミュレーションいたします。
スムーズな導入には早めのシミュレーションがカギとなります。
まずはお問い合わせください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
コストに関する記事一覧
-

介護施設の給食委託。選び方のポイントと成功するコツを紹介!
介護施設の給食委託をテーマにお届けする記事です。給食委託会社の選び方で重視すべきポイントのほか、介護施設における食事の重要性や委託以外の給食提供方法などもまとめて詳しくお伝えしています。
-

法改正対応に向けた食事体制の見直しとは?ニュークックチルの活用と加算取得のポイントを解説
2024年度の診療報酬改定では、食事提供体制加算や施設基準の見直しなど、食事関連の制度が大きく変わりました。法改正対応を進めるには、最新の加算要件や届け出内容の確認、記録体制の整備が欠かせません。
今回は、改定内容の全体像と現場で必要な対応策をわかりやすく整理しました。さらに、食事体制の見直しを進める中で活用できる選択肢のひとつとして、業務効率化や適温提供に強みを持つニュークックチルもご紹介します。 -

老人ホームは食事で選ばれる時代!最先端のクックチルシステムとは?
今や老人ホームを選ぶポイントは、おいしい食事!厨房で再加熱するだけの簡単調理で、さまざまな食事形態にも対応可能な「クックチル」について解説していきます。