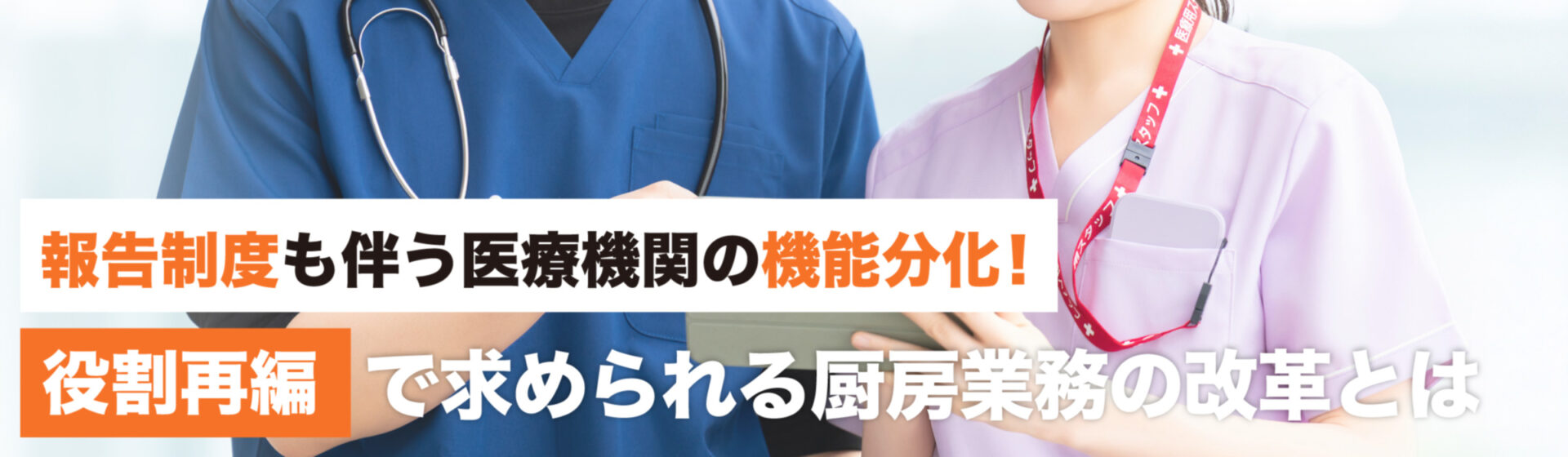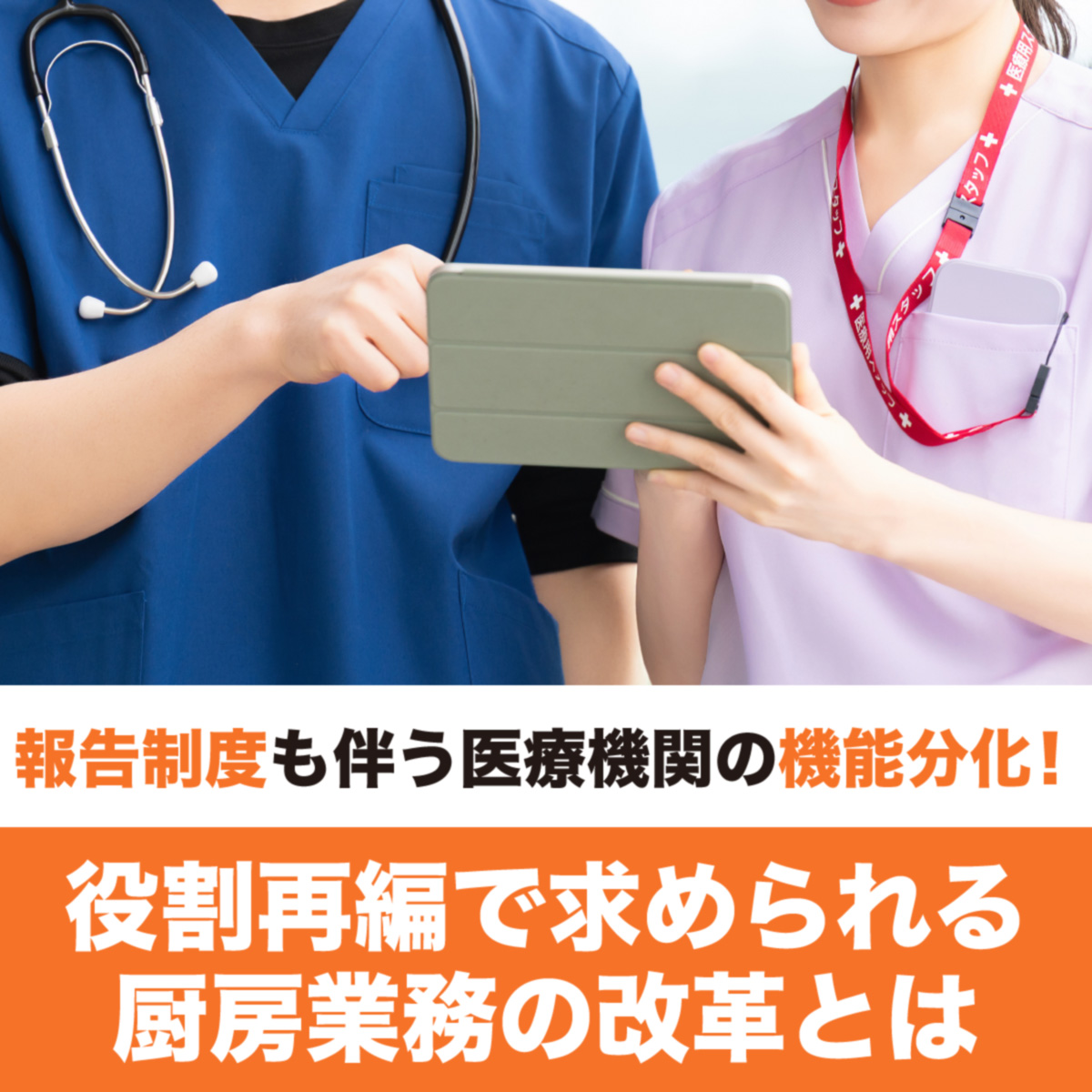近年の日本では、少子高齢化が異例のスピードで進行しています。少子高齢化によって生じる問題の一つが、医療・介護の需要増加に伴う混乱です。政府は、少子高齢化社会においても医療・介護の提供体制が整えられるよう、さまざまな施策を打ち出しています。
今回の記事は、政府主導の施策にとって重要な医療機関の機能分化をテーマにお届けします。機能分化を図るために整備された報告制度に関してもまとめて解説。後半では、医療機関の役割再編と同時に行うべき非医療部門の見直しについてもお伝えします。
目次
医療機関の機能分化とは
少子高齢化の現状と医療・介護への影響
冒頭で触れた通り、日本は将来的に医療・介護の需要が増加する見込みです。少子高齢化の進行は具体的な数値に表れています。総務省統計局が公表した2025(令和7)年1月1日時点の総人口(概算値)は1億2355万2千人で、前年同月よりも59万2千人減少。パーセンテージにすると0.48%の減少です。内訳をみると15歳未満人口は2.46%、15〜64歳人口は0.31%、65歳以上人口は0.03%の減少。ところが、後期高齢者である75歳以上人口のみに絞ってみると、3.48%の増加となっています。
2016(平成28)年の出生児数は100万人超えでしたが、翌年は90万人台へと減少。そこから減少傾向が続いた結果、2024(令和6)年には70万人割れとなり、次世代が育たなくなることへの懸念がさらに大きくなりました。一方、同年10月1日時点での高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)は29.3%です。2070(令和52)年には2.6人に1人が65歳以上、約4人に1人が75歳以上になると推測されています。
このまま少子高齢化が進めば、多くの現役世代によって支えられている日本社会の仕組みは崩壊してしまうでしょう。医療・介護の分野については、高齢者の利用が増えることで各費用が増大し、医療機関や介護施設の人手不足がより深刻になることも問題視されています。つまり、今後は人材や費用が限られる中で、医療・介護の提供体制を安定させなくてはならないのです。

地域医療構想の基盤となる医療機関の機能分化
医療機関の機能分化は、政府が推進している地域医療構想の基盤となる取り組みです。地域医療構想は、2014(平成26)年6月成立の医療介護総合確保推進法によって制度化されました。当初の目的は、第一次ベビーブームに生まれた団塊世代が後期高齢者となる2025(令和7)年に向け、各個人に適した良質な医療を効率的に提供できるようにすること。その目的を達成するため、医療機関の機能分化・連携を促しています。ただし、病床の削減や統廃合を前提にはしていません。政府は、都道府県が主体的に地域の状況を見極め、役割再編をするよう求めています。
機能分化・連携を促す仕組み
医療機関には高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4機能があります。まずは、各機能において必要な病床数を推計。都道府県は各医療機関から現状と今後の方向性について報告を受け、協議を行います。こうした流れを経て、需要にマッチした医療提供体制を整えていくのです。もちろん、需要や医療機関の状況は変わることもあります。2022〜2023(令和4〜5)年度には、各医療機関における対応方針の策定や検証・見直しが行われました。
2024(令和6)年には新たな地域医療構想が公表されました。高齢者の人口がピークを迎える2040(令和22)年を見据え、需要増加が想定される外来・在宅医療、医療と介護の連携体制などに重点が置かれました。医療機関の機能分化・連携・役割再編については、引き続き進めていく必要があるとしています。
医療機関の主な報告制度
本項目では、医療機関の機能分化・連携・役割再編などに活用されている主な報告制度を簡単にまとめました。
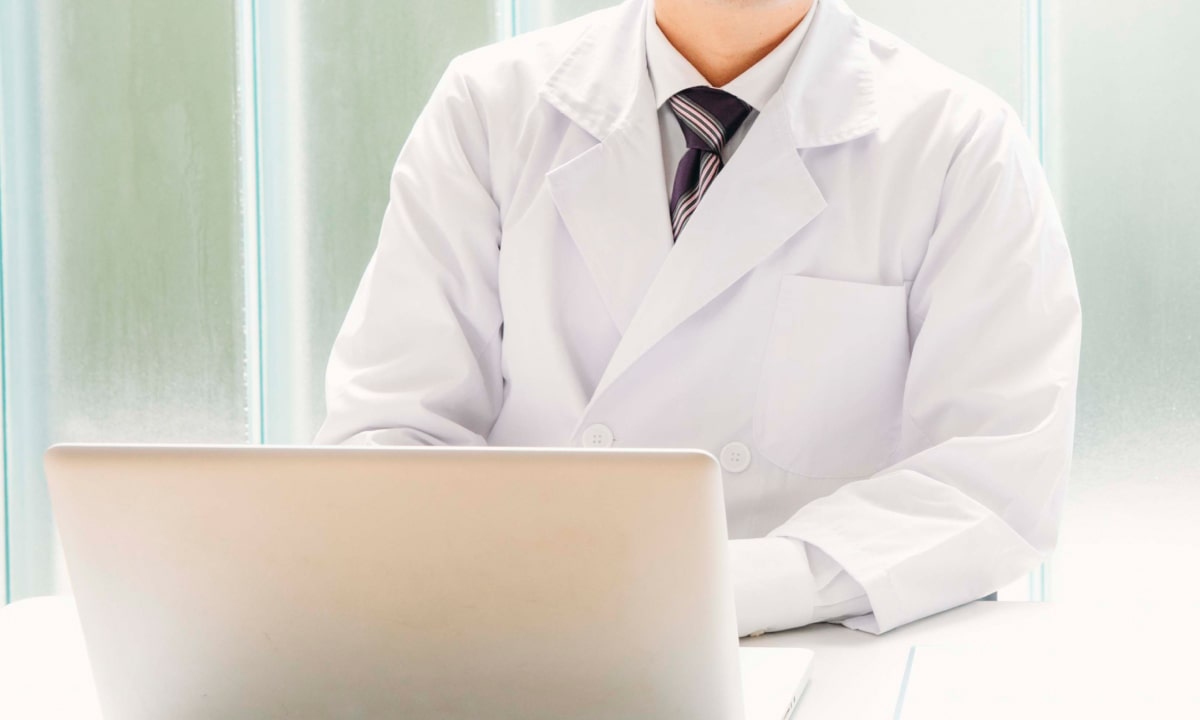
病床機能報告制度
病床機能の現状と今後の方向性を都道府県に報告する制度です。前述した機能分化・連携を促す仕組みが、これに該当します。病院は各病棟、有床診療所は施設全体で高度急性期・急性期・回復期・慢性期のいずれかを選択。幅広い病期に対応する病院の場合は、実情との乖離をなくすため、患者数が多い機能を選択するように指導されています。
外来機能報告制度
外来患者の待ち時間短縮、外来担当医師の負担軽減などを図るための制度です。病院と有床診療所は義務、無床診療所は任意で、外来機能の現状を都道府県に報告します。紹介受診重点外来を重点に置いており、以下の3点について実施状況を把握することが目的です。一定の基準を満たすと、紹介受診重点医療機関として認められます。
- 医療資源を重点的に活⽤する⼊院の前後の外来(例:がん手術前後の外来)
- ⾼額等の医療機器・設備を必要とする外来(例:化学療法や放射線治療を行う外来)
- 特定の領域に特化した機能を有する外来(例:紹介患者への外来)
医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度
国民全員が最適な医療機関や薬局を選べるようにするための制度です。都道府県は、医療機関や薬局から報告された機能情報を取りまとめて公表。国民は、厚生労働省が運用する医療情報ネット(ナビイ)にて症状・目的にあわせた医療機関や薬局を探すことができます。
医薬品・医療機器等安全性情報報告制度
医薬品・医療機器等の安全性を確保するための制度です。医療機関や薬局、ドラッグストアをはじめ、業務において医薬品・医療機器・再生医療等製品を取り扱う施設はすべて報告対象となります。医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用後に副作用、感染症、不具合などが生じた場合、厚生労働省に報告。医薬部外品や化粧品に関しても、同様の対応が求められています。
かかりつけ医機能報告制度
地域のかかりつけ医機能を確保するための制度です。特定機能病院と歯科医療機関を除き、すべての医療機関が報告対象。都道府県は、以下の2点について実施状況を把握し、不足する機能を補うための取り組みや地域内での連携強化などに努めます。
- 1号機能:住民の日常生活において必要な診療を総合的かつ継続的に行う機能
- 2号機能:通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護サービス等と連携した医療提供
非医療部門の見直しと最適化も重要

医療機関においては、機能分化・連携・役割再編を行うだけでなく、非医療部門の見直しも必要といわれています。ほとんどの病院や診療所は、医師が診療を行うだけでは成り立ちません。医療の現場は、経営、事務、情報管理、設備メンテナンス、警備、病院給食、送迎など、さまざまな業務によって支えられています。
良質な医療を効率よく提供するためには、上記に挙げたような非医療部門の最適化も重要です。コスト運用や人員配置、業務フローなどの現状を細部までしっかりと把握し、課題改善に向けて動くことが医療提供体制の整備につながります。
また、患者が最適な医療を受けられることはもちろんですが、医療従事者が働きやすいことも非常に大きなポイント。無理なく長期的に働ける環境は人手不足対策として有効であり、結果的には施設運営の安定化にメリットをもたらすのです。
厨房業務の再定義はナリコマがサポート

ナリコマは、医療機関における厨房業務の再定義をお手伝いしております。治療食・介護食への展開も可能な日替わりの献立サービスでは、クックチル方式により厨房の調理工程を簡略化。オリジナルシステムによる事務系作業の効率化、専任アドバイザーによる現場改善のご提案など、負担が大きくなりがちな厨房業務を細やかにサポートいたします。病院給食の見直しや最適化をお考えの際には、ぜひ一度ナリコマにご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。
コストに関する記事一覧
-

介護施設の給食委託。選び方のポイントと成功するコツを紹介!
介護施設の給食委託をテーマにお届けする記事です。給食委託会社の選び方で重視すべきポイントのほか、介護施設における食事の重要性や委託以外の給食提供方法などもまとめて詳しくお伝えしています。
-

給食の食材費高騰を抑えるための具体策とは|病院・介護施設での取り組みを考える
病院や介護施設では、毎日多くの利用者に給食を提供しています。近年の物価高騰により、食材費の負担が大きく増しているのが現状です。特に、円安や原材料費の高騰、人件費や物流コストの上昇が重なり、経営を圧迫する要因となっています。
このような厳しい状況の中で、施設側は食材費のコストを抑えつつ、栄養バランスのとれた給食を提供する工夫が求められています。本記事では、食材費が高騰する背景や影響を整理し、病院・介護施設で実践できる具体的な対策をご紹介します。食材費の負担を軽減しながら、安定した給食提供を続けるためのヒントを探していきましょう。 -

育成就労制度とは?技能実習制度の制度変更による違いや特徴を解説
「育成就労制度」は、2024年に創設され3年以内に施行される制度です。この記事では、旧制度である「技能実習制度」の概要や課題を振り返りながら、制度変更によりどう変わるのかを、育成就労制度の特徴や受け入れ企業の実務のポイントも押さえながら解説します。