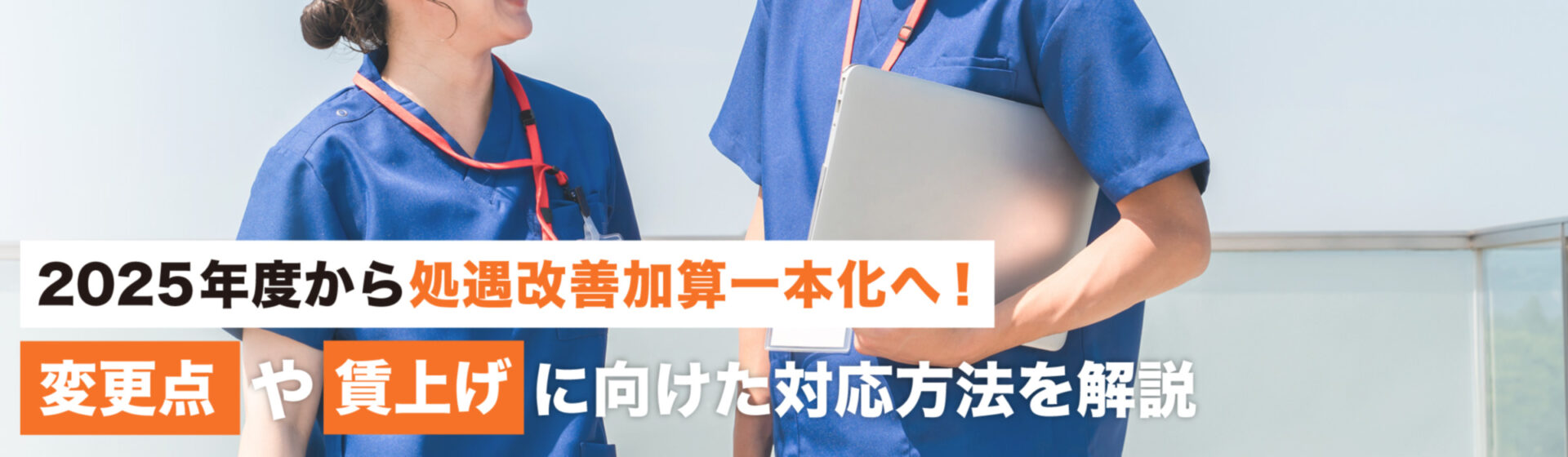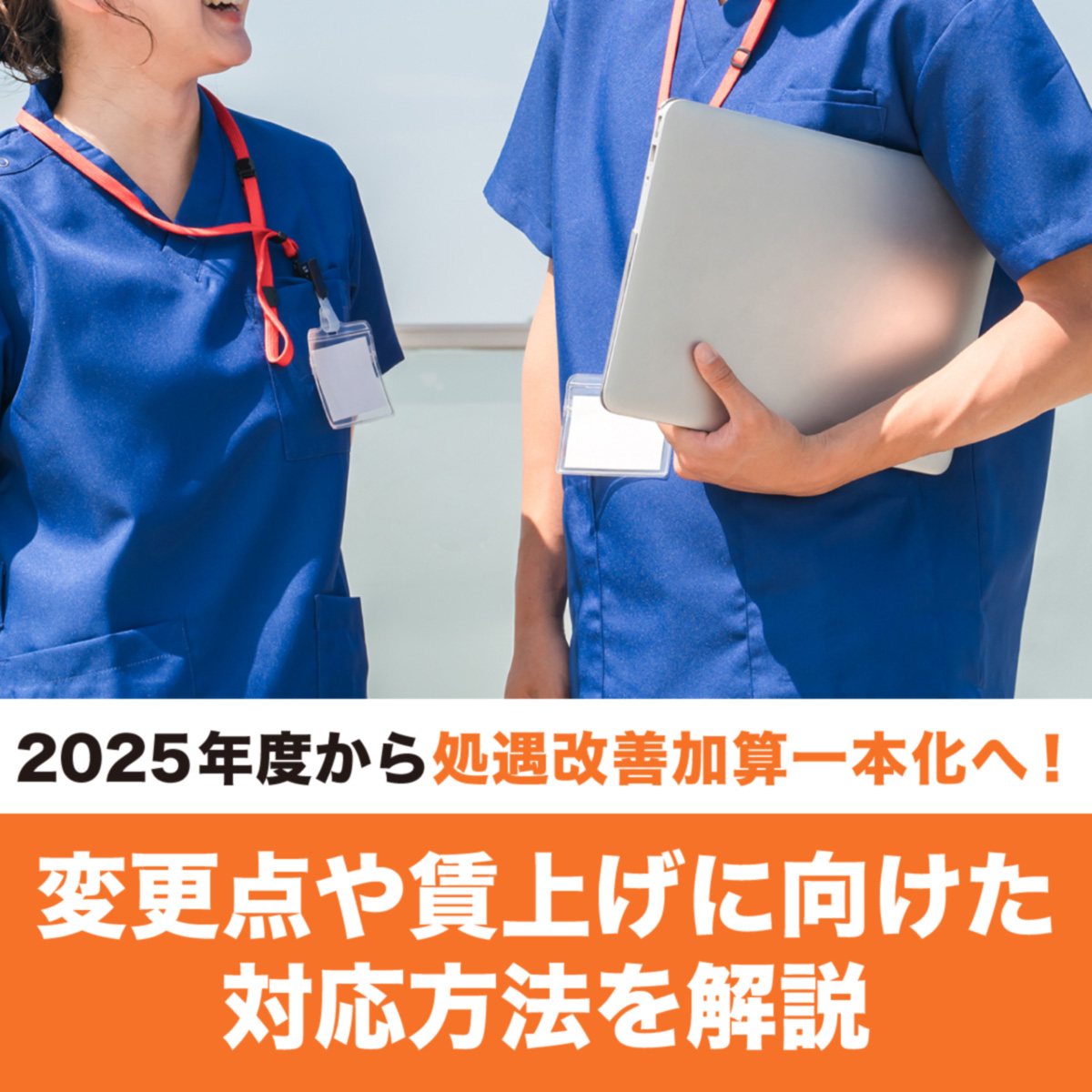介護職員処遇改善加算は、介護職員の賃金や環境の改善などを目的に取り入れられている制度です。利用には事業所が要件を満たす必要がありますが、介護職員の賃上げをはじめ、人手不足の課題解決にもメリットが期待できます。2025年度からは今までの環境が変わり、処遇改善加算一本化制度へと変更になりました。この記事では、主な変更点と共に、賃上げにつなげるための対応方法として取り組みのコツも解説します。
目次
2025年度の処遇改善加算制度変更までの賃上げの歩み

2025年までの間に介護職員の処遇改善は段階的に行われてきました。下記は、厚生労働省の「介護従事者処遇状況等調査」による、各年の取り組み前後の賃金の差を調査した実績の概要です。
- 2009年4月:月額9,000円の賃金改善
- 2009年度補正予算:月額15,000円の賃金改善
- 2012年4月:月額6,000円の賃金改善
- 2015年4月:月額13,000円の賃金改善
- 2017年4月:月額14,000円の賃金改善
- 2019年10月:月額18,000円の賃金改善、勤続年数10年以上の介護福祉士は月額21,000円の賃金改善
- 2022年10月:基本給等が月額10,000円の賃金改善(平均給与額全体では月額17,000円の賃金改善)
- 2024年6月:基本給等が月額11,000円の賃金改善(平均給与額全体では月額14,000円の賃金改善)
厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」の結果では、介護職員等処遇改善加算を取得している施設や事業所において、2023年度と2024年度を比較して月給・常勤の介護職員の基本給等が11,130円増加していることがわかっています。平均給与額としては、13,960円の増加となりました。今後も、業務効率化や職場環境の改善などに取り組む事業者には、賃上げにつながる支援の実施が予定されています。
2025年度の処遇改善加算一本化の特徴
2025年度から処遇改善加算制度の一本化が完全施行となりましたが、その背景には、介護職員の人材確保をさらに推進し、2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップにつなげることが目指されています。

今まで「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等加算」の合計の加算率だったものが、新加算として「介護職員等処遇改善加算」となり、4段階の加算率のシンプルな構成になりました。2024年度末までは経過措置期間が設けられていましたが、2025年度以降は新加算のシステムとなります。
一本化後の新加算の算定要件は、下記の「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3種類です。
キャリアパス要件
キャリアパス要件の主な内容と新加算の種類は下記です。
|
キャリアパス要件の種類 |
内容 |
該当する新加算の種類 |
|
キャリアパス要件Ⅰ |
介護職員の職位や職責、職務内容などに応じた任用等の要件を定めて、賃金体系を整備する。 |
Ⅰ~Ⅳ |
|
キャリアパス要件Ⅱ |
介護職員の資質向上の目標や規定内容に関する具体的な計画を策定し、研修の実施などを行う。 |
Ⅰ~Ⅳ |
|
キャリアパス要件Ⅲ |
経験や資格、一定の基準などに基づいて、昇給する仕組みを整備する。 |
Ⅰ~Ⅲ |
|
キャリアパス要件Ⅳ |
経験や技能のある介護職員のうち1人以上が、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上となること。 |
Ⅰ・Ⅱ |
|
キャリアパス要件Ⅴ |
サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置する。 |
Ⅰ |
新加算ⅣとⅢのキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、申請時点で未対応でも、2025年度中(2026年3月末まで)に対応するとの誓約をすれば可能となっています。キャリアパス要件Ⅳについては、小規模事業所等で加算額全体が少額といった場合などにより、440万円以上の賃上げが難しい場合は免除となります。
月額賃金改善要件
月額賃金改善要件には「月額賃金改善要件Ⅰ」と「月額賃金改善要件Ⅱ」があります。
|
月額賃金改善要件の種類 |
内容 |
該当する新加算の種類 |
|
月額賃金改善要件Ⅰ |
新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を月給の改善に充てること。 |
Ⅰ~Ⅳ |
|
月額賃金改善要件Ⅱ |
前年度と比較して、前制度のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基 本給等の改善を行うこと。 |
Ⅰ~Ⅳ |
「月額賃金改善要件Ⅰ」では、賃金総額は一定のままでも可能ですが、一時金で主に加算による賃金改善を行っている場合は、一時金の一部を基本給・毎月の手当に付け替える対応を行わなければいけないことがあります。
また、「月額賃金改善要件Ⅱ」は、前制度のベースアップ等加算が未算定の場合にのみ適用されるため注意しましょう。2024年5月までに旧制度で算定していて、なおベースアップ等加算が未算定で、2026年3月までに新規に新制度で算定する場合が対象です。
職場環境等要件
職場環境等要件には、下記の内容があります。
|
内容 |
該当する新加算の種類 |
|
6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上、また生産性向上は2つ以上取り組むこと。 |
Ⅲ・Ⅳ |
|
6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上、また生産性向上は3つ以上で必須項目を含み取り組むこと。 さらに、情報公表システム等で、実施した内容について具体的に公表すること。 |
Ⅰ・Ⅱ |

6つの区分は下記の項目となり、前制度と大きく変わりません。
- 入職促進に向けた取組
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 両立支援・多様な働き方の推進
- 腰痛を含む心身の健康管理
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
- やりがい・働きがいの醸成
個々の区分の具体的内容も前制度と比較して大きく変わらない部分があるものの、例えば、有給休暇が取得しやすい環境の整備に関する項目がより具体的で充実した内容になるなど、部分的に変更点があるためよく確認しましょう。また、生産性向上のための取り組みの内容が4項目から8項目に増えており、新加算ⅡまたはⅠを目指す場合、下記の項目のどちらかが必須となります。
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
職場環境等要件は、申請時点で未対応でも、2025年度中(2026年3月末まで)に対応するとの誓約をすれば可能となります。また「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請している場合は2025年度は免除されます。
新加算の賃上げに向けた対応方法

前制度では、加算の種類によって事業所内での職種間配分が決められていましたが、一本化後は職種間配分のルールが緩和されました。介護職員への配分が基本で、経験や技能のある職員に重点的に配分することが前提ですが、加算全体を事業所内で柔軟に配分することが認められています。
新加算では加算率の引き上げが行われており、取り組み方次第で補助金の対象にもなるなど、得られるメリットはさまざまです。また、処遇改善加算によって一定の賃上げを行うと、賃上げ促進税制により法人税等の税額控除の対象にもなります。
職場環境等要件に取り組むコツ
職場環境等要件の個々の要件は、工夫して取り組めば普段の業務の中で徐々に取り入れやすい事柄が多いです。例えば「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」では、短時間でも年に数回面談を行うことで定期的な相談の機会を確保できます。「やりがい・働きがいの醸成」では、ちょっとした感謝でもカードに書いて伝える仕組みなどを作ることで、ケアの好事例の共有などに役立つでしょう。
新加算ⅡまたはⅠを目指す場合の必須要件の一つである「現場の課題の見える化」については、定例会議などの時間に課題について話し合ったり、思いつくことを付箋などに書いたりすることで実施しやすくなります。
賃上げとあわせた給食業務改善にはナリコマのサービスもご活用ください

介護施設の給食業務の人手不足解消には、賃上げとあわせて、業務自体の改善も役立ちます。スキルを問わず簡単に行える業務に改善することで、より多くの人が働きやすくなり、離職も防ぎやすくなるでしょう。ナリコマでは、簡単に調理できるクックチルやニュークックチルのサービスをご提供しております。施設の給食業務改善の際には、ぜひご活用ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
コストに関する記事一覧
-

ニュークックチルに必要な再加熱機器とは?スチームコンベクション・再加熱ワゴン・マイクロ波加熱装置を紹介
病院や介護施設で導入が進むニュークックチル。効率的な調理体制を整えるために欠かせないのが「再加熱機器」です。でも実際、どんな機器を用意すればいいの?と悩まれる方も多いはず。
調理を前日に終えておける仕組みは魅力ですが、食事を提供する直前に安全かつおいしく仕上げるためには、専用の再加熱機器が必要になります。
ただ、再加熱機器といっても「スチームコンベクション」「再加熱ワゴン」「マイクロ波加熱装置」など種類はさまざま。それぞれ仕組みや特徴が異なり、自施設の配膳スタイルや厨房動線によって、適した機器は変わってきます。
今回は、ニュークックチルを運用するために必要な再加熱機器と、その違いや導入時のポイントを解説します。 -

給食用食材の調達&調理はどうする?病院や介護福祉施設でのポイントも解説
学校や保育園、病院、介護福祉施設など、さまざまな場所で提供されている給食。そこに欠かせないものの一つが食材です。日本は豊かな食文化が楽しめる国ですが、近年では国産・輸入問わず、食材をスムーズに調達することが難しくなってきました。
今回の記事は、給食における食材について詳しくお届け。食材調達の現状、病院や介護福祉施設の給食用食材で配慮すべきポイントなどを解説します。 -

進化する病院食!おいしい病院食はクックチルシステムで叶えられる
今もなお、ネガティブなイメージが付きまとう病院食。病院食は味気ないというイメージはもう昔の話です。現在では、患者の治療や回復を支えるため、栄養バランスだけでなく、おいしさや見た目に配慮した食事が提供されています。進化を遂げるおいしい病院食、その裏にある技術や取り組みに迫ります。