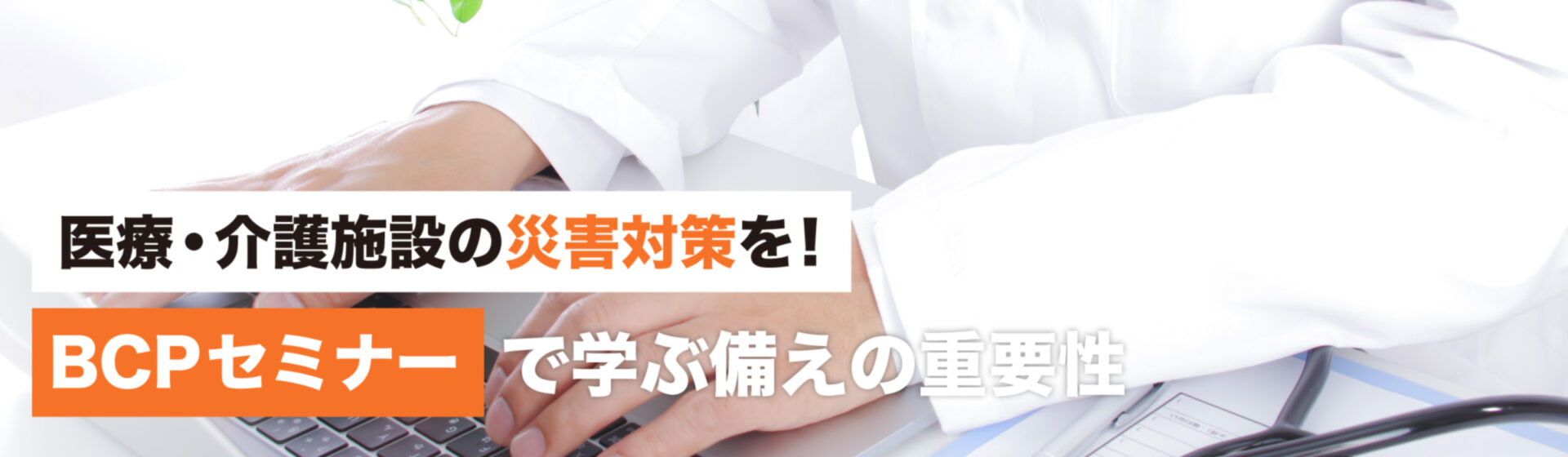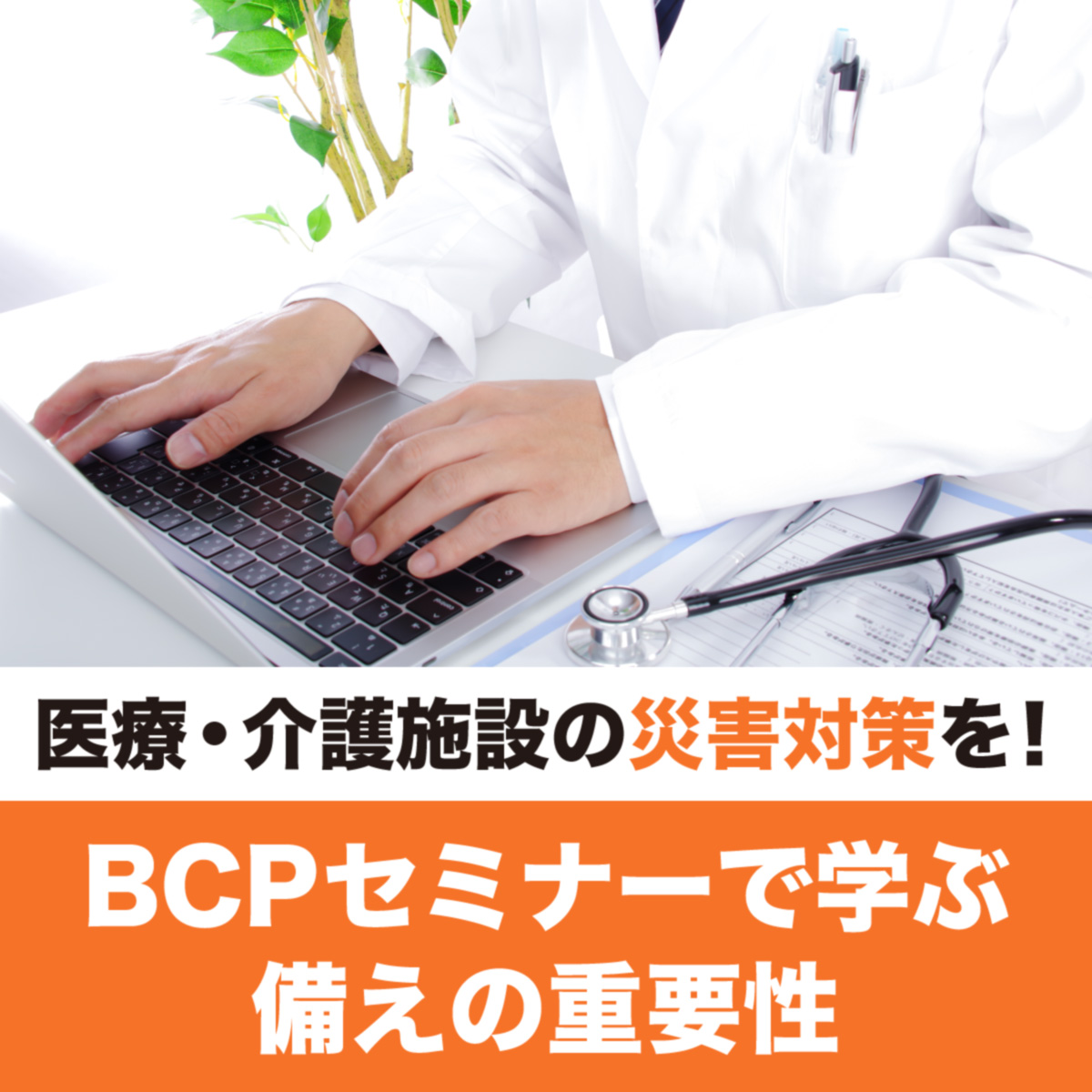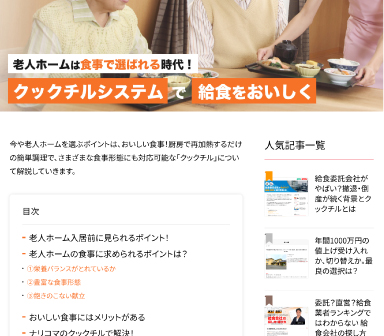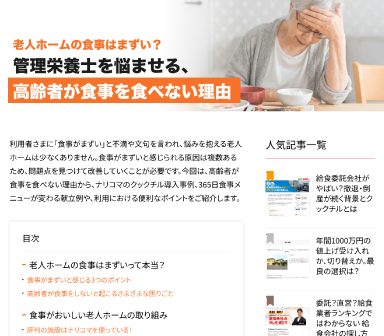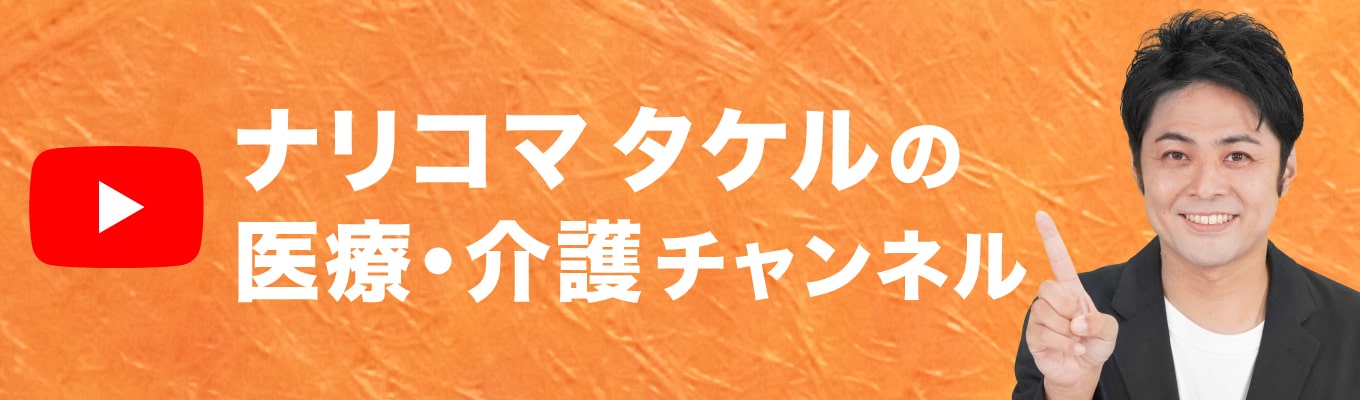病院や介護施設は、災害や緊急事態の発生時、入院患者や施設利用者の安全と健康を守りながら、必要な医療・介護サービスを継続しなければなりません。そのためには、事業継続計画(BCP)の策定が不可欠です。BCP(Business Continuity Plan)とは、災害時において、業務を継続するための計画を指しています。病院・介護施設では特に「建物や設備の損壊」「インフラの停止」「人手不足」などのリスクを想定した備えが求められます。
しかし、対応するべき事柄が多すぎて、具体的にどのような対策を行ったらよいかお悩みの方もいることでしょう。そこで役立つのが、「BCP策定のポイントを学べるセミナー」です。今回は、病院・介護施設におけるBCPの重要性と、セミナーを活用して効果的に備える方法について詳しく解説します。
目次
病院・介護事業者におけるBCPの重要性とは
災害や感染症の発生時、病院・介護施設は患者や利用者の生命を支える重要な役割を担っています。しかし、インフラの停止や人手不足によりサービスの提供が困難になると、利用者の健康や生活に深刻な影響を及ぼします。そのため、医療・介護の現場では、普段からBCPを策定し、いざという時に迅速に対応できる体制を整えておくことが大切です。

病院・介護業界が直面する災害リスク
介護施設や病院では、災害時に以下のようなリスクに直面する可能性があります。
- 建物や設備の損壊:地震や台風などによる被害で、施設の機能が停止する。
- 社会インフラの停止:停電や断水、物流の混乱により、医療・介護サービスの継続が困難になる。
- 人手不足:職員が出勤できない、または避難対応に追われ、本来の業務に人手が回らなくなる。
特に、介護施設の利用者は、日常生活や健康維持において、支援がなくては困難な方が多いです。サービスの提供が滞ると生活や生命に直接的な影響が生じるため、業務が停止しないように対策を取らねばなりません。
BCP策定がもたらすメリット
BCPの策定は病院や介護施設において、単なるリスク対策というだけではありません。実は経営や施設運営の面でもたくさんのメリットがあるのです。
患者や利用者・職員の安全が確保できる
病院や介護施設においては、患者や利用者の移送やインフラの確保など、業務を継続することは命を守ることと同じです。自然災害や感染症などの緊急事態が発生した際、BCPが策定されている施設では迅速かつ適切な対応が可能になり、患者や利用者、職員の安全確保へとつながります。
節税優遇や金融支援が受けられる
2019年に中小企業庁より施行された「中小企業強靱化法」によって、BCPを策定することで、下記の税制優遇措置や補助金を受けることができます。
- 対策強化のための設備投資に対する特別償却(20%)
- 信用保険の保証枠の追加
- 日本政策金融公庫・BCP融資の拡充による防災に係る設備資金の貸付金利の引き下げ
- 補助金採択にあたって加点措置が受けられる
- 自家用発電設備等導入への一部補助
感染症発生時にワクチンの優先接種を受けられる
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の第二十八条には、厚生労働大臣の登録を受けている「登録事業者」の業務従事者は、優先的にワクチン接種ができる旨が書かれています。
ここで指している「登録事業者」とは、BCPを策定していることが条件となり、BCPの有無が職員や利用者の安全に直結する場合もあるのです。
BCP策定に必要なポイントとは
医療機関や介護施設において、BCPの策定は患者の命を守り、非常時にも地域医療を崩壊させないためにも重要なものです。BCPの策定のために押さえておきたいポイントをご紹介します。

リスクの洗い出し・優先業務の特定
BCP策定の第一歩は、施設が直面する可能性のあるリスクを洗い出し、非常時に優先すべき業務を明確にすることが挙げられます。特に医療・介護の現場では、患者・利用者の生命維持に関わる業務を最優先としますが、自然災害、感染症、人為的ミスなど、発生しうるリスクを幅広く想定しながら、事業に与える影響の大きさを判断して対策を考えなくてはなりません。
また、災害時には限られた人員と設備での対応を強いられる場合もあるでしょう。職員の出勤状況や、病院・施設の被災状況に応じて対応できるよう、業務の優先順位を決めることが不可欠です。
備蓄品の確保
患者・利用者の安全を確保しながら業務を継続するためには、非常時に必要な備蓄品の確保も必要不可欠です。特に、食料や飲料水、医薬品、感染症対策用品など、施設の運営に欠かせない物資を十分に準備しておくことが求められます。また、備蓄品は単に用意するだけでなく、使用期限や管理方法を明確にし、定期的に点検と補充を行うことが重要です。
職員教育と訓練
BCPは策定したら終わり、ではありません。実際の災害時に機能しなければ意味がないため、職員への教育や定期的な訓練を行っていくことも必要です。
災害時の対応マニュアルの周知や、シミュレーション訓練の実施によって、緊急時でも適切な対応ができるようになります。また、訓練を通じて課題を確認しながら解消していくことで、災害時でもスムーズに行動できるでしょう。定期的に見直しを行い、最新のリスクや施設の状況に応じて更新していきましょう。
BCPセミナーで学べることやそのメリット
BCPセミナーでは、医療機関や介護施設に特化した内容を学びます。また、具体的な事例をもとにリスク対策を学べるので、実際の災害や緊急事態への危機対応力の向上が期待できます。

病院向けBCPセミナーの特徴
病院では、地震や台風などの自然災害に加え、サイバー攻撃への備えも求められています。病院がターゲットになりやすい理由としては、患者の病歴や診断情報、保険情報など、収益性が高い個人情報を有しているほか、病院で使用しているシステムは脆弱性を突かれやすいといった特徴があるためです。
近年、医療機関を狙ったサイバー攻撃が増加しており、電子カルテの閲覧不可や、診療停止、患者の個人情報漏洩といった被害が報告されています。こうしたリスクに対応するため、病院向けのセミナーではIT-BCPに特化したものもあり、システム障害やサイバー攻撃を受けた際に迅速に診療体制を復旧させる方法を学ぶことができます。
また、サイバー攻撃だけでなく電力確保も大変重要です。命をつなぐ医療機器は停電になっても絶対に止めることはできません。太陽光発電や蓄電池を活用した電力確保の手法の紹介など、停電時にも医療を継続するために具体的な対策を学べます。
介護施設向けBCPセミナーの特徴
介護施設は2024年4月からBCPの策定が義務化されています。介護施設向けのBCPセミナーでは、BCPの基本的な理解を深める講義に加え、実際にひな形を活用してBCPを策定する演習を行うものもあります。
自然災害時の対応策や感染症発生時のBCP策定方法について学び、施設の実情に合わせた対策を具体的に検討できるのが特徴です。策定後の研修や訓練の進め方についてもセミナーで取り扱っている場合もあり、継続的にBCPを運用・改善していくために必要な技術を身につけられます。
ナリコマのBCPに関する取り組み
ナリコマは、病院や介護施設向けに完全調理済み食品(クックチル)を提供する企業として、厨房のBCP対策にも力を入れています。災害時の食事提供を支える非常食の確保や、BCP策定に役立つ情報提供を行い、施設の事業継続をサポートしています。

災害に備えた非常食の確保
病院や介護施設では、災害時であっても入院患者や利用者への食事提供を止めることはできません。しかし、大規模な災害が発生すると、建物の損壊や物流のストップなどから、食材調達も困難になる可能性があります。ライフラインが断たれても食事を提供するために、非常食を備えておくことも重要です。ナリコマでは、災害時にも迅速に対応できる体制を整えており、全国6ヵ所のセントラルキッチンで製造・配送を行っています。
また、栄養価に配慮しつつ、加熱不要で提供できるほか、利用者の身体能力に合わせた4形態の非常食を用意しています。
ナリコマの非常食の特徴
- 温めずにそのまま食べられる
- 栄養価が考慮されている
- 長期保存に適したパッケージ、常温で長期保存可能
- 強度の高い段ボールを使用
- 管理しやすいよう箱の側面には2ヵ所に商品名と最短の賞味期限を記載
- ナリコマ契約施設はポイントでの購入も可能
- 未契約施設にも提供が可能(諸条件あり)
病院・介護施設の厨房のBCP対策に、ぜひナリコマの非常食をお役立てください。
BCP策定セミナーの開催
現在、BCPの策定が義務付けられているのは介護施設と、病院の中では災害拠点病院のみ。災害拠点病院では2019年の時点でほぼ100%策定が完了していますが、病院全体で見てみるとのBCP策定率は25%と決して高くはありません。
ナリコマでは、BCP策定を支援する無料セミナー「30分でわかる!これから作るBCPセミナー」を開催しています。これからBCPを策定しようと考えている病院向けに、BCPの概要や策定に必要なポイントをわかりやすく解説しているセミナーです。BCPの策定に関してお悩みの方は、下記ページのフォームよりお気軽にお申込みください。
BCP策定に関するナリコマの取り組みとして、セミナー以外にもお役立ち情報の無料ダウンロードができます。BCP策定までの流れや、BCP策定のポイントがよくわかる資料を公開しておりますので、こちらもぜひご活用ください。
動画でわかりやすく知りたいという方には、YouTubeの「ナリコマ タケルの医療・介護チャンネル」がお勧めです。BCPに関する動画を公開しており、いつでも学べる環境を提供しています。
BCP策定の第一歩はナリコマの無料セミナーから!
病院や介護施設の運営において、災害時や緊急事態への備えは決して後回しにすることはできません。しかし、何から手をつければいいのかわからなかったり、具体的な策定方法がわからずに悩んだりしている施設も多いのではないでしょうか。

そんな時には、ぜひナリコマの無料BCPセミナーをご活用ください。BCPセミナーは事業継続のために必要な知識と実践方法を学ぶ絶好の機会です。ナリコマは、単なる食品提供にとどまらず、病院や介護施設の「万が一」に備えるお手伝いを全力で行います。今こそ、ナリコマのセミナーを活用し、一緒に災害時でも安心できる環境づくりを始めましょう!
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。
コストに関する記事一覧
-

ニュークックチルの運用をスムーズに!導入スケジュール作成時の留意点
近年は少子高齢化が進んでおり、さまざまな現場で人手不足が深刻化しています。病院や介護福祉施設などの給食を提供している厨房も例外ではありません。給食業界は以前から人手不足の傾向が強く、日常的に負担が増えたり、長時間労働が続いたりすることが問題といわれてきました。
今回の記事は、そんな厨房業務の負担軽減や効率化を実現するニュークックチルについてお伝えします。導入スケジュールを作成する際に留意すべきポイントを順に解説。ぜひ最後までお読みいただき、スケジュール管理の参考になさってください。 -

安い給食委託会社のメリットとデメリットとは
給食コストの上昇は業界全体の課題となっています。少しでも給食コストを抑えるために安い給食委託会社に切り替えを検討している方必見! 安い給食委託会社のコストダウンの仕組みについても紹介しています。
-

賃金上昇&物価上昇で運営が難しい!病院や介護福祉施設でコストを下げるには?
近年では急速に物価上昇が進んでいますが、同時に、各業界では賃上げの動きもみられるようになっています。病院や介護福祉施設はかねてから運営が難しく、赤字になりやすいといわれてきました。しかし、賃金上昇や物価上昇の影響は大きく、依然として厳しい状況は続いているようです。
本記事では、賃金上昇と物価上昇が進む現状を解説し、病院や介護福祉施設が直面している赤字問題やコスト削減のポイントなどについてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。