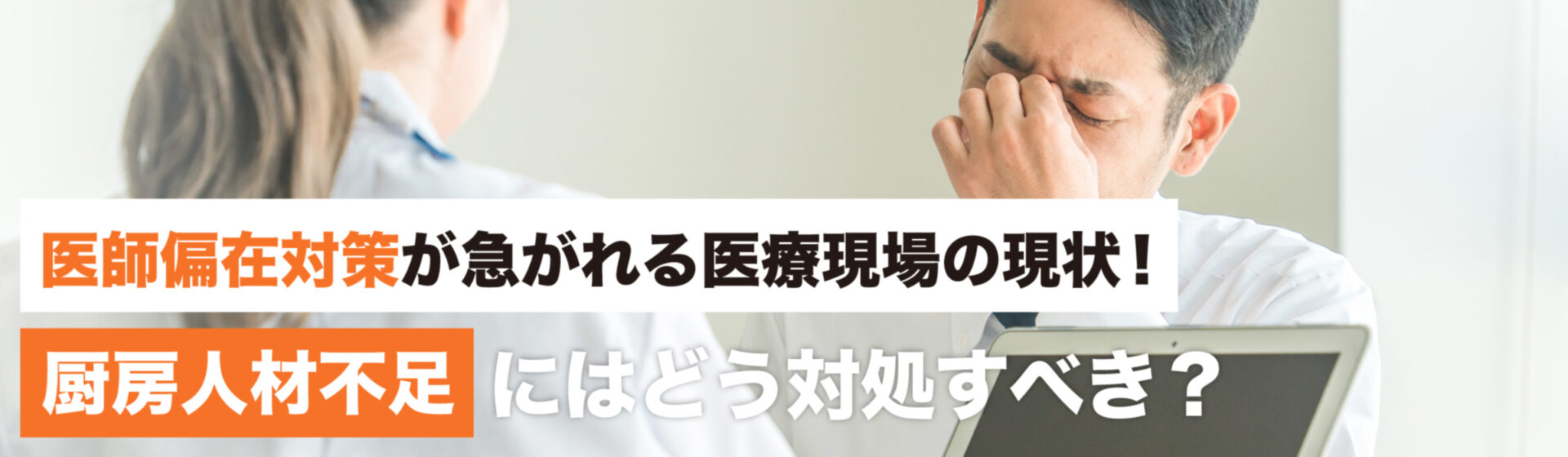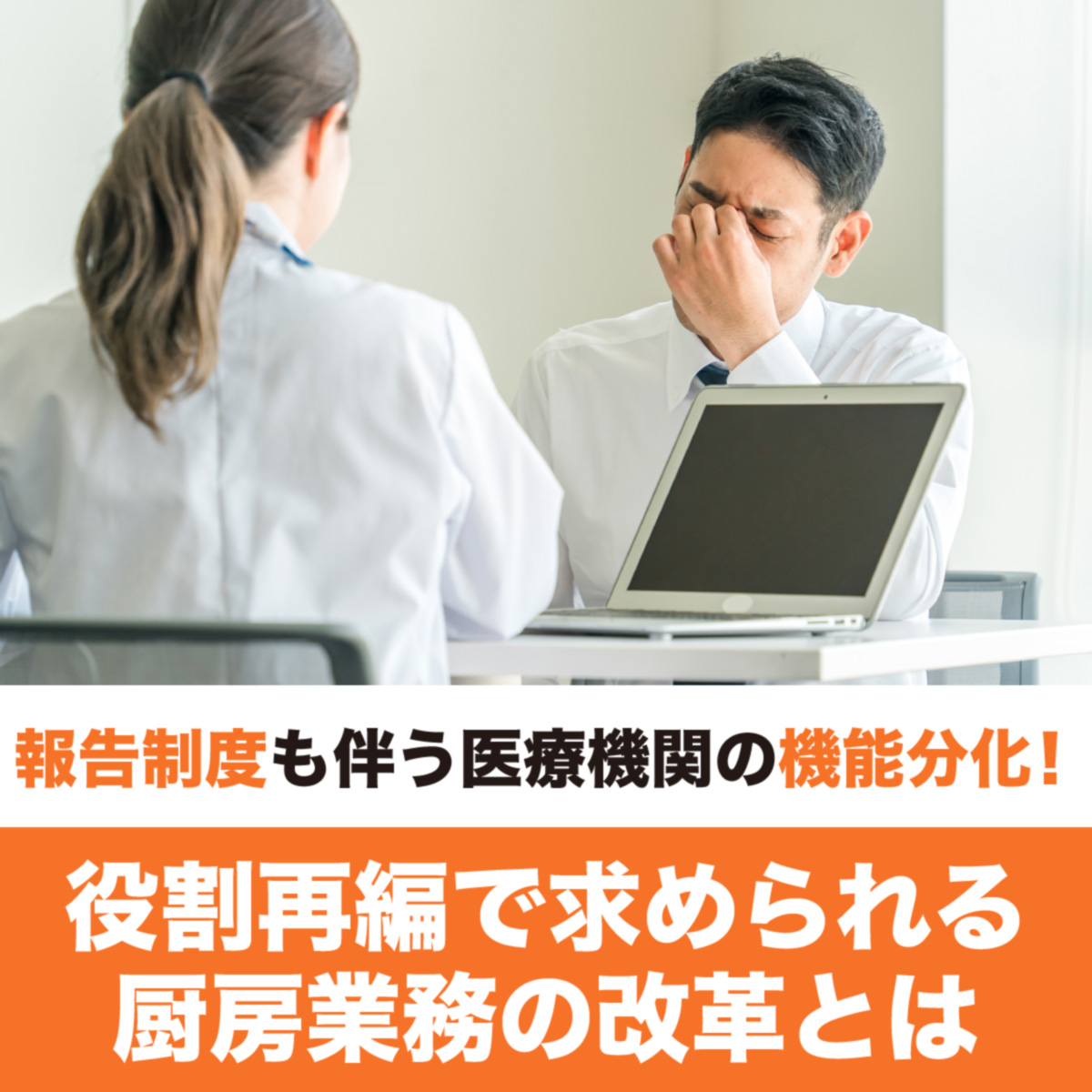近年の日本は少子高齢化が進んでおり、総人口も減少傾向です。さまざまな社会保障を必要とする高齢者が増える一方、主な労働者である若者が減少しているため、将来的に多くの問題が生じるとされています。人材不足は、早期に解決すべき問題の一つ。医療業界は高齢者からの需要増加が見込まれており、良質かつ効率的な医療提供体制の構築が課題とされています。
今回の記事では、医療業界の人材不足解消に向けた医師偏在対策をクローズアップ。医師の偏在が起こっている現状や、その対策について詳しくお伝えします。記事後半では、厨房などの非医療部門における人材不足に関しても解説。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
目次
地方病院支援として期待される医師偏在対策
地域によって偏りがある医療従事者の数
医療業界の人材不足は、「医療従事者の数が少ない」という単純な問題ではありません。「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」をみると、医師は増加傾向にあります。同年公表の「衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」をみても、准看護師は減少傾向ですが、保健師・助産師・看護師は増加しているのです。

ところが、地域によっては人員の偏りが生じています。全国の人口10万対医師数は前回(令和2年の256.6人)より5.5人増加した262.1人ですが、都道府県や指定都市・特別区・中核市ごとの数には差があります。都道府県別の数を例にすると、上位の徳島県335.7人、高知県335.2人、京都府334.3人に対し、下位は埼玉県180.2人、茨城県202.0人、千葉県209.0人。このような地域による偏在は、医師に限らず、ほかの医療系専門職においても発生しています。
こうした状況に陥ってしまう原因の一つは、都市部での勤務を希望する人が多いこと。日本においては、居住や移転、職業選択の自由が保障されています。医療従事者が個人や家庭の事情を踏まえ、住みやすく働きやすい土地に身を置くことは、ごく一般的な流れといえるでしょう。しかし、今後さらに進行する少子高齢化社会に対応していくためには、都心部以外の医療体制も整え、誰もが適切な医療を受けられるようにしなければならないのです。
診療科による医師の偏在も問題に
前述した地域差以外では、診療科による偏在もあるようです。24時間体制が求められる救急科や外科、産科などは、特に医師不足が深刻といわれています。日本医師会総合政策研究機構によるレポートでは、平成22(2010)年から令和2(2020)年にかけては専門分化が進み、包括的なケアを行う内科と外科の医師が減少したと報告されています。35歳未満の若手医師に限定すると、小児科も大きく減少。その一方で、形成外科や美容外科を希望する若手医師は増えているようです。
また、令和4(2022)年の女性医師数は2年前より4.6%増加。皮膚科、眼科、小児科、産婦人科などは女性医師が多い傾向にあり、これも診療科による偏在に影響しているのではないかという見方もあります。
医師偏在対策は医療提供体制の安定化に不可欠
中小規模の病院や診療所が多い地方では、前述したような医師の偏在が特に大きく影響し、医療提供体制が不安定になることもあります。状況によっては、病院や診療所の運営継続が難しくなるかもしれません。こうした地方の医療提供体制を安定させるには、医師偏在対策を迅速に進める必要があります。

対策の基礎となるのは、各都道府県が策定する医師確保計画です。国が提示した医師偏在指標によって状況を把握し、医師確保の方針や目標医師数を設定。地域医療対策協議会が協議や調整を行い、地域医療支援センターと連携しながら計画を進めていきます。実際にどのようなことが行われているのか、主な施策例をみてみましょう。
・大学医学部と連携した地域枠
卒業後、特定の地域・診療科で診察することを条件にした学生向けの選抜枠です。
・臨床研修医の募集定員上限数を都道府県別に設定
全国の臨床研修希望者に対する募集定員倍率を縮小し、都道府県別で人数の上限を設定。医学部や医師が多い地域においては、医師が少ない地域への配慮が求められます。
・専攻医の採用上限数を都道府県別・診療科別に設定
日本専門医機構が、都道府県別・診療科別の必要医師数を考慮した採用上限数を設定。一般的には、シーリング制度と呼ばれています。
・キャリア形成プログラム
医師の能力開発・向上を図り、人材不足の現場も支援するプログラムです。都道府県が連携している医療施設で若手医師の臨床研修や専門研修を実施。研修を終えた若手医師は、人材不足の地域や医療施設にて一定期間勤務します。
医師以外の人材不足も深刻な医療現場

医療機関における人材不足は、医師などの専門職に限ったことではありません。冒頭で触れた少子高齢化の影響から、非医療部門においても人が集まりにくくなっているのです。病院給食の提供、各種設備のメンテナンス、施設内外の清掃や警備、患者の送迎サービスなど、病院や診療所はさまざまな業務に支えられています。
もちろん、施設によって必要な人材は異なります。しかし、少子高齢化が進む今後は、従来のような人員配置ができなくなる可能性も高いのです。施設を維持し、持続可能な医療提供体制を整えるには、非医療部門も含めた省力運営を目指すことが重要といえるでしょう。
厨房における人材不足解消・負担軽減のポイントとは
病院給食を提供している医療機関では、厨房人材不足も問題になっているかもしれません。最後は、厨房における人材不足解消と負担軽減のポイントをまとめてお伝えしておきましょう。
①外国人や高齢者の雇用
人材不足解消に向けて最初に取り組みやすいポイントは、採用の間口を広げること。近年では、人材確保のために外国人や高齢者の雇用が注目されています。言葉の壁があったり、力仕事には不向きだったりするケースも想定されますが、適材適所を心がけることで業務はスムーズに回るでしょう。長期的に働ける人材育成のため、研修や指導を丁寧に行うことも大切です。
②全面もしくは一部業務の委託化
現状が直営であれば、委託サービスによって人材不足解消と負担軽減を図るのもいいでしょう。ただし、直営から委託への切り替えは、コストが大幅に増えるかもしれません。コストを抑えるには、全面委託ではなく、一部業務を委託化するという方法もあります。
また、病院給食では治療食、禁止食、介護食などのバリエーションも必要になるため、委託であっても柔軟な対応力や連携体制が欠かせません。委託業者ごとにメリットとデメリットを洗い出し、施設に適したサービスを見極めることが重要です。

③IT技術や新調理方式の導入による業務効率化
業務効率化は、負担軽減への近道です。アプリなどのIT技術を導入すると、煩雑な事務や管理業務の手間を削減できるかもしれません。また、調理方式の見直しも有効です。新調理方式といわれるクックチルやニュークックチル、クックフリーズなどを導入すると、厨房での工数が大きく変わります。
もちろん、IT技術や新調理方式の導入にはコストがかかります。施設に適したシステムかどうか判断するためにも、事前に費用対効果のシミュレーションを行い、じっくり検討するといいでしょう。
ナリコマの直営支援型厨房運営で効率アップ!

ナリコマでは、給食業務の効率化に最適な直営支援型厨房運営をご提案しております。弊社セントラルキッチンから完全調理済み食品をお届けするため、人材不足でも大きな負担をかけずに食事提供が可能。栄養価が高くバリエーションも豊富な献立、治療食や介護食への展開などもご好評いただいております。医療機関における厨房人材不足のお悩みは、ぜひ一度ナリコマにご相談ください。
コストや人員配置の
シミュレーションをしませんか?
導入前から導入後まで常にお客さまに寄り添うナリコマだからこそ、厨房の視察をしたうえでの最適解をご提案。
食材費、人件費、消耗品費などのコストだけでなく、導入後の人員削減について個別でシミュレーションいたします。
スムーズな導入には早めのシミュレーションがカギとなります。
まずはお問い合わせください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
人材不足に関する記事一覧
-

医療・介護施設の災害対策を!BCPセミナーで学ぶ備えの重要性
病院や介護施設は、災害や緊急事態の発生時、入院患者や施設利用者の安全と健康を守りながら、必要な医療・介護サービスを継続しなければなりません。そのためには、事業継続計画(BCP)の策定が不可欠です。BCP(Business Continuity Plan)とは、災害時において、業務を継続するための計画を指しています。病院・介護施設では特に「建物や設備の損壊」「インフラの停止」「人手不足」などのリスクを想定した備えが求められます。
しかし、対応するべき事柄が多すぎて、具体的にどのような対策を行ったらよいかお悩みの方もいることでしょう。そこで役立つのが、「BCP策定のポイントを学べるセミナー」です。今回は、病院・介護施設におけるBCPの重要性と、セミナーを活用して効果的に備える方法について詳しく解説します。 -

ダイバーシティ推進を目指して!多国籍人材を活かした成功例のヒント
近年、ダイバーシティ経営がさまざまな企業で注目されており、日本で働く外国人労働者も過去最多となっています。こうした環境を経て、多国籍人材を含めた多様性経営に取り組みたいと考える施設さまもいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、ダイバーシティに関連するインクルージョンなどの基礎知識も踏まえて、ダイバーシティ推進のメリットや社内浸透のステップ、企業事例から得られる成功例のヒントなどを解説します。
-

厨房業務を効率化するコツ!病院や介護施設の人手不足をクックチルで解消
近年の人手不足の影響も受け、厨房業務にはさまざまな課題があります。今回は、どうすれば厨房業務の効率化ができるのか?について、効率化のコツや人手不足の解消にもつながる対策方法、クックチルが役立つポイントについて解説します。病院や介護施設の厨房業務管理にお悩みの際にもぜひご参考ください。