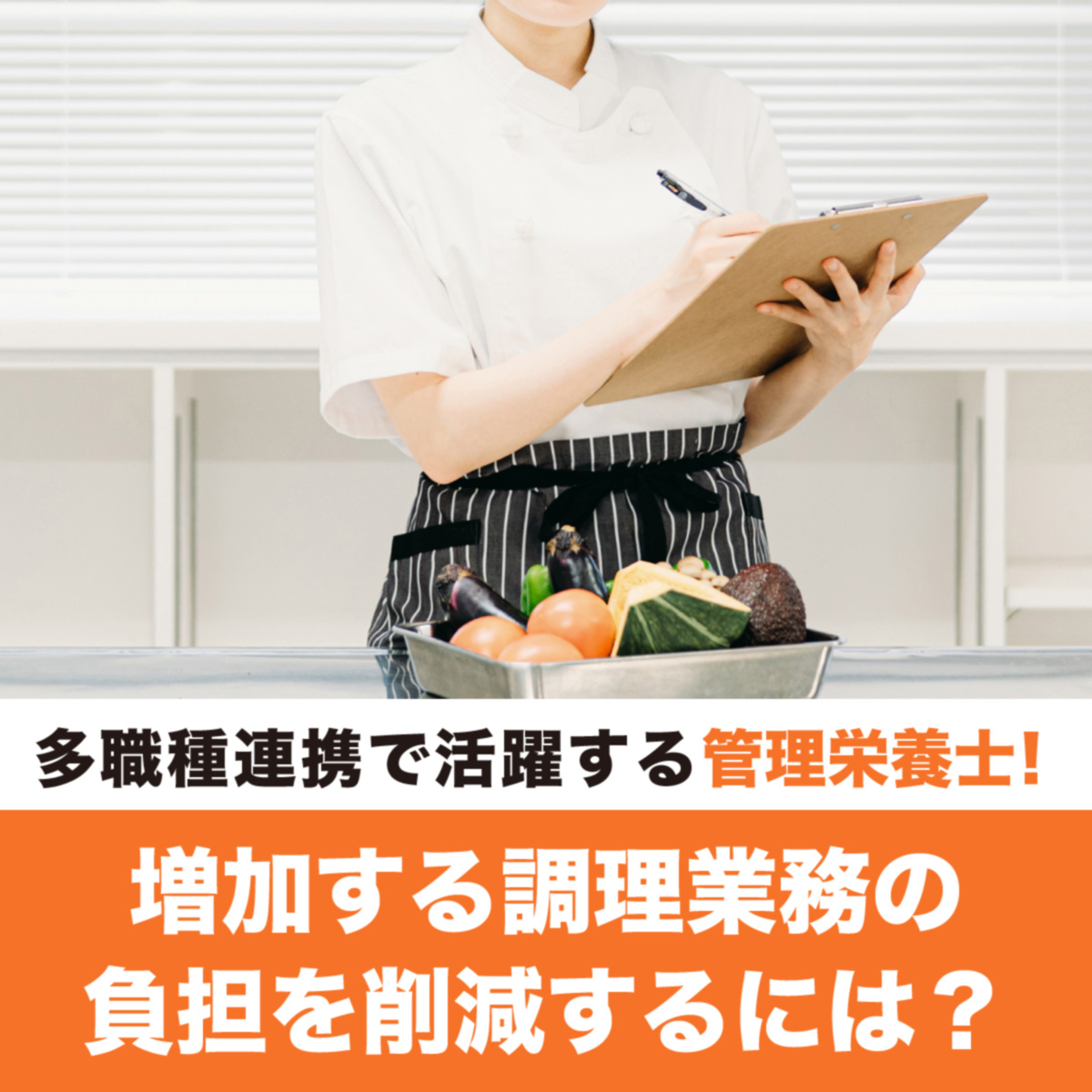医療や介護の現場では多職種連携が重視され、管理栄養士も活躍しています。しかし、実際の管理栄養士の勤務環境では、業務内容が調理業務に偏っているとの声も挙げられ、多職種連携のデメリットにもつながる課題となっています。この記事では、多職種連携の概要と管理栄養士の役割を振り返ると共に、管理栄養士の業務を妨げる原因と、調理業務の負担削減に役立つクックチルの特徴を解説します。
目次
多職種連携の強みと管理栄養士の役割
医療や介護の現場では「多職種連携」という用語が度々登場し注目されています。多職種連携とは、分野の異なる専門職が連携して働くことです。それぞれの専門分野の知識や技術を活かすことで、目的に向かってより効果的なサービスの提供が可能となり、連携というスタイルならではのメリットが期待できます。

医療の現場では「チーム医療」と呼ばれる取り組みがあり、医師と共に看護師や薬剤師などの医療の専門職が協力して患者さまをサポートしていますが、これも多職種連携のスタイルです。また医療と介護共に、医療や介護が必要な高齢者の方が可能な限り住み慣れた地域で自立した暮らしが送れるようにサポートする「地域包括ケアシステム」が重要視されていますが、地域包括ケアシステムには多職種連携が必要です。
医療や介護の現場における多職種連携では、下記のような職種が活躍しています。
- 医師
- 看護師
- 薬剤師
- 言語聴覚士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 管理栄養士
- 介護福祉士
- ケアマネジャー
- 生活相談員
- 医療ソーシャルワーカー
多職種連携における管理栄養士の仕事
管理栄養士は多職種連携において、医療と介護の現場の両方で活躍している職種です。管理栄養士の主な役割は、食事などを通して患者さまや利用者さまの栄養状態を良好にするためのサポートを行うことです。病気の治療も含めて健康的な生活を送るうえでは栄養をしっかり摂ることが大切になるため、管理栄養士は、食べる・栄養を摂るという視点から栄養指導や給食管理を行います。
管理栄養士の仕事内容は職場によって異なりますが、病院や介護施設では例えば下記のような業務があります。
- 食事内容や栄養状態の調査と指導
- 献立の作成
- 調理や調理指導
- 調理方法の検討や指導
- 食材の選定や発注
- 制限食・介護食・アレルギー対応食などの管理
- 食事の配膳や用意全般
また、医師や保健師と共に生活習慣や食生活を改善するための指導やサポートを行う特定保健指導も管理栄養士の仕事の一つです。
多職種連携のメリットを妨げる要因
日本では介護保険制度が導入された2000年頃から多職種連携が注目されるようになりましたが、必要性は認識されていながらも、効率の良い連携で効果が十分に発揮されているとはいえない現状です。多職種が協力することでさまざまなメリットが得られるとは言っても、そもそも連携自体はあまり容易なことではありません。同じ課題解決に向かって取り組んでいても、職種によって知識の内容や細かい目標が異なる場合があるのが難点です。多職種連携を成功させるには、他の職種について理解する姿勢を持ち、良好なコミュニケーション関係を築くことが大切です。

しかし、近年では多職種連携のための環境作りそのものが難しいことがあります。その原因の一つが人手不足です。人手不足の影響で、必要となる専門職がそろわない、自身の職種の専門性を高めるための学習場所すらもない、といった問題が起きることがあります。また、人手不足により一人当たりの業務負担が増えてしまう状況も見られます。
管理栄養士の職場環境と職務を圧迫する調理業務
株式会社エス・エム・エスが2024年12月に調査した「管理栄養士・栄養士1,990人に聞いた働き方の実態調査」の結果の中で、仕事にやりがいを感じていると回答した割合は69.5%でした。しかしその中で、やりたい仕事ができていると回答したのは約半数の36.4%に留まっています。
勤務先に満足していると回答したのは全体で47.3%となり、半分以上はどちらともいえないか不満と回答しています。加えて、本来の業務に集中できていると答えたのは41.9%と、5割以下となっており、業務内容では電話や窓口対応を任されることもあるようです。そのうえで、月平均の残業時間が10時間以下は65.7%となっており、81時間以上との回答が0.4%ありました。
こうした結果を見ると、本来の業務が行えず仕事に満足できない原因としても人手不足の影響がうかがえます。実際に、勤務先に満足していない理由の2位は、人手が足りず忙しすぎるという理由でした。管理栄養士の悩みでは、調理業務ばかりを任され他の業務ができない、という声も挙げられています。病院や介護施設の給食業務も含めて給食業界は人手不足が深刻なため、管理栄養士が調理業務を増やさなければ業務が回らない状況も珍しくない現状です。
管理栄養士の負担削減には厨房改革から!
給食業務の人手不足により管理栄養士が調理に専念せざるを得ず、栄養指導などに時間が取れない状況では、管理栄養士としての役割を全うできないことで多職種連携のデメリットにもつながります。そのため、管理栄養士の負担を削減するには、根本的な調理業務の負担を減らす工夫が必要です。しかし社会的な課題でもある人手不足はすぐには解決が難しいため、人手不足でもこなせる厨房に改革していくのが解決への近道といえるでしょう。
調理方式を見直そう!課題解決に役立つクックチル
厨房業務の人手が足りない場合の解決方法では、調理方式の変更がよく注目されています。食事の度に調理を行うクックサーブが従来のなじみある調理方式ですが、近年では新調理方式として効率の良い調理方式が複数挙げられ、その中の一つがクックチルです。クックチルでは、加熱調理した食品を急速冷却してチルド保存しておき、食事前に再加熱と盛り付けを行い提供します。
クックチル食品を事前に用意しておけば、厨房で食事の準備をする際は、温めと盛り付けを行うだけで提供できるため、その際の調理専門のスタッフは必要なくなります。また、簡単な作業のため、スキルを問わず任せることが可能です。調理業務自体の負担を削減できれば、管理栄養士は他の業務により尽力することができるでしょう。
ナリコマのクックチルと導入事例

ナリコマでは、病院や介護施設に特化して、委託ではなく直営での厨房運営サポートを行っています。ナリコマのクックチルは、28日サイクルと365日サイクルの日替わり献立があり、個々の施設さまの環境に合わせた食事提供が可能です。また、介護食や治療食にも対応しています。
以下では、ナリコマの導入によって管理栄養士の業務改善につながった事例をご紹介します。
厨房作業時間が216時間短縮できた!
厨房作業に膨大な時間を取られる中、調理師や調理員が欠員することになり、栄養管理の時間確保も検討しナリコマを導入していただきました。厨房作業・発注・検品・献立作成に毎月約1658時間かかっていたところ、導入後は1442時間となり216時間短縮できたとのことです。また、時間確保だけでなく、人件費のコスト削減もできたとお伺いしております。
患者さまや利用者さまとのコミュニケーションの時間が増えた!

慢性的な厨房の人手不足により職員が疲弊し、求人にも応募がない中でナリコマを導入していただきました。導入後は、簡単な業務内容により求人への応募者が増え、求人を出す必要もなくなったとのことです。厨房業務が安定し、管理栄養士の献立作成業務がなくなったことで、患者さまや利用者さまとのコミュニケーションに時間を使えるようになったとお伺いしております。
調理業務負担を削減する厨房改革はナリコマにご相談ください!

ナリコマでは、クックチルのほか、早朝や遅番の無人化も可能となるニュークックチルシステムにも対応しています。厨房運営のスペシャリストが多数在籍しており、個々の施設さまに合わせたサポートを行います。管理栄養士の業務負担にお悩みの施設さまは、ぜひ一度ご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
人材不足に関する記事一覧
-

厨房の人手不足解決はどこから手をつけるべきか?
厨房の人手不足が問題となっている給食業界。人手不足による影響は施設の評価につながることもあります。今すぐに人手不足をどうにかしたい場合、どんな解決策があるかを解説し、クックチル導入における人手不足解消のためのメリットについても紹介します。
-

外国人労働者の離職率低下に向けた社内整備!定着支援やサポート制度について解説
外国人労働者の離職率低下のためには、職場環境を見直して改善することも必要です。この記事では、外国人労働者に関する課題や離職の原因を探りながら、定着支援や日本語教育などの社内整備のポイントとあわせて、事業所が受けられるサポート制度などを解説します。給食業務の人手不足の課題解決に役立つ厨房改革のコツもまとめましたので、あわせてご参考ください。
-

介護業界の人材不足をどう乗り越える?現場に役立つ3つの対策とは
介護の現場では、今も人手不足が大きな課題となっています。高齢者の増加とともに介護ニーズは拡大する一方で、必要な人材の確保が追いつかず、現場は常にギリギリの状態でまわっている…といった声も少なくありません。
厚生労働省の試算によると、2025年度末には約37万人もの介護人材が不足する見込みです。求人倍率が上がっても定着率は上がらず、離職につながる原因には、過酷な労働環境や賃金や働き方のアンバランスさの問題など、仕組みそのものに課題があるのが現実です。
こうした中、「環境を変えるだけでは人は集まらない」と感じている施設も増えて来ていますが、今できる現実的な対策には、一体どんなことがあるのでしょうか。
この記事では、介護現場で取り入れられ始めている3つの打開策「外国人採用」「スキマバイト」「ICT導入」について、事例や活用ポイントを交えながら、わかりやすくご紹介していきます。