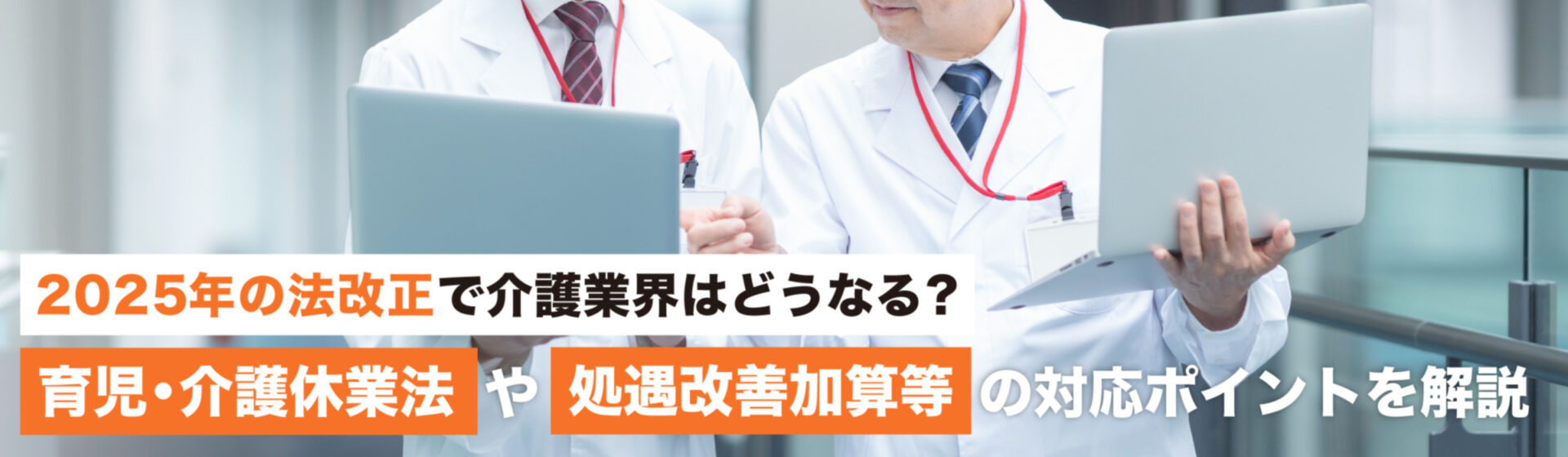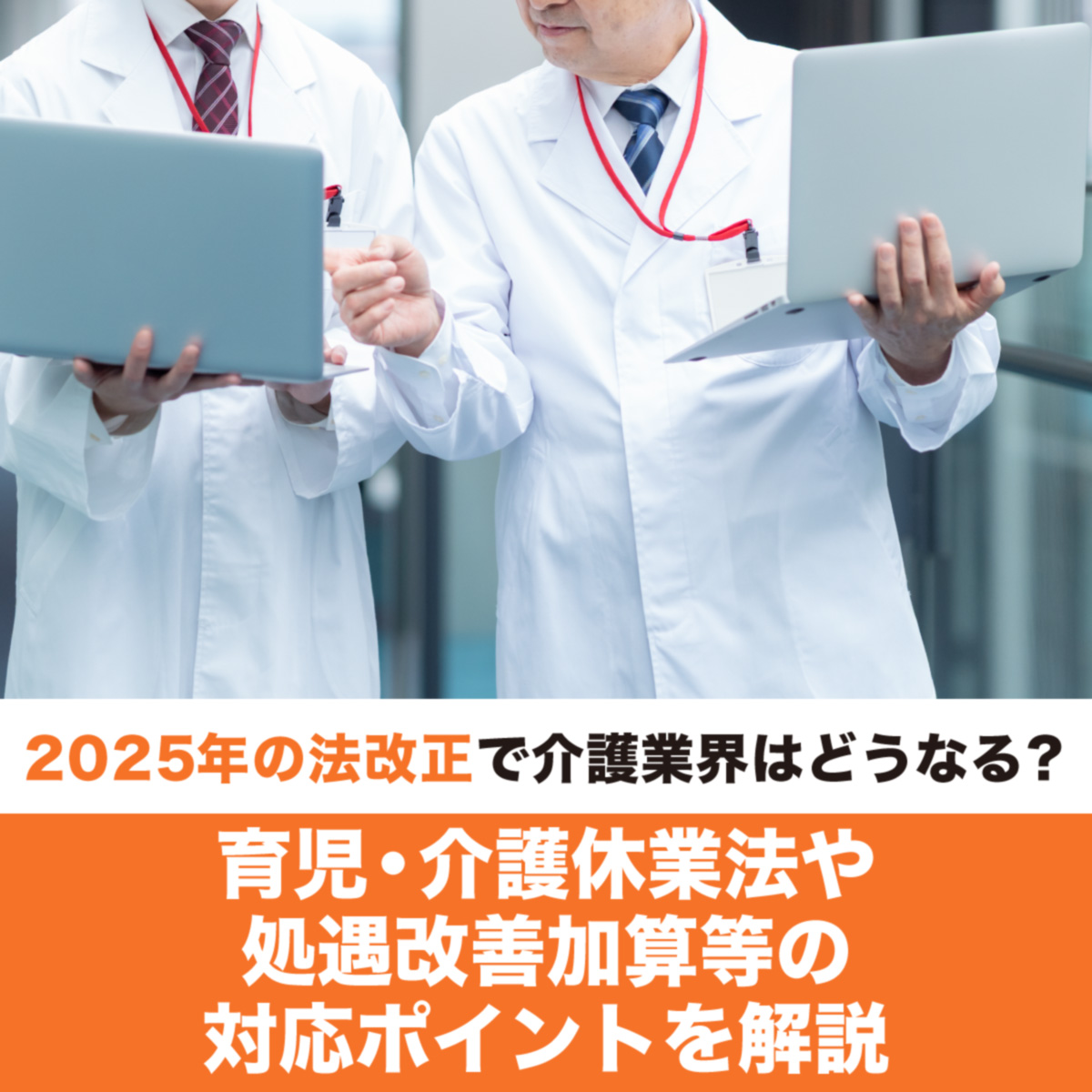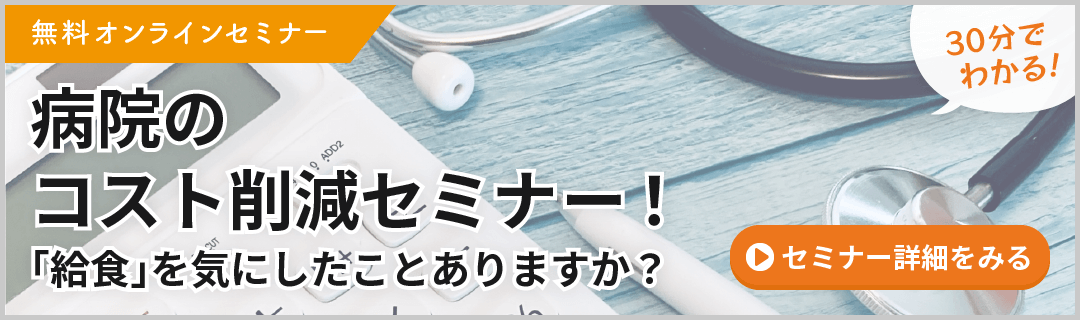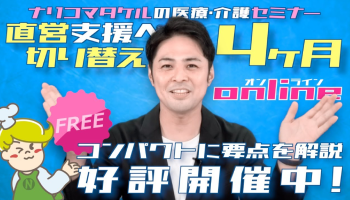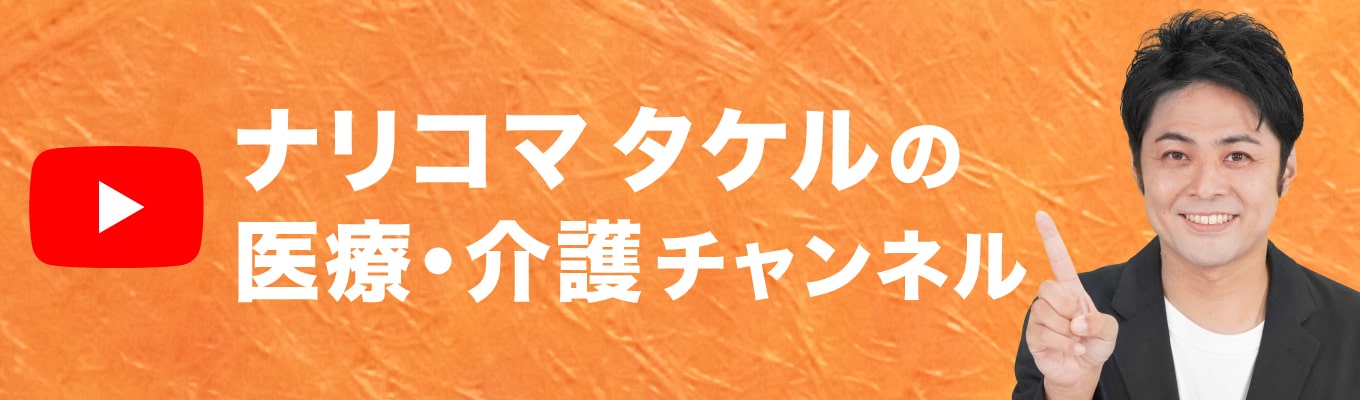介護業界は、社会情勢や法改正に伴いさまざまに環境が変化しています。今回は、2025年に主に改正される部分に視点を当て、育児・介護休業法や処遇改善加算の改正、介護保険法改正による新制度のスタートについて、改正内容と事業所の対応ポイントをまとめました。今後の運営方針や準備の優先順位を検討する際にぜひご参考ください。
目次
育児・介護休業法改正
育児休業法は1991年に制定され、翌年1992年4月から施行された、30年以上の歴史がある制度です。現在では「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」となり、社会情勢に伴い改正を経て内容が進化してきました。改正の背景には、男性と女性の間で育児休業取得率に大きな差が見られたことや、高齢化が進む中で家族の介護をしながら働く人が増えたことなどが関係しています。あわせて、育児や介護のために離職を選択せざるを得ない状況を防止する目的もあります。

さらに2025年から段階的に施行される今回の改正では、男女共に仕事と育児・介護の両立ができることだけでなく、育児中の多様な働き方を可能にすることで家庭内で育児と家事の分担をしながら男女共に希望するキャリアを形成できることや、支援制度を活用できずに介護のために離職してしまう状況の防止などが考えられています。
2025年の改正ポイント
改正された育児・介護休業法は、2025年の4月と10月に段階的に施行されます。4月1日から施行の内容では、子供の看護休暇の見直しによる対象年齢や取得理由の拡大や、所定外労働の制限の対象拡大、短時間勤務制度の代替措置としてテレワークも可能とすることなどが含まれ、子育て中のより働きやすい環境に改善されました。また、事業所は、介護離職防止のための雇用環境整備や個別の周知・意向確認などが必要となり、従業員が介護のためにテレワークを選択できるようにすることも努力義務となります。
10月1日から施行の内容では、育児中の従業員に対する柔軟な働き方を実現するための措置や、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取など、事業所側が対応するべき事柄が義務化されます。
事業所の対応ポイント
改正された内容のうち、育児休業取得状況の公表義務については、適用が拡大されたものの義務化されるのは従業員数300人超の企業です。それ以外の項目は全企業が対象となり、新設された内容もあるためよく確認しましょう。改正に伴い、就業規則等の見直しが必要となる部分も多くあります。
変更内容では、適用範囲が拡大される場合に限らず、撤廃される内容もあるため注意が必要です。例えば、子供の看護休暇や介護休暇の取得において、継続雇用期間6か月未満の労働者の除外は施行後は不可となります。
介護中や育児中の従業員に対しては、周知や意向を確認する面談などを設けることが必要で、介護休業制度などの情報提供や育児中の働き方の意向に対する配慮を行うことも義務となります。改正の本来の目的を理解したうえで、より従業員にとって働きやすい職場作りを意識すると良いでしょう。
処遇改善加算の制度改正
介護職員の処遇改善については、2009年頃から数回にわたって、賃金改善を伴い制度が改正されてきました。2025年から完全施行される今回の制度改正は、できるだけ多くの事業所で、介護職員の処遇改善のための措置が活用されることを目的に設けられたもので、処遇改善加算がさらに取得しやすい内容に工夫されています。

2025年の改正ポイント
2024年5月までは「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等加算」の段階に分かれ、合計の加算率となっていました。2024年6月からは、新加算としてこれらの段階が一本化され「介護職員等処遇改善加算」のみとなった点が大きな特徴です。2024年度末までは経過措置期間でしたが、2025年度以降は制度改正後の内容が完全施行となりました。
場合によって条件が免除となる部分もいくつかあり、要件が弾力化されたことで処遇改善加算が取得しやすくなっています。また、申請様式の簡素化も意識され、より申請しやすくなったこともメリットです。
事業所の対応ポイント
まずは新加算の制度について知識を身に付け、計画的に準備していきましょう。職場環境等要件のルールも2024年度までの内容と変更になっているため、細かい部分も確認して把握することが大切です。
例えば、どの段階を目指すにも区分ごとに規定数の項目の取り組みを行う必要があり、「加算Ⅰ」または「加算Ⅱ」を目指す場合は「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の中で必須項目があります。加えて「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」は、内容自体が大きく変わっていることもポイントです。
介護職員等処遇改善加算の算定や、職場環境改善などに向けた規定の取り組みの計画や実施により補助金の対象となるため、補助金の申請とあわせて計画することも役立ちます。
介護保険法改正と新制度のスタート
介護保険法が改正され、第115条の44の2の規定により、介護サービス事業者の経営情報についての公表や報告に関する新たな制度が2024年4月1日から施行されています。この制度によって、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の介護サービス事業者の収益や費用等の経営情報の調査や分析を行ったうえで、内容の公表に努めることが定められています。そのため、原則として全ての介護サービス事業者は、事業所を管轄する都道府県知事に経営情報を報告することが義務化されました。

2025年の改正ポイント
介護サービス事業者が都道府県知事に報告する際には、電磁的方法を利用して双方が同一の情報を閲覧できることが求められており、厚生労働省の運営するシステムで行うこととなっています。厚生労働省は「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」を新設し、2025年1月から運用をスタートさせました。
事業所の対応ポイント
報告義務の対象となる介護サービス事業者は、収益や費用の内容、職員の職種別人員数など指定された事項を、「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」を利用して報告する必要があります。毎会計年度終了後3か月以内の期限があるため、期限内に行うように注意しましょう。
また、介護サービス情報公表制度も見直しが行われ2024年に改正されており、新たな報告事項として、財務状況の分かる書類が必要となりました。一部対象外もありますが、こちらも原則として全ての介護サービス事業者が報告の対象となるため、見落としのないようにあわせて確認しておきましょう。
法改正に伴う業務負担には人手不足の根本的な解決を!

介護業界の人手不足は深刻な状態となっており、今回の法改正や制度改正により環境改善は期待できるものの、新たな環境に対応する業務負担が増える可能性があります。外部に依頼する場合にはコストがかかるため、総合的に判断し全体の業務を最適化していきましょう。現在の業務内容を見直して、改善できるポイントを探すのも役立ちます。
厨房の人手不足にはナリコマのニュークックチルをご検討ください!

例えば、介護施設の厨房の人手不足には、クックチルを進化させたニュークックチルシステムがおすすめです。食材を調理後に急速冷却してからチルド状態で盛り付けまで行い、対応機器内に保存しておくことで、食事の際には自動の再加熱のみで提供できます。ニュークックチルシステムを活用すれば、朝夕のシフトを無人化できるため、人手不足の課題解決に役立つでしょう。育児や介護による時短勤務の希望にも対応しやすくなります。まずはぜひ一度、ナリコマのサービスについてお気軽にお問い合わせください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
人材不足に関する記事一覧
-

介護職員のキャリア研修を考える!未経験スタートや管理職向けなど目的別の設計方法
介護職員のキャリア研修に取り組むことで、個々の職員のスキルアップを促し施設全体の質を高めることができます。この記事では、介護職の仕事を未経験からスタートした場合の一般的なキャリアアップの流れや、介護福祉士からのキャリアアップ、リーダー育成や管理職向け研修などに注目し、キャリア研修の設計や導入のコツを解説します。介護職員のキャリアアップや幹部研修を検討している施設の担当者さまはぜひご参考ください。
-

老人ホームの厨房業務はなぜ大変?調理スタッフの負担を減らす運営改善方法
老人ホームの厨房の仕事は大変というイメージを持たれ、求人になかなか人が集まらないことも珍しくありません。給食調理員や調理補助の仕事は無資格や未経験でも働くことができるため、最初のハードルは低いものの、きつい・辞めたいという声が多い現状です。この記事では、給食調理員や調理補助の仕事の特徴に注目しながら、老人ホームの厨房業務が大変だといわれる理由も踏まえて、調理スタッフの負担を軽減させる厨房運営改善方法のポイントを解説します。
-

病院の管理栄養士はなぜ大変?働き方は改善できる?
たくさんの患者さんが入院している病院にとって、毎日の給食を提供することはとても重要な業務の一つです。療養のために入院している患者さんは、きちんと栄養をとったり、エネルギーを補ったりする必要があるでしょう。また、入院設備がない病院でも、健康維持のための食生活について患者さんに指導する機会があります。
今回の記事は、そんな病院で働く管理栄養士の実態に迫ります。「大変」「つらい」といったイメージが強い病院管理栄養士の主な仕事内容をお伝えし、向いている人の特徴なども併せて解説。近年さまざまな業界において課題となっている、働き方の改善ポイントについても触れていきます。ぜひ最後までお読みください。