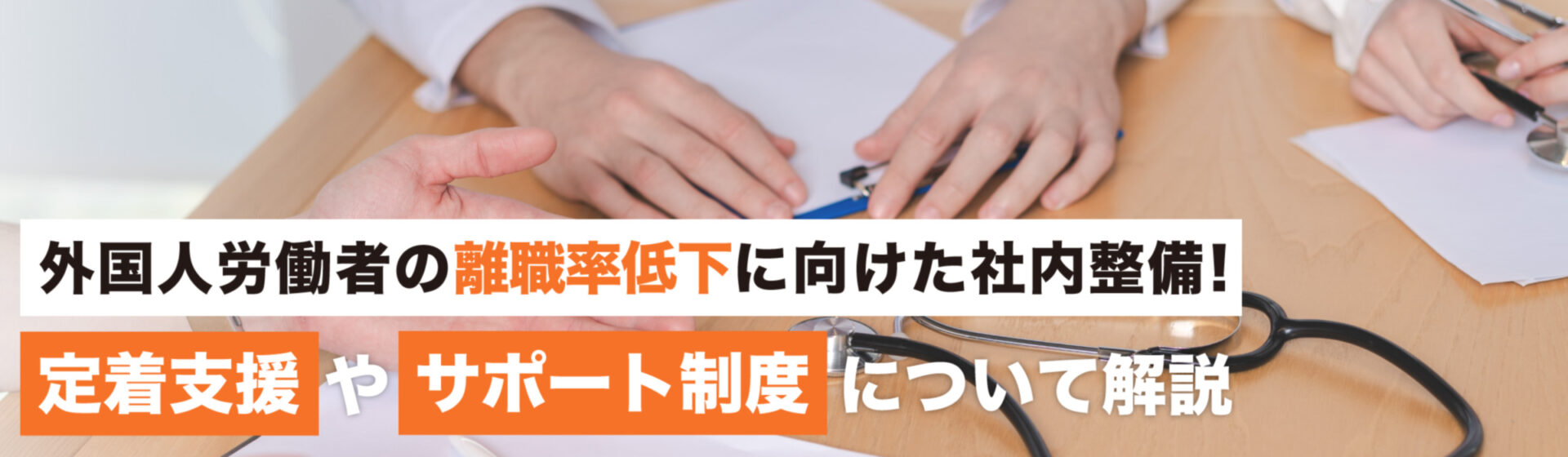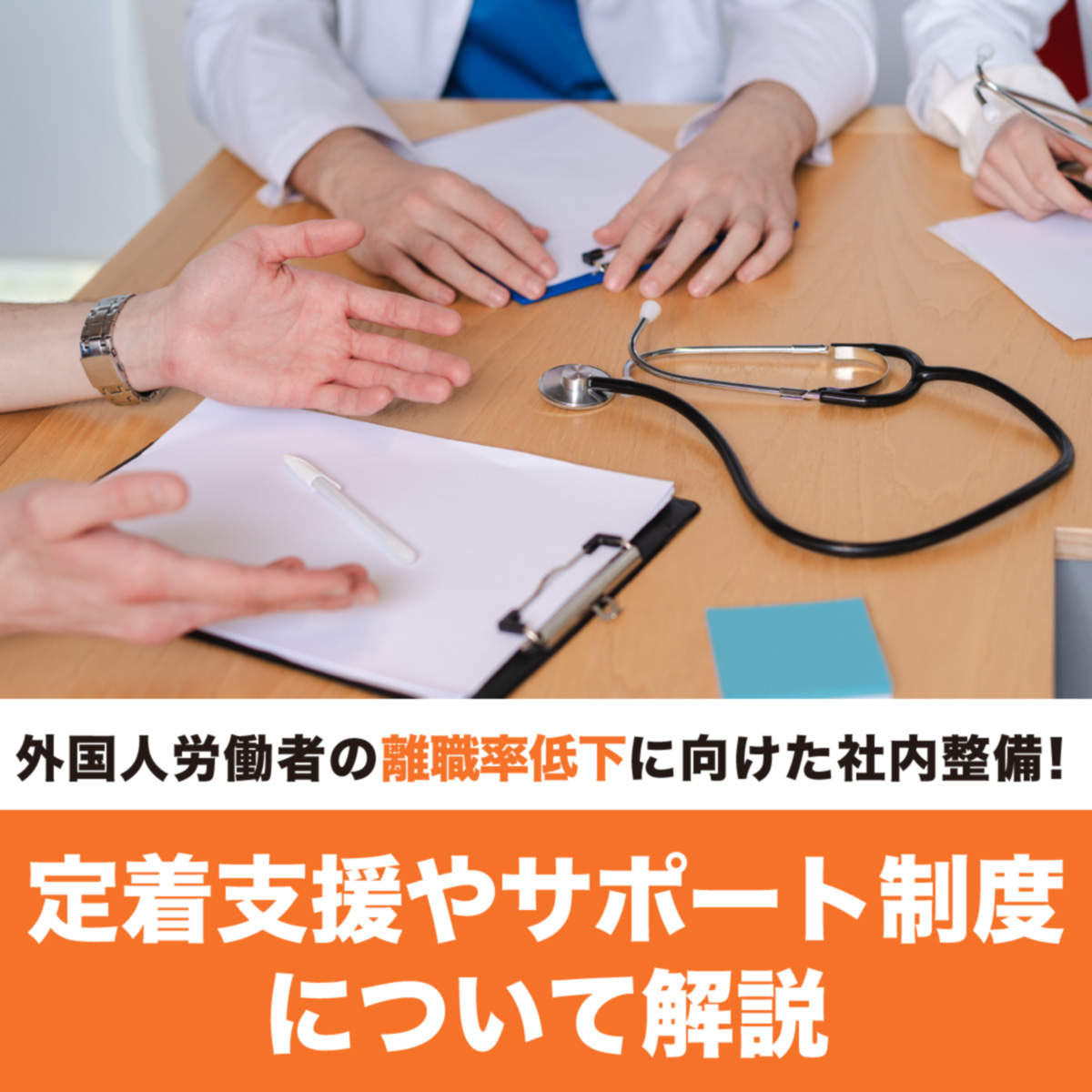外国人労働者の離職率低下のためには、職場環境を見直して改善することも必要です。この記事では、外国人労働者に関する課題や離職の原因を探りながら、定着支援や日本語教育などの社内整備のポイントとあわせて、事業所が受けられるサポート制度などを解説します。給食業務の人手不足の課題解決に役立つ厨房改革のコツもまとめましたので、あわせてご参考ください。
目次
外国人労働者との間で生まれる課題
日本で働く外国人労働者は、厚生労働省の調査によると、2024年10月末の時点で2,302,587人となり、届出が義務化された2007年以降過去最多となりました。国内では、専門的・技術的分野の在留資格をはじめ、技能実習や身分に基づく在留資格などを持つ外国人が働いていますが、同時に外国人労働者と雇用する事業所の間でさまざまな課題も生まれています。

厚生労働省の「令和5年外国人雇用実態調査」によると、外国人労働者の雇用に関する課題において、事業所全体で最も割合が多いのは「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」という課題で、全体の44.8%を占めていました。「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」といった課題も19.6%と割合が多く、言語や文化などの外国特有の課題に悩まされていることがうかがえます。あわせて「離職・転職が懸念される、定着しない」といった課題の割合も14.8%を占めていました。
近年では、2023年に失踪した外国人技能実習生の数が9,753人となりました。その理由として職場でのトラブルも大きな原因と想定されています。こうした背景も踏まえると、外国人労働者の離職率低下を目指すには、外国人労働者の働く環境を改善することが重要であるといえるでしょう。
外国人労働者の離職につながる原因

外国人労働者が離職する原因はさまざまですが、例えば下記のような事柄が考えられています。
- 給与や待遇に対する不満がある
- 業務内容が予想と違った
- キャリアアップが期待できない
- 職場での文化の違いになじめない
- 想定以上の日本語能力を求められる
- 良好なコミュニケーションや人間関係の形成が困難である
前述した、厚生労働省による「令和5年外国人雇用実態調査」の中では、労働者側の調査における就労上のトラブルについて、「トラブルや困ったことをどこに相談すればよいかわからなかった」「事前の説明以上に高い日本語能力を求められた」というトラブルが比較的高い割合となっていました。これらの結果からも、外国人労働者がコミュニケーションや職場環境に負担を感じていることがうかがえます。
他にも、事前に仕事内容や賃金、労働時間、就業条件などについて説明がなかった、事前に説明された仕事内容や就業条件が実際と違っていた、という声も挙がっており、雇用する事業所側のサポート体制に問題があることも垣間見えます。
外国人労働者の離職率低下のための社内整備
先述したように、外国人労働者の離職原因には、コミュニケーションエラーがさまざまに影響している可能性があるため、まずはこうした根本的な課題を解決しながら外国人労働者にとって働きやすい環境にするための社内整備が必要です。ポイントとなるのは下記の二つです。
- 事前情報と実際の環境の不一致をなくす
- コミュニケーションの取り方を工夫する
まずは、外国人と働くことを従業員全員が意識し、異文化を受け入れるための知識を身に付けることから始めましょう。最初に社内で受け入れる体制を整えることで、信頼関係の基盤作りに役立ちます。下記では、外国人労働者とのコミュニケーションも踏まえた、面接や定着支援などの社内整備のポイントを解説します。

外国人労働者を面接する際の工夫
外国人労働者から事前に聞いていた情報と違うといわれてしまう背景には、最初の求人票の内容や面接に課題が隠れている場合もあります。求人票には実際の環境についても文章で明確に表し、面接時から良好なコミュニケーションを取れるように工夫してみましょう。職場環境や周辺環境、仕事内容、キャリアアップの条件などを誤解のないように丁寧に伝えることが大切です。より自社に適した人材を探すために、改めて面接内容を見直してみるのも良いでしょう。
雇用側については、中でも「異文化適応力」を面接の際に判断することが役立ちます。適応力に伴い、柔軟性や学習姿勢などを兼ねそろえていれば、外国人労働者が事前に予想した内容と多少のズレがあったとしても、社内でのサポート次第で離職を避けられる可能性が高まるでしょう。面接で押さえておきたいポイントは主に下記の3つです。
- 希望する条件や志望動機:なぜ日本で働きたいと思ったか、日本にどれくらい滞在したいか、などの今後の展望など。
- 就労経験やスキル:仕事で頑張った経験や、日本語をどうやって勉強したかなど。
- 人柄:長所や短所、趣味、信仰する宗教など。
- 準備してきた質問以外への返答:日本語能力を確認できる。
- 仕事内容、給与(収入)への理解:何を求めているかの理解、金銭への意欲が強すぎないか(転職につながるかどうか)。
- 日本に来る目的、何年働きたいか:年数を決めている場合は継続できるかを判断。
また、実際に外国人労働者が就労してからも、面談を定期的に行い、現在の状況を把握しながら随時サポートしていくと良いでしょう。面接の際には、仕事上の事柄だけでなく、生活面の悩みなどを聞くことも参考になります。

社内全体で行う定着支援&日本語教育のコツ
日本の生活に慣れていない外国人労働者は、日本はどこでも便利な国で、夜勤を行えば給料が上がるなど、特定のイメージを持っていることにより、入国や就労後に思っていた環境と違うと感じるケースが多いようです。そのため、こうした理想と現実のギャップがあることを前提にしたうえで、定着支援を上手に行うことが大切です。
定着支援では、職場環境だけでなく、生活全般に視野を広げて支援しましょう。受け入れ前に外国人労働者の住環境を整えるステップがありますが、入社後も地域に溶け込めるようなサポートが必要です。また、大きな困難につながる日本語力についても、語学力アップのためにサポートしましょう。普段から積極的な声かけなどを心掛けるほか、ノートで読み書きも踏まえたやり取りを行う「こうかんノート」や、スマホのツールを利用する方法も推奨されています。
コミュニケーションの取り方については、単なる指導のつもりが誤って伝わり、強い不快感を与えてしまい深刻な結果につながるケースもあるため注意が必要です。個々の外国人労働者の文化や日本語力を理解し、こうした誤解を避けるための丁寧なコミュニケーションを工夫しましょう。
事業所が受けられるサポート制度
外国人労働者を雇用するうえでは事業所にも負担があるため、事業所のためのサポート制度も設けられています。例えば、厚生労働省からは「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」として、外国人特有の事情に配慮して就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む際の経費の一部をサポートするための助成金があります。そのほかにも、各自治体によるサポート制度がさまざまにあるため、活用することで外国人労働者の定着支援がより行いやすくなるでしょう。
差し迫った給食業務の人手不足解消に役立つ厨房改革

病院や介護施設の給食業務は、人手不足が深刻となり、外国人労働者の雇用も促進されています。こうした給食業務でも外国人労働者の働きやすさを意識することが役立ちますが、差し迫った人手不足の課題解決には、厨房改革自体に目を向けることもポイントです。
調理作業の負担を軽減するクックチル
厨房改革では、調理方式の変更およびクックチルの導入がおすすめです。クックチルは、加熱調理した食品を急速冷却し、食事の際に再加熱と盛り付けを行い提供する方法です。ククックチル食品を利用すれば、厨房での作業は簡素化された内容になるため、外国人労働者にも覚えやすいメリットがあります。
外国人労働者にもわかりやすいナリコマのクックチルシステム
 ナリコマは「登録支援機関」の認定を取得しており、また病院や介護施設に特化したクックチル食品の提供ができ、直営での厨房運営をサポートしております。ナリコマのクックチルシステムで外国人労働者でもわかりやすい業務環境の整備が可能です。
ナリコマは「登録支援機関」の認定を取得しており、また病院や介護施設に特化したクックチル食品の提供ができ、直営での厨房運営をサポートしております。ナリコマのクックチルシステムで外国人労働者でもわかりやすい業務環境の整備が可能です。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。
コストに関する記事一覧
-

給食委託会社の選び方は?正しい選び方のポイントを解説
今後の需要が見込まれる給食委託会社の選び方についてお届けする記事です。最適な給食委託会社を選ぶための重要なポイントを挙げ、項目ごとに詳しく解説。給食委託を検討する際にお役立ていただけます。
-

報告制度も伴う医療機関の機能分化!役割再編で求められる厨房業務の改革とは
近年の日本では、少子高齢化が異例のスピードで進行しています。少子高齢化によって生じる問題の一つが、医療・介護の需要増加に伴う混乱です。政府は、少子高齢化社会においても医療・介護の提供体制が整えられるよう、さまざまな施策を打ち出しています。
今回の記事は、政府主導の施策にとって重要な医療機関の機能分化をテーマにお届けします。機能分化を図るために整備された報告制度に関してもまとめて解説。後半では、医療機関の役割再編と同時に行うべき非医療部門の見直しについてもお伝えします。 -

配食・宅食の違い!配食サービスで注目されているクックチルのメリット
配食・宅食サービスは、高齢者の食生活の課題解決に役立ちます。この記事では、配食・宅食の言葉の違いやサービスの共通点などの基礎知識に加えて、高齢者が入居する福祉施設で役立つ配食サービスについて解説します。配食サービスでは、調理方法として注目されているクックチルの概要やメリットについてもまとめましたので、あわせて参考にしてみてください。