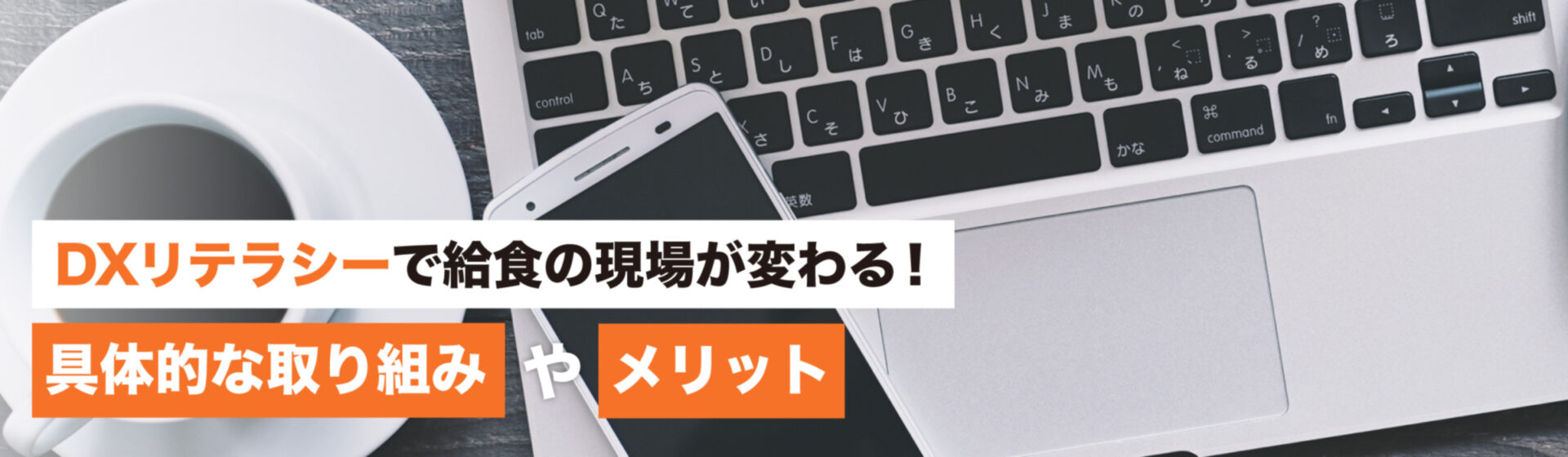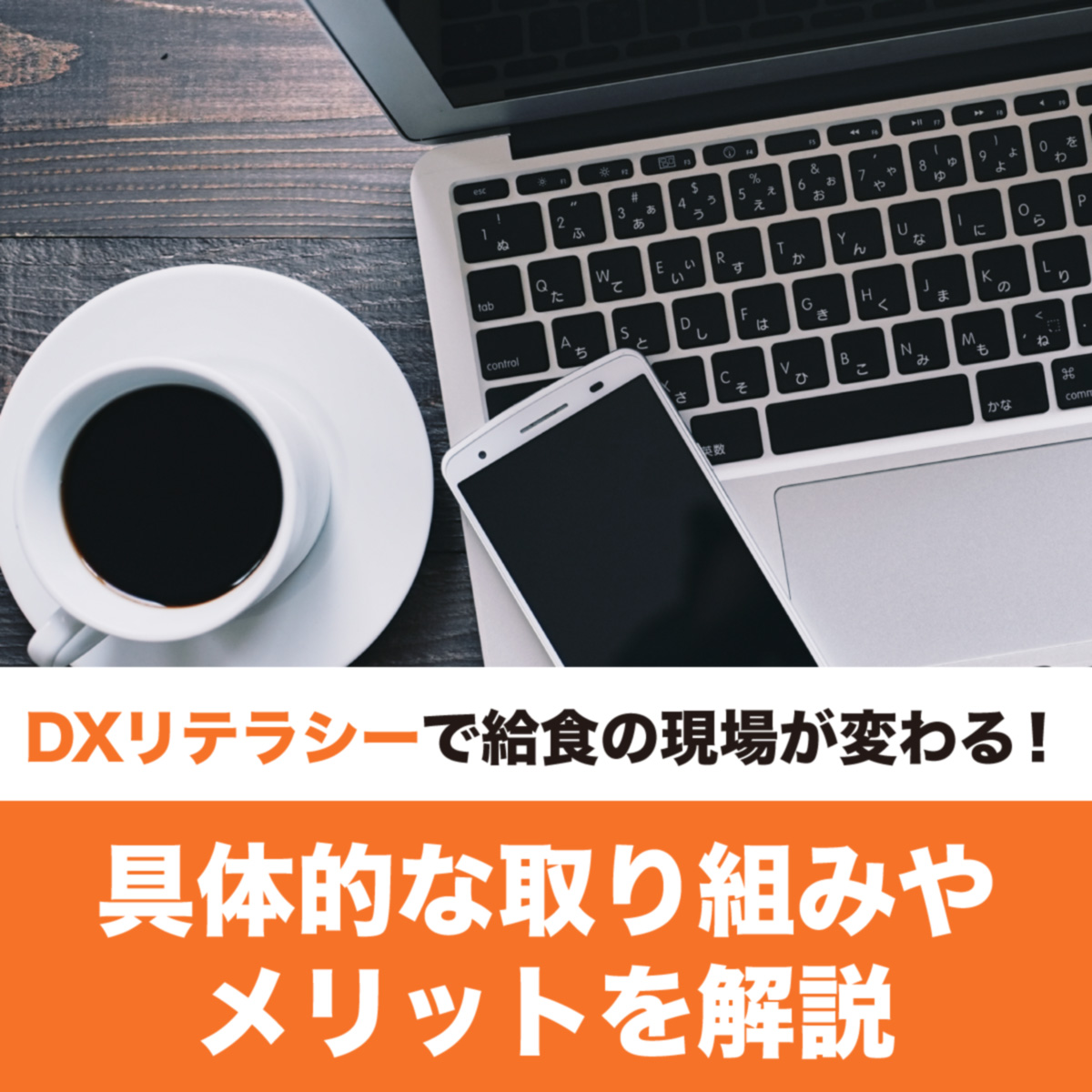みなさんは、「DXリテラシー」という言葉に聞き覚えがあるでしょうか? 近年では、業界を問わずDXリテラシーの重要性を意識する企業が増えてきています。今回の記事は、そんなDXリテラシーについて詳しくお届け。「そもそもDXって何?」という疑問を抱く方にもご理解いただけるよう、言葉のルーツや定義、その重要性もしっかりとお伝えします。給食現場における具体的な取り組みやDXリテラシー向上のメリットについても解説。ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考になさってください。
目次
各業界で注目度大!DXリテラシーとは?
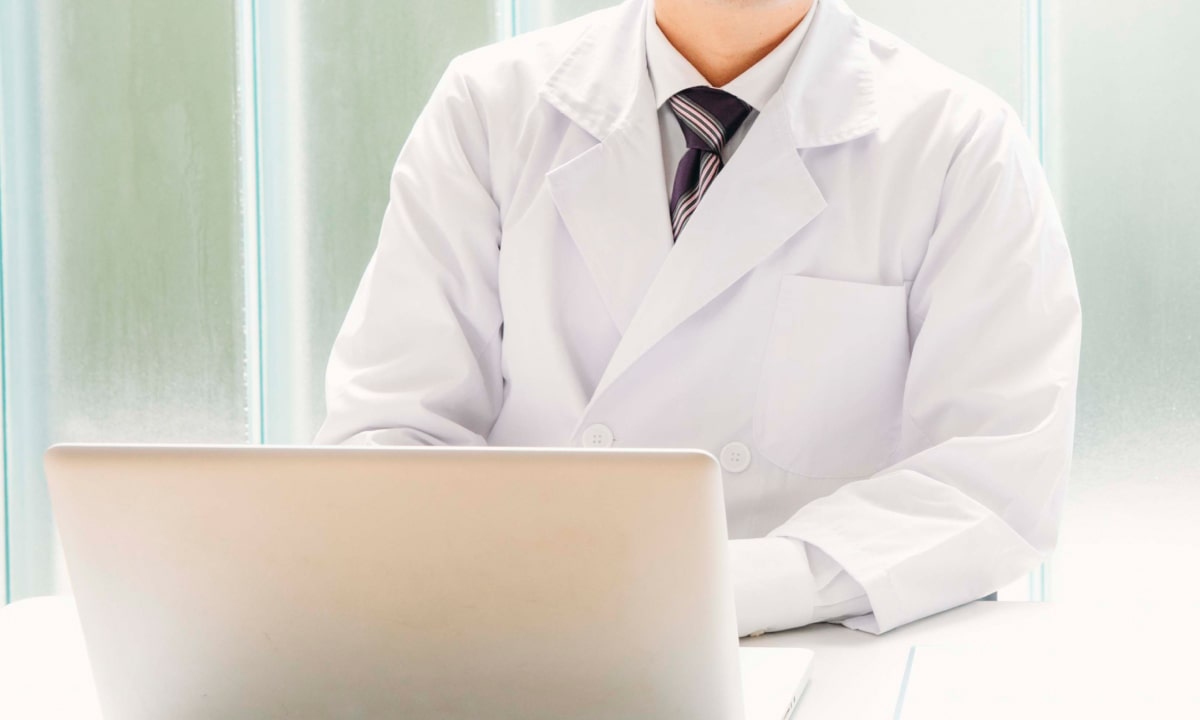
DXの定義
DXは、“Digital Transformation”(デジタルトランスフォーメーション)のこと。2004年、当時スウェーデン・ウメオ大学の教授を務めていたエリック・ストルターマン氏が提唱した概念だそうです。ちなみに、略称の二文字目がXになるのは、英語の「Transformation」が「X-formation」と略して表示されることに由来します。
Transformationは「変化」「変形」「変容」などの意味があり、DXは日本語訳で「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義されています。この内容からわかるように、DXはもともと社会全体にかかわる言葉でした。しかし、最近はビジネスの中で用いられるケースも増えてきたようです。
日本においては、2018年に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」を公開。その中で、DXは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。
このような定義は、一見IT化と同じような印象を受けるでしょう。しかし、IT化は情報技術(IT)を活用して業務の効率化を図ること。一方のDXは情報技術を含むデジタル技術全般を取り上げており、さらに広い視点での変革を掲げています。IT化はDX推進のために必要なもの、と考えると理解しやすいかもしれません。
DXリテラシーの重要性
リテラシーは、特定の分野における知識やそれらを活用する能力のことを指します。DXの定義とあわせて考えると、DXリテラシーは「データやデジタル技術についての知識や理解があり、それらを活用して組織・ビジネスを変革する能力」といった意味になります。
先に、経済産業省が公開したDX推進のガイドラインについて述べましたが、実はその背景には「2025年の崖」に対する懸念があるのです。「2025年の崖」は、日本の企業がDX推進をしなかった場合、業務効率や競争力が落ちて年間最大12兆円もの経済損失が発生すると予測されている状況を表しています。
主な問題点は、既存の基幹システムが老朽化したり、ソフトウエアが時代遅れになったりすること。しかし、IT人材は年々不足している傾向にあり、「レバテックIT人材白書2024」によると「経験者採用が難しいため未経験者も採用する」と答えた企業が全体の47.6%を占めています。そんな状況だからこそ、今後は働き手一人ひとりのDXリテラシーを高め、企業もしくは業界全体でDXを推進していく必要があるのです。
DXリテラシーが高い給食現場の取り組み
近年では、食品(food)と技術(technology)を組み合わせた「フードテック」という言葉が登場。生産・加工・調理・流通・消費など、あらゆる食分野で最先端技術を活用しようという動きがあるのです。その一端を担う、DXリテラシーが高い給食現場の取り組みをご紹介します。

事例①アプリを使った献立作成や栄養指導
管理栄養士による栄養指導をサポートするスマホ向けアプリ「おいしい健康」は、各診療ガイドラインに基づき、入院・外来患者、介護施設利用者の献立作成や栄養管理をAIで対応。食事基準は医師や管理栄養士が設定できるため、給食に反映させていた栄養指導の内容を、家庭内の食生活にもわかりやすく引き継ぐことができます。
事例②保護者も安心のアレルギー特化型アプリ
「きょうの給食」は、株式会社JOINT CREWが開発したウェブアプリ。2024年6月より、千葉県君津市の小学校で実証実験がスタートしました。給食の献立が確認できるほか、アレルギー情報を自動で通知するなど、保護者も安心できる機能があります。
事例③給食業務全般の効率化システムを開発
給食製造を行う株式会社フレアサービスでは、業務効率化のシステムを独自に開発しました。食材管理や献立作成、帳票作成などの自動化、セントラルキッチンの生産性アップに向けた導線の可視化といった幅広い改革を実現。結果的に労働時間も削減できたそうです。
事例④モバイルオーダーができるデリバリー型給食
LINEアプリ上のモバイルオーダーサービス「PECOFREE」は、栄養士監修のお弁当を給食として届けてくれます。予約できるため、大人数の学校や企業が利用しやすく、フードロスも削減。お弁当の製造業者と学校や企業をつなぐ役割も果たしています。
事例⑤人の手が必要だった食器洗浄を自動化
コネクテッドロボティクス株式会社では、給食センターなど大型施設向けの食洗機ロボットを開発しています。現時点では試作品のみですが、既存のベルトコンベア式食洗システムやコンベア型食洗機と併用可能。画像認識技術などを活用して同じ種類の食器を仕分け、重ねていくことができるようです。
給食現場でDXリテラシーを向上させるメリット
先ほどご紹介した事例からもわかるように、給食現場を発展させていくにはDXリテラシーの向上がカギとなります。
DX推進で得られる最大のメリットは、やはり業務が効率化できること。これまで時間をかけて行っていた作業を可能な限り自動化すれば、当然ほかの業務にも手が回るようになります。現場で働く一人ひとりに時間や心の余裕が生まれると、単純なミスを防ぐことや業務の質を上げることにもつながるでしょう。給食現場の大きな課題といわれる長時間労働や人手不足の状況も改善しやすくなります。

また、経営面ではコスト削減というメリットがあります。例えば、事務作業を効率化した場合、そこに必要だった事務用品が一つなくなるだけでもコスト削減に。原材料費やエネルギー費、人件費などをはじめ、給食にかかるコストが軒並み高騰化している昨今ではかなり重要な部分といえるのではないでしょうか。
経営者はもちろん、現場で働く方々のDXリテラシーを向上すれば、今後得られるメリットは増えていくでしょう。
ナリコマ独自のシステムで給食現場のDXリテラシーを向上!
2024年10月1日、ナリコマは経済産業省のDX認定制度に基づき「DX認定事業者」として認定されました。実は、病院・介護福祉施設に特化した給食会社としては初の認定です。

以前より、ナリコマは給食DXに力を入れてきました。受発注データや献立作成、栄養情報、物流などを独自システムで管理。IoTデバイスの導入によって検品作業を簡易化したり、帳票作成などの事務負担を軽くしたりする取り組みを行っています。
また、調理業務の負担を少なくするために、クックチルやニュークックチルの導入もご提案中。一部だけでなく、給食業務全体を見据えたDXを追求し続けています。病院、介護福祉施設の給食現場の業務効率化に関してお悩みの際には、ぜひ一度ナリコマにご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
セントラルキッチンに関する記事一覧
-

医療DXの推進はメリット多数!取り組み事例を紹介
近年は、「DX」という言葉がさまざまなメディアで散見されるようになりました。あらゆる産業で推進が望まれていますが、実際、医療の現場ではどのようなメリットがあるのでしょうか? 本記事では、医療DXの概要と共に、解消すべき課題や導入事例などもまとめてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
-

セントラルキッチンでクックチルを製造!おいしさの理由とは
セントラルキッチンは、今や飲食関連の業務に欠かせない存在となっています。導入先は飲食店やスーパーマーケット、入院設備のある病院、介護施設など多種多様。今回の記事は、そんなセントラルキッチンのシステムについてお届けします。
セントラルキッチンの仕組みと特長だけでなく、そこで調理されるクックチルに関しても詳しく解説。近年注目を浴びているセントラルキッチンの魅力をお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、導入のご参考になさってください。 -

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。