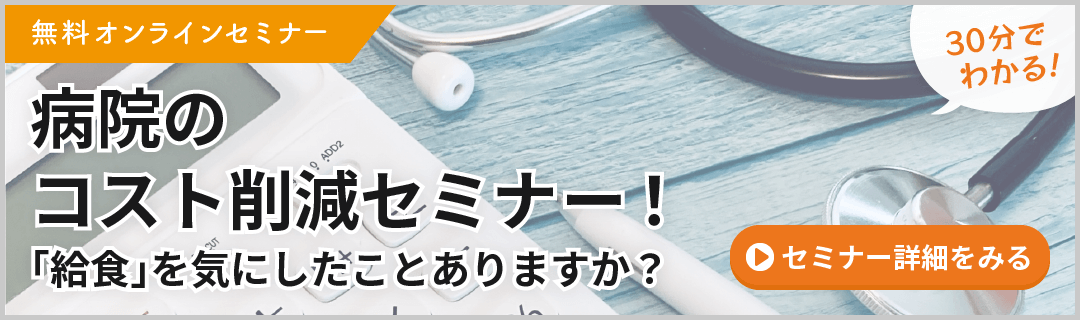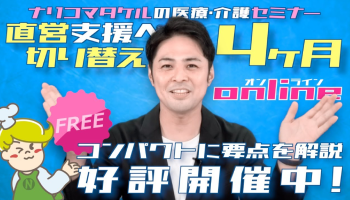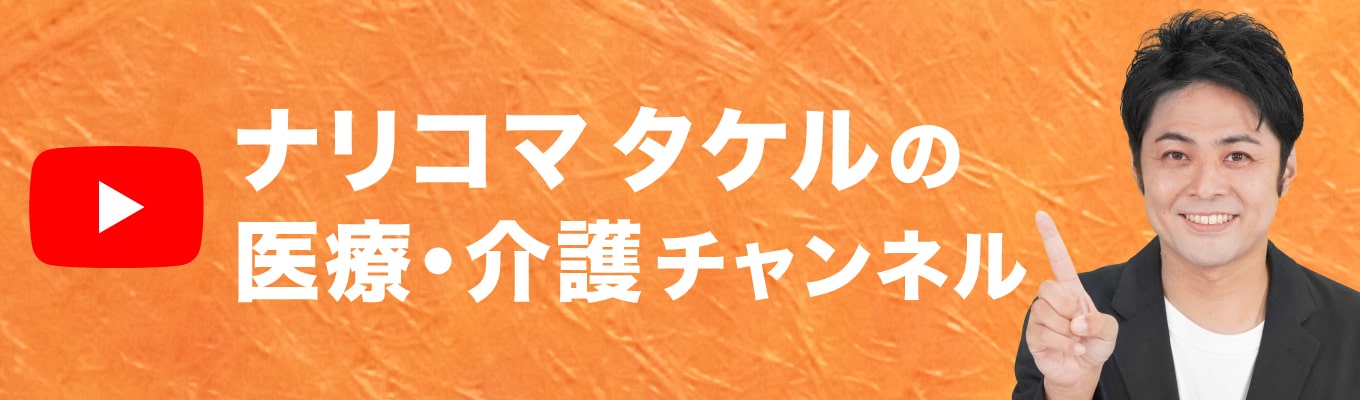病院や介護施設の給食費・厨房管理費の予算オーバーの悩みは、近年さまざまなところで取り上げられています。物価高騰や人件費の上昇により、年度末の赤字が続くことも珍しくない状況で深刻な課題となっています。そこで注目されているのが、新調理システム「クックチル」です。
この記事では、近年の給食費の赤字について、原因やデメリットを詳しく掘り下げながら、課題解決に役立つクックチルの特徴やメリットを解説します。
目次
病院や介護施設を悩ます給食費

近年、病院や特別養護老人ホームなどの介護施設の給食費は深刻な赤字となり、給食費の赤字問題はさまざまなところで取り上げられ解決策が検討されています。
病院では、給食部門の収入が減少していることも赤字につながる要因です。厚生労働省による2017年度の「入院時食事療養の収支等に関する実態調査」の段階で、調査対象全体で患者1人あたり1日に約700円の赤字という結果が出ていました。その結果を踏まえ、公益社団法人奈良県栄養士会では「2023年度 入院時食事療養の収支等に関する実態調査」を行ったところ、患者1人あたり1日に約600円の赤字という結果が出ました。
また、介護施設に関する事柄では、2025年1月8日に公益社団法人全国老人福祉施設協議会が厚生労働省に「食費の基準費用額の見直しにかかる要望」を提出しました。要望書の資料に含まれた「特養の食費に対する物価高騰の影響」の中では、公益社団法人全国老人福祉施設協議会が行った調査によって、特養や短期の平均定員81.8人とした給食関連費用の試算について、ひと月あたり約57万円の赤字という結果が出ています。
給食費の予算が足りない原因とは?
給食費の予算が足りない大きな原因として、物価の高騰や人件費の上昇が挙げられています。しかし、どちらも給食を提供する上でなくてはならない費用であり削減が難しいため、容易には解決できない課題です。ここでは、物価の高騰や人件費の上昇の現状を詳しく解説します。

物価の高騰
一般家庭にも大きな影響を与えている物価の高騰は、同じく病院や介護施設の給食費にも影響を与えています。2025年1月に公表された「2020年基準 消費者物価指数 全国 2024年平均」では、2020年を基準とした2024年の全国平均において、2023年と比較した総合指数は2.7%も上昇していました。
食品の物価ももちろん上昇しており、野菜や穀類、果物、肉類、菓子類などが全て値上がりしています。2023年との比較においてとくに目立ったのは、24.2%上昇したタマネギや、28.8%上昇したうるち米(コシヒカリを除く)です。2024年の12月は、2023年の12月と比較して、キャベツが125.7%も値上がりし2倍以上の価格になったほか、うるち米(コシヒカリを除く)が65.5%の上昇、みかんが25.2%の上昇など、大幅な値上げが見られました。
また、物価高騰は食品だけでなく光熱費にも及び、2023年12月と比較して2024年12月は、電気代が18.7%上昇、ガス代が7.8%上昇しました。こうした物価高騰の現状を見ると、食材の購入から調理に至るまでにかかるコストが上昇していることが、給食費の赤字にも大きく影響していることがわかります。
人件費の上昇
病院や介護施設の給食費にかかる費用は、材料費などの食品に関する費用だけでなく、食事を用意するための人件費も必要になります。近年では、病院や介護施設共に給食に関する人件費の上昇が見られます。
先述した公益社団法人全国老人福祉施設協議会による「特養の食費に対する物価高騰の影響」の中では、「食費(基準費用額)に関する調査」によって、2022年6月と2024年6月を比較した際に、調理員の人件費が利用者1人1日あたり37.4円増加していることが挙げられました。
物価の高騰に伴い人件費も上昇することで、さらなる赤字を生んでいることがうかがえます。ただし、病院や介護施設の調理員は人手不足の課題が既にあるため、人件費を削減することは困難な状況です。
給食費の赤字が招く食事品質の低下
病院や介護施設の食事は、患者さまや利用者さまの治療や健康維持にとって欠かせないものです。栄養管理がきちんと行われた食事を提供し、残さず食べてもらえるようにおいしく作る必要があるでしょう。しかし、食品の価格が高く理想の食材が手に入らない、人手不足で業務が滞るといったことがあると、安全でおいしい食事の提供はどんどん難しくなり、結果として食事の品質の低下につながります。

具体的には、食材のバリエーションが減り見た目も味わいもおいしくない、食べても物足りなく感じる、提供前に料理が冷めてしまう、治療食や介護食が一般の献立と異なり不満につながる、といったケースが考えられます。また、業務の滞りは食中毒のリスクもあるため注意が必要です。食事品質の低下によって、食事をきちんと食べてもらえず、治療や健康維持の妨げになるおそれがあるでしょう。
給食費・厨房管理費の赤字を解決するクックチル
物価高騰や人手不足など、根本的な原因を解決するには、食事提供のシステム自体を見直すことも一つの方法です。クックチルは厨房改革に役立つ新調理システムで、病院や介護施設ではクックチルの導入が注目されています。ここでは、クックチルの概要やメリットを解説します。

新調理システム「クックチル」の安全でおいしい食事
クックチルは、食事の度に調理する従来の方法とは異なり、保存できるところが特長です。クックチルでは、食品を加熱調理した後に冷却してチルド保存しておき、食べるタイミングで再加熱して盛り付けを行い提供します。そのため、効率の良い調理と食事提供が可能になります。
クックチルの調理は、食材の中心温度と加熱時間の定義があり管理された状態で加熱殺菌され、加熱後は急速冷却で90分以内に中心温度を3℃まで下げてからチルド保存する、という決まりがあるため、衛生的に食事管理ができることもメリットです。
調理済みのクックチル食品を利用すれば、厨房では湯せんやスチームコンベクションを使って温めるだけの簡単調理で用意できます。クックチル食品の選び方を工夫すれば、栄養面や介護食が配慮された食事の提供を簡単に行うことができるでしょう。
物価高騰や人件費上昇を解決するクックチルのメリット
クックチル食品は、セントラルキッチンでまとめて作られるため、食材を一度に大量に仕入れることで食材費のコスト削減につなげることができます。クックチル食品を導入すれば、調理後に発生する余分な食材が出る心配もなく、食品ロスの削減と合わせて廃棄のコスト削減にも役立つでしょう。また、施設の厨房では温める程度の調理作業のため、水道光熱費のコスト削減ができます。
また、クックチル食品を利用すると調理の作業工程が大幅に減少されるため、早朝からの調理準備などの勤務がなくなり、その分の人件費削減に役立ちます。早朝勤務などがなくなることでシフトの負担が軽減し、調理スキルを問わない業務のため人手が集まりやすいなどのメリットも期待でき、人手不足の解消にも役立つでしょう。
ナリコマが予算不足の厨房運営をサポートします

ナリコマのクックチルを導入すれば、厨房運営がよりシンプルになり、運営コスト削減に働きかけることができます。HACCPの理念に基づいた温度管理の元に製造したクックチル食品は、食中毒や異物混入のリスクを軽減し、衛生的な食事の提供に役立ちます。
また、ナリコマでは、病院や介護施設に特化したサービスを提供しており、医療食や介護食にも対応しています。嚥下力や咀嚼力に合わせて、普通食・ソフト食・ミキサー食・ゼリー食の形態から選べるため、個々の人に合わせた食事の用意も手間なく準備可能です。
立ち上げだけでなく導入後もアドバイザーが継続的にサポートし、厨房運営の力になります。まずは一度ご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
コストに関する記事一覧
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。 -

給食業務を委託すると食材費はどうなる?物価高騰を上手に乗り切る方法とは
近年、給食業界はよりいっそう厳しい状況にあるといわれています。その主な要因の一つとされているのが、急速に進む物価高騰です。今回は、そんな物価高騰に対して給食業務をどのように行っていくべきか考えてみましょう。
キーワードは、委託給食と食材費。給食業務の委託サービスについて詳しく紹介し、委託にした場合の食材費がどうなるのか解説します。記事後半では食材費削減のアイデアもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。 -

ちゃんと食べていても体重が減っていく?高齢者の食事は少量高栄養で!
高齢者になると健康上の問題が目立つようになります。当然個人差はありますが、健康状態を左右する食事の困りごとはいち早く解決したいものでしょう。「若い頃と同じように食べられなくなった」「食欲がなくなってきた」といった声は、いつの時代も聞こえてきます。
本記事で取り上げるのは、しっかり食べているのに体重が減るという「やせ(低体重)」の問題。高齢者の体重減少を引き起こす理由や具体的な原因を解説し、「やせ」の危険性についてもお伝えします。
また、そんな高齢者の食生活をサポートする少量高栄養の介護食・給食についても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。