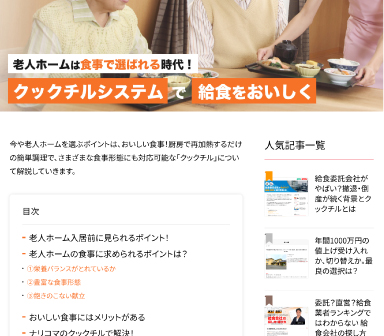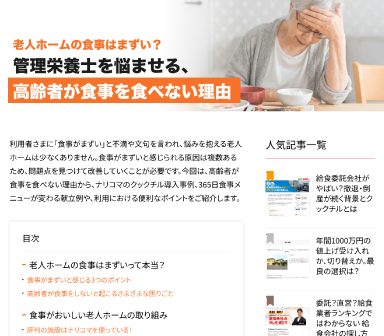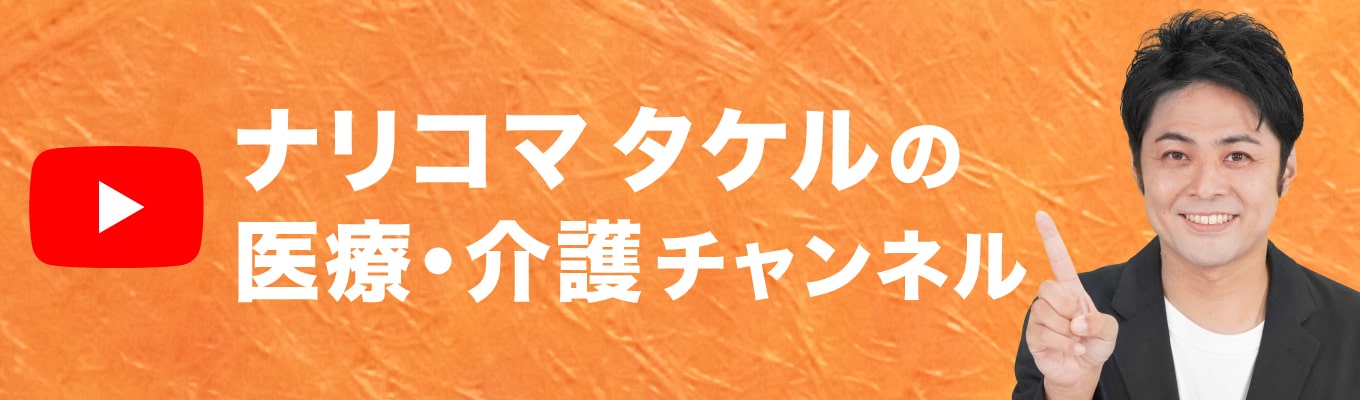現在の日本は少子高齢化が社会問題として取り上げられており、今後、要介護の高齢者人口は増えていくとみられています。そうした状況に対応するため、近年では高齢者向けの施設・サービスなどのバリエーションが拡大。高齢者の健やかな暮らしを守れるよう、介護ツールや老年医学に対する関心も高まってきました。
今回の記事は、そんな高齢者の健康にまつわる注目ワード、フレイルをピックアップ。フレイルの定義や診断基準などを詳しく解説し、予防になる食生活のポイントもまとめてお伝えします。ぜひご参考になさってください。
目次
フレイルとは?
フレイルは、健康な状態と介護が必要な状態の中間を表す言葉。つまり、要介護の一歩手前にあることを指しています。言葉の由来は、海外の老年医学で用いられる英語の「Frailty(フレイルティ)」です。以前は「虚弱」という直接的な日本語訳が使われていましたが、2014年5月に一般社団法人日本老年医学会が「フレイル」と改めました。

加齢によって心身が衰えていくことは、人として自然な流れといえるかもしれません。しかし、高齢者が心身の不調をそのままにしていると、要介護になってしまう可能性が高くなるのです。日本老年医学会はこの過程を重要視。フレイルが発症しやすい高齢者に対しては、日常的に適切な介入や支援を行うことが生活機能の維持・向上につながり、介護予防にもなると提唱しました。では、どのような状態をフレイルと呼ぶのでしょうか?
フレイルの診断基準
フレイルの発症には身体的・精神的・社会的な要因があり、老年医学専門のリンダ・P・フリード博士が提唱した5つの診断基準が設けられています。3つ以上に該当する場合はフレイル、1つまたは2つに該当する場合は前段階のプレフレイルと診断。いずれにしても、その兆候にいち早く気付き、治療や生活習慣の改善などを進めることが大切です。
①体重が大きく減少している
半年間で5%以上、もしくは年間で4.5kg以上の体重減少がみられる場合は要注意です。意図しない体重減少は、何かしらの疾患によるものかもしれません。痛みなどの自覚症状が少ない疾患もあるため、医療機関での診察や検査を受け、詳しく調べる必要があるしょう。
②疲労感がある
少し動いただけで疲れてしまったり、疲れを感じてやる気がなくなったりすることもフレイルの特徴です。このような状態が続くのであれば、心身の疾患を疑いましょう。また、複数の病院で薬を処方されている場合は、飲み合わせ等が悪影響を及ぼすケースもあるようです。
③歩く速度が遅くなっている
歩く速度と加齢は大きく関係しています。高齢になると足腰が弱くなったり、心肺機能が衰えたりして、若いときと同じような速度で歩くのが難しくなるのです。もちろん、疾患が影響しているケースもあるでしょう。フレイルの基準は、1.0m/秒未満とされています。
④筋力が低下している
筋力が落ちてしまうこともまた、フレイルの特徴です。加齢だけでなく、疾患や投薬、活動量の減少、栄養不足など、考えられる要因はさまざま。握力は診断材料のひとつで、男性は28kg未満、女性は18kg未満をフレイルの基準としています。
⑤身体的な活動が少ない
仕事や人間関係によって環境が変わり、身体的な活動が少なくなるケースがあります。人と会うのが面倒だと感じたり、外出の機会が明らかに減ったりしているときは要注意。「軽い運動・体操」と「定期的な運動・スポーツ」のどちらも週一回に満たないのであれば、フレイルの可能性があるかもしれません。
フレイル予防のポイント①栄養バランスのとれた献立

ここからは、フレイル予防に効果的な食生活のポイントを解説します。最初にお伝えしたいポイントは、毎日の食事で栄養をしっかりとること。栄養不足は、フレイルの前段階となる筋肉量や筋力の低下につながってしまいます。一日三食を欠かさず食べ、栄養バランスのとれた献立を考えることが重要です。
特に注目したい栄養素はたんぱく質、ビタミンD、カルシウムの三つ。たんぱく質には体内で生成されないアミノ酸が含まれており、筋肉をつくるために必要です。内臓や皮膚の健康維持にも欠かせません。たんぱく質を効率よくとるには、肉や魚、大豆製品、乳製品などがおすすめです。
また、ビタミンDは骨や筋肉の健康を支える栄養素で、一部の魚介類やきのこ類、卵などに多く含まれています。そして、カルシウムは骨をつくり、丈夫にする栄養素。乳製品や大豆食品、海藻類などに多く含まれています。
フレイル予防には、こうした栄養バランスの調整に加え、主食・主菜・副菜をそろえることも大切です。すべて手作りにすると手間ひまがかかるため、冷凍食品や加工食品の活用も推奨されています。
フレイル予防のポイント②規則正しいリズム
前の項目で「一日三食を欠かさずに」と述べましたが、それと同時に、食生活のリズムを意識することも重要です。いつも不規則な時間に食事をしていると、自律神経が乱れて心身の不調が出やすくなったり、免疫力が落ちて罹患したりする可能性が高くなります。そういった食生活の改善が、将来的にはフレイルの発症を防ぐことになるのです。
ここで覚えておきたいポイントは、朝食・昼食・夕食をとる時間について。食事の時間をある程度決めておくことで、一日のリズムも整いやすくなります。厳密に決めるのは難しいかもしれませんが、一日の流れをあまり大きく崩さないようにしましょう。

規則正しいリズムで生活すると、自律神経が乱れにくくなったり、腸内環境が良くなって免疫力がついたりするといわれています。このほか、精神的に安定する、適正体重が維持しやすくなるなどのメリットもあります。
さらに、米国国民健康栄養調査(NHANES)による研究では、規則正しく生活する高齢者の行動バターンが活動的になるという結果も出ているようです。フレイル予防の効果を高めるには、食生活だけでなく、起床・就寝時間なども一定にするといいかもしれません。
フレイル予防のポイント③誰かと一緒に食べる
誰かと一緒に食事をする「共食」も、フレイル予防になる食生活のスタイルです。なぜかというと、一人で食事をすると献立が好きなものだけに偏ったり、品数が少なくなったりする傾向が強くなるから。先に述べたように、一日三食をしっかり食べ、バランスよく栄養をとることはとても重要なのです。

また、食べながらコミュニケーションがとれることもメリットになります。家族や友人と話をすることで、食事そのものに対する楽しみが生まれるのです。食事の時間が楽しめなくなると、食欲が落ちてしまったり、食事を抜いてしまったりするケースもあるといいます。そうなれば、必要な栄養が足りなくなったり、食生活のリズムが崩れてしまったりするでしょう。
つまり、食生活を通じた社会参加に大きな意味があるのです。家族や友人が遠方でなかなか会えないような状況なら、テレビ電話やオンライン通話などを利用しながら食事をするのも効果的といわれています。
ナリコマの献立サービスは栄養面も安心!
ここまでお伝えしてきたように、フレイル予防には食生活の見直しが欠かせません。ナリコマでは、介護福祉施設に最適な献立サービス「すこやか」を展開中です。管理栄養士が手がける栄養バランスのいい献立を365日日替わりでお届け。高齢者のみなさまが十分な栄養をとれるように、ミキサー食やゼリー食などの介護食は少量高栄養を目指しています。

また、栄養面だけでなく、おいしさや楽しさへのこだわりも満載。料理にあわせて配合した出汁、和食から洋食までそろった幅広いバリエーション、郷土料理や行事食の提供など、食生活を豊かにする工夫を凝らしています。フレイル予防にも役立つ献立は、ぜひナリコマにおまかせください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
セントラルキッチンに関する記事一覧
-

医療DXの推進はメリット多数!取り組み事例を紹介
近年は、「DX」という言葉がさまざまなメディアで散見されるようになりました。あらゆる産業で推進が望まれていますが、実際、医療の現場ではどのようなメリットがあるのでしょうか? 本記事では、医療DXの概要と共に、解消すべき課題や導入事例などもまとめてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
-

嚥下食の準備を簡単に!クックチルを活用した効率的な提供方法
自分の口から食事を摂ることは、とても大切なこと。栄養補給だけでなく、健康維持や認知機能の衰えを防いだり、高齢者にとって食事はとても重要なものです。嚥下機能が低下してくると、通常の食事では摂取が困難になってしまうため、低栄養状態に陥り、筋肉量の減少にもつながりかねません。そのため、身体機能に合わせた食事形態で提供することがなにより大切ですが、嚥下食の準備は手間も時間もかかるため、調理する側の負担も大きくなってしまいます。
「嚥下食を手軽に準備するためにもっと便利な方法はないだろうか…。」そんなお悩みにはクックチルを活用するのも一つの手です。今回は、嚥下食が抱える課題をもとに、クックチルで叶える効率的な嚥下食の提供についてご紹介します。 -

病院給食の衛生管理には院外調理を上手に使おう!
安全・安心・おいしい食事であることが求められる病院給食。HACCPの理念に基づいた衛生管理を行う院外調理品(クックチル)の導入によって、衛生管理の強化と品質の高い食事を同時に叶えることができます。
さらに人材不足の解消やコスト効率の向上、衛生管理に関するスタッフ教育までもフォローが可能です。病院給食に院外調理品(クックチル)を使うメリットについて詳しく紹介していきます。