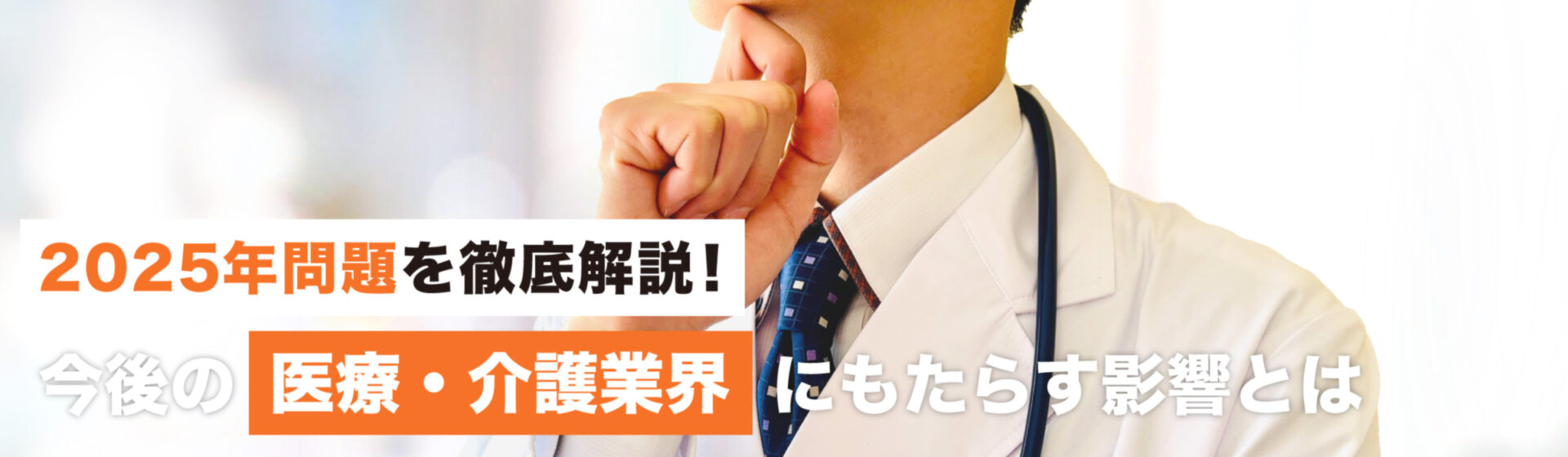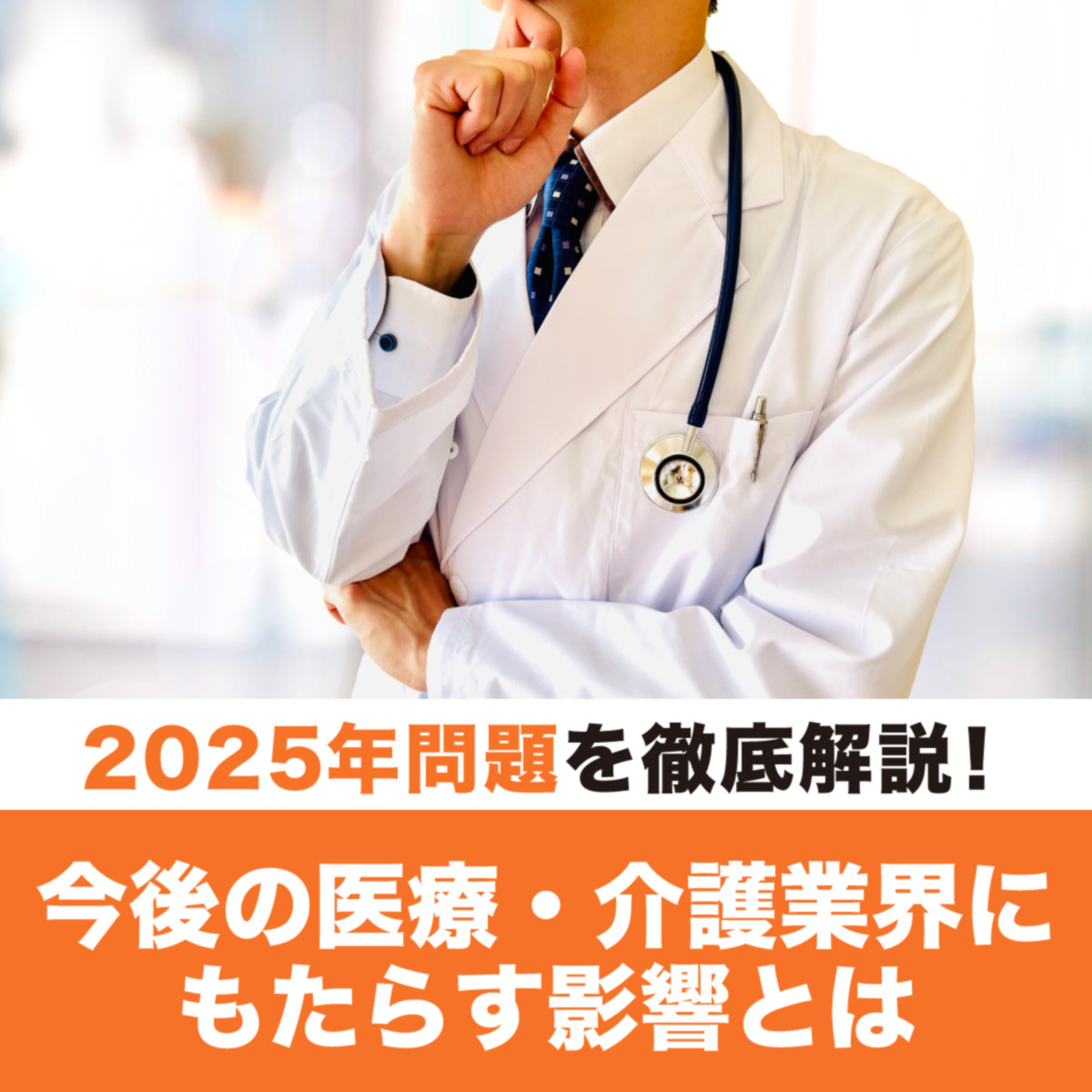2025年問題は日本の将来を大きく左右することから、これまでに何度もニュースなどで取り上げられてきました。さまざまな業界への影響が懸念されていますが、医療・介護業界も例外ではありません。今回の記事は、そんな2025年問題について徹底解説。医療・介護業界にもたらす影響と今後求められる対策について、詳しくお伝えします。
目次
2025年問題とは
日本では、1947年〜1949年に第一次ベビーブームがありました。その時期に生まれた人々を団塊世代と呼んでいます。2025年以降は団塊世代が75歳以上になるため、高齢化社会がよりいっそう深刻化する見込み。社会・経済面において幅広い影響を与え、雇用や福祉、医療などで問題が生じてきます。2025年問題は、そうしたさまざまな問題の総称です。

事実、高齢化社会の進行は具体的な数値として現れています。近年の総人口は減少傾向。2024年11月1日時点の確定値は1億2378万4千人で、前年同月と比べて0.45%減少しています。内訳をみると、64歳以下の人口は減少していますが、65歳以上の人口は0.04%、75歳以上の人口は3.51%増加。厚生労働省によれば、2025年には75歳以上の人口が全人口の約18%になるとみられています。
また、2040年も同様の問題が指摘されています。1971年〜1974年には第二次ベビーブームがありました。2040年は、その時期に生まれた団塊ジュニア世代が高齢者になるタイミング。65歳以上の人口が全人口の約35%になると予測されているのです。現時点ではこれが高齢者人口増加のピークと考えられており、社会保障制度や公共施設・インフラが維持できなくなる可能性も高いといいます。
つまり、2025年問題も2040年問題も一時しのぎでは済まされず、根本的な対策が求められているのです。もちろん、高齢者からの需要が高い医療・介護業界の逼迫も大きな懸念の一つ。次の項目では、二つの業界にもたらす影響を詳しくみていきましょう。
医療業界にもたらす影響

①医療従事者や医療施設の減少
2025年問題の根源となっているのは急速に進み続ける高齢化社会です。高齢者が増える一方で、主な労働者となる若い世代は減少傾向。こうした状況では、新たな医療従事者が生まれる可能性も下がります。当然ながら、病院や診療所は必要な人材が集まらなければ運営できません。医師や看護師などの医療従事者が少なくなっていくということは、結果的に医療施設の減少にもつながってしまうのです。
②需要と供給のアンバランス
高齢者の場合、何かと不調を抱えていることもあるでしょう。高齢化社会が進む今後は、病院や診療所を利用する高齢者がますます多くなると考えられます。しかし、前述した医療従事者や医療施設の減少により、従来と同じ対応ができなくなるかもしれません。さらに、通院が難しい高齢者には在宅医療によるケアも必要です。ここで問題となるのは需要と供給のアンバランス。人材と施設が限られる中でも、適切な医療を提供しなければならないのです。
③医療費の大幅な増加
医療を受ける人が多ければ、それに比例して医療費も増加します。国民健康保険や医療保険の制度を活用することになりますが、2025年問題では、その財源確保が難しくなるという点が挙げられています。財源は、被保険者や事業所などが納める保険料。ところが、将来的には若い世代が少なくなり、保険制度を支える主な労働者の負担が重くなってしまうのです。そのため、制度そのものの見直しも必要だといわれています。
介護業界にもたらす影響

①人手不足のさらなる深刻化
以前から、介護業界における人手不足は重要な課題として取り上げられてきましたが、いまだ完全な解決には至っていません。若い世代が減少していることだけでなく、精神的・身体的な負担が大きいこと、業務と報酬のバランスがとれていないことなども人手不足の原因といわれています。2025年問題によって、そうした人手不足の状況はさらに進んでいくでしょう。しかし、介護の需要は増え続けるため、事業所や施設は人材確保のために試行錯誤しなければならないのです。
②介護保険制度が持続できない可能性
介護保険は、介護サービスを支える要素の一つ。高齢者が増えると、介護保険を利用するケースも多くなるでしょう。先に述べた医療費の件と同様、こちらも保険料を収める被保険者や事業所などが少なくなれば、制度が破綻してしまいます。その結果、介護サービスの内容が変わったり、対応できる範囲が狭くなったりする可能性もあるのです。充実した介護サービスを提供し続けるには、財源を安定させることも重要といえます。
③要介護でも支援が受けられない状況
①と②で述べたことが影響し、要介護の高齢者が支援を受けられなくなる可能性もあるといいます。厚生労働省が行った調査によると、2022年4月1日時点における特別養護老人ホームの入所待ち人数は23.3万人。東京都においては、2024年に退所者が増加したことで入所しやすくなったとの話もあります。しかし、全国的に状況が変わったとは考えにくいでしょう。今後は、要介護レベルが低い高齢者は後回しにされたり、要介護の認定基準が変わったりというケースが出てくるかもしれません。
2025年問題を乗り切るための対策
医療・介護業界が2025年問題を乗り切るには、政府主導による各種制度などの整備が不可欠です。しかし、ほかにも現場で実践すべき対策があります。本項目では、二つの業界に共通する対策のポイントをまとめました。

人材確保に向けた労働環境の改善
現在は政府が働き方改革を推進していますが、医療・介護業界ではもともと負担の大きな労働環境が多く、あまり改善が進まないという話も出ています。ところが、2025年問題で指摘される労働者の減少を考慮するなら、働きやすい環境が人材確保の要となるのです。適正な労働時間や報酬、風通しの良さなど、これまで以上に魅力的な職場づくりが求められるでしょう。
専門知識・スキルの向上
人材確保がある程度できたとしても、労働者が減少していく状況は簡単に変わりません。そのため、限られた人数で業務を行わなければならないケースもあるでしょう。医療・介護をきちんと提供し続けるには、個々の専門知識・スキルを向上させ、業務全体の質や効率を高めていくことが大切です。
専門性が生きる多職種連携
今後増え続ける高齢者をケアしていくため、特に重要といわれているのが多職種連携です。医療と介護の垣根を越え、医師・看護師・介護士・栄養士・薬剤師などが協力体制を築きます。それぞれの専門性を生かした総合的なケアができるようになり、結果的に医療や介護サービスの質が上がることも期待できます。また、連携をとるようになれば、業務全体が円滑に進むというメリットも生まれます。
IT技術の幅広い活用
人手不足の解消や労働時間の短縮、業務の効率化などには、AIを含むIT技術の活用が推奨されています。もちろん、2025年問題は専門的な業務のみに限った話ではありません。医療・介護で必要な業務全般においてIT技術を取り入れるのも、対策として有効でしょう。患者や施設利用者のデータをアプリで管理したり、アナログな事務作業をデジタル化したりと、現場によってさまざまな活用方法が考えられます。
給食業務の効率化はナリコマにおまかせ
ナリコマでは、医療・介護に特化した献立サービスを提供しています。おいしくてバリエーションも豊富な介護食のほか、治療食の展開も可能。調理システムは、再加熱と簡単な盛り付けだけで提供できるクックチル方式です。

専門アドバイザーや独自アプリによるサポートも充実しており、業務効率化の実績も多数ございます。人手不足など、2025年問題の影響を受けやすい給食業務。どんな小さなお悩みでも、ぜひ一度ナリコマにご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
人材不足に関する記事一覧
-

老人ホームの厨房業務はなぜ大変?調理スタッフの負担を減らす運営改善方法
老人ホームの厨房の仕事は大変というイメージを持たれ、求人になかなか人が集まらないことも珍しくありません。給食調理員や調理補助の仕事は無資格や未経験でも働くことができるため、最初のハードルは低いものの、きつい・辞めたいという声が多い現状です。この記事では、給食調理員や調理補助の仕事の特徴に注目しながら、老人ホームの厨房業務が大変だといわれる理由も踏まえて、調理スタッフの負担を軽減させる厨房運営改善方法のポイントを解説します。
-

転職・キャリアアップしたい社会人へ|今こそ始めるリスキリングのススメ
最近、「リスキリング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。仕事の内容や求められるスキルがどんどん変わっていく今の時代。そんな中で注目されているのが、この「リスキリング(学び直し)」です。
「このままで大丈夫かな?」
「もっと自分にできることを増やしたい」
といった思いを持つ方も多いのではないでしょうか。
大手企業をはじめ、医療や介護の現場でも、リスキリングに取り組む動きが広がっており、それぞれの業界や職種に合ったやり方で、人材育成や働き方の見直しが進められているのです。
リスキリングが注目される背景や、注目のスキルに加えて、実際の進め方、企業や施設での成功事例を業界別にご紹介します。 -

地域包括ケアの仕組みとは?多職種連携や課題についても詳しく解説
日本は将来的に高齢者が激増するといわれています。そんな高齢化社会を支える医療・介護・福祉のあり方として推進されているのが「地域包括ケア」というシステムです。本記事では、地域包括ケアの基本的な仕組みについて詳しくお伝えします。また、その中で重要視される多職種連携や、今後の課題や対策についても解説。ぜひ最後までお読みください。