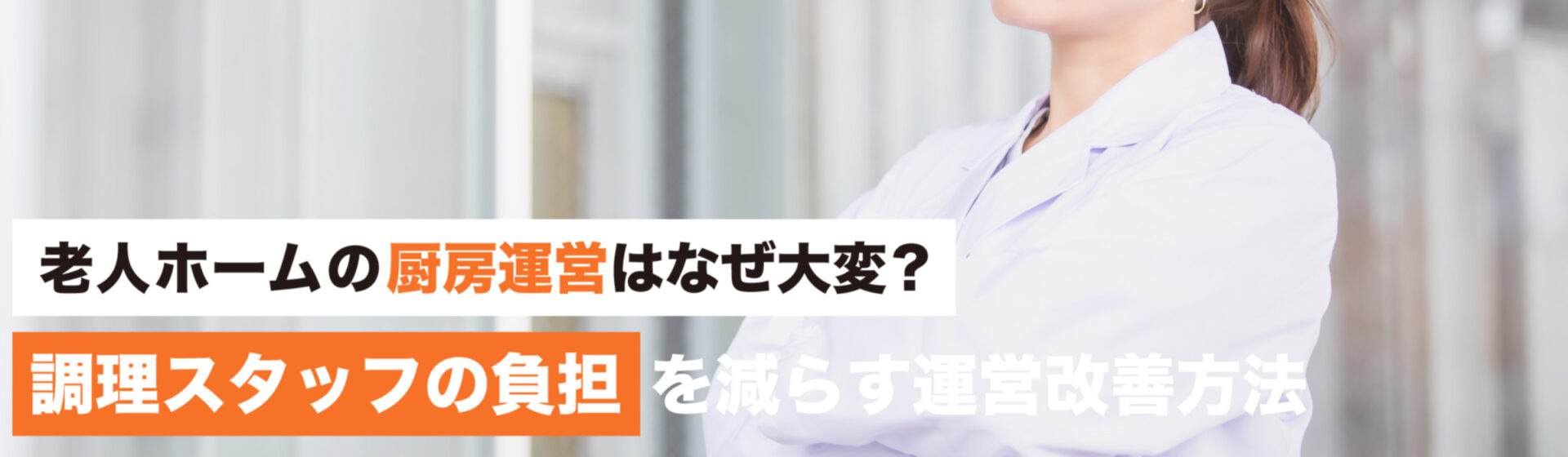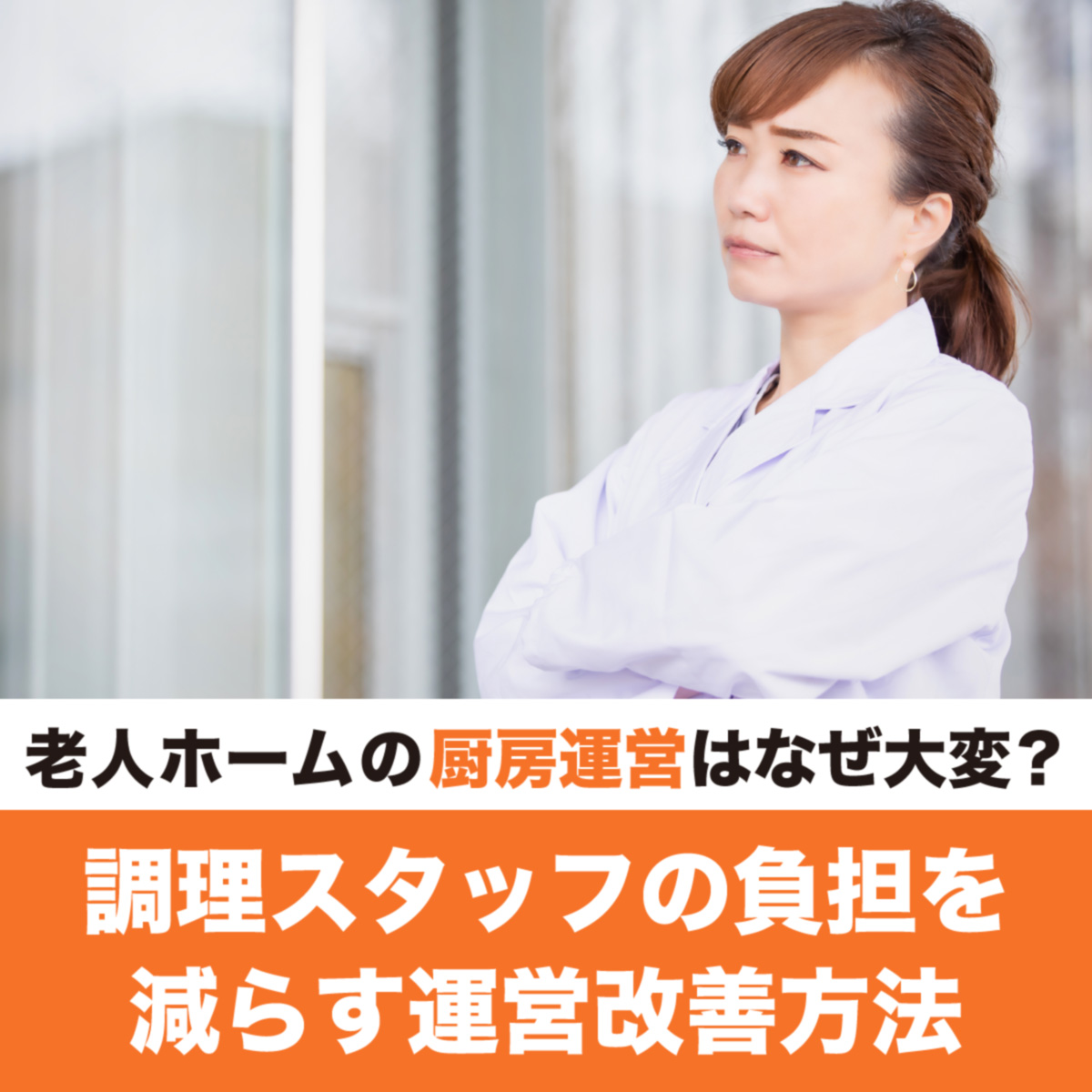老人ホームの厨房の仕事は大変というイメージを持たれ、求人になかなか人が集まらないことも珍しくありません。給食調理員や調理補助の仕事は無資格や未経験でも働くことができるため、最初のハードルは低いものの、きつい・辞めたいという声が多い現状です。この記事では、給食調理員や調理補助の仕事の特徴に注目しながら、老人ホームの厨房業務が大変だといわれる理由も踏まえて、調理スタッフの負担を軽減させる厨房運営改善方法のポイントを解説します。
目次
給食調理員や調理補助の仕事とは
給食調理員は、給食用の料理を作る仕事で、就業場所は介護施設や病院、学校、保健所、給食委託会社などさまざまです。主に管理栄養士や栄養士による指示や献立表に従って、食事の提供を行います。仕事内容には、献立表やレシピに従って調理を行うだけでなく、盛り付けや配膳のほか、調理場の清掃、食器の洗浄、残飯の処分なども含まれます。場合によっては、食材の発注や検品などを行うこともあるでしょう。

調理補助は、文字通り調理員の補助を行う仕事で、調理員の作業をサポートするのが特徴です。調理器具や食器の準備をしたり、食材の下処理を行ったりするほか、温めや盛り付けをまかされることもありますが、メインとなる調理作業は行いません。その他、食事を配膳したり、後片付けや食器洗浄を行うことがあります。
資格がなくても働ける
給食調理員や調理補助の仕事は、特別に資格や経験がなくても就業可能です。学歴も問われないことが多く、アルバイトやパートとしての募集もあるため、比較的就業までのハードルは低いでしょう。求人内容によって条件や待遇は異なりますが、未経験から始める人が半数以上の職場や、入社時に研修や講習会などを設けているところもあります。
経験を積めば資格取得も可能
未経験や無資格の状態で調理業務についても、仕事の継続次第では資格取得や昇進が可能です。調理師の資格を取得するには、「2年以上調理業務に従事した者」という受験資格があるため、規定に沿う施設で調理業務として認められた業務を2年以上行う必要があります。勤務時間や業務内容などの指定はありますが、給食施設の調理業務も対象の範囲です。
また、調理師の免許を取得し指定の実務経験などを積めば、調理技術技能評価試験を受けることも可能で、合格すると厚生労働省から「専⾨調理師・調理技能⼠」の称号をもらうことができ、調理師学校の教員資格も得られます。こうした資格の取得によって、給食調理員から調理主任や施設の責任者などに昇進できる可能性が広がります。
老人ホームの厨房業務が大変な理由
給食調理員や調理補助の仕事は、資格や経験、学歴を問わない求人が多く、働き始めやすいうえに、継続すれば資格取得や昇進の可能性が期待できるメリットがあります。しかし「老人ホーム 調理」と検索すると「大変」「辞めたい」「きつい」というワードが同時によく検索されている状況があり、老人ホームの厨房業務の大変さがうかがえます。ここでは、その理由を探り解説します。

厨房業務のデメリット
給食調理員や調理補助の仕事は、仕事を始めやすいメリットはあっても、継続して働くうえでは大変なことがいろいろあります。人それぞれ感じ方は異なりますが、例えば下記のようなデメリットが挙げられます。
- 重労働
- 厳しい衛生管理
- チームワークが必要
- 覚えることが多い
調理業務では、重労働による負担がよく挙げられており、体力がない人には向いていない仕事といわれることもあります。立ちっぱなしの作業となり、大量の野菜を切るなど単純作業を延々と繰り返す、重い調理器具を使う、といった個々の作業の負担が大きく、腱鞘炎が起きたり、腰を傷めたりするケースも珍しくありません。包丁作業のように、気の抜けない慎重な作業を長時間行う負担もあるでしょう。
また、食事を提供する業務のため、適切な衛生管理が欠かせません。調理場や調理器具の消毒に始まり、食材の洗い方や加熱温度なども全て決められた衛生基準に従って行う必要があります。加えて、時間内に作るためには全員で協力して作業を分担する必要があり、時間に追われる中でチームワークを形成しなければなりません。こうした作業をこなすうえで覚える事柄が多く、さらにスピードも求められる現状があります。
老人ホームの厨房業務はさらに大変?
先述したように、調理員や調理補助の仕事自体に大変さがありますが、老人ホームの厨房業務には下記のようにさらに負担になるポイントが挙げられます。
- 介護食や治療食への対応が必要
- 早朝からの勤務
老人ホームの場合、嚥下力や咀嚼力が落ちている利用者さまのために、やわらかくする、きざむ、とろみをつけるなどの工夫が必要となり、通常の食事作りに加えて業務量が増えます。また、疾患を抱えている方には、減塩や低糖質などに調整した治療食に変更することも必要です。加えて、個別のアレルギー対応なども欠かせません。

さらに老人ホームでは1日3食の用意のため、朝食作りを行うには早朝に出勤しなければならず、朝の5:30に勤務が始まるところもあります。老人ホームの厨房業務は一般的な調理業務よりも業務量が増えるうえに、過酷なシフトに対応しなければならず生活リズムが崩れやすいことも大変さにつながる特徴です。
離職率に伴い圧迫される厨房業務
厚生労働省の「令和5年 雇用動向調査結果の概要」によると、2023年の1年間における産業別の入職者数と離職者数では、「宿泊業、飲食サービス業」が入職者数と離職者数共に一番多い結果が出ています。一般労働者とパートタイム労働者を合わせて、32.6%が入職しても26.6%は離職してしまう状況です。調理師も含まれる業種のため、調理員の業務の大変さをうかがい知ることができます。
さらに介護業界は近年人手不足であり、厨房業務の人手不足も例外ではありません。人員が足りないことで一人当たりの業務量が増加し、頻繁に残業が発生し、調理員がどんどん疲弊していく状況で離職にもつながる原因となっています。
調理スタッフの負担を減らす厨房運営改善にはニュークックチルがおすすめ
先述したように、近年の老人ホームの厨房業務は困難を極める状況にあります。「大変」「つらい」という業務のイメージを払拭して求人に応募してもらうには、まず厨房運営そのものを改善するのもカギです。厨房運営の改善では、現在の厨房業務のデメリットをなるべく少なくできるように、下記のようなポイントに注目して取り組んでみましょう。
- 一人当たりの業務負担を削減する
- 早朝のシフトを削減する
人手が足りない中で業務負担や業務時間を削減するには、調理自体の方法を変えることも役立ちます。そこで注目されているのがニュークックチルの調理方式です。
業務負担改善と人手不足を同時に解決できるニュークックチル
ニュークックチルは、クックチルの方式をさらに進化させたもので、食品を加熱調理した後に急速冷却してチルド状態のまま盛り付けまで行っておき、食事のタイミングで再加熱して提供する方法です。対応機器内に保存しておくと自動で再加熱されるため、食事が温まったらすぐに配膳することができます。

そのため、食事提供の際の業務が簡素化されることにより、早朝や遅番の無人化が可能となります。朝のシフトは8:30〜、夕方のシフトは17:00までという勤務形態も可能となるため、シフトの負担を大きく削減できるでしょう。調理済みのクックチル食品を導入すれば、食材の下処理や専門的な調理作業が不要となり、誰でも簡単に食事の準備ができるため、個々の業務負担を削減することができます。
ナリコマでは調理スタッフ用のマニュアルも完備!

ナリコマでは、介護食に対応したクックチル食品があり、ニュークックチルシステムにも対応しています。また、スタッフ育成に役立つ厨房マニュアルをダウンロードするだけで簡単に利用できるほか、初めて作る献立やニュークックチルに慣れていないスタッフでもイメージしやすいように、厨房ノウハウをまとめた動画も配信しています。ナリコマのサービスを厨房運営方法の改善にぜひお役立てください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
人材不足に関する記事一覧
-

特定技能制度を活用したい!外国人の在留資格や雇用方法などを解説
近年の人手不足の課題解決の一つとして、特定技能制度が注目されています。この記事では、特定技能制度による在留資格「特定技能」の概要から、産業分野一覧、試験等の詳細や資格取得までの流れ、雇用方法などをわかりやすく解説します。病院や介護施設の厨房業務の人手不足にお悩みの施設さまはぜひご参考ください。
-

介護現場に働き方の変化を|シフト柔軟化と業務改善で叶える離職防止と人材確保
今、介護現場の働き方の変化が大きなテーマとなっています。
慢性的な人手不足や離職率の高さに加え、2025年問題など将来の人材不足を見据え、柔軟な働き方や業務改善の必要性がますます高まっています。
今回は、シフト柔軟化・短時間勤務・業務改善策をどう取り入れ、「選ばれる職場」「続けられる現場」を目指していけるのか、取り組みのヒントや実践のポイントをお伝えします。
さらに、ナリコマのクックチルによる厨房業務の負担軽減策もご紹介し、働きやすさとサービス品質を両立するヒントをお届けします。 -

育成就労制度とは?技能実習制度の制度変更による違いや特徴を解説
「育成就労制度」は、2024年に創設され3年以内に施行される制度です。この記事では、旧制度である「技能実習制度」の概要や課題を振り返りながら、制度変更によりどう変わるのかを、育成就労制度の特徴や受け入れ企業の実務のポイントも押さえながら解説します。