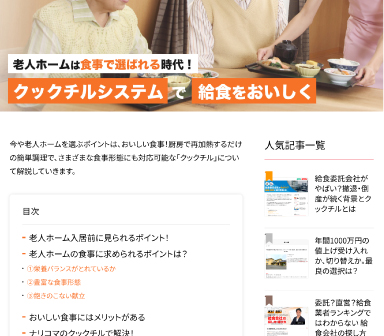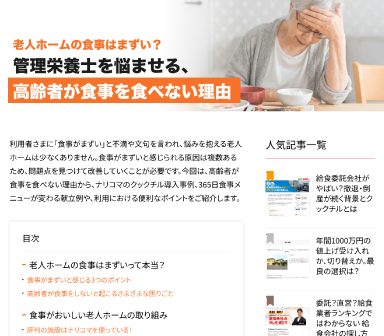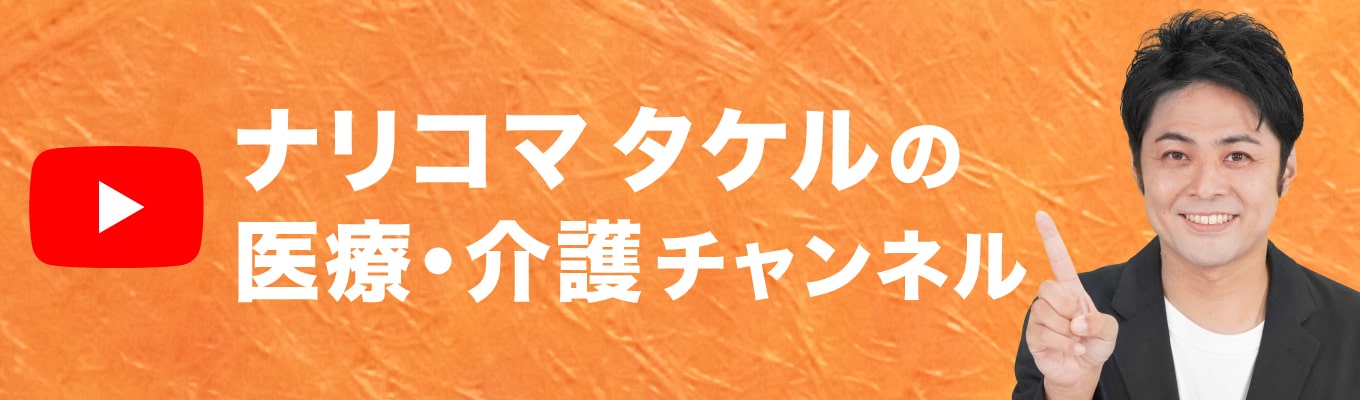日本では少子高齢化が社会問題として取り上げられており、この先も数十年にわたって65歳以上の人口率が上昇し続けるとみられています。近年は介護系施設・サービスの利用者も大きく増加。そこには、高齢化の進行状況が顕著に現れているといえるでしょう。
今回お届けするテーマは、年々増えていく高齢者の健康問題と深くかかわる「フレイル」です。フレイルの定義や診断基準などをお伝えし、日常生活における予防策を紹介。記事後半では食生活に焦点を当て、フレイル予防のためのポイントを詳しく解説します。
目次
高齢者が陥りやすいフレイル
フレイルの定義
フレイルは、健常と要介護の中間に当たる状態です。加齢によって心身が衰え、身体機能・認知機能の低下などがみられます。海外の老年医学において使われる用語「Frailty(フレイルティ)」に由来しており、もともとは「虚弱」という日本語訳が使われてきました。しかし、一般社団法人日本老年医学会はより適切な日本語訳を検討。認知度を高め、予防の重要性も伝えやすくなるよう、2014年5月に「フレイル」という表現に改めました。

高齢者の場合、フレイルを経て要介護へと移行するケースが一般的です。そのため、日常生活の中で兆候や症状にいち早く気付き、適切な介入・支援を行うことが重要と考えられています。フレイルに陥る主な要因は、身体的、精神的、社会的なもの。そういった要因を取り除いたり、改善したりすることで、健常な状態に戻れる可能性が高くなります。
フレイルの診断基準
フレイルかどうかを診断するには、老年医学の専門家であるリンダ・P・フリード博士が提唱した国際的な基準を用います。いずれにも当てはまらなければ健常。該当数が1〜2項目ならプレ・フレイル、3項目以上ならフレイルと診断されます。では、各項目を詳しくみていきましょう。
①大幅な体重減少
ダイエットしているわけではなく、いつも通りに食事をして体重が大きく減ってしまう場合は注意が必要です。フレイルの診断基準は1年間で4.5kg以上、半年で2〜3kgの減少とされています。
②歩行速度の低下
高齢者の多くは、加齢が原因で心肺機能が低下したり、足腰が弱くなったりします。フレイルを診断する基準は歩行速度。「以前より歩くのが遅くなった」と感じる場合、フレイルの可能性があります。具体的な診断基準は1.0m/秒未満です。
③疲労感
「何もやる気が起きない」「外に出るのが面倒だ」「疲れやすくなった気がする」といったことがある場合は、フレイルかもしれません。もちろん一時的な話であれば問題ありませんが、週3〜4日ほど続くようなら要注意です。
④筋力の低下
筋力の低下は、フレイルの代表的な症状です。握力が診断基準になっており、男性は26kg未満、女性は18kg未満とされています。このように、筋肉量が減り、筋力も低下した状態はサルコペニアと呼ばれることも。加えて、起立や歩行にも支障がある状態はロコモティブシンドローム(通称:ロコモ)といいます。どちらもフレイルの一部と考えていいでしょう。
⑤身体活動量の減少
高齢者がフレイルに陥ると、身体活動量が減ってしまうケースは多いようです。「軽い運動・体操」と「定期的な運動・スポーツ」のいずれもしていない場合は、フレイルの可能性があります。
日本では、上記のほか、厚生労働省が2006年に導入した基本チェックリストも活用されています。全部で25項目あり、身体的・精神的・社会的な内容をしっかりカバー。多面性のあるフレイルが診断しやすいよう工夫されています。
フレイルを防ぐために重要なこと
フレイルの症状は主に加齢によって起こるとされています。しかし、心身が衰える要因はそれだけではありません。生活習慣や環境、疾患など、考えられる要因はさまざま。本項目では、高齢者自身が取り組めるフレイル予防のポイントをまとめてみました。
フレイル予防のポイント①適度な運動を習慣化
もちろん個人差はありますが、歳を重ねると、多くの人は若いときと同じように動くのが難しくなるでしょう。だからといって、自発的に動かなくなると筋肉量が減り、筋力もどんどん低下してしまいます。
先にお伝えしたサルコペニアやロコモティブシンドロームにならないためにも、日常生活に運動を取り入れるのがおすすめ。無理のない範囲で、まずは簡単な体操や散歩などを毎日の習慣にするといいでしょう。
フレイル予防のポイント②健康管理の徹底
高齢者の中には、疾患を抱える人も多いかもしれません。疾患が負担になると、行動範囲が狭くなったり、家の中でもあまり動かなくなったりすることも想定できます。適切な治療を受け、症状を改善、もしくは悪化させないことが重要です。
また、インフルエンザや風邪などの感染症を予防することも大切。重症化して入院した場合、寝たきりになってしまう恐れもあります。つまり、日頃からしっかりと健康管理をすることがフレイル予防に効果的なのです。

フレイル予防のポイント③栄養バランスのとれた食生活
筋肉や骨を支える大事なものといえば、毎日の食事です。栄養不足にならないことはもちろん、栄養が偏らないようにバランスよく食べることも大きなポイント。また、食事でのストレスや不自由を生まないよう、口腔内をこまめにケアしたり、嚥下訓練や咀嚼訓練などを行ったりするのもおすすめです。
フレイル予防のポイント④コミュニティへの参加
社会的孤立はフレイルの要因になるといわれています。趣味のサークル、ボランティア活動などのコミュニティに参加することで、身体活動量が自然に増えるでしょう。さらに、人との関わりや会話によって、精神的な健康も保ちやすくなります。
フレイル予防になる食事とは?
本項目では、予防のポイント③で挙げた食生活について、もう少し細かくみていきましょう。
一日三食のリズムをつくる
フレイルを予防する上で最も大事なのは、一日三食、しっかり食べること。食事を抜いてしまうと、十分な栄養がとれません。また、まとめてたくさん食べると血糖値が急激に上がり、健康上のリスクも高くなるのです。ただし、ある程度決まった時間に食べることも重要。規則的に食事をすると生活リズムが整い、さまざまな疾患の予防にもなります。

主食・主菜・副菜で栄養バランスを整える
食事は主食・主菜・副菜をそろえ、栄養バランスのいい献立を考えましょう。特に重要な栄養素は、筋肉をつくるたんぱく質。具体的には肉、魚、卵、大豆食品などがおすすめです。筋肉や骨の健康を支えるビタミンDが豊富な一部の魚介類やきのこ類、骨をつくり丈夫にするカルシウムが多い乳製品なども取り入れると、よりいっそうフレイル予防に効果的。食事の準備が負担になる高齢者は、手軽な冷凍食品や加工食品も活用するといいでしょう。
「共食」を意識する
フレイル予防には、誰かと一緒に食べる「共食」が非常に有効とされています。一人で食べるといつも同じような献立になったり、心が不安定になったりする可能性が高くなるそうです。同居人がいる場合は、できるだけ一緒に食卓を囲むようにしましょう。家族や友人が遠方にいる場合は、テレビ電話やオンライン通話で話しながら食事をするという方法もあります。
フレイル予防にも◎!おいしくて高栄養の献立サービス

ナリコマでは、365日日替わりの献立サービスをご提案しております。常食のほかにソフト食・ミキサー食・ゼリー食も展開。嚥下機能に不安がある高齢者の方々も安心してお召し上がりいただけます。また、献立はおいしさにこだわるだけでなく、バランスよく十分な栄養がとれるように計算済み。フレイル予防の食事としても役立ちますので、ご興味があればぜひ一度ナリコマにお問い合わせください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
委託に関する記事一覧
-

地域包括ケアの仕組みとは?多職種連携や課題についても詳しく解説
日本は将来的に高齢者が激増するといわれています。そんな高齢化社会を支える医療・介護・福祉のあり方として推進されているのが「地域包括ケア」というシステムです。本記事では、地域包括ケアの基本的な仕組みについて詳しくお伝えします。また、その中で重要視される多職種連携や、今後の課題や対策についても解説。ぜひ最後までお読みください。
-

介護福祉教育研修制度でスキルアップ!実務者研修や認知症ケア研修等のサポートや実施のコツ
介護福祉教育研修制度の充実は、個々のスタッフのスキルアップを促し、より高度なサービスを提供できる施設運営にも役立ちます。この記事では、介護福祉士になるために必要な研修や、実務者研修の資格講座内容などを改めて振り返りながら、介護資格取得支援制度への取り組みや認知症ケア研修等の法定研修のサポートや実施のコツを解説します。
-

給食委託会社切り替え時に必要なものって?
施設給食に対する悩みが増えてきたら、それは給食委託会社の切り替え時かもしれません。
委託会社切り替えのメリットやデメリット、次の給食会社を選ぶ際に確認しておきたいポイントもご紹介!
給食委託会社以外の運営方式「直営支援方式」についても解説しています。