BCPは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った用語で、事業継続計画を意味しています。危機的な状況下でも重要な事業を中断させない、または早期復旧させるための計画です。この記事では、さまざまな災害がある中で、BCPが病院や介護施設に必要な理由とその役割について、高齢者が災害時に受ける影響と共に解説します。
目次
さまざまな災害に必要不可欠なBCP

日常で起こり得る災害はさまざまにありますが、その中でも大きく、自然災害・人為災害・特殊災害、の種類に分けることができます。これらの3つの災害には、下記のような特徴があります。
- 自然災害:自然現象による、地震・津波・台風・洪水・火山噴火などの災害
- 人為災害:人為的な要因による、大規模火災・大型交通事故・化学爆発などの災害
- 特殊災害:自然災害と人為災害の混合など、化学物質・生物・放射性物質・核・爆発物などによる災害
これらの災害は予測するのが困難なうえ、特殊災害は自然災害と人為災害が組み合わさったものが多いこともあり、さらに避けるのが難しいでしょう。内容によって分類の考え方が異なる場合もありますが、感染症によるパンデミックもこうした災害の一つです。
いつ発生するかわからない災害に対応するには、日頃から備えておくことが大切です。災害の内容は多岐にわたり、水や非常食の確保など部分的な備えでは間に合わないこともあるため、緊急時にどう行動するかということも必要になります。過去に起きた災害では、適切なマニュアルがないことや内容が不十分だったことなどが課題となっていました。そういった課題も受けて近年ではBCPが重要視され、災害拠点病院や介護事業所ではBCPの策定が義務化されています。
施設の環境に合ったBCPを策定しよう
BCPは、義務化されている災害拠点病院や介護事業所だけでなく、さまざまな事業所でも策定が推奨され、内閣府のホームページでは業種ごとのガイドラインが提供されています。その中にもありますが、病院や介護施設のBCPは、厚生労働省によるガイドラインを参考にしてみてください。介護施設向けのBCP資料は、各自治体の情報も参考になります。

また、病院や介護施設のBCPは環境や状況によって作り方が異なるため、情報も細分化されています。病院向けに提供されている資料によっては、例えば、災害拠点病院用のBCPと災害拠点病院以外のBCP、災害拠点連携病院向けや一般医療機関向けなどによってガイドラインが分かれていることがあるでしょう。介護施設では自然災害用と感染症用を作ることが必要です。
普段の業務内容がそれぞれの施設によって異なるように、BCPもまた、個々の業務における緊急事態に備えた内容にする必要があります。そのため、環境に合わせて内容を工夫しましょう。策定の際には、運営する施設に適した情報集めが役立ちます。
高齢者が災害で受ける影響とBCPの役割
持病があったり、身体が自由に動かなかったり、体力が低下していたり、と日常生活の段階で不自由さを抱えている高齢者は、災害時により多くの影響を受けやすいことがあります。安全な場所に避難することも自力では難しいことがあるため、どのように助けるのかをあらかじめ考えておくことが必須です。ここでは、災害が高齢者に与える影響とBCPによって予防できることを解説します。

災害が高齢者にもたらすこと
災害時には、普段とは違う環境で長時間過ごさなければいけない場合があります。身体を自由に動かせない状態で同じ姿勢をとり続けることで、エコノミー症候群を引き起こすことがあり注意が必要です。衛生環境が整わない環境では、身体の抵抗力が低下していることにより、食中毒や感染症にもかかりやすくなります。また、災害時の環境は精神面にも影響を及ぼすことがあり、不安感が強くなる高齢者もいます。
災害後の避難生活によって、持病を悪化させたり、身体機能がさらに低下したり、認知症が進行したりすることがあるため、高齢者の避難生活にはさまざまな注意と対策が必要です。
BCPにより予防できること
BCPは、非常事態のデメリットをなるべく避けて業務を継続させるための計画です。BCPを策定し職員に浸透させ、非常時でも通常の業務を最大限継続することで、災害時に高齢者が受ける影響を最小限に抑えることができるでしょう。避難時には、業務や高齢者への対応も含め過酷な状況で職員が疲弊し体調を崩すケースもあり、そうなるとより状況は悪化します。BCPは、病院や介護施設で働く職員を守るためにも重要な計画です。
BCPの策定では、あらかじめ全体の意思決定者や個々の担当業務を決めておくため、非常時でも混乱を招きにくくなります。災害の内容に合わせて、電気やガス、水道などが止まった場合や、衛生面の対策などを検討しマニュアル化するため、冷静に最適な行動をとることが可能です。
ナリコマの災害対策と対応実績
ナリコマには全国に6ヵ所のセントラルキッチンがあり、各対応エリアに営業所があるため、非常時には全国規模で各セントラルキッチンと営業所が協力して対応することができます。また、今後も対応エリアは拡大予定のため、それに伴い非常時に対応できるエリアも拡大されます。

ナリコマの非常食
ナリコマは、過去の災害の体験から、非常時でも衛生的に食事を摂ることの重要性を知り、非加熱でもすぐに食べられる非常食を開発いたしました。非常時は気力や体力も消耗しやすいため、心身の回復のためにも食事は必要不可欠です。また、ただ食べられれば良いというのではなく、栄養が摂れておいしいことも重要です。
そのため、ナリコマでは、非常時でも日常と変わらないおいしい食事を楽しめることを前提に、献立とおいしさにこだわりました。そうして生まれたのが、ナリコマのひまわり非常食です。ひまわり非常食は、誰でも簡単に非加熱調理で温めずに食べることができます。また、介護食作りのプロが手掛けており、普通食・ソフト食・ミキサー食・ゼリー食の4形態から選べます。
ナリコマの災害対応実績
ナリコマでは、過去に起きた災害時もできる限りの対応を行ってきました。2016年の熊本地震では、交通が一時不通となりましたが、地震発生の2日後から8日間の支援を行い、契約施設と未契約施設合計26の施設さまに、水やパン、非常食、消耗品などの必要な物資をお届けいたしました。
2024年の能登半島地震では、交通に問題がなかったため、一部遅延はしたものの当日中に契約施設さまに救援物資をお届けすることができました。とくに飲料水が不足していたため、全国のセントラルキッチンで協力して飲料水を確保し、非常食や消耗品と共にお届けいたしました。
BCP&ナリコマの非常食を災害時の備えに
ナリコマでは、BCP策定に役立つ資料の配布や無料セミナーも行っているため、BCP策定にお悩みの施設さまはお気軽にお問い合わせください。

ナリコマの非常食は受注生産のため、ご希望に合う数量をご注文いただけます。契約施設さまは、よりお得にポイントでご購入できるシステムもあるため、現在ナリコマのサービスをご利用中の施設さまもぜひご検討ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
委託に関する記事一覧
-
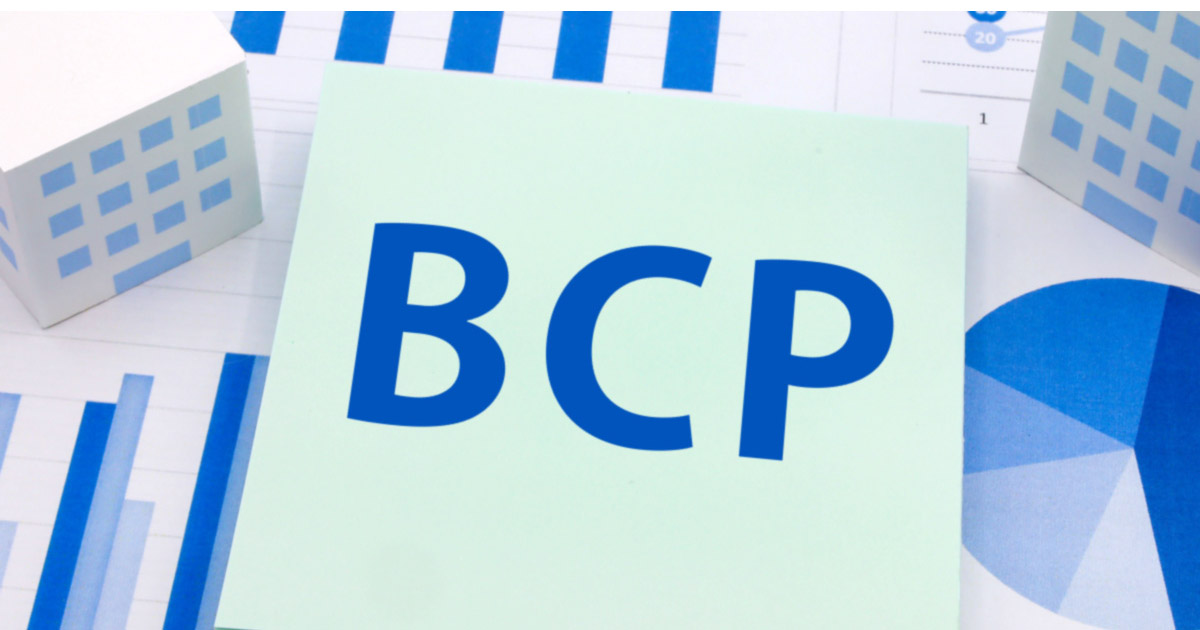
災害と介護研修の取り組み方とは?BCP研修や防災訓練など災害対応教育を強化しよう
災害と介護研修について日頃から考え、対策を練っておくことはとても重要です。この記事では、災害対応教育の重要性を法定研修と共に振り返りながら、介護施設や事業所が行うべきBCP研修や、防災訓練に取り組む際のポイント、給食提供に関する厨房のBCP対策について解説します。
-

介護福祉教育研修制度でスキルアップ!実務者研修や認知症ケア研修等のサポートや実施のコツ
介護福祉教育研修制度の充実は、個々のスタッフのスキルアップを促し、より高度なサービスを提供できる施設運営にも役立ちます。この記事では、介護福祉士になるために必要な研修や、実務者研修の資格講座内容などを改めて振り返りながら、介護資格取得支援制度への取り組みや認知症ケア研修等の法定研修のサポートや実施のコツを解説します。
-

介護施設に適した食事の提供体制とは?外部委託の選定ポイントも紹介
日本は65歳以上の高齢者人口が年々増加しており、2043年には3,953万人でピークを迎えるといわれています。一方、2024年10月1日時点で1億2380万人余の総人口は減少していく見込み。今後は高齢化率が上昇し、2070年には2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になると推測されています。
こうした背景から、近年では介護福祉サービスの需要が高まっています。今回お届けする記事のテーマは、そんな高齢者ケアの拠点となる介護施設の食事。食事の重要性や提供体制について解説し、外部委託業者の選定ポイントなどもあわせてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
セントラルキッチンに関する記事一覧
-

PHR活用のススメ!基本的な仕組みやメリットをまとめて解説
近年は健康管理への関心が高まっており、各種メディアでもさまざまな用語や情報が取り上げられています。本記事でピックアップするPHRは、健康に関する個人情報管理の一つ。PHRの仕組みやメリット、活用方法などをまとめて詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。
-

医療DXの一環として病院給食も見直しを!業務効率化と厨房省人化が改革のカギ
医療DXは世界各国で推進されており、日本も例外ではありません。しかし、どちらかというと歩みは遅く、これまでの環境とあまり変わっていない医療機関も多いようです。本記事では、そんな医療DXと密接な関係にある病院給食に注目。医療DXを進める中で病院給食がどうあるべきなのか、詳しく解説します。











