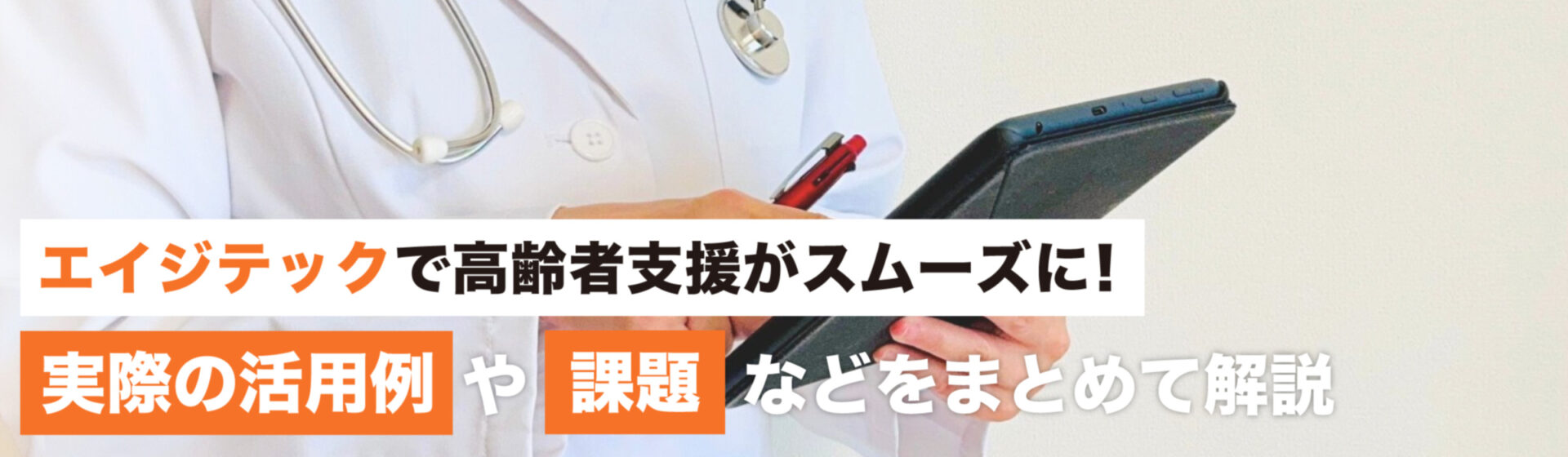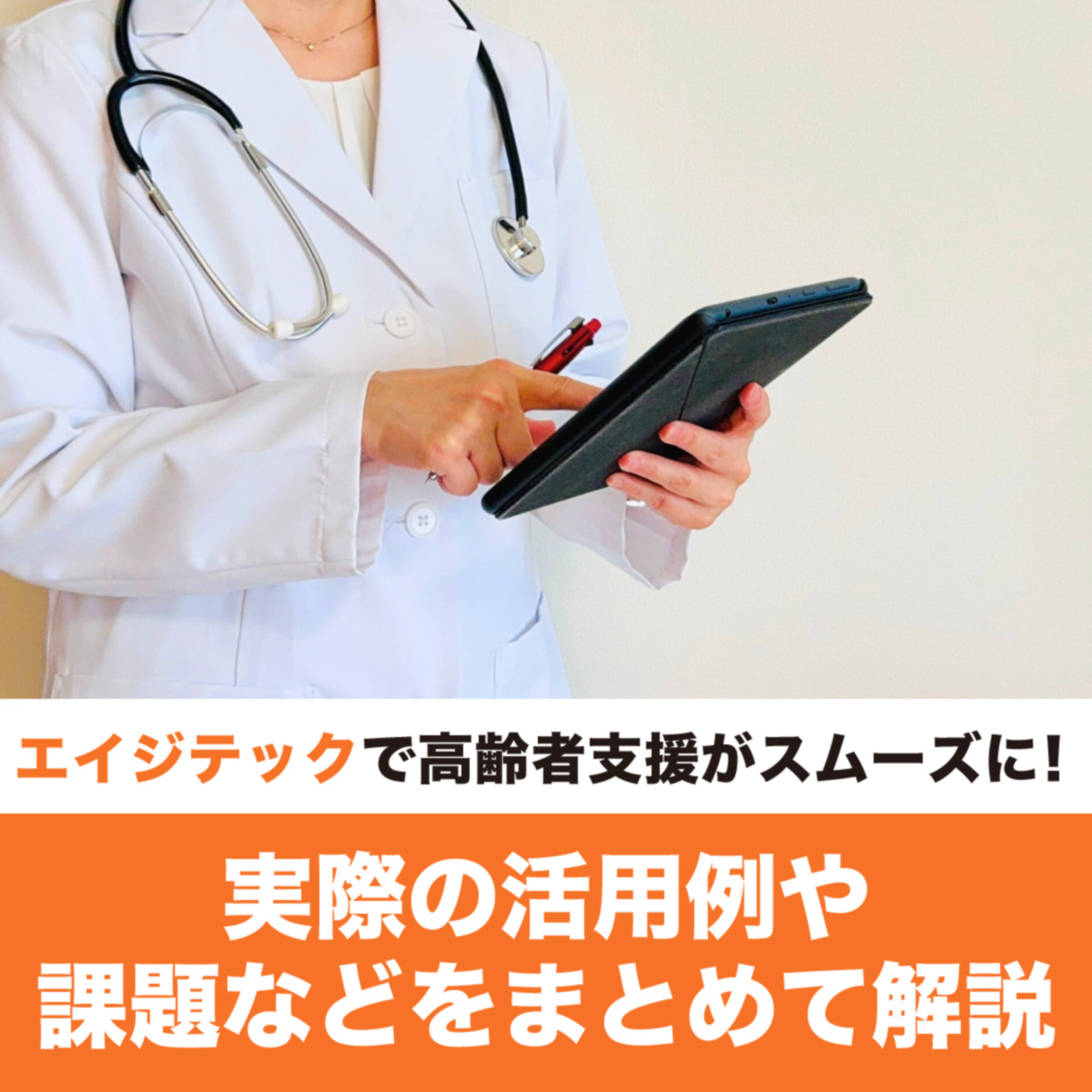私たちの日常生活は、これまで開発・研究されてきたさまざまな技術に支えられています。「技術がなければ暮らしていけない」といっても過言ではないかもしれません。この数年で注目度が上がっているエイジテック(Age Tech)もまた、将来的に不可欠な存在になる可能性があります。今回の記事は、そんなエイジテックについて詳しく解説。概要や活用例、今後の課題などをまとめてお伝えします。ぜひ最後までお読みください。
目次
エイジテックの概要

エイジテックは、年齢を意味する「Age(エイジ)」と技術を意味する「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語。高齢者を対象とした技術と、その技術を使ったサービスのことを指します。高齢者が抱える問題を解決すると共に、生活の質を向上させ、健やかに暮らせるようサポートすることが主な目的です。
近年は情報通信やAI、ロボットなどをはじめとする多種多様な技術が研究され、驚くほど進化し続けています。エイジテックには、そういった数々の技術が含まれています。具体例はのちほどお伝えしますが、適用されている分野も医療・介護・生活支援・レジャーなど、さまざまです。
エイジテックが注目される理由
エイジテックの注目度が上がっている主な理由は、近年特に重要な社会問題として指摘されている少子高齢化です。内閣府が公開した「令和6年版高齢白書」によると、日本の総人口は令和5(2023)年10月1日時点で1億2,435万人。高齢者といわれる65歳以上人口は3,623万人で、全体の29.1%を占めています。この高齢化率は令和22(2040)年に34.8%でピークを迎えますが、令和52(2070)年には38.7%まで上昇すると推測されているのです。
しかし、高齢化が進む一方、総人口は減っていくといわれています。令和38年は1億人を下回る9,965万人に、令和52年はさらに減少し8,700万人になるという推測があります。人口減少の要因とされるのは、出生数の変化です。平成22(2010)年に1,071万人だった出生数は、令和4(2022)年時点で771万人まで減少。出生率(人口1,000人当たりの出生数)にすると8.5%から6.3%まで落ち込んでいます。将来的にも上昇する目処は立っておらず、令和32(2050)年には6.0%を下回ると考えられています。
推測通りに少子高齢化が進んだ場合、いくつかの問題が懸念されています。実は、エイジテックが注目される理由はそこにあるのです。実際にどのようなことが問題になるのか、エイジテックとの関係も含めて詳しくみていきましょう。

①医療費・介護費用の増加
高齢化が進むと、医療や介護を必要とする人も増えていきます。そこで問題となるのが、医療費や介護費用といった社会保障費の増加です。平成30(2018)年を基準にすると、令和7(2025)年は医療費が1.2倍、介護費用が1.4倍の見込み。高齢化率がピークとされる令和22(2040)年には医療費が1.7倍、介護費用が2.4倍になるとみられています。
このような状況が続けば、従来の制度をそのまま適用するのは難しくなります。制度の見直しはもちろんですが、同時に、医療や介護に関するコストを抑えることも重要なのです。エイジテックは、医療・介護業務の効率化やサービスの利便性向上などに貢献できるものであり、結果としてコスト削減にもつながると考えられています。
②人材不足の深刻化
前述したように、高齢者が多くなれば医療・介護のニーズも高くなります。ところが、現在は高齢化だけでなく少子化も進んでいる状況。労働者として社会全体を支える若年・中年層が減少すれば、やがて医師や看護師、介護福祉士などの人材不足も深刻化していきます。
医療・介護業界は労働環境が厳しいことも影響し、以前から人材不足が課題といわれてきました。しかし、少子高齢化によってさらなる苦境に陥ってしまう可能性があるのです。エイジテックは将来的に人材不足の現場を支え、良質な医療・介護サービスを効率的に提供できるのではないかと期待されています。
③高齢者の孤立
少子高齢化の進行には、高齢者が孤立しやすくなるという懸念もあります。令和2(2020)年時点で65歳以上の単独世帯数は6,717世帯でしたが、令和22(2040)年には10,413世帯まで増加する見込み。令和32(2050)年には10,839世帯となり、独居率は男性が26.1%、女性が29.3%になると推測されています。エイジテックは、そんな高齢者の孤立状態を支えたり、防いだりする役割も担っているのです。
エイジテックの活用例
では、エイジテックの活用例を種類ごとにみてみましょう。
高齢者自身が使うエイジテック
食生活、服薬、バイタルデータ、歩数などをスマートフォンやタブレットに記録できる健康アプリは、日常生活に寄り添うエイジテック。ホームセキュリティシステムや家電製品のリモコンなどが高齢者向けに使いやすくデザインされていることも、活用例の一つです。
医療・介護従事者や行政が使うエイジテック
医療・介護施設では、医療機器や福祉機器などにエイジテックが導入されています。具体的にはオンライン診療やリハビリシステム、介護ベッド、徘徊防止システム、可動式入浴台などがあります。また、行政でもAIを搭載したコミュニケーションアプリの開発など、高齢者の健康や安心を支える取り組みが進められています。

高齢者を支える個人が使うエイジテック
高齢者を支える家族などが使うエイジテックもあります。例えば、自宅で安全に過ごすための手すりやスロープ、離れて暮らす家族も様子がわかる見守りアプリ、双方向の通話ができるビデオチャットアプリなどが挙げられます。
高齢期に備えて使うエイジテック
エイジテックは、高齢期の健やかな暮らしに備えて活用されることもあります。この場合は主なターゲットが若年・中年層で、スマートフォンやウエアラブルデバイス向けの健康管理アプリ、遺伝子検査などが挙げられます。
エイジテック導入における課題
前述した活用例からもわかるように、エイジテックには高齢者の生活の質を向上させるほか、医療・介護従事者の負担軽減や現場の業務サポートといった導入効果が得られます。しかし、活用し続けるためには二つの大きな課題を解決しなくてはなりません。

一つ目の課題は、開発・導入費用を確保すること。新たな技術を生み出すには、長期にわたる研究や実験などを行う必要があり、多額の費用がかかります。その環境を整えるためには、開発元だけに頼らず、政府や自治体も支援体制を構築すべきでしょう。
もう一つの課題は、高齢者や医療・介護従事者が正しく使いこなせるかどうかという点です。最も重要なのは、エイジテックを活用した製品やサービスについてよく理解すること。わからないからといってそのままにせず、高齢者や医療・介護従事者が自ら学ぶ姿勢を持つことも大切です。
ここにもエイジテック!ナリコマの介護食
ナリコマでは、高齢者が安心してお召し上がりいただける介護食をご用意しております。ソフト食・ゼリー食・ミキサー食のバリエーションがあり、普通食と同じメニューでご提供。新たな調理技術により、少食でも十分な栄養がとれる「少量高栄養」の介護食を追求しています。

また、基本の献立サービス「すこやか」は365日日替わりでお届け。長期利用の方も、飽きずにお楽しみいただけます。また、厨房のサポート体制も充実。調理工程を減らすクックチル方式の採用、発注や帳票管理に使える独自システムなど、業務効率化にも貢献することができます。医療・介護施設のお食事は、ぜひナリコマにおまかせください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
セントラルキッチンに関する記事一覧
-

給食委託会社切り替え時に必要なものって?
施設給食に対する悩みが増えてきたら、それは給食委託会社の切り替え時かもしれません。
委託会社切り替えのメリットやデメリット、次の給食会社を選ぶ際に確認しておきたいポイントもご紹介!
給食委託会社以外の運営方式「直営支援方式」についても解説しています。 -

DXリテラシーで給食の現場が変わる!具体的な取り組みやメリットを解説
みなさんは、「DXリテラシー」という言葉に聞き覚えがあるでしょうか? 近年では、業界を問わずDXリテラシーの重要性を意識する企業が増えてきています。今回の記事は、そんなDXリテラシーについて詳しくお届け。「そもそもDXって何?」という疑問を抱く方にもご理解いただけるよう、言葉のルーツや定義、その重要性もしっかりとお伝えします。給食現場における具体的な取り組みやDXリテラシー向上のメリットについても解説。ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考になさってください。
-

給食業務のICT活用に向けた教育研修!ICT基礎・ICT機器導入研修を踏まえたDX研修設計のコツ
病院や介護施設を含む給食現場では、近年の課題解決に向けてICT活用を望む環境が増えてきています。この記事では、給食現場でICTを活用するメリットとあわせて、従業員の教育研修に役立つ、ICT基礎研修・ICT機器導入研修・DX研修の設計のコツを解説します。給食業務のICT活用やICT関連の研修設計をご検討中の際にはぜひご参考ください。