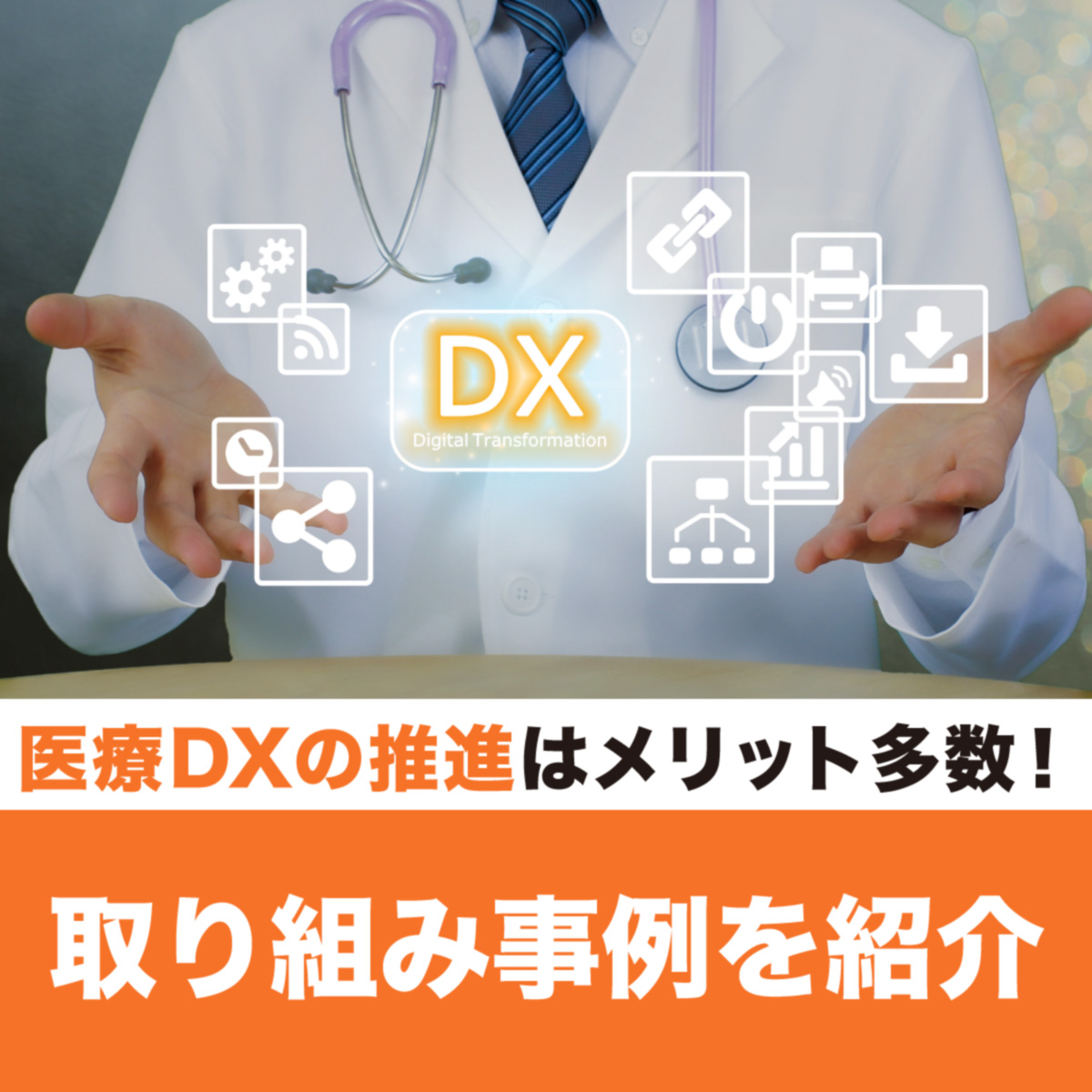近年は、「DX」という言葉がさまざまなメディアで散見されるようになりました。あらゆる産業で推進が望まれていますが、実際、医療の現場ではどのようなメリットがあるのでしょうか? 本記事では、医療DXの概要と共に、解消すべき課題や導入事例などもまとめてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
目次
医療DXの概要
DXの定義
DXは、Digital Transformation(デジタル・トランスフォーメーション)の略称です。2004年、スウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱。当初は「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義されていました。この考え方は世界へと広がり、近年のビジネス界においては「IT技術やデータを駆使し、業務プロセスや事業内容だけでなく組織全体に変化・改革をもたらすこと」という意味で用いられるようになっています。

日本でDXの注目度が上がってきたのは2010年以降のこと。2018年には、経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」を発表しました。現在も引き続き、あらゆる産業に対してDXの推進を呼びかけています。
医療DX推進本部の設置
政府は2022年に医療DXの推進本部を設置しました。医療DXにおいて最も重要なポイントは、保健・医療・介護の各段階で発生するデータを有効活用し、業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図ること。2030年度までに実現すべき目的として、以下のような内容が挙げられています。
①国民のさらなる健康増進
②切れ目なく質の高い医療等の効率的な提供
③医療機関等の業務効率化
④システム人材等の有効活用
⑤医療情報の二次利用の環境整備
現在、日本は高齢化社会が急速に進んでいる状況です。「令和6年 高齢社会白書」によると、令和5(2023)年10月1日時点の高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)は29.1%。この割合は令和22(2040)年に34.8%、令和52(2070)年に38.7%まで上昇すると予測されています。
そうした高齢化によって生じる問題の一つといわれているのが、医療機関等の現場における人手不足の深刻化。現時点でも人手が十分とはいえない業界ですが、さらに状況は悪化し、従来通りの対応ができなくなる可能性も指摘されています。だからこそ、政府はDXを推進し、先に挙げた5つの目的を達成することで、国民全員が安心して暮らせる社会を継続できると考えているのです。
医療DXで解消すべき課題

課題①人手不足
医療業界では厳しい勤務体制や労働条件の現場が多く、人がなかなか集まらないケースもよくあるといいます。日本は高齢化だけでなく少子化も進んでいるため、このままでは主な労働者の若年・中年層は減少する一方でしょう。前述したように、人手不足を解消しなければ、これまでと同じように業務を行うことさえ難しくなっていくのです。
医療DXは、病院や診療所が問題なく機能しているという前提がなければ成り立ちません。だからこそ、将来的に深刻化が予想される人手不足は、できるだけ早く解消すべき課題なのです。人を集めるためには、長時間勤務の見直し、心身の負担軽減、報酬の調整など、働きやすい環境を整えるのも重要といえます。
課題②デジタル格差
医療DXに欠かせない最大の要素といえば、デジタル技術です。しかし、医療従事者がデジタル機器に対する知識やスキルを持っていなければ、何らかのシステムを導入しても正しく活用することができません。現場においてデジタル格差がある場合は、デジタル機器に強い人材の採用・育成にも力を入れるべきでしょう。
また、医療を必要とする患者側にも類似の課題があります。デジタル機器になじみがない高齢者などは、医療DXによる利用環境の変化についていけない可能性があるのです。デジタルスキルに個人差があると、受けられる医療にも格差が生まれてしまいます。
課題③IT化の遅れ
医療業界は、ほかの業界と比べてIT化が遅いといわれています。厚生労働省による「医療施設調査」の結果によると、一般病院の電子カルテシステム普及率は平成29(2017)年時点で46.7%(調査対象施設数:7,353)。令和2(2020)年にやっと57.2%(調査対象施設数:7,179)まで増加し、全体の半数を超えました。令和5年(2023)には65.6%(調査対象施設数:7,065)となっていますが、規模別の内訳をみると200床未満のところは59%です。
さらに、同年の一般診療所における普及率は55%(調査対象施設数:104,894)。いまだに紙ベースのカルテを使っているところは多いといえるでしょう。こうした一部のデータだけでも、IT化の進んでいない現状が見えてきます。
しかし、IT化には導入コストだけでなく、継続的なメンテナンスコストもかかります。病院や診療所の多くは赤字の状況が続いているため、膨大なコストがかかるIT化は後回しになってしまうのかもしれません。ただ、医療DXの推進にはIT化が欠かせないのも事実。現場では、非医療部門も含めたコスト全体の見直しを行う必要があるでしょう。
医療DXの導入事例からみるメリット
電子カルテ導入による業務効率化
前述の課題③で少し触れましたが、電子カルテ導入は医療DXのメインともいえる取り組みです。紙ベースのカルテと比べ、医療情報の閲覧がスムーズになり、医療の質が向上するというメリットが生まれます。
アプリ等による医療情報の共有
スマートフォンを使った医療情報の共有は、医療従事者だけでなく、患者にとっても身近に感じられるメリットです。医療従事者向けのアプリは、従来のPHSに代わるコミュニケーション手段として登場。診断画像や動画も含めた患者情報の共有、ナースコールの受信や出退勤時刻の記録などに活用されています。
また、患者向けには電子カルテと連携したアプリも登場。検査の予定や結果、投薬記録などをリアルタイムで確認できます。アプリによっては、外来の待ち状況や駐車場の空き状況まで見られる便利機能も搭載。患者の家族も利用でき、汎用性に長けています。

オンライン診療・予約の活用
オンライン診療は、対応可能な診療科が限られるものの、地域や環境による医療格差の解消につながります。患者にとっては通院の負担がなくなり、受診しやすいことも魅力です。また、オンライン予約は利便性を上げ、事務方の電話業務削減にも貢献しています。
さらに、こうしたオンラインシステムを応用した事例として、5G /ローカル5Gのライブ中継による遠隔診療を開設した病院もあります。数少ない専門医が他病院にいる患者を診察できるようになり、双方にとって大きなメリットが生まれました。
医療材料・機器管理体制の構築
医療材料や医療機器の管理では、ICタグを使ったRFIDシステムが採用されています。院内外で、いくつかの在庫管理工程を自動化。院内では機器の使用実績を記録したり、消耗品の在庫状況に合わせて自動発注を行ったりします。院外の物流倉庫では、製品のピッキングや補充などをロボットが行い、人件費削減に貢献している事例があります。
各種コストの削減
先に挙げたメリットでも少し触れていますが、医療DXはコスト削減にも有効です。カルテや処方箋、医療情報の提供などがペーパーレスになれば、印刷費や書類管理スペースがかなり節約できます。また、少人数かつ時短で業務が回るようになると、従業員や労働時間も削減可能。つまり、金銭面だけでなく、人材や時間のコストまで無駄を省くことができるのです。
給食部門のDXはナリコマにご相談ください

病院や診療所におけるDXは、非医療部門でも必要といわれています。ナリコマでは、病院給食を提供する厨房業務のDXを推進中。クックチル方式を採用した調理業務の効率化に加え、独自システムによる事務・検品作業の負担軽減など、幅広いサポートを行っております。給食部門の見直しを検討される際には、ぜひ一度ナリコマにご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
セントラルキッチンに関する記事一覧
-

PHR活用のススメ!基本的な仕組みやメリットをまとめて解説
近年は健康管理への関心が高まっており、各種メディアでもさまざまな用語や情報が取り上げられています。本記事でピックアップするPHRは、健康に関する個人情報管理の一つ。PHRの仕組みやメリット、活用方法などをまとめて詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
-

DXリテラシーで給食の現場が変わる!具体的な取り組みやメリットを解説
みなさんは、「DXリテラシー」という言葉に聞き覚えがあるでしょうか? 近年では、業界を問わずDXリテラシーの重要性を意識する企業が増えてきています。今回の記事は、そんなDXリテラシーについて詳しくお届け。「そもそもDXって何?」という疑問を抱く方にもご理解いただけるよう、言葉のルーツや定義、その重要性もしっかりとお伝えします。給食現場における具体的な取り組みやDXリテラシー向上のメリットについても解説。ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考になさってください。
-

病院給食の衛生管理には院外調理を上手に使おう!
安全・安心・おいしい食事であることが求められる病院給食。HACCPの理念に基づいた衛生管理を行う院外調理品(クックチル)の導入によって、衛生管理の強化と品質の高い食事を同時に叶えることができます。
さらに人材不足の解消やコスト効率の向上、衛生管理に関するスタッフ教育までもフォローが可能です。病院給食に院外調理品(クックチル)を使うメリットについて詳しく紹介していきます。