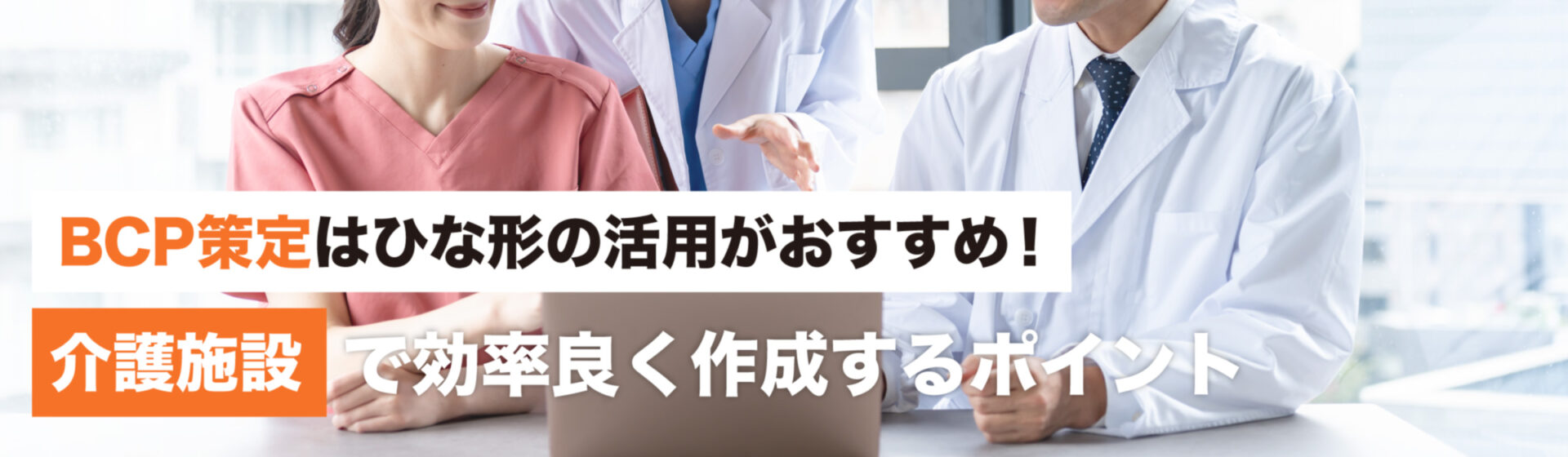BCPは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った言葉で、事業継続計画を意味しています。危機的な状況下でも重要な事業を中断させない、または早期復旧させるための計画です。介護施設では、BCPの策定が義務付けられており、感染症用と自然災害用の2つのBCPを策定する必要があります。これらのBCPを策定する際には、ひな形を活用するのも一つの方法です。
この記事では、BCPをスムーズに策定するのに役立つガイドラインやひな形の解説とあわせて、ひな形を使用したBCP策定のポイントを解説します。
目次
まずはBCPのガイドラインをチェック
介護施設・事業所のBCP策定に役立つ情報は、厚生労働省をはじめ、各自治体からも提供されていることがあります。BCP策定の際にはひな形を使用すると作成しやすくなりますが、いきなりひな形を見てもわかりづらいことがあるため、まずはBCPに関する情報集めやガイドラインのチェックから行うのがおすすめです。
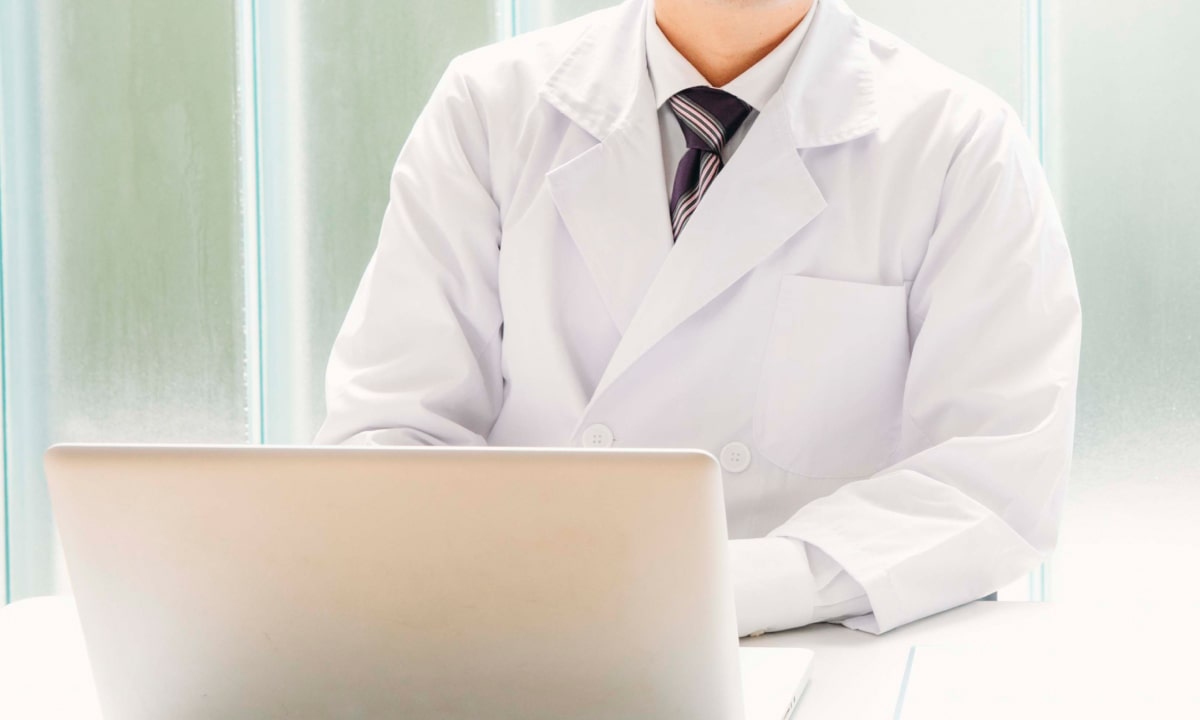
厚生労働省のホームページでは、感染症用と自然災害用のそれぞれのガイドラインが用意されています。このガイドラインでは、BCPとは何か?という事柄から解説があるため、予備知識がない場合にもわかりやすい内容です。また、各自治体でも、介護施設・事業所向けに、BCP策定の支援として情報の発信や資料提供などを行っている場合があるため、自治体のWebサイトを確認してみるのも役立ちます。
厚生労働省の提供するガイドラインでは、BCPの概要に加えて、自然災害と感染症のBCPの違いや、自然災害における従来の防災計画とBCPの違い、感染症における従来の感染対策マニュアルとBCPの違いなどもまとめられています。BCPの基礎知識を身に付けるとより策定しやすくなるでしょう。
介護サービス事業者が求められる役割とは?
感染症や自然災害が起こった際に、介護サービス事業者が求められる役割はいずれの場合も下記の3つです。
- サービスを継続させること
- 利用者さまの安全を確保すること
- 働く職員の安全を確保すること
サービスの継続はBCPの主な目的ですが、利用者さまや職員の安全を確保する視点からも大切なポイントです。利用者さまは、高齢に伴い体力が衰えていたり、疾患を抱えていたりと抵抗力が弱いことが多いため、感染症で重症化する可能性が高くなります。自然災害が発生した場合も含めて、非常時に深刻な人的被害につながる危険性があるため、根本的なリスクを把握したうえでの安全確保が必要です。
また、サービスを提供し続ける中で職員の存在は必要不可欠です。感染症の場合は職員にも感染のリスクがあり、自然災害発生時では非常時の暮らしを強いられたうえで業務にあたらなければなりません。非常時は長時間の勤務や精神的負担を受け過酷な労働環境になることが想定されるため、個々の職員の安全を確保することも同様に重要です。

BCPの作成で得られること
下記は、BCPを作成することで得られる事柄です。
- 危機的状況下における体制の構築
- 感染者発生や自然災害発生時の対応・対策の準備
- 非常時における業務の優先順位の把握
BCPの作成により、感染症や自然災害が発生した際の体制をあらかじめ構築するため、危機的状況下でも業務の役割分担や意思決定者などが既に決まった状態で対応することができます。感染症や自然災害が発生した場合に備えて、どう行動するかを決めておき、対応や対策の準備をしておくため、予定通りの行動を取りやすいでしょう。業務の優先順位もあらかじめ決めておくため、非常時の現場での混乱を抑えて冷静に対処するうえで役立ちます。
こうしたBCPのメリットを上手く活かすためには、普段からの研修や訓練も欠かせません。計画通り実行するための周知・研修・訓練を必ず行いましょう。また、それによって新しい発見があった際にはBCPを見直してアップグレードすることも大切です。
BCP策定に役立つひな形
2023年度の厚生労働省の調査「介護サービス事業者における業務継続に向けた取組状況の把握およびICTの活用状況に関する調査研究事業」の結果では、BCPの策定が完了した事業所のうち、約7~8割が厚生労働省のガイドラインやひな形を活用したと回答しています。ひな形はPDFやエクセルファイルなどでダウンロードでき、既に項目が整理されているため、順番に記載していくだけで作成可能です。

ひな形には、項目だけのものと例示入りのものがあり、例示入りのひな形はある程度の内容も記載されているためイメージがわかりやすく、より作りやすいものになっています。厚生労働省のホームページでは、動画でも作り方の解説が行われており、約1時間程度で見られる内容となっているため、あわせて参考にしてみてください。
参考:厚生労働省 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
参照:厚生労働省 介護サービス事業者における業務継続に向けた取組状況の把握およびICTの活用状況に関する調査研究事業 2023年度
ひな形は施設形態に合わせて選ぶ
厚生労働省から提供されているひな形は、感染症や自然災害の違いだけでなく、施設の形態ごとに種類が分かれています。感染症用のひな形では、入所系・通所系・訪問系があるため、策定が必要な施設の形態に合わせて選びましょう。自然災害用のひな形は、共通の内容とサービス固有の内容があり、共通の内容にサービス固有の内容を追加する形となります。
ひな形を活用した動画説明でも、入所系・通所系・訪問系・居宅介護支援系と個々に資料が分かれているため、当てはまるものを参考にしてみてください。
ひな形を使ったBCP策定のポイント
BCPのひな形は、厚生労働省だけでなく自治体や民間の法人などでも提供している場合があります。ひな形によって、構成の枠だけのものや例文が記載されているものがありますが、実際の作りやすさは作る側の感覚によって個々に異なるでしょう。作りやすいひな形を選ぶこともBCPを効率良く策定するコツです。

例文があらかじめ入っているひな形は、必要に応じて修正や追加、削除などを行い内容を調整していきます。例えば、厚生労働省の例示入りひな形の場合、ひな形の中で黒字・赤字・青字・緑字と部分的に文章の色が分かれており、色によって意味や行うことが異なります。黒字の部分は必要に応じて加筆や削除による修正を行う、赤字の部分は固有の内容となるため必ず見直して修正するなどの決まりがあるため、ひな形のルールを理解したうえで取り掛かるようにしましょう。
危機的状況下での対策本部のメンバーや、誰がいつどこに何を連絡するかといった情報伝達の流れなど、施設ごとに独自の内容を記載する箇所は多くあります。そのため、BCP策定前に内容を決めることが必要となりますが、内容を決める段階でひな形を確認しておくとよりわかりやすくなるでしょう。
BCPは見直しでレベルアップする
先述したBCPの作成で得られることでも少し触れましたが、BCPの策定後は、関係者に周知をして、研修や訓練を行うなど、職員全体で把握して行動できるようにシミュレーションすることが必要です。BCPを初めて策定した段階では文面上の対策に過ぎませんが、非常事態を想像して行動してみることで、新たな課題が見えてくることがあります。こうした課題を発見し、BCPを見直し改善することもBCPの策定では重要なポイントです。
定期的に訓練や見直しのステップを繰り返すことでBCPがレベルアップし、より活用できるものに変化します。介護施設のBCPでは、この見直しまでが義務の範囲となっています。そのため、一度の策定で完璧さを求めるよりも、まずは作成し、シミュレーションを繰り返してブラッシュアップしていくと良いでしょう。
BCPの備蓄品に役立つナリコマの非常食
自然災害用のBCPのひな形では、さまざまな備蓄品のリストがあり、個々に内容が記載されています。これらは施設による固有の内容となりますので、一つずつ確認しながらリストアップして備えておきましょう。食事に関するリストでは、飲料や食品をはじめ食べる際の衛生用品なども必要になります。介護施設の場合、高齢者向けの食事となるため、普通食だけでなく、ソフト食やゼリー食などの介護食の用意も必要になるでしょう。

ナリコマでは、介護食にも対応した非常食のご用意があります。普通食・ソフト食・ミキサー食・ゼリー食の形態があり、誰でも簡単に非加熱調理でそのままお召し上がりいただけます。BCP策定に伴う備蓄品として、ぜひご利用ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。
コストに関する記事一覧
-

障がい者施設における給食の役割とは?提供時の注意点もあわせて解説
現在、障がい者向けの施設はどのくらいの数あるのでしょうか? 厚生労働省が令和4年10月1日に行った「社会福祉施設等調査」によると、障がい者支援施設等の数は約5,500施設で、在所者は約15万人だそうです。
給食はすべての施設が提供しているわけではありませんが、障がい者の方々にとって非常に重要な要素の一つ。今回の記事は、そんな障がい者施設における給食を取り上げます。給食の役割や提供時の注意点、運営方法などを詳しく解説。ぜひ最後までお読みください。 -

値上げは必須!介護給食の重要性と現状を詳しく解説
介護給食は、全国各地の特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで提供されている食事のこと。近年はさまざまなコストが上昇している状況にあり、介護給食の値上げも強く求められています。
本記事では、そんな介護の現場における給食をクローズアップ。給食の重要性についてお伝えするほか、調理にコストがかかる理由や厳しい現状、コスト削減方法などを解説します。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
-

介護業界の人材不足をどう乗り越える?現場に役立つ3つの対策とは
介護の現場では、今も人手不足が大きな課題となっています。高齢者の増加とともに介護ニーズは拡大する一方で、必要な人材の確保が追いつかず、現場は常にギリギリの状態でまわっている…といった声も少なくありません。
厚生労働省の試算によると、2025年度末には約37万人もの介護人材が不足する見込みです。求人倍率が上がっても定着率は上がらず、離職につながる原因には、過酷な労働環境や賃金や働き方のアンバランスさの問題など、仕組みそのものに課題があるのが現実です。
こうした中、「環境を変えるだけでは人は集まらない」と感じている施設も増えて来ていますが、今できる現実的な対策には、一体どんなことがあるのでしょうか。
この記事では、介護現場で取り入れられ始めている3つの打開策「外国人採用」「スキマバイト」「ICT導入」について、事例や活用ポイントを交えながら、わかりやすくご紹介していきます。