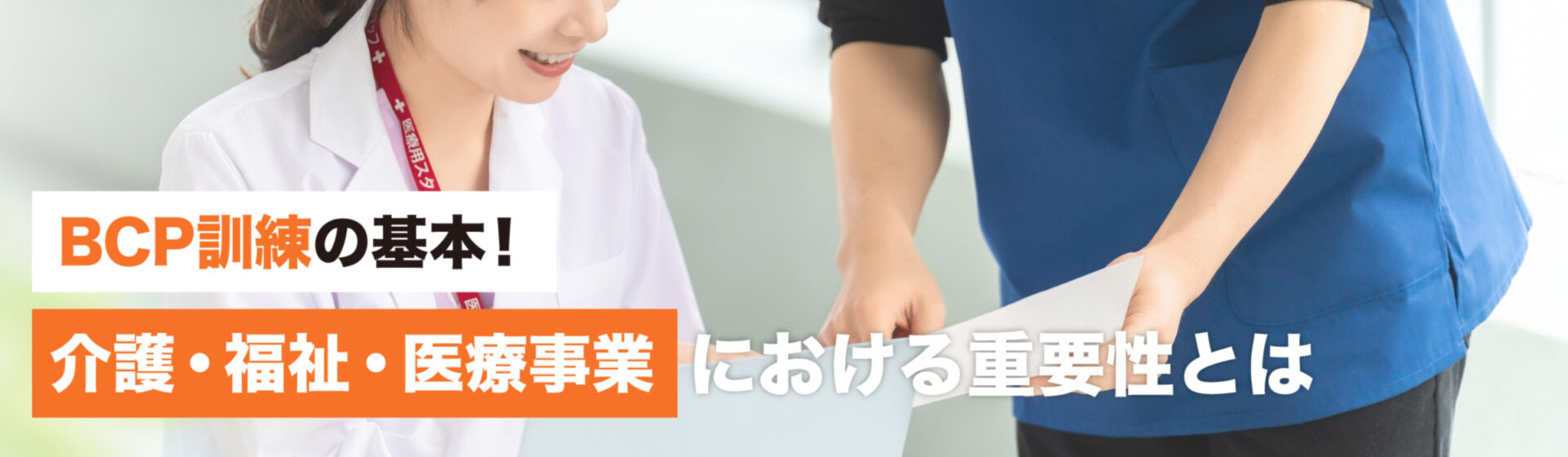リスクマネジメントの一つであるBCP(事業継続計画)は、自然災害や感染症拡大などの緊急事態が発生しても事業を続けられるようにするための取り組み。近年はさまざまな業界で策定が進んでいますが、その際に必ずついて回るものが「訓練」です。
今回の記事は、そんなBCP訓練について詳しくお届けします。BCP訓練の目的や介護・福祉・医療事業における重要性をお伝えすると共に、主な種類や内容、手順なども解説。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
目次
BCP訓練の目的とは?
防災用品は、その収納場所や使い方がわかっていなければ、いざというときに活用することができません。同様に、緊急時の対応についてまとめたBCPも、策定しただけでは意味がないといえます。冒頭でお伝えした通り、BCP策定後には訓練が必要です。訓練の実施には次のような目的があります。

BCP訓練の目的①従業員への周知と防災意識の定着
緊急事態は、いつ、どのように発生するのかわかりません。迅速に適切な対応がとれるように、BCPはすべての従業員に周知しておくべきです。訓練を行うと、緊急時のイメージに具体性が増し、一人ひとりが担う役割も明確になるでしょう。
また、訓練を日常的な業務の一環として取り入れることで、防災意識の定着も期待できます。従業員の防災意識が高いほど、いざというときの対応力も身に付きやすくなるでしょう。結果的に、従業員自身の安全を守ることにもつながります。
BCP訓練の目的②改善点の発見と見直し
時が経てば、事業内容や周辺の事情が変わるかもしれません。つまり、最初に策定したBCPがその後も通用するとは限らないのです。訓練によって、思わぬ改善点が見つかることもあります。従業員同士で意見交換をすれば、より良い内容に変更することもできるでしょう。さらに、設備などの不足・不備があっても事前に対処でき、安全性や安心感が高まります。
介護福祉施設や病院でのBCP訓練は特に重要
続いて、介護・福祉・医療事業におけるBCP訓練の重要性を考えてみましょう。介護福祉施設には高齢者や障がい者、病院には病気を抱えた患者が集まっています。介護や看護、治療に直結する業務が滞った場合、大勢の命が危険にさらされてしまうのです。
特に、新型インフルエンザなどの感染症では重症化のリスクが高い人も多いため、深刻な事態を引き起こすかもしれません。従業員も感染して業務が回らなくなれば、さらなる混乱が生じてしまうでしょう。

また、介護福祉施設や病院は公共性が高い場所です。そのため、地域に貢献する役割も求められています。介護福祉施設であれば避難スペースの提供や在宅高齢者の支援、病院であれば急増した感染者や負傷者の受け入れなど、いろいろな役割が考えられます。
平時の主要な業務を継続することに加え、緊急時の対応を可能にする意味でも、定期的なBCP訓練が欠かせないといえるでしょう。すべての従業員がBCPを十分に理解し、訓練によって適切な対応力を身に付けていれば、弱い立場にある施設利用者や患者を安全に守り抜くことができるのです。
BCP訓練の主な種類と内容
BCP訓練を大まかに分類すると、机上訓練と実働訓練があります。それぞれを簡単に説明するなら、机上訓練は「会議室などに集まって議論しながら、緊急時の状況を想定した上で役割分担や対応手順などを確認する訓練」、実働訓練は「現地でBCPの内容に沿って行動し、対応力を向上する訓練」です。

訓練の実施方法は必ずどちらかというわけではなく、場合によっては机上と実働を組み合わせて行います。では、主な訓練の内容を具体的にみていきましょう。
電話連絡網・緊急時通報訓練
従業員同士が連絡を取り合うことができるかどうかを確認する訓練です。連絡網を準備し、きちんと機能するかどうか試します。連絡網を常に最新の情報にしておくことが重要なポイント。スムーズに連絡できる状況を整えておくと、業務を行う人員確保にも役立ちます。
対策本部設置訓練と意思決定訓練
対策本部設置訓練は、緊急事態が発生したと想定して対策本部を立ち上げる訓練です。内容は対策本部役員向け。どのような状況で立ち上げるのか、誰がどこに集まるのかなど、緊急時の初動対応を決めておきます。意思決定訓練は、状況の変化にあわせて対策本部役員が何をすべきか具体的にイメージする訓練です。
参集訓練
早朝や夜間、休日などの緊急時を想定し、従業員を集める訓練です。徒歩や自転車で移動可能な従業員を対象に、限られた人数で初動対応ができるかどうかを確認します。
代替施設への移動訓練
現在の施設などが使えなくなった場合を想定し、代わりとなる場所への移動や復旧の手順を確認する訓練です。前述したように、公共性の高い介護福祉施設や病院は緊急時の拠点となる可能性がありますが、甚大な被害を受けた際には移動を余儀なくされるかもしれません。施設利用者や患者をどのように移動させるか、各種ケアに関する重要な情報をどのように持ち出すかなど、細かなシミュレーションをしておく必要があります。
バックアップデータを取り出す訓練
電気や通信が止まった状況を想定し、業務に必要なバックアップデータを取り出す訓練です。近年では電子データが増えていますが、パソコンや通信機器がまったく使えない可能性を考え、紙ベースでの復旧を目指す訓練もあります。
総合訓練
BCPに基づき、緊急事態発生から復旧に至るまでの流れを時系列で確認する訓練です。近隣の関連事業者や施設、自治体などと連携して行われることもあります。
BCP訓練を行うためのステップ4つ
介護福祉施設や病院では、立場が弱い高齢者や障がい者、患者のみなさんを守る使命もあります。介護事業においてはBCPへの取り組みが義務化されており、訓練は年二回以上(在宅系は年一回以上)と決められています。いずれにしても、BCP訓練は次のような手順を踏み、丁寧に行うことが重要です。
ステップ①BCP策定と事前準備
BCP訓練の目的を確認し、訓練の種類を決定。緊急事態を想定したシナリオなど、基本となる内容を作成します。また、全従業員への事前説明、システムなどの準備も行います。
ステップ②机上訓練・実働訓練の実施
BCPの内容に沿って、必要な訓練を実施します。
ステップ③訓練結果の評価
すべての訓練が終わったら、その結果を振り返ります。訓練によって見えた課題や改善点があれば、まとめておきます。
ステップ④BCPの修正と更新
課題や改善点に対し、BCPを適宜修正します。また、必要であれば情報を新しい内容に更新し、改めて全従業員に周知します。
緊急時の備えは確実に!

BCPを機能させるには日頃の訓練が重要となりますが、それ以外にもきちんと備えをしておくことでより安心感が高まり、いざというときに地域とも連携しやすくなります。介護・福祉・医療事業における高齢者や障がい者、患者への給食は、緊急時でも止めるわけにはいきません。水はもちろん、非常食や栄養機能食品などもしっかりと備蓄しておく必要があるでしょう。
ナリコマでは、介護福祉施設や病院に最適な完全調理済み食品をお届けしております。緊急時にもできる限りの対応を心がけており、非常食もご用意。提供しやすさやおいしさにこだわっているだけでなく、嚥下機能に不安がある方向けにソフト食、ミキサー食、ゼリー食も展開しています。緊急時にも対応した献立サービスをお探しの際には、ぜひ一度ご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。
コストに関する記事一覧
-

介護施設の給食委託。選び方のポイントと成功するコツを紹介!
介護施設の給食委託をテーマにお届けする記事です。給食委託会社の選び方で重視すべきポイントのほか、介護施設における食事の重要性や委託以外の給食提供方法などもまとめて詳しくお伝えしています。
-

給食委託費に含まれるものとは?直営と委託の違いやコスト削減のコツを解説
厨房運営で大きな課題となるのがコスト問題です。直営から委託に切り替えただけでは上手く改善できないケースも見られ、解決が難しい問題となっています。給食委託費としてくくられるコストには、様々な費用が含まれています。そこで今回は、給食運営の直営と委託の違いを改めて振り返りながら、給食委託費に含まれるものの内訳や給食委託費を削減する見直しのポイント、さらなるコスト削減に向けて給食運営をもっとシンプルにするコツを解説します。
-

育成就労制度とは?技能実習制度の制度変更による違いや特徴を解説
「育成就労制度」は、2024年に創設され3年以内に施行される制度です。この記事では、旧制度である「技能実習制度」の概要や課題を振り返りながら、制度変更によりどう変わるのかを、育成就労制度の特徴や受け入れ企業の実務のポイントも押さえながら解説します。