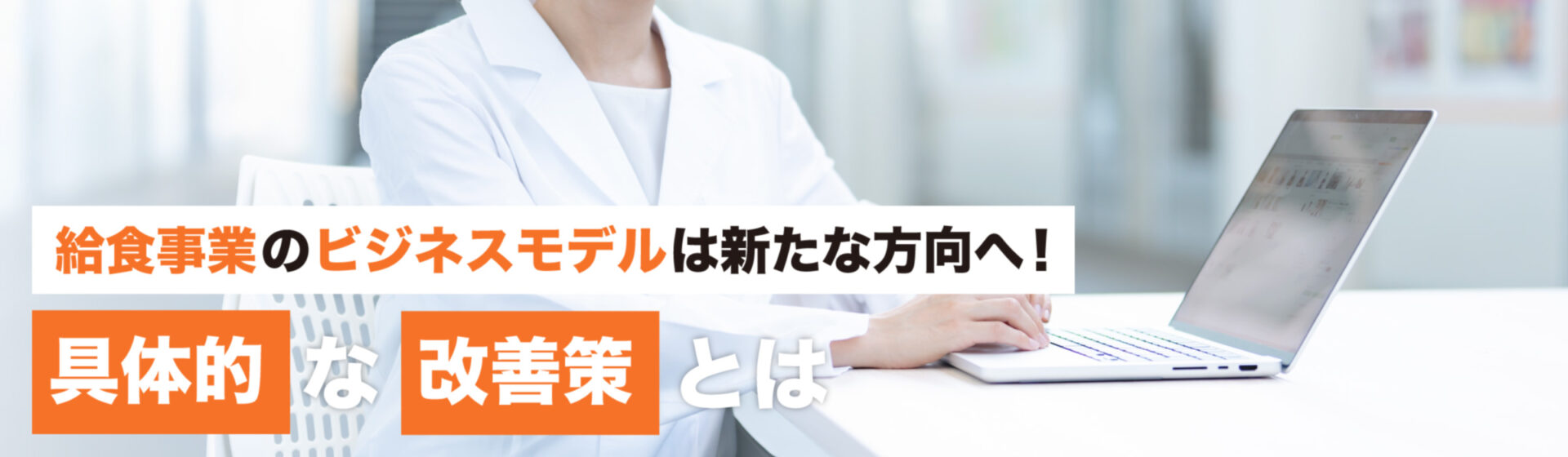年々厳しさが増している給食事業。ニュースなどでは、ついに「給食ビジネスモデルの崩壊」といった見出しまでみられるようになりました。今回の記事は、そんな給食事業のビジネスモデルについて取り上げます。給食業界の市場動向を見ながら、これまでのビジネスモデルと今後に向けた改善策などをまとめて解説。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
目次
給食業界の市場動向とビジネスモデルの主な要素

近年における給食市場の動向
2024年4月〜6月、株式会社矢野経済研究所は給食事業における市場調査を実施しました。対象分野は事業所対面給食、弁当給食(事業所弁当給食と在宅配食サービス)、病院給食、高齢者施設給食、学校給食、幼稚園・保育園給食です。
末端売上高ベースの調査結果から市場規模と前年度比(%)を抜粋すると、2019年度4兆8,465億円(100.6%)→2020年度4兆3,307億円(89.4%)→2021年度4兆4,923億円(103.7%)→2022年度4兆6,124億円(102.7%)→2023年度4兆7,915億円(103.9%)となっています。
2020年度は新型コロナウイルスが流行し、行動制限などによって給食業界全体が大きな打撃を受けました。その後、新型コロナウイルスの影響が縮小してきたため、給食市場も少しずつ回復傾向にあるようです。
給食事業のビジネスモデルとは
給食事業は学校や一般企業、病院、介護福祉施設などを対象とした食事提供サービスを展開しています。一般的なビジネスモデルは、以下のような要素で構成されています。
- 給食業務全般もしくは一部を受託
- 調理師や管理栄養士などの人材確保
- 給食に使う原材料などの仕入れ
- 受託先の厨房で調理して給食を提供
- 受託先を増やすことで収益拡大
上記にあるように、調理を行う厨房は受託先で準備されていることがほとんど。そのため、給食事業は新規参入しやすいという見方もあるようです。ところが、実際には経営状況が厳しい企業も多く、給食業界は今後の動向が注視されています。
給食業界において旧来のビジネスモデルは限界を迎えている
2023年9月のはじめ、一部の学校や学生寮の給食が突然提供されなくなりました。該当施設に給食を提供していたのは広島県中区に本社を置き、近年では北海道や九州地方でも事業を展開していた企業。給食提供先は全国約150カ所にまで増えていたといいます。

給食が提供できなくなった理由について、コスト高騰化が原因とみられています。競合で受注価格が下がってしまい、採算が合わなくなったそう。そんな経営状況にある中、新型コロナウイルスの流行による業務停滞や売上減少なども影響したようで、最終的な負債は約16億8千万円に。試行錯誤を重ねても経営再建ができず、2023年9月25日には広島地方裁判所から破産手続き開始決定を受けました。
このニュースは各種メディアで大きく取り上げられたため、給食事業にあまりなじみがない方も驚いたかもしれません。そして、赤字や業績悪化が増えてきた給食業界にとっては、旧来のビジネスモデルが通用しなくなってきた現状を痛感する機会にもなりました。
課題も多い給食事業のビジネスモデル
前述でも触れましたが、現在、旧来のビジネスモデルで給食事業を継続するのは厳しいという見方があります。本項目では、そんな給食事業が対応していかなければならない課題をまとめました。

課題①人手不足の深刻化
給食事業において、人手不足は以前から指摘されている問題。日本では少子化が進んでいるため、若年層の労働人口が減少すると予測されています。ところが、給食の現場では「なかなか人が集まらない」という悩みが尽きません。
人が集まらない主な要因は、労働環境の厳しさと給与水準の低さです。業務が効率化されていないケースも多く、早朝や深夜にも働くような環境がなくなりません。また、給食事業に携わる管理栄養士や栄養士、調理師などの給与は平均300〜400万円台といわれています。
課題②原材料費の高騰化や食料供給の不安定化
給食に欠かせない原材料の価格は、近年急激に高騰しています。総務省が発表した食料全体の消費者物価指数では、2020年を基準の100とした場合、2024年は122.5まで上昇。生鮮食品を除外した場合も120.1と高い指数になっており、物価高の影響が顕著に表れているといえます。
また、食料供給が不安定化していることも問題の一つ。世界的に増加している自然災害や異常気象は農作物、畜産物、水産物などに直接的な打撃を与えます。生産量・収穫量が落ち込めば当然価格は上昇するだけでなく、仕入れ自体が困難になる可能性もあります。
課題③エネルギー費の上昇
近年は、各種エネルギーの価格も上昇傾向にあります。給食事業では調理をはじめとする厨房業務が必ず発生するでしょう。水道費や光熱費の増加は、給食にかかるコスト全体に影響があります。給食センターなどでは、これまで以上にコストがかかるかもしれません。また、ガソリン価格が高騰すると物流費も上昇します。原材料を調達する際など、配送費が高くなる可能性があるでしょう。
課題④献立やサービスの自由度が低い
給食事業は学校や病院、介護福祉施設などを対象としています。食べる人にあわせた食事量や栄養バランスが決まっている、持病などで禁食があるなど、あまり自由がききません。その上、競争入札が多く、受託元が値上げに応じてくれないこともあります。実施のところは、予算が限られているにもかかわらず、いろいろなニーズに応えなければならないようです。
給食事業のビジネスモデルはどう改善すべき?
では、給食事業のビジネスモデルにおける改善策をみてみましょう。

改善策①業務効率化を図る
ITなどを使った業務効率化により、人手不足やコスト増加の課題は改善されるかもしれません。働きやすい環境を整えたり、無駄な工程をなくし水道光熱費を抑えたりと、細かく見直せる部分は多いでしょう。
改善策②衛生・安全管理を強化する
現在は老若男女問わず、食の安全について関心が高まっています。衛生・安全管理を強化することで、思わぬ事故を起こしにくくなるのはもちろん、安心感を大きな強みとしてアピールできるでしょう。
改善策③受託元との関係性を見直す
課題④の中で「受託元が値上げに応じてくれない」とお伝えしましたが、その原因がコミュニケーション不足の可能性もあります。受託元と強固な信頼関係を築くことができれば、そういった交渉もスムーズになるかもしれません。
改善策④他企業との連携やM&Aも視野に入れる
他企業との連携やM&Aが課題改善につながることもあります。お互いに持っていない強みや得意分野などをうまく組み合わせて活用できるようになれば、多くのメリットが生まれるかもしれません。
給食事業のお悩みは一度ナリコマにご相談ください

今後、給食事業のビジネスモデルは新たな形に変わっていく必要があるでしょう。ナリコマでは、主に病院や介護福祉施設の給食事業をサポートしています。クックチル方式による現場の負担軽減、独自システムによる事務作業の効率化など、これからの時代に最適な方法をご提案中。365日日替わりの献立サービスやバリエーション豊かな介護食、いざというときの非常食などもご用意しております。給食に関するお悩みがありましたら、ぜひ一度ナリコマにご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
人材不足に関する記事一覧
-

病院の管理栄養士はなぜ大変?働き方は改善できる?
たくさんの患者さんが入院している病院にとって、毎日の給食を提供することはとても重要な業務の一つです。療養のために入院している患者さんは、きちんと栄養をとったり、エネルギーを補ったりする必要があるでしょう。また、入院設備がない病院でも、健康維持のための食生活について患者さんに指導する機会があります。
今回の記事は、そんな病院で働く管理栄養士の実態に迫ります。「大変」「つらい」といったイメージが強い病院管理栄養士の主な仕事内容をお伝えし、向いている人の特徴なども併せて解説。近年さまざまな業界において課題となっている、働き方の改善ポイントについても触れていきます。ぜひ最後までお読みください。 -

地域包括ケアの仕組みとは?多職種連携や課題についても詳しく解説
日本は将来的に高齢者が激増するといわれています。そんな高齢化社会を支える医療・介護・福祉のあり方として推進されているのが「地域包括ケア」というシステムです。本記事では、地域包括ケアの基本的な仕組みについて詳しくお伝えします。また、その中で重要視される多職種連携や、今後の課題や対策についても解説。ぜひ最後までお読みください。
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。