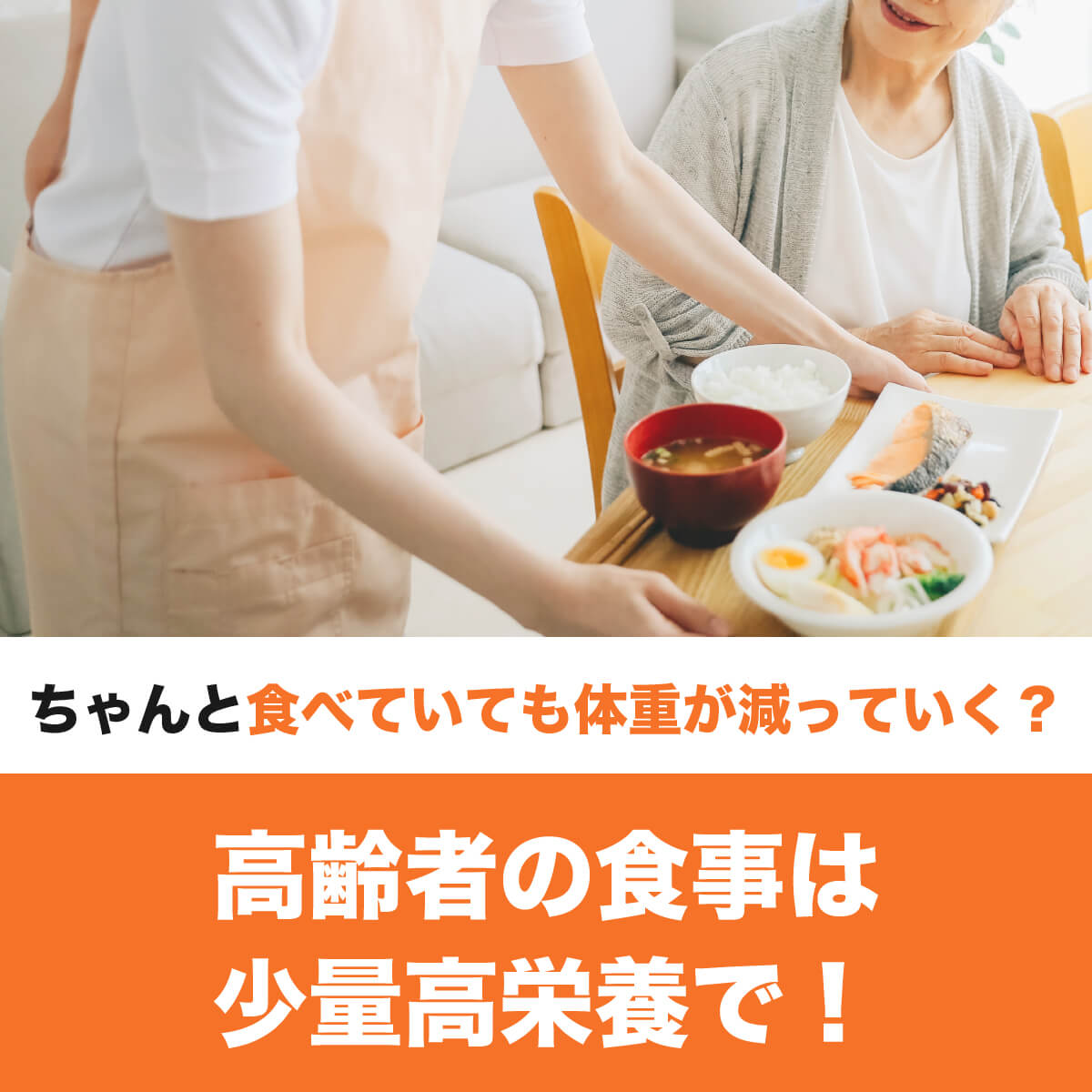高齢者になると健康上の問題が目立つようになります。当然個人差はありますが、健康状態を左右する食事の困りごとはいち早く解決したいものでしょう。「若い頃と同じように食べられなくなった」「食欲がなくなってきた」といった声は、いつの時代も聞こえてきます。
本記事で取り上げるのは、しっかり食べているのに体重が減るという「やせ(低体重)」の問題。高齢者の体重減少を引き起こす理由や具体的な原因を解説し、「やせ」の危険性についてもお伝えします。
また、そんな高齢者の食生活をサポートする少量高栄養の介護食・給食についても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
高齢者の体重が減少する理由
一般的に、体が必要とするカロリーを十分に摂取できない場合、体重は自然と減少していきます。カロリー不足から体重が減少してしまう原因の多くは、病気による食欲減退や消化器系の問題などが挙げられるそうです。
ところが、当事者が高齢者であれば「加齢により食が細くなった」ということも考えられます。これといった持病もなく健やかな毎日を過ごしていても、自身の若い頃と比べるとあまり食べなくなり体重も減った、と実感している高齢者の方々は少なくありません。
高齢者の食が細くなり体重が減少する理由は、大きく分けて「身体的な理由」「精神的な理由」「社会的・経済的な理由」「医学的な理由」の4つがあります。それぞれの理由について細かくみていきましょう。
①身体的な理由

唾液の分泌量が減ったり、味覚や嗅覚が衰えたりするほか、食べ物を飲み込むための嚥下機能がスムーズに働かなくなることもあります。また、消化管運動機能が低下する傾向も強くなります。その結果、食欲が抑えられてしまうのです。
②精神的な理由
加齢によって不安感や抑うつ、認知症など、精神的・神経的なストレスが生じやすくなることがあります。そのストレスの影響で、食欲が急激に落ちてしまいます。
③社会的・経済的な理由
一緒に食卓を囲む家族や同居人がいない一人暮らしをしていると、食欲減退を引き起こすことがあります。経済的な面では、極端な節約生活をしている場合もあります。どちらにしても、自然と食べる量が少なくなってしまいます。
④医学的な理由
持病がある場合、病気そのもののストレスだけでなく、投与された薬の作用が関係しているかもしれません。また、厳しい食事療法を実践している方であれば、それが体重減少につながることもあります。
食べているのになぜ体重が減るの?
前述したように、高齢者の体重減少はさまざまな理由によって食欲が落ち、食べる量が減ってしまうことからはじまります。ただ、高齢者といっても全員が同じような状態にあるわけではありません。
なかには、自分はたくさん食べている!と自信をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。しかしその一方、食べているのに体重が減るという話が高齢者によくみられる「やせ」の問題として浮上しています。本項目では、その詳しい原因について解説します。
筋肉量が減少している
筋肉量は、消費カロリーと深い関わりがあります。加齢による筋肉量の減少は、男女ともに起こること。近年では、サルコペニア(筋肉の衰え)という医学用語も使われるようになりました。

65歳以上になると、若い頃と比べて10%ほど筋肉量が少なくなるという研究結果があります。高齢者は自然と筋肉量が減ってしまうため、消費カロリーも少なくなるのです。
つまり、少し食べれば活動できるようになるということ。しっかり食べているつもりでも、実際の量は多くない……そんな状況から、体重減少につながってしまうのです。
何らかの病気にかかっている
持病がない高齢者は、わざわざ病院に通う必要がありません。体重減少の陰に病気が隠れている可能性もあります。たとえば、体重減少と同時に食欲減退や下痢といった症状があれば、一度医師にみていただくとよいかもしれません。
また、糖尿病は食事に含まれる糖をエネルギーに変えるのが難しくなり、体内のたんぱく質や脂肪などをエネルギーとして使いはじめます。特徴として、急激な体重減少が多くみられます。このほか、日本人に多い疾患のひとつである悪性腫瘍(がん)も筋肉量が減ってしまうため、体重減少を引き起こします。
無意識のうちにストレスを感じている
前の項目で挙げた社会的な理由(③社会的・経済的な理由)の繰り返しになりますが、一人暮らしの高齢者は社会的に孤立しがちです。知らず知らずのうちに感じる孤独感がストレスとなり、食べる量が減ってしまいます。
このように、高齢者は自覚症状があまりないまま、食べているのに体重が減るという「やせ」の状態に陥りやすくなるのです。
低体重の危険

「やせ」の状態は、高齢者にどのような影響を与えるのでしょうか。高齢者が今まで通りの日常生活を送れなくなり、要介護の状態に近づくことを「フレイル」といいます。厚生労働省では、高齢者が長く健康で過ごしていくためにはフレイルの予防が重要だと提言しています。本記事のテーマとなっている体重減少を抑えることも、もちろん立派なフレイルの予防といえるでしょう。
体重減少が進んで「やせ」になった高齢者の場合、まず懸念されるのが体力や免疫力の著しい低下です。筋肉量が減ってすぐに疲れるため寝たきりになりやすく、ウイルスや細菌に感染しやすくなります。
加えて筋肉や骨も衰えるため、食べ物をかむ力や飲み込む力がなくなったり、転んで骨折しやすくなったりすることも。そしてうまく食事ができなくなれば十分な栄養をとることができず、むくみや腹水が起こるリスクもぐんと高まります。
つまり、「やせ」は高齢者にとって非常に危険なことなのです。フレイルを防ぐためにも、普段から体重減少を抑えられるような生活習慣を意識したほうがよいでしょう。具体的には、無理のない範囲で行う軽い運動、栄養バランスのとれた食事、食欲がわく生活環境などが挙げられます。
少量高栄養の食事をとるためには

「やせ」の状態もしくはそれに近い状態に陥った高齢者は、さまざまなリスクを抱えてしまいます。先ほど述べたように、体重減少を抑える基本的な対策は生活習慣を見直すこと。特に、食生活においては少量高栄養の食事を意識するのがおすすめです。古くからいわれてきたことですが、健康的な食事の基本は一汁三菜。その中でも少量高栄養を実現するには、いくつかのポイントがあります。
少量でも高カロリーの食材には、代表的なものとしてアーモンドやピスタチオなどのナッツ類、チーズやヨーグルトをはじめとする乳製品、大豆の加工食品などがあります。また、一度にたくさん食べられなくても、何回かに分けて十分な量を達成することも少量高栄養の考え方の一つでしょう。
医薬部外品や栄養補助食品を活用し、食物繊維やたんぱく質など、高齢者に不足しがちな栄養素を中心に取り入れるのも有効でしょう。
このほか、食材の栄養価を損なわない調理方法、口腔内や胃腸に負担が少なく食も進む形状といった点に配慮するのも効果的です。
少量高栄養の介護食はナリコマにおまかせ

今回は、高齢者の体重減少をテーマにお届けしました。ナリコマグループでは、病院や介護/福祉施設向けの介護食・給食を提供中です。近年では新製法を導入することで、食材比率や栄養価の向上、調味料使用量の削減、食品ロスの解消などを実現しました。
病院や福祉施設の現場に最適な少量高栄養の介護食・給食は、ぜひナリコマグループにおまかせください。
ナリコマでは、無料相談も行っておりますので、まずはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
ナリコマが施設経営と厨房運営の両面を全力でサポートいたします!
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
コストに関する記事一覧
-

給食業界の現状!早期改善が求められる課題3つ
給食は保育所や学校、病院、介護・福祉施設、社員食堂など、いろいろな場所で人々のお腹を満たし、健康を支えています。しかし、その給食を提供する側に目を向けると、いくつかの課題が浮き彫りに。近年、給食業界は厳しい状況にあると指摘されており、早めの対策が必要といわれているのです。
本記事では、給食業界が抱える複数の課題から、特に重視すべき3つをピックアップ。課題の内容とともに、その要因や改善のポイントも詳しくお伝えします。
-

入院患者の笑顔を引き出す!おいしい病院食がもたらす効果とは
昨今、医療の現場で「食事と栄養」が重要視されるようになってから、病院食もかつての「おいしくない」といったイメージを払拭し始めています。おいしい病院食は、入院患者の健康を支えるだけでなく、療養生活に楽しさや彩りをもたらす大切な要素です。本記事では、おいしい病院食が患者に与える効果や、見た目や味への工夫、そしてナリコマによる品質へのこだわりについて詳しく解説します。
-

給食業界における最大の課題!コスト高騰化を乗り切る解決策とは
近年は数多くの商品やサービスの値上げラッシュが続いており、多種多様な業界はもちろん、消費者にも大きな影響を及ぼしています。食品や日用品の買い出しで「高くなった」と実感している方は少なくないでしょう。値上げの主な理由は、生産費や人件費といった各種コストの高騰化。この件は、給食業界においても最大の課題として解決が求められています。
本記事では、今や身近なテーマともいえるコスト高騰化について解説。詳しい要因を見ながら、給食を必要としている施設の現状や具体的な解決策などをお伝えしていきます。ぜひ最後までお読みください。