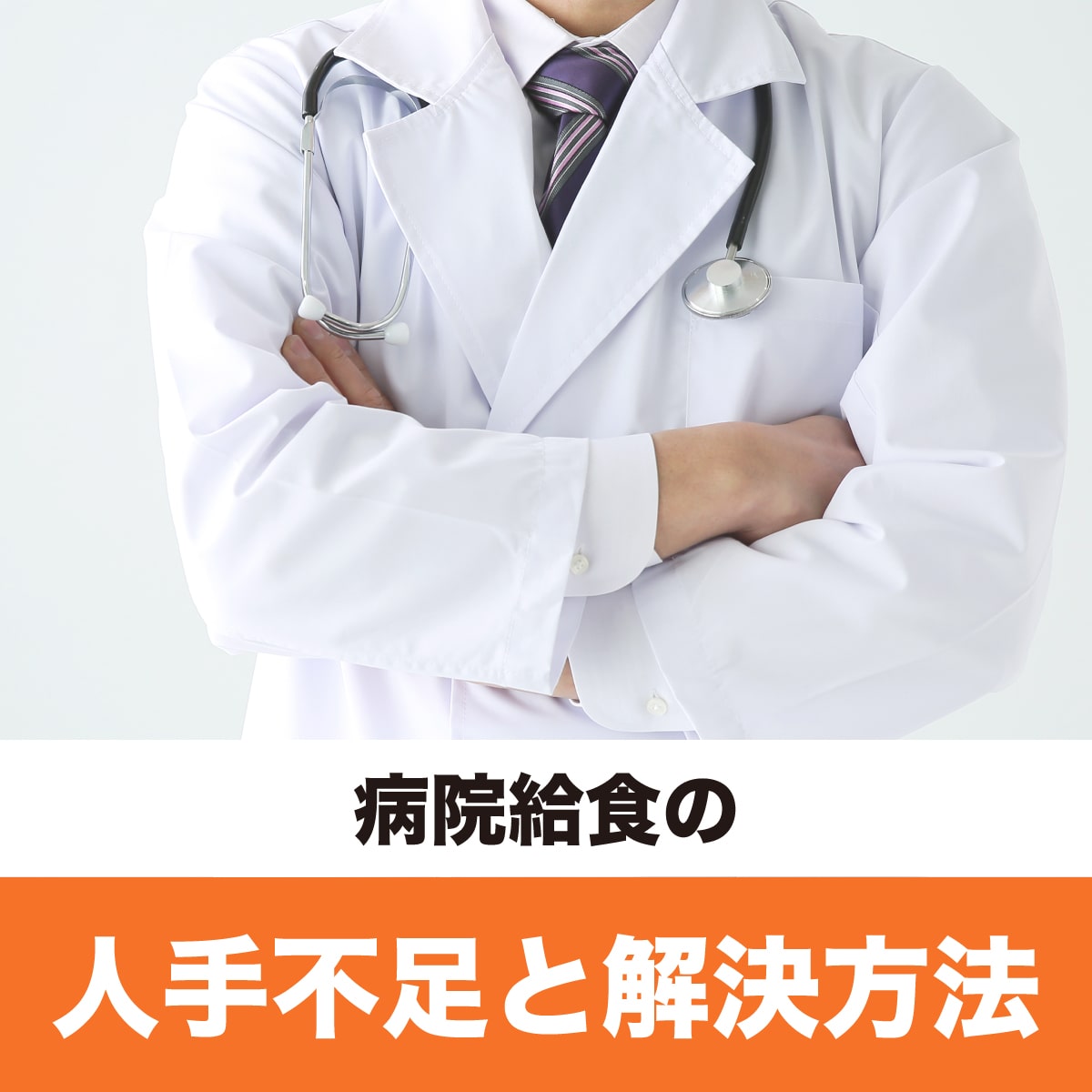人手不足に加えて、給食に関わるコストの上昇は、病院給食部門にとって大きな課題とされています。多くの病院で赤字となっている給食部門を救うためには、クックチルシステムを扱う院外調理業者への委託も一つの手です。
今回は、病院給食が抱える実態とその解決方法について解説していきます。
目次
病院の給食業務の実態

入院患者さんの病状回復のために、栄養面はもちろん、状態に合わせた形態で提供する病院給食。ただの栄養補給だけではなく、治療の一環としても大事な役割を持っています。
昨今、病院給食業務の大きな課題としては「給食コストの上昇」と「人手不足」の2点が挙げられます。
ここでは詳しく、給食業務の実態についてご紹介していきます。
給食コストの上昇
厚生労働省により行われた「入院時食事療養の収支等に関する実態調査」(平成29年度)の資料の中で、病院給食部門は多くの病院で赤字であるといった結果が出ており、厳しい状況に置かれているのが現状です。
これは、昨今の水道光熱費の上昇や食材価格が高騰し続けているにも関わらず、入院時食事療養費は上がることなく約30年間変更されていなかったという背景があるからです。
令和6年6月より食事療養費が640円から670円へ改定されましたが、原材料などの価格高騰は今後も上昇していくことが予想されますので、今後も病院給食のコストについては悩みの種となることでしょう。
慢性的な人手不足
出生率の低下を更新し続けている日本ですが、少子高齢化に歯止めがかかりません。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によると、全人口に占める15歳未満人口の割合は2020年の11.9%から、2070年には9.2%に減少し、15歳から64歳までの割合は2020年の59.5%から、2070年には52.1%に減少すると予想されています。
また、65歳以上人口の割合は2020年の28.6%から、2070年には38.7%に増加する見込みとされているのが現状です。
また、厚生労働省による「令和2年(2020)患者調査」にて、入院患者さんの7割以上が65歳以上という結果が出ています。
このことから、病院給食のサービスを受ける入院患者さんに対して、サービスを提供する側の高齢化や栄養士や調理師の不足など、常に人手不足が叫ばれているのです。病院給食業務を円滑に進めるためには、給食コストの改善と人手不足の解消に対応していくことが望まれます。
病院給食の人手不足は何が原因なのか

病院給食部門の慢性的な人手不足が起こってしまう背景には何があるのでしょうか。
病院給食には365日3食欠かさずの提供が必須です。1回たりとも欠かすことはできません。
朝食の対応では早朝から、夕食後の片付けや調理機器の洗浄等にかかる作業で遅くまでの勤務となり、労働の過酷さから離職率も高く、作業者が集まりにくい傾向にあります。
また、人手不足が常態化していることにより休みが取りにくかったり、入院患者さんの病態に応じた治療食や食事形態の変更に関わる業務量の多さについても、人手不足に陥る一因だとされています。
人手不足の解消には作業時間の短縮などの業務の効率化を図り、業務環境を改善することが必要です。
人手不足解決の方法とは
病院給食業務が抱える人手不足の解決に向けて、どのような対応が有効なのでしょうか?
厚生労働省「労働力調査 2023年度(令和5年度)」によると、昨今では女性と65歳以上の就業者が微増しています。
また、外国人労働者数も年々増加の一途を辿っているため、「女性」や「高齢者」、「外国人」が働きやすい業務体系に改善していくことが人手不足解決のヒントとなるでしょう。
朝食業務の場合、業務量の多さなどから公共交通機関を利用しているスタッフは始発での出勤でも間に合わない場合もあり、まずは業務内容の見直しを行うことで、少人数でも効率よく円滑に業務を進めることができるでしょう。
病院給食を院内調理している場合には、クックチルなどを検討してみるのもおすすめです。
クックチル・ニュークックチルを導入するメリット

ナリコマのクックチル・ニュークックチルとは
少人数のスタッフでも品質の高い食事提供を行うためのサービスとして、ナリコマでは「クックチル」「ニュークックチル」の二つを提供しています。
クックチルは、全国6か所にあるセントラルキッチンにて加熱調理されたものを30分以内に急速冷凍し、おいしさをそのままに製造日から5日間の保存を可能とした完全調理品です。
院内での食材下処理や調理の作業を省き、食事前に再加熱し提供するだけの簡単作業で、食事提供が可能になります。
厳しい衛生管理が必要とされている病院給食ですが、セントラルキッチンではHACCPの理念に基づいた衛生管理のもと安全安心な食事作りを行っていますので、衛生管理対策も十分です。
ニュークックチルは、クックチル食品をチルド状態のまま盛り付けまで行い、専用の対応機器内に保存したものを食事前に再加熱して提供します。すでに盛り付けが完了しているため、提供までにかかる時間と人材コストを抑えることが可能です。
少ない人材で病院給食業務にあたることができるため、シフトの管理もしやすく人材不足にも悩みにくくなるでしょう。
また、ナリコマでは病床機能に合わせて、28日サイクルの「すこやか」と、365日サイクルの「やすらぎ」の二つの献立サービスをご用意しています。
メリット①作業時間の短縮
クックチル・ニュークックチルは再加熱・盛り付けだけで提供できるため、外国人スタッフや新人スタッフ、高齢のスタッフなど、どんな方でも簡単に作業することができます。
シフト時間の短縮による業務の効率化で、人材にかかるコストも削減できるでしょう。
メリット②導入前後のサポートシステムも充実
ナリコマは食事提供だけではなく、人材採用やスタッフ教育、コスト面など、病院給食業務に関わる毎日の業務を全力的にサポートいたします。
業務効率化をサポート
発注業務にはオリジナルシステムを使用しており、これまで煩雑だった発注作業も簡単に行うことができます。
さらに、発注漏れや選択ミスなどがあった場合には、メールなどでお知らせが届くため、発注トラブルも未然に防ぐことが可能です。
検品作業もコードをスキャンするだけの簡単作業なので、業務にかかる時間を短縮できます。
人材・教育サービス
厨房業務を円滑に進めるためのマニュアルも完備しています。
厨房機器の取り扱いや盛り付けなどの業務フローが確認できるため、新規の現場スタッフにも業務に入る前に事前教育ができるため、即戦力として活躍してもらうことができます。
外国人スタッフ向けの外国語マニュアルの用意もあります。
また、他施設のスタッフとも交流できるスキルアップ教育も実施していますので、業務に関わる工夫など、交流の中で発見できる機会があります。
また、人手不足に陥った場合にも、ナリコマでは求人情報の分析とアドバイスを行うほか、オプションサポートとして人材派遣なども行います。
経営サポート
人手不足解消だけでなく、経営面に役立つアドバイスも行います。
食材費や人件費などのコストを、専任アドバイザーがナリコマ独自のシートを使って収支分析と改善策の提案いたします。
発注システムと連動しているため、厨房運営費もリアルタイムでチェックが可能です。
厨房受託事業を30年以上続けているナリコマだからこそ実現できる、厨房運営に関わるノウハウを持って全力サポートします。
赤字になってしまいがちな病院給食部門も、ナリコマでは現状を詳細に伺ったうえで、業務負荷の軽減やコストの改善にご協力いたします。
現場の課題解決はナリコマにお任せ下さい
病院給食業務の大きな課題とされている人手不足や人材の定着。
これからの病院給食を考える上で、これらの課題の解決には業務の効率化を進めて行くことは大変重要です。
ナリコマのクックチル・ニュークックチルなら、業務時間の短縮やコスト面での改善をお約束します。スタッフ教育や毎日の業務も手厚く支援!毎日の給食業務をより効率的に、課題解決のお手伝いをいたします。
困難な状況から脱出したい!そんな時にはナリコマのクックチル・ニュークックチルをぜひご検討下さい。
無料相談も行っておりますので、詳しいサービス内容や料金については、まずはこちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。
専門スタッフが現場の課題をお伺いし、最適な運営プランのご提案をいたします。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
人材不足に関する記事一覧
-

育児・介護休業法の改正で小学校就学前まで残業免除!制度の周知の仕方は?
2025年から、改正された新しい育児・介護休業法が段階的に施行されます。これにより、小学校就学前までの子供がいる場合の残業免除や、介護のためのテレワーク導入などが可能となり、育児中や介護中により働きやすくなることが期待できます。この記事では、今回の改正内容とあわせて、制度の周知方法など事業所側が押さえておきたいポイントを解説します。法改正に沿った就業規則や勤務体制の見直しを行う際にぜひお役立てください。
-

2025年問題を徹底解説!今後の医療・介護業界にもたらす影響とは
2025年問題は日本の将来を大きく左右することから、これまでに何度もニュースなどで取り上げられてきました。さまざまな業界への影響が懸念されていますが、医療・介護業界も例外ではありません。今回の記事は、そんな2025年問題について徹底解説。医療・介護業界にもたらす影響と今後求められる対策について、詳しくお伝えします。
-

BCP訓練の基本!介護・福祉・医療事業における重要性とは
リスクマネジメントの一つであるBCP(事業継続計画)は、自然災害や感染症拡大などの緊急事態が発生しても事業を続けられるようにするための取り組み。近年はさまざまな業界で策定が進んでいますが、その際に必ずついて回るものが「訓練」です。
今回の記事は、そんなBCP訓練について詳しくお届けします。BCP訓練の目的や介護・福祉・医療事業における重要性をお伝えすると共に、主な種類や内容、手順なども解説。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。