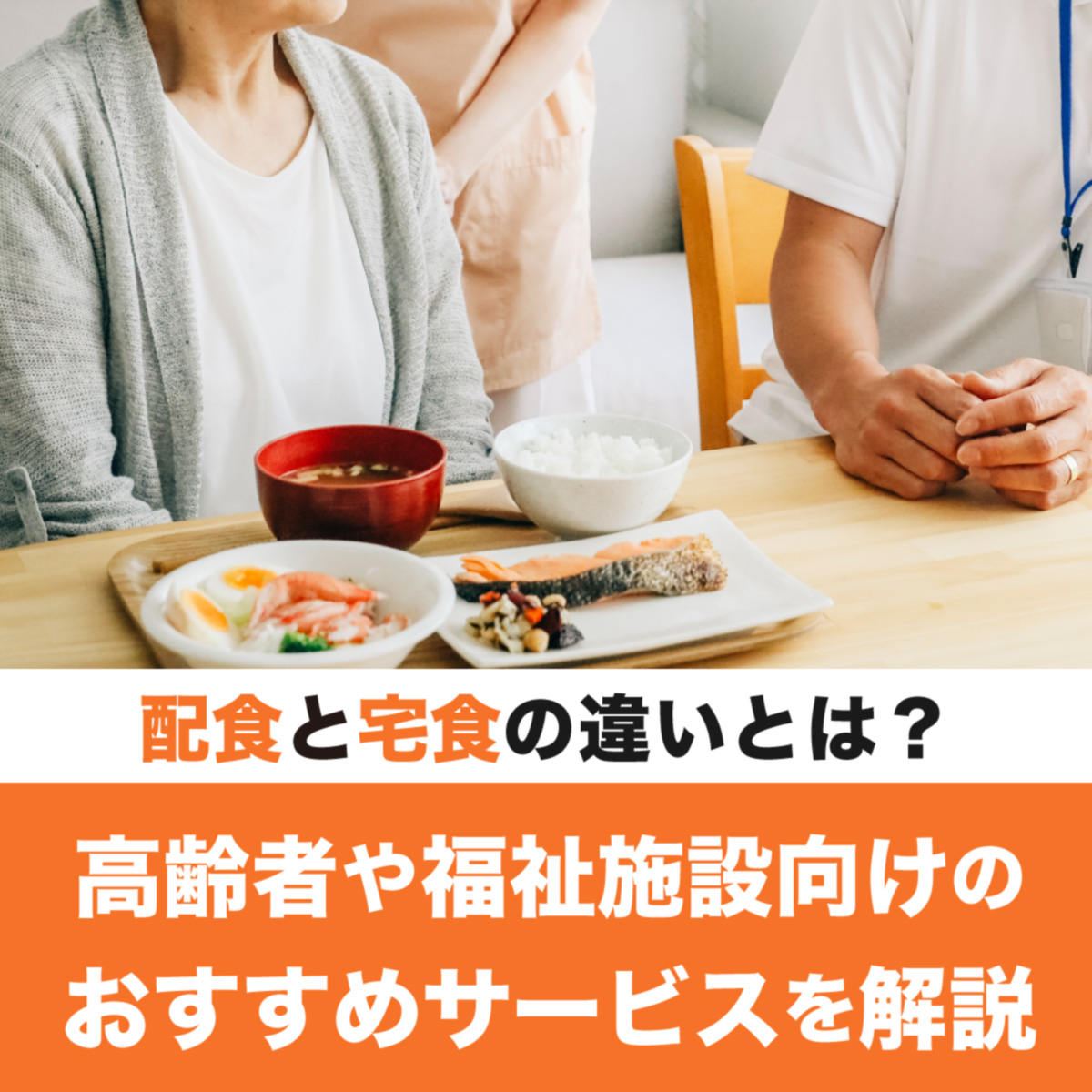配食と宅食の言葉の意味は似ていますが、それぞれが指す事柄には違いがあります。この記事では、配食と宅食の意味合いの違いと共にそれぞれのサービスの特徴を解説します。高齢者や福祉施設におすすめの配食サービスのメリットなど、今後の給食現場の課題解決に役立つ内容もまとめましたので、配食サービスをご検討中の施設さまもぜひご参考ください。
目次
配食とは?宅食との違いについて

配食と宅食は似たような意味があり、言葉の使い分けとして明確な定義の違いはありませんが、使用される場面では区別されることがあるため意味合いの違いを把握しておきましょう。
配食には、食事を配達するという意味があり、在宅の高齢者に対する食事の配達の意味で使われることもあります。一般的には、自宅のほかに福祉施設や病院などの施設への配達も含めて使われることが多いでしょう。配食は、高齢者向けの食事の配達が意味されているように、利用者層が主に高齢者の場合に使われていることも特徴です。
これに対して宅食は、主に自宅に食事を配達するサービスとして認識されていることが多いです。定期的な配送がよく見られ、毎日の食事を自宅に届けてもらえるサービスで、お弁当から自分で簡単に作れるキットまで製品のタイプもさまざまです。また、配食と違い、宅食は年齢層が限定されていないことも特徴で、幅広い年齢の方に利用されています。
配食・宅食とデリバリーサービスの違い
配食と宅食で共通している特徴は、栄養バランスに配慮した食事の提供がよく見られることです。そして、デリバリーサービスとの違いでもあります。デリバリーサービスも自宅やオフィスなどに食事を届けてもらえますが、内容はさまざまで普段の外食と同じように顧客が好きなものやそのときに食べたいものを選べるため、特別に栄養面が意識されている訳ではありません。
また、デリバリーサービスは、一般的に注文の頻度がその都度のため、定期的な注文を行う配食や宅食とはスタイルが異なります。配食・宅食とデリバリーサービスでは、目的の違いによって得られるメリットも異なるでしょう。
配食・宅食のサービスの特徴
ここでは、配食を福祉施設へのお届けも含めた高齢者向けの食事配達サービス、宅食を自宅への食事配達サービスとして、それぞれのサービスの特徴を解説します。配食サービスはお届け先の違いによってサービス内容が異なり、宅食サービスは自宅での利用に特化したサービスがさまざまにあります。
配食サービスの特徴
配食はお届け先が自宅に特化してないため、どこに届けるのかによってサービス内容も変わります。たとえば、在宅の高齢者向けの食事配達サービスや、福祉施設や病院向けの食事配達サービスがあり、個人で利用する場合と法人で利用する場合では業者の選び方も異なります。サービスを提供する業者はそれぞれ、個人向けと施設向けなどに分かれていることが多いため、目的に合わせて選びましょう。
個人向けのサービスでは、自治体のホームページなどで配食サービスが紹介されていることもあります。自治体のサービスによって異なりますが、1日に1食または2食などサービス内容や対象者が限定されている場合もあるため、詳しい条件の確認も必要です。
また施設向けの配食サービスでは、何名から利用可能かといった提供条件もあるため条件に見合うかどうかもあわせて検討する必要があるでしょう。朝食のみ、デイサービス用のみ、など、用途にあわせて効率良く利用できるものを選ぶと役立ちます。

宅食サービスの特徴
配食サービスは主に高齢者向けの内容が多いですが、宅食サービスでは幅広い年齢層向けの食事が提供されています。高齢者に限らず、仕事や子育てが忙しくバランスのとれた食事作りが難しい方などにも重宝するサービスです。利用する年齢層が広いことから、ライフスタイルの違いも伴い、サービス内容は多岐にわたっています。
普通食からきざみ食などの介護食まで対応していたり、年齢に関わらず食べやすく作られていたりと、さまざまな工夫が見られます。お弁当に限らず、おかずのみや自分で調理する過程のあるミールキットなど、製品のスタイルがさまざまにあり選択肢の自由度が高いのも特徴です。
そのまま食べられるお弁当スタイル
お弁当スタイルは、おかずとご飯がセットになったいわゆるお弁当のため、そのまますぐに食べられて便利です。製品によって内容は異なりますが、栄養バランスやカロリーなども調整されているためそのまま健康管理に役立てられることもメリットです。
おかずのみが届くスタイル
宅食サービスでは、おかずのみを配達してもらう選択肢もよく見られます。自宅で好きな主食を組み合わせることができるため、白米だけでなく、雑穀米やパンを合わせるといったアレンジもできるでしょう。おかずの栄養バランスやカロリーが気になるときや、おかず作りが負担になっているときなどにも役立つスタイルです。
自分で作るミールキットスタイル
お弁当やおかずのように、調理済みの食事が届くだけでなく、自分で作るミールキットも宅食サービスの製品の一つです。ミールキットは、下処理などが済んだ食材がレシピと共に届き、家に常備しやすい調味料と簡単な調理で作れるのが特徴です。自分で材料を買いに行く手間がなく、レシピに見合う分量が届くため余った材料の使い道に悩むこともありません。短時間で出来たての料理と調理の楽しみを味わえることもメリットです。
福祉施設向けの配食サービス
配食サービスの中には、高齢者の暮らす福祉施設向けに特化したサービスも提供されています。近年、介護施設などでは人手不足などの課題があり、食事に関する悩みもさまざまにありますが、配食サービスの利用は福祉施設が抱えるこれらの課題解決にも役立ちます。

福祉施設で配食サービスが重宝する背景と課題
高齢者が暮らす福祉施設では、食事のマンネリ化や食事を提供するスタッフの人手不足など、食事に関する悩みがさまざまに挙げられます。ここでは、高齢者が暮らす施設の食事に関する課題と配食サービスを利用するメリットについて解説します。
食事のマンネリ化
食事のマンネリ化を防ぐことは、介護施設などでよく心掛けられている事柄の一つです。食事に飽きた、おいしくない、といった理由で利用者さまが食べなくなってしまうと健康状態にも影響するため、なるべく食べてもらえる工夫が必要です。配食サービスでは、日替わりの献立などでマンネリ化を防ぐことも意識されているため、サービスの利用で手軽に改善することができます。
施設の人手不足
近年、介護サービスの人手不足が深刻化しており、給食現場でも人手不足の課題が目立っています。2024年に厚生労働省から今後必要になる介護職員の数として、2026年度には約240万人、2040年度には約272万人という数値が挙げられました。そのため、今後も人手不足の課題に悩まされることが伺えます。配食サービスの利用は、介護職員の食事の準備などの負担軽減につながるため、福祉施設の人手不足の解決にも役立ちます。
介護食への対応
高齢者の食事の準備では、嚥下状態などに合わせた食事作りも必要になります。ミキサー食やゼリー食など、個々の利用者さまに合わせて作るのは時間や労力もかかり大変です。配食サービスの食事では、こうした介護食に対応していることもよく見られるため、製品を選ぶだけで簡単に用意することができます。
ナリコマが提供する配食サービス
ナリコマは、福祉施設や病院向けに特化した配食サービスを提供しているため、介護施設の給食現場の課題をスムーズに解決できるサービスも備えています。栄養バランスの整った食事というだけでなく、食べる楽しみも損なうことなくおいしい献立作りに力を入れており、365日サイクルのため飽きのこないメニューが魅力です。
嚥下力や咀嚼力に合わせて選べるよう、4形態の用意があるため、個々の利用者さまが食べやすい状態の食事を選択できます。形状は変わっても献立は同一のため、味わいが損なわれることもありません。
また、調理済みのクックチル食品を再加熱する簡単な調理作業のため、人を選ばず誰でも用意可能です。厨房の人手不足の課題も同時に解決できるでしょう。
福祉施設の配食はナリコマにおまかせください

ナリコマには、福祉施設の配食に最適なサービスがあり、厨房運営のスペシャリストが在籍しているためさまざまな課題解決のサポートができます。少人数のグループホームでも利用可能で、対応地域も幅広く現在も対応エリアの拡大中です。福祉施設の給食でお悩みの施設さまは、まずはご相談だけでもかまいませんのでお気軽にお問い合わせください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
委託に関する記事一覧
-

災害時に役立つBCP!病院や介護施設が備えておくべきことは?
BCPは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った用語で、事業継続計画を意味しています。危機的な状況下でも重要な事業を中断させない、または早期復旧させるための計画です。この記事では、さまざまな災害がある中で、BCPが病院や介護施設に必要な理由とその役割について、高齢者が災害時に受ける影響と共に解説します。
-

介護施設に適した食事の提供体制とは?外部委託の選定ポイントも紹介
日本は65歳以上の高齢者人口が年々増加しており、2043年には3,953万人でピークを迎えるといわれています。一方、2024年10月1日時点で1億2380万人余の総人口は減少していく見込み。今後は高齢化率が上昇し、2070年には2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上になると推測されています。
こうした背景から、近年では介護福祉サービスの需要が高まっています。今回お届けする記事のテーマは、そんな高齢者ケアの拠点となる介護施設の食事。食事の重要性や提供体制について解説し、外部委託業者の選定ポイントなどもあわせてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。 -

病院給食は委託と直営どちらがおすすめ?
医療施設や介護施設などで絶対に必要なものといえば、毎日の食事。今回は、病院給食にスポットを当てた記事をお届けします。現在は調理師や管理栄養士などの人材不足、食材をはじめとするさまざまなコスト高騰に伴い、委託費の値上がりも懸念されています。そんな問題が浮上してきている中で、病院給食はどのように運営されているのでしょうか?
本記事では病院給食の現状について触れ、委託と直営それぞれのメリットやデメリットを解説。さらに、病院給食を効率よく運営するためのポイントやおすすめの調理・提供方法などをお伝えします。