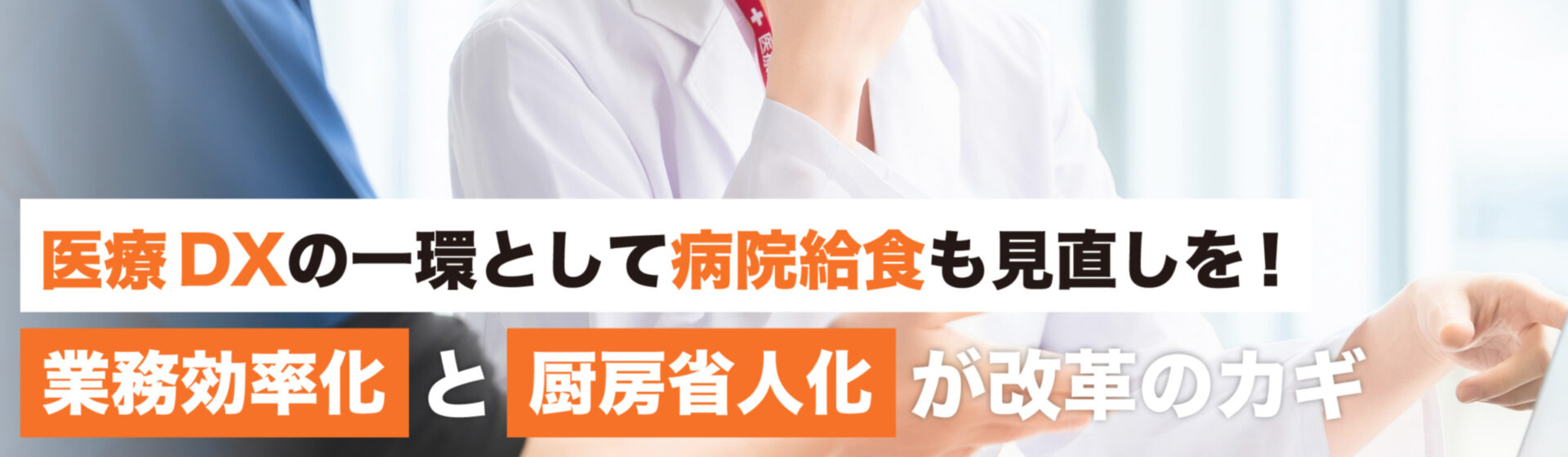医療DXは世界各国で推進されており、日本も例外ではありません。しかし、どちらかというと歩みは遅く、これまでの環境とあまり変わっていない医療機関も多いようです。本記事では、そんな医療DXと密接な関係にある病院給食に注目。医療DXを進める中で病院給食がどうあるべきなのか、詳しく解説します。
目次
医療DXでは非医療業務の最適化も重要
日本における医療DXの必要性

近年の日本では、急速に進んでいる少子高齢化が大きな社会問題として取り上げられています。内閣府が公表した「令和6年版 高齢社会白書」によると、令和5年10月1日時点の総人口は1億2,435万人で、高齢化率(総人口における65歳以上人口の割合)は29.1%。これを75歳以上人口に絞り込んだ場合も、16.1%と高い割合です。
総人口は将来的に減少し、令和38年には1億人を割ると推測されています。その一方で、高齢化率は上昇する見込み。令和22年には34.8%、令和52年には38.7%まで達するといわれ、2.6人に1人が65歳以上という状況に陥ります。しかし、総人口が減少すれば、必然的に高齢者を支える現役世代の人口も少なくなるのです。実際のところ、出生数は平成28年を境に過去最低を更新し続け、令和6年には約68万人となりました。
少子高齢化の進行は、医療業界に大きな影響を与えます。高齢者は慢性的な疾患を抱えやすく、医療機関を利用する機会も多くなります。すなわち、高齢化は医療費の増加にもつながるのです。また、増加していく患者をケアするためには相応の人員が必要ですが、現役世代の人口が少なくなれば、医療業界の人手不足も深刻化します。このように、需要と供給のバランスが崩れると、従来の医療体制が維持できなくなるかもしれません。

そこで重視されているのが、医療DXの推進です。医療DXはデータやデジタル技術を活用し、医療・保健・介護の専門施設や関係者が連携することで、国民全員に良質な医療やケアを提供する目的があります。人員や時間が限られる中で、業務効率化ができることも大きなメリットです。身近な導入事例としては、マイナンバーカードと健康保険証の一体化、電子カルテ連携、電子処方箋の運用、オンライン診療などが挙げられます。
ところが、日本におけるDXの現状は諸外国よりも遅れています。IT人材がいないこと、既存のシステムを使い続けていること、企業が環境を変えようとしないことなど、DXが進まない要因はいくつかあるようです。医療業界も例外ではなく、制度やシステムを整える以外に、医療機関や医療従事者の意識も変えていく必要があるでしょう。
並行して進めるべき非医療業務の最適化
医療機関では、非医療業務も日常的に行われています。該当する業務は幅広く、受付、会計、運営、管理、清掃、警備、給食、送迎、廃棄物処理など、病院やクリニックを維持するためには欠かせないものばかりです。しかし、非医療業務における課題を残したままでは、医療DXの効果も半減してしまいます。
医療DXを進める際には、同時に非医療業務の最適化も行うことで総合的なメリットが生まれます。病院やクリニック全体の業務改善ができ、労働環境も整いやすくなります。医療の質が上がったり、利便性が高くなったりする効果も期待できるため、患者にとってもメリットがあるといえるでしょう。
病院給食における課題とは
ここからは、医療DXの推進と並行して見直すべき非医療業務の一つ、給食に焦点を当てます。まずは、どのような課題があるのか確認しておきましょう。

病院給食の課題①人手不足への対策
給食を提供する厨房は、以前より人手不足に悩まされています。本来必要な人員に達していなければ厨房職員一人ひとりに負担がかかり、結果的に残業時間が増えてしまうというケースもあるようです。前述した少子高齢化の問題を考慮すると、将来的には人手不足がさらに進んでしまう可能性が高いといえるでしょう。人手不足は労働環境の悪化にもつながるため、最優先で取り組まなければならない課題です。
病院給食の課題②物価高騰への対策
長らく続いている物価高騰は、給食運営に打撃を与えています。総務省統計局が公表した2025年(令和7年)4月分の「2020年基準 消費者物価指数」では、総合指数が111.5。前年同月と比べても3.6%上昇しており、物価高騰が進んでいることを示しています。その中でも、給食を提供するために欠かせない食料は124.0、光熱・水道は117.9と、総合指数を超える高水準。食材等の配送に必要なガソリンなどのエネルギーも125.6となっており、給食に関するコストは全体的に増加しています。
しかし、病院給食の場合は入院時食事療養費制度によって価格が決められているのです。物価高騰でも価格転嫁ができない状況は、間違いなく病院運営を圧迫しています。その上、近年では最低賃金の引き上げが行われたため、人件費も上昇。給食運営において、コスト削減は非常に重要な課題となっています。
病院給食の課題③安定的な供給と品質保持
病院給食は治療の一環として扱われます。そのため、人手不足や物価高騰を理由に提供を止めるわけにはいかず、安定的な供給体制の構築が求められています。また、給食の品質を維持することも大切です。患者が食べなくなってしまうと、治療にも悪影響を与えてしまいます。
働き方が変わる!厨房業務改革のカギ
先に挙げた病院給食の課題を解決するには、厨房業務の改革が必要です。改革のカギとなるのは業務効率化と厨房省人化。改革が成功すれば、労働環境が整い、人も集まりやすくなります。本項目では、具体的な対策をまとめました。

自動調理機などによる機械化
機械化しても問題ない工程では、自動調理機や調理ロボットなどを活用するといいでしょう。業務効率化と厨房省人化が実現するだけでなく、品質が安定するというメリットも加わります。
セントラルキッチンの利用
セントラルキッチンを利用すると、クックチルやクックフリーズなどの完全調理済み食品を配送してもらうことができ、調理スキルがない職員も対応しやすくなります。厨房では再加熱や盛り付けなどがメインになるため、人員を減らすことができ、作業効率も上がります。
動線の見直しと不要品の処分
動線の見直しは業務効率化に有効です。厨房のスペースを考慮し、作業台や設備の大きさ、配置を変えることで、調理や提供の工程がスムーズに回るようになるかもしれません。同時に、不要な調理器具や食器を処分すると、片付けやすさにもつながります。
管理・事務作業のデジタル化
厨房業務には、食材や調味料の在庫管理、衛生管理、スケジュール管理などのデスクワークも含まれます。医療DXにも通じる部分ですが、紙ベースで業務を行っている場合は、アプリなどを導入してデジタル化すると作業効率が上がるでしょう。
厨房業務のお悩みは給食DXに強いナリコマへ

ナリコマは、これからの時代に適した給食DXに取り組んでいます。2024年10月1日には、経済産業省が定めるDX認定制度に基づき、DX認定事業者として認定されました。医療DXと同様、人手不足でも食事を安定的に提供できる体制をしっかりサポート。自社セントラルキッチンからクックチル食品をお届けする日替わりの献立サービス、事務作業の効率化を支えるオリジナルシステムなど、長年培ってきたノウハウにより厨房業務の改善を目指します。医療機関における導入実績も多数ございますので、この機会にぜひ一度ナリコマにご相談ください。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
セントラルキッチンに関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

DXリテラシーで給食の現場が変わる!具体的な取り組みやメリットを解説
みなさんは、「DXリテラシー」という言葉に聞き覚えがあるでしょうか? 近年では、業界を問わずDXリテラシーの重要性を意識する企業が増えてきています。今回の記事は、そんなDXリテラシーについて詳しくお届け。「そもそもDXって何?」という疑問を抱く方にもご理解いただけるよう、言葉のルーツや定義、その重要性もしっかりとお伝えします。給食現場における具体的な取り組みやDXリテラシー向上のメリットについても解説。ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考になさってください。
-

値上げは必須!介護給食の重要性と現状を詳しく解説
介護給食は、全国各地の特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで提供されている食事のこと。近年はさまざまなコストが上昇している状況にあり、介護給食の値上げも強く求められています。
本記事では、そんな介護の現場における給食をクローズアップ。給食の重要性についてお伝えするほか、調理にコストがかかる理由や厳しい現状、コスト削減方法などを解説します。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。