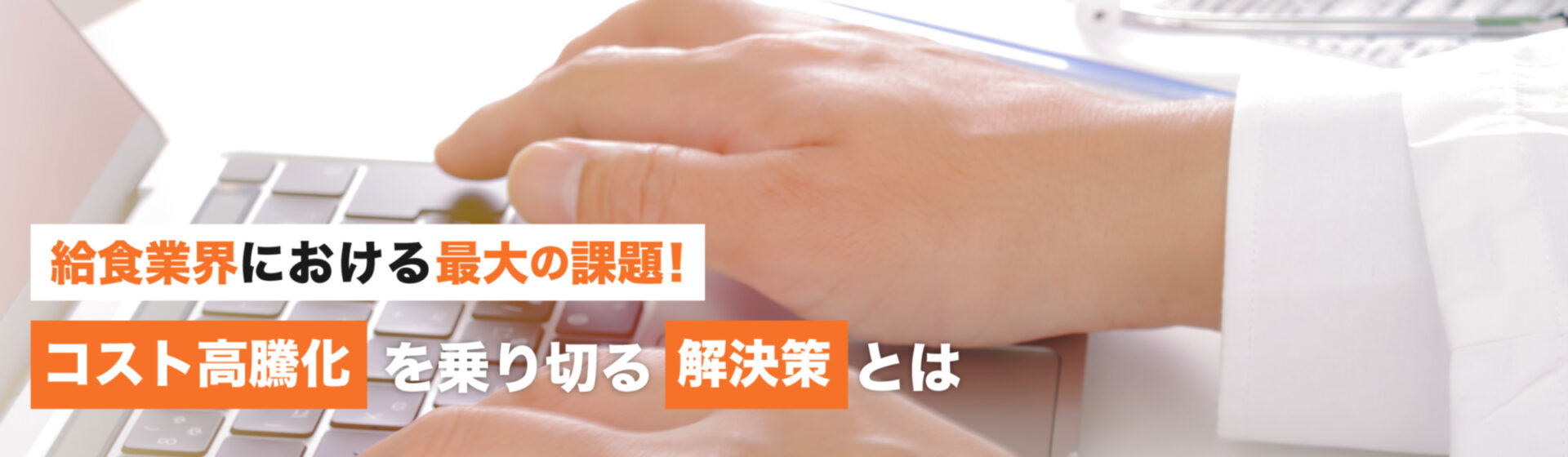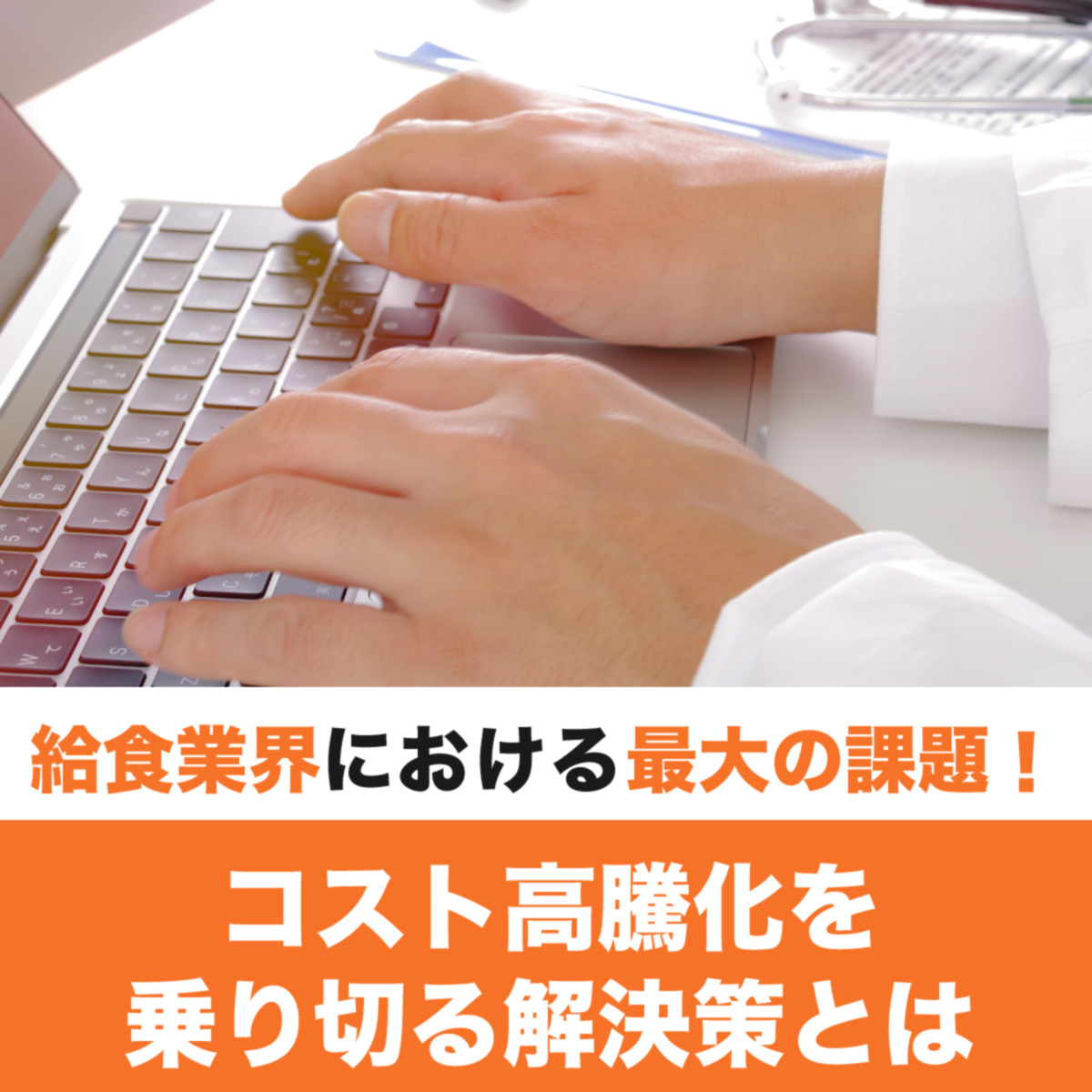近年は数多くの商品やサービスの値上げラッシュが続いており、多種多様な業界はもちろん、消費者にも大きな影響を及ぼしています。食品や日用品の買い出しで「高くなった」と実感している方は少なくないでしょう。値上げの主な理由は、生産費や人件費といった各種コストの高騰化。この件は、給食業界においても最大の課題として解決が求められています。
本記事では、今や身近なテーマともいえるコスト高騰化について解説。詳しい要因を見ながら、給食を必要としている施設の現状や具体的な解決策などをお伝えしていきます。ぜひ最後までお読みください。
目次
各種コストが高騰している要因

最初に述べたように、コスト高騰化は給食業界に限った課題ではありません。では、さまざまな業界に共通するコスト高騰化の要因を詳しくみてみましょう。
コスト高騰化の要因①新型コロナウイルスの流行
2019年12月、中国の武漢市で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。それに続いて、日本を含めた世界各国で感染者が激増。人々は接触を避けるために外出や外食を控え、企業ではリモートワークやオンライン会議が行われるようになりました。
ところが、リモートやオンラインに切り替えられない医療・福祉業界、物流業界、建設業界などは人手不足が進んでパンク状態に。次第に需要と供給のバランスが崩れていき、各種コストが高騰化しました。また、飲食業界は感染防止対策のほか、需要が高まったテイクアウトやデリバリーのためにコストが増加したといいます。もちろん、他の業界もコスト面で苦しめられた事例がたくさんあるはずです。
こうして社会全体が大きな影響を受けた後も、新型コロナウイルスの問題は長期化。2025年現在、感染者数は当初と比べて大幅に減りましたが、感染拡大によって変化した社会は以前と同じに戻ったわけではありません。どこの企業もコストがなかなか下げられないという意味では、いまだに新型コロナウイルスの影響が残っているといえるでしょう。
コスト高騰化の要因②世界情勢の変化
2022年2月、ロシアがウクライナに対して本格的な軍事侵攻を開始。世界各国がロシア産の天然ガスや原油、石炭などを輸入しなくなりました。新型コロナウイルスのケースと同様、需要と供給のバランスが崩れ、エネルギー価格は高騰化したのです。さらに追い打ちをかけるように、2023年10月にはパレスチナ問題が悪化。中東地域における各エネルギー資源の調達ルートが不安定になってしまいました。
こうした世界情勢は、エネルギー資源が少ない日本にとっても他人事ではありません。今のところウクライナ侵攻やパレスチナ問題の画期的な解決策はなく、エネルギー価格が下がる見込みは薄いといえそうです。
コスト高騰化の要因③急速に進む円安
ここ数年の米ドル/日本円相場を見ると、円安傾向にあります。特に、2022年から2024年にかけてはその傾向が顕著です。2020年には105円前後でしたが、2024年になると160円台に。円安が急速に進んだのは、アメリカと日本で金利差が拡大しているからだといわれています。
円安は輸入品の価格を左右し、前の項目で挙げたエネルギー資源はもちろん、食料品や電子部品、医薬品などにも影響を及ぼします。その結果、生産・製造、サービス等にかかるコストが全体的に上がってしまうのです。
コスト高騰化の要因④賃金の上昇
近年の日本では「働き方改革」というワードが生まれ、国や企業が労働環境改善のためにいろいろな策を講じています。厚生労働省「毎月勤労統計調査令和6年8月分」によると、前年同月比で実質賃金は0.6%減となっていますが、名目賃金はおおむね3.0%増という結果に。こうした賃金の上昇も、コスト高騰化につながっているといえるでしょう。
給食が必要な施設の現状

給食が必要な施設は、全国にどのくらいあるのでしょうか?厚生労働省「令和5年度衛生行政報告例の概況」によると、2019年は93,118施設でしたが、2023年には95,236施設まで増加。そのうち51,159施設は特定給食施設と呼ばれています。
「健康増進法第20条第1項」に規定された特定給食施設は、「特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設」を指します。その約60%を占めるのは、学校と児童福祉施設。続いて病院や老人福祉施設が約10%ずつ、介護老人施設が5%ほどとなっています。
2023年5月1日の「学校給食実施状況等調査」によれば、給食を提供している学校のほとんどが完全給食を採用。50%以上は調理・運搬・食器洗浄などを外部委託に頼っていることも明らかにされています。また、2024年5月の「病院給食実態調査」では、調査対象の123施設のうち約70%が全面・一部委託と外注で給食を提供していることがわかりました。
このほか、株式会社矢野経済研究所が行った国内給食市場規模の調査によると、新型コロナウイルスの影響で給食の需要が一時的に落ち込んだとのこと。しかし、その後は回復傾向にあり、令和5年の末端売上高ベースは前年度比103.9%の4兆7,915億円に達したと発表しています。
以上のようなデータからも推測できるように、もし給食の供給が止まれば、多くの人々の健康が損なわれてしまう恐れがあります。だからこそ、給食業界最大の課題といえるコスト高騰化は早急に解決し、安定した供給体制を整える必要があるのです。
コスト高騰化を乗り切る解決策
本項目では、給食業界が抱える大きな課題、コスト高騰化の解決策をまとめてお伝えします。

ポイント①水道光熱費節約のため、時短調理を取り入れる
水やガス、電気などを節約するには、調理の工数を減らすことが近道。レシピを見直せば、料理によっては冷凍のゆで野菜、下処理済みの肉や魚なども活用できるでしょう。ただし、最初に水道光熱費の詳細をきちんと把握することが重要です。
ポイント②発注・在庫管理を徹底し、食品ロスを減らす
原材料費が上がっているため、食品ロスの防止はコスト削減に効果大。必要な食材を厳選して発注するほか、在庫の管理を細かく行い、最後まで使い切るようにします。
ポイント③新しい食材や安価な食材に変更する
代替食品としてよく知られる大豆ミートなど、新しい食材を使うことでコスト削減になる場合があります。もともと使っている食材に味が似ている、かつ安価な食材に変更するのもおすすめです。
ポイント④一部委託や宅配弁当などを活用する
直営の場合ですが、すべての給食を自分たちで賄うよりも、一部を委託にしたり、宅配弁当で補ったりする方が安く済むかもしれません。業者によって価格やサービス内容に幅があるため、比較検討をじっくり行う必要があります。
ポイント⑤従業員の働き方や作業効率を見直す
実際の現場がどのように回っているのか、細かく見直すことで人件費が減らせる可能性もあります。従業員を無駄に配置している時間がないか、電子化・単純化できる事務作業がないかなど、全体を隅々までチェックすることが大切です。
コスト削減にはナリコマのニュークックチルがおすすめ

今回は、給食業界最大の課題とされるコスト高騰化についてお届けしました。ナリコマでは、医療施設や介護施設向けのサービスをご提案しています。厨房のコスト削減には、ニュークックチルがおすすめです。調理した料理を容器に盛り付け、そのまま専用機器でチルド保存。お食事の時間に合わせて再加熱するだけで提供でき、一時的に厨房を無人化することができます。
早朝の出勤や深夜の残業がないスケジュールを組むことができるため、従業員の負担減はもちろん、人件費の削減も実現しやすいシステムです。コスト高騰化の解決策をお探しの際には、ぜひご検討ください。
コストや人員配置の
シミュレーションをしませんか?
導入前から導入後まで常にお客さまに寄り添うナリコマだからこそ、厨房の視察をしたうえでの最適解をご提案。
食材費、人件費、消耗品費などのコストだけでなく、導入後の人員削減について個別でシミュレーションいたします。
スムーズな導入には早めのシミュレーションがカギとなります。
まずはお問い合わせください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
コストに関する記事一覧
-

ニュークックチルの運用を安定化!機器メンテナンスの重要性を解説
近年の日本は高齢化が急速に進んでおり、医療や介護福祉サービスの需要も増加傾向にあります。病院や特別養護老人ホームなどにおいて欠かせないものといえば、毎日の食事です。ニュークックチルは厨房業務の業務効率化や負担軽減に有効であることから、人手不足や負担増加に悩む医療・介護福祉業界でも注目を集めています。今回の記事は、ニュークックチルの運用に欠かせない厨房機器とメンテナンスについて解説。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
-

病院食の献立一週間!写真つきでわかりやすいクックチル献立!
残念ながら、患者さまの間で「病院食がまずい」という意見は少なくありません。今回は、病院食がなぜまずいと思われてしまうのか、という疑問と共に、クックチルの一週間の献立や、おいしさを追求したこだわりポイントをご紹介します。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。