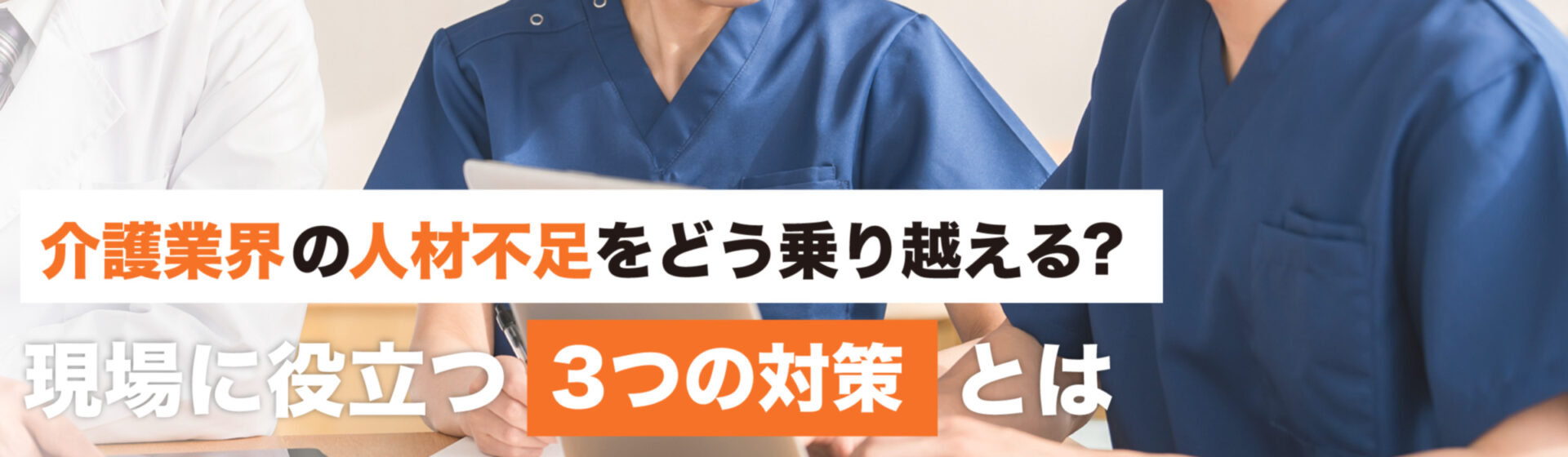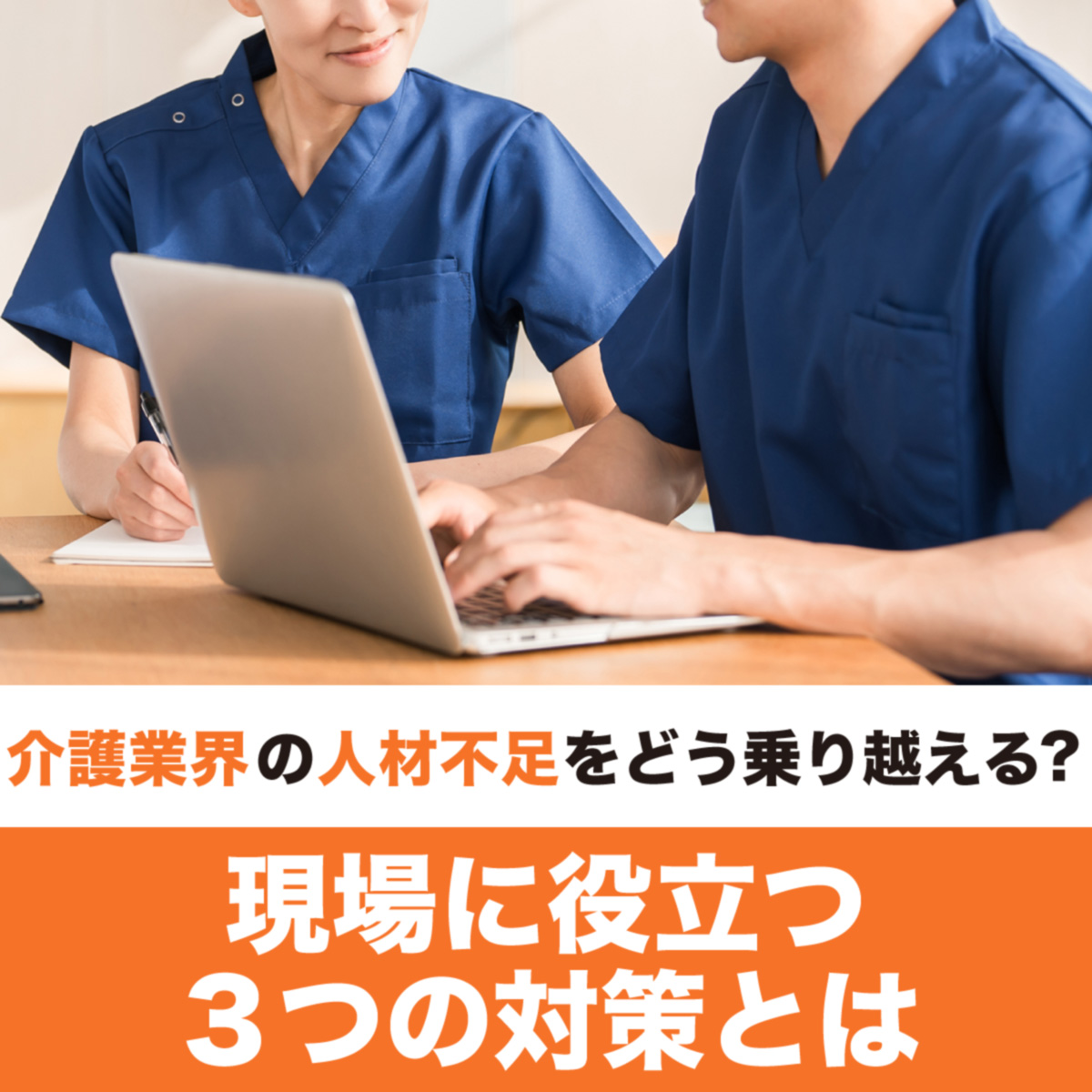介護の現場では、今も人手不足が大きな課題となっています。高齢者の増加とともに介護ニーズは拡大する一方で、必要な人材の確保が追いつかず、現場は常にギリギリの状態でまわっている…といった声も少なくありません。
厚生労働省の試算によると、2025年度末には約37万人もの介護人材が不足する見込みです。求人倍率が上がっても定着率は上がらず、離職につながる原因には、過酷な労働環境や賃金や働き方のアンバランスさの問題など、仕組みそのものに課題があるのが現実です。
こうした中、「環境を変えるだけでは人は集まらない」と感じている施設も増えて来ていますが、今できる現実的な対策には、一体どんなことがあるのでしょうか。
この記事では、介護現場で取り入れられ始めている3つの打開策「外国人採用」「スキマバイト」「ICT導入」について、事例や活用ポイントを交えながら、わかりやすくご紹介していきます。
目次
なぜ人が集まらない?介護業界の人材不足の現状
介護の現場では、長年にわたって人手不足が深刻化しており、今やその影響は施設の運営全体に及んでいます。

2025年問題がもたらす介護ニーズの急増
2025年、日本は「団塊の世代」がすべて後期高齢者(75歳以上)となる年を迎えます。これにより、高齢者人口が一気に増加し、介護サービスの需要も急激に高まると予測されています。厚生労働省の「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)について」によれば、2025年度末に必要とされる介護人材は約253万人です。
しかし、実際に確保できる人材は215万人程度と見込まれており、約38万人もの人手が不足する計算になります。この「介護の担い手不足」という問題は、介護の世界で最も深刻な悩みのひとつです。
求人は増えても定着しない現実
人材不足をどうにかしようと求人を出しても、応募数は伸び悩み、せっかく採用できてもすぐに辞めてしまうといった状況は、介護施設の現場では珍しくありません。その背景には、介護業務の身体的・精神的な負担の大きさがあります。多くの施設では人手が足りず、一人あたりの業務量が過剰になってしまいがち。さらに他業種に比べると給与水準が低いといった待遇面の課題も、離職の大きな要因になっています。現場を支えるスタッフの定着が難しくなれば、結果的に残った職員にさらに負担がのしかかり、悪循環が生まれてしまいます。
職場環境の改善だけでは限界がある
人材不足を根本から改善するべく、多くの施設では労働環境の見直しに取り組んでいます。夜勤回数を減らす、希望休の調整をしやすくしたり、ICTを導入して記録業務の負担を軽減したり、少しずつでも前に進もうとする動きが見られます。しかし根本的な人手不足が続いているため、職場環境の改善だけでは限界があるのです。人材の確保・定着に向けて、従来のやり方にとらわれず、新しい工夫を取り入れる余地がありそうです。
人材不足を解消へ導く3つの具体策

介護現場の人手不足を乗り越えるには、これまでとは異なる視点や取り組みが必要です。ここでは、今注目されている3つの対策をご紹介します。
1. 介護現場で広がる外国人採用
人材確保の新しい選択肢として注目されているのが、外国人の受け入れです。近年では、介護分野においても外国人材を積極的に採用する施設が増えており、国も介護分野で働く外国人を受け入れるための在留資格制度を整備しています。
代表的な制度には「特定技能」「技能実習」「EPA(経済連携協定)」があります。なかでも「特定技能」は一定の日本語力と介護知識がある人材が対象となり、長期的な就労が可能な点が特徴です。
メリット
・長期的に働ける人材として見込みが立てやすい
・採用の選択肢が広がり、人手不足の緩和につながる
デメリット
・言葉の壁や文化の違いによって、現場のコミュニケーションに時間がかかることも
・利用者や他の職員との相互理解を深める工夫が必要
受け入れにはサポート体制や、文化の違いへの理解が不可欠ですが、それ以上に「共に働く仲間」として育てていく姿勢が重要です。外国人材の採用は、現場に新しい風をもたらしてくれる大きな可能性を秘めています。
2. スキマバイト・短時間勤務人材の活用
「副業で少しだけ働きたい」「短時間でも収入がほしい」といった、新しい働き方として広がってきているスキマバイト。実は介護業界でも、副業や短時間勤務の人材を受け入れる動きが広がっていることをご存知ですか? 2023年には、スキマバイトアプリ「タイミー」が介護業界専門チームを発足し、介護分野への普及活動を本格化させています。タイミーでは、保有資格やこれまでの経験に合わせて、担当できる業務をマッチングし、無資格の方には「介護職員初任者研修」の機会も提供しています。
しかし、スキマバイトにただ来てもらうだけではうまくいきません。短時間の勤務でも即戦力として活躍してもらうためには、受け入れ側の準備が欠かせないのです。現場でスムーズに働いてもらうために、下記をチェックしておきましょう。
- 作業マニュアルを整備しているか
- 無資格者と有資格者の業務範囲が明確になっているか
- 誰が何を担当するかが共有されているか
こうした「受け入れる体制」が整っていれば、スキマバイトは大きな戦力になります。柔軟な働き方を選びたい人と、人手が欲しい現場、お互いのニーズをうまくつなげることで、介護現場の働き方にも新しい可能性が広がるでしょう。

3. ICT導入による業務の効率化
人手が足りないからといって、すべてを人の力だけで補おうとすると、現場の負担は増すばかり。そんな状況を打開する手段として注目されているのが、ICT(情報通信技術)の導入です。介護現場でICTを活用することで、これまで時間や労力をかけていた作業がぐっと効率化され、職員一人ひとりの負担が軽減されます。
国もこの動きを後押ししており、「介護テクノロジー導入支援事業」などの補助制度もあります。「ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ|厚生労働省」によると、国からの支援を受けたICT機器のうち最も多かったのは「介護ソフト」(67.5%)、次いで「タブレット端末」(53.6%)でした。また、導入効果としては、「文書作成の時間が短くなった」「情報共有がしやすくなった」「話し合いの時間が増えた」「入力済み情報が他の文書にも使えるようになった」などの声が寄せられています。
ICTは、人手を置き換えるのではなく、「支える仕組み」として機能します。負担の大きい介護の現場だからこそ、こうしたツールを上手に取り入れることで、働きやすさも、サービスの質も、同時に高めていくことができるのです。職員の負担を軽減することで、定着率が高まっていくことでしょう。
ナリコマのサービス・体制を活用しよう
人材不足に悩む介護現場では、人を増やすだけでなく、人手をかけずに回る仕組みを整えることも重要であることをお伝えしました。ナリコマでは、そんな現場の声に応えるサービスとサポート体制を用意しています。

人手不足の現場に「完全調理済み食品」という選択肢
厨房の人手不足に悩む施設が増えるなか、ナリコマの「クックチル」が注目されています。クックチルとは、加熱調理した食品を急速冷却し、チルド保存した状態で納品する方式。施設では再加熱するだけで提供できるため、調理や仕込みの負担を大幅に減らすことができます。ある特別養護老人ホームでは、クックチルの導入後、献立作成や発注業務にかかる時間が削減され、栄養ケア・マネジメントに集中できる体制が整いました。非常勤職員のシフトも柔軟に組めるようになり、有給取得率や求人応募も向上しています。
手をかけなくても、おいしい食事を届けるクックチルの仕組みは、今の時代に合った働き方を支える手段です。コストや導入の流れについても、ナリコマが丁寧にサポートします。
食事提供だけじゃない!発注や帳票も簡単に
食事を作ることだけが厨房業務ではありません。日々の発注作業や帳票の管理など、施設給食においては調理以外にも多くの業務が存在しています。このような間接業務の負担を減らすことも、人手不足の現場にとっては大きなポイントです。ナリコマでは、発注や帳票作成も簡単にできる独自のシステムを導入しています。食材によって業者が分かれることもなく、ナリコマ一本で手配が完了するため、確認や調整の手間が大きく減ります。
また、帳票作成もスムーズです。給食管理に必要な書類や監査対応に使う帳票類も、ナリコマのシステムから簡単に出力できるため、慣れていない職員でも扱いやすいのが特長です。ナリコマでは、調理や発注などの業務をデジタルの力で省力化し、厨房運営が無理なく続けられるよう支援しています。持続可能な仕組みづくりで、現場の負担を少しずつ軽くしていくことが、給食DXの目指すかたちなのです。
外国人介護技能実習生の受け入れもサポート
ナリコマでは、外国人介護技能実習生の受け入れもサポートしています。制度の説明や必要な手続きについては、担当者が同席しながら準備を進めるため、初めてでも安心です。クックチルは作業手順がわかりやすく、外国人や新人スタッフでもスムーズに取り組める仕組みです。検品システムも使いやすく、作業のミス防止にも役立ちます。多様な人材が働きやすい環境づくりが求められる今、こうした仕組みとサポート体制が人手不足の現場を支えます。
人材不足には複数の対策を組み合わせて立ち向かおう

介護の人手不足に正解はひとつではありません。現場に合った方法をいくつか組み合わせていくことが現実的な対応になります。外国人材の受け入れ、スキマバイトの活用、ICTの導入など、それぞれの施設に合った工夫を組み合わせることが、持続可能な運営につながっていくのです。
また、ナリコマのように「人の手を減らす」ことに向き合うサービスを活用することで、採用や定着に頼りすぎない仕組みづくりも可能です。人手不足の時代でも、安心しておいしい食事を届け続けられるよう、ナリコマは、「人手に頼らない仕組みづくり」で、介護現場の持続的な運営をこれからも支えていきます。
クックチル活用の
「直営支援型」は
ナリコマに相談を!
急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。
「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。
こちらもおすすめ
人材不足に関する記事一覧
-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで
介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。
高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。
研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?
介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。
コストに関する記事一覧
-

ニュークックチルの運用を安定化!機器メンテナンスの重要性を解説
近年の日本は高齢化が急速に進んでおり、医療や介護福祉サービスの需要も増加傾向にあります。病院や特別養護老人ホームなどにおいて欠かせないものといえば、毎日の食事です。ニュークックチルは厨房業務の業務効率化や負担軽減に有効であることから、人手不足や負担増加に悩む医療・介護福祉業界でも注目を集めています。今回の記事は、ニュークックチルの運用に欠かせない厨房機器とメンテナンスについて解説。ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。
-

育成就労制度とは?技能実習制度の制度変更による違いや特徴を解説
「育成就労制度」は、2024年に創設され3年以内に施行される制度です。この記事では、旧制度である「技能実習制度」の概要や課題を振り返りながら、制度変更によりどう変わるのかを、育成就労制度の特徴や受け入れ企業の実務のポイントも押さえながら解説します。
-

医療・介護施設の災害対策を!BCPセミナーで学ぶ備えの重要性
病院や介護施設は、災害や緊急事態の発生時、入院患者や施設利用者の安全と健康を守りながら、必要な医療・介護サービスを継続しなければなりません。そのためには、事業継続計画(BCP)の策定が不可欠です。BCP(Business Continuity Plan)とは、災害時において、業務を継続するための計画を指しています。病院・介護施設では特に「建物や設備の損壊」「インフラの停止」「人手不足」などのリスクを想定した備えが求められます。
しかし、対応するべき事柄が多すぎて、具体的にどのような対策を行ったらよいかお悩みの方もいることでしょう。そこで役立つのが、「BCP策定のポイントを学べるセミナー」です。今回は、病院・介護施設におけるBCPの重要性と、セミナーを活用して効果的に備える方法について詳しく解説します。