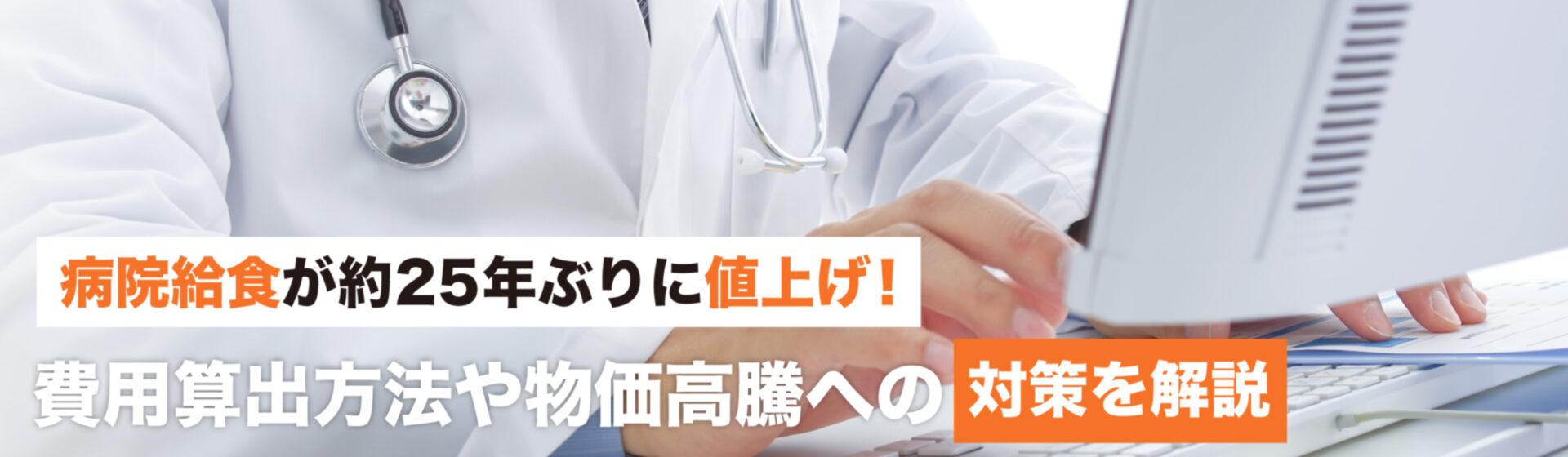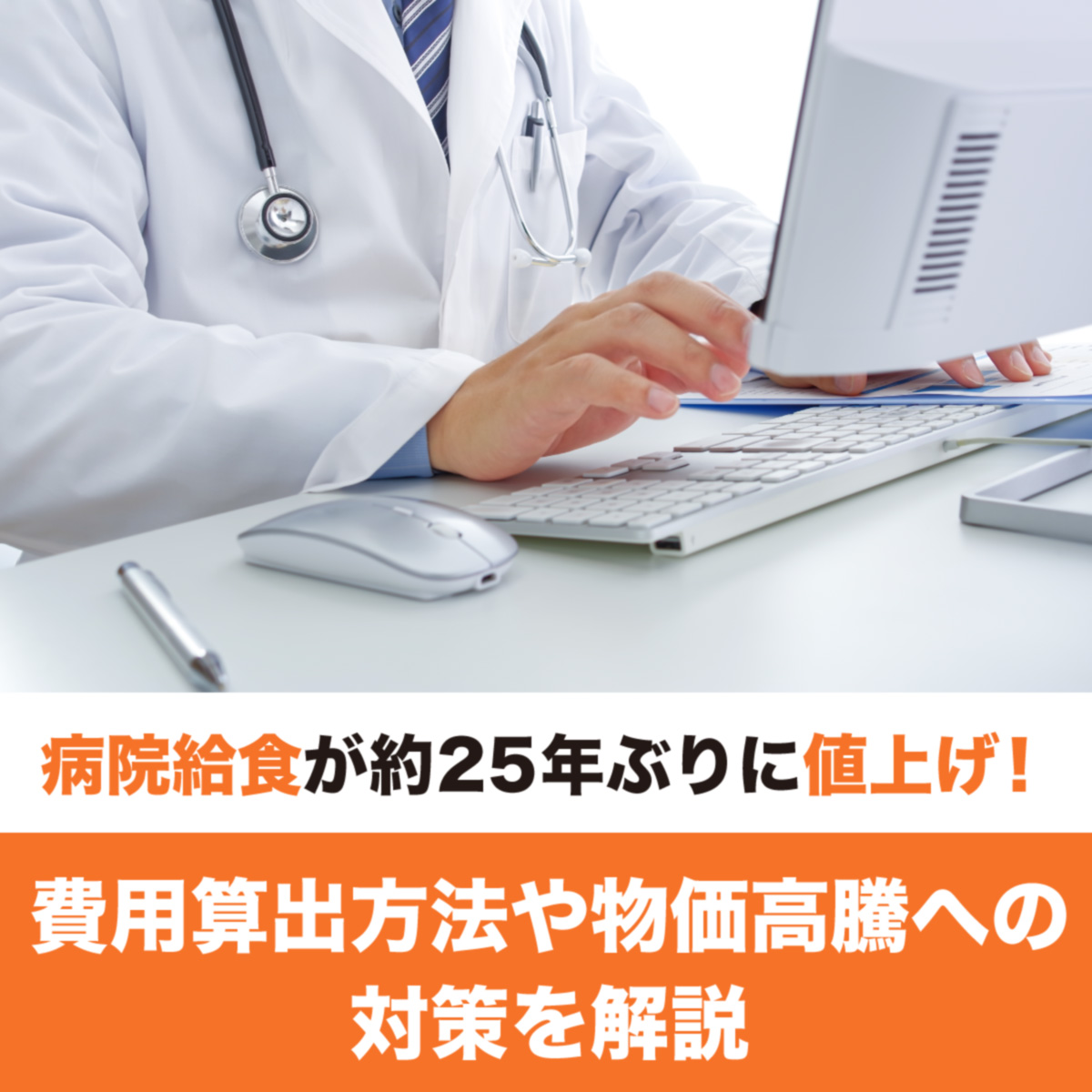病院給食は、その名の通り、主に入院患者さんに提供されています。価格は長らく据え置かれてきましたが、2024年6月1日に値上げが行われたことで注目を集めました。今回の記事は、この「病院給食の値上げ」をテーマにお届けします。
病院における給食の重要性や、値上げに至った背景などを詳しく解説。近年さまざまなところで影響を及ぼしている物価高騰への対策についてもまとめてみました。ぜひ最後までお読みください。
目次
病院給食の重要性

病院給食は、1948年に「医療法」が制定されたことから始まりました。それ以前は患者さんや家族が病室で自炊をしていたそうですが、「医療法」では、病院に対して給食施設と栄養士の設置を義務付けたといいます。
1950年に開始した「完全給食制度」では、栄養・衛生面の問題がなくなるように患者さんの食事を管理するため、病院給食は治療の一環として位置付けられました。こうした経緯をみると、病院給食は昭和の頃から重要性が高まっていたことがうかがえます。
現在の病院給食は、入院時食事療養という名目で扱われています。患者さんを診断した医師の指示に従い、管理栄養士が一人ひとりにあわせた栄養管理計画を作成。アレルギーや食の好みも考慮し、栄養指導なども実施します。もちろん、患者さんの状態が変われば、それに伴って栄養管理計画も変更。つまり、個別かつ細やかな対応が求められます。
以上のことからわかるように、病院給食は単なる食事ではなく、患者さんの治療や早期回復のために必要とされているのです。また、退院後の食生活における目安という役割もあります。学校や社員食堂などで提供される給食とは意味や目的が大きく異なっており、重要性もより高いといえるでしょう。
病院給食を値上げした背景
冒頭でお伝えしたように、2024年6月1日から病院給食が値上げされました。値上げは、約25年ぶりだといいます。消費税率はもともと3%でしたが、1998年以降に5%、8%、10%と引き上げられてきたにもかかわらず、病院給食の価格は変化なし。2023年には全日本民主医療機関連合会や公益社団法人日本メディカル給食協会などが、厚生労働省に対して病院給食の値上げに関する要望書を提出しました。
では、今回の値上げにはどういった背景があるのでしょうか? 最も注目すべき点は、近年急速に進んでいる物価高騰です。その要因はいくつかありますが、ここでは主なものをまとめてみました。

物価高騰の要因①感染症の流行や天候不順
2020年頃に爆発的な流行が始まった新型コロナウイルスは、人の流れを途絶えさせ、日本だけでなく世界各国で経済的な打撃を与えました。当時上昇していた原材料価格は、新型コロナウイルスの流行が落ち着いてきた現在も下がる気配はありません。
また、天候不順によって農作物が不作となるケースも多くみられました。不作になれば、価格が上昇したり、出荷が止まって代替品を頼らざるを得なくなったりします。
物価高騰の要因②ロシアのウクライナ侵攻など
2022年2月から現在まで続くロシアのウクライナ侵攻は、エネルギー価格を変動させました。ロシアは石油、天然ガスなどのエネルギー資源が豊富。ところが、ウクライナ侵攻によって各国への輸出が制限される事態になったのです。
このほか、2023年10月に中東のイスラエル・パレスチナ問題が深刻化したこともエネルギー価格に影響があります。中東はサウジアラビアをはじめとする石油生産国が集まっているため、周辺地域で軍事衝突が起こるだけでも輸送ルートが確保しにくくなってしまうのです。
物価高騰の要因③円安の継続
2022年以降のドル円相場は、急速に円安が進行中。三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が公表しているデータを見ると、顧客電信売相場(TTS)の年平均は2021年110.80 円→2022年132.43円→2023年141.56円→2024年152.58円と推移しており、円安が止まらない状況もはっきりと現れています。
主な原因はアメリカと日本の金利政策が異なること、日本経済が停滞していることなど。円安は、海外における価格競争で有利になるなどのメリットがありますが、その一方で輸入に頼る日用品や食品の価格は上がり、個人消費にまで多大な影響を及ぼします。
約25年ぶりとなった病院給食の値上げは、上記に挙げたような物価高騰の状況を考慮し、医療機関の負担を減らす目的があったようです。
病院給食の費用算出方法

病院給食の費用は、1994年から導入された「入院時食事療法費制度」に従って算定されています。制度発足当初は一日当たり1,900円と定められており、1997年には+20円の1,920円に値上げ。2006年に実施された診療報酬改定では、一日当たりから一食当たりの算定に変更されました。しかし、一食当たりの価格は640円だったため、一日当たりでは以前と変わらない1,920円のまま。その後2024年6月1日まで、病院給食の価格は据え置かれてきたのです。
病院給食の費用はまず、国が一食当たりの総額と自己負担額を決定。その二つの差額を入院時食事療養費として、医療保険から病院などに支給しています。現在の総額はこれまでの価格に+30円で、一食当たり670円です。一般所得者なら自己負担が490円で保険給付が180円、住民税非課税世帯なら自己負担が230円で保険給付が440円。住民税非課税に加え、所得が一定基準に満たない70歳以上なら自己負担は110円、保険給付が550円となります。
今回はこのような値上げが実現しましたが、物価高騰の影響はかなり大きく、病院給食の現状はまだまだ厳しいようです。続いて、実際の給食現場で行われている対策を見ていきましょう。
病院給食における物価高騰への対策
病院を含めたさまざまな給食現場では、物価高騰を乗り切るためにさまざまな対策をしているようです。株式会社エス・エム・エスが実施した「物価高騰による施設等の給食への影響調査(期間:2023年7月24日〜8月2日)」によると、調査対象施設の99.6%が食材の値上がりを実感しているとのこと。それに伴い、新たなメニューの開発や献立づくりも難航している施設が多いようです。以下に、物価高騰への具体的な対策をまとめてみました。
- 単価が高い食材を使わなくなった、もしくは使う回数が減った
- 肉や魚より安価な豆腐、大豆製品を使うようになった
- 揚げ物の回数を減らした
- ロスが出ないように発注数を調整している
- 安く仕入れるために業者を変更した
- 食材だけでなく、消耗品にも無駄がないか見直した
このように、現場ではコスト削減に向けた工夫が行われています。今のところ物価高騰の状況がすぐに改善される見込みはないため、病院給食に関しても引き続き何かしらの対策を続けていかなければならないでしょう。
病院給食のことならナリコマにおまかせください

値上げが実施されても、なお厳しい病院給食の現場。ナリコマでは、そんな現場のための献立サービスをご用意しております。慢性期・精神科病院には365日日替わりの「すこやか」、急性期・回復期病院には28日日替わりの「やすらぎ」がおすすめです。
現場の負担やコストを減らせるよう、どちらもクックチルを活用。セントラルキッチンから完全調理済み食品をお届けするので、再加熱や盛り付けなどの簡単な仕上げをするだけで提供できます。嚥下機能にあわせた食形態はもちろん、必要に応じて治療食にも展開可能。新しい形の病院給食をお探しの際は、ぜひナリコマにご相談ください。
コストや人員配置の
シミュレーションをしませんか?
導入前から導入後まで常にお客さまに寄り添うナリコマだからこそ、厨房の視察をしたうえでの最適解をご提案。
食材費、人件費、消耗品費などのコストだけでなく、導入後の人員削減について個別でシミュレーションいたします。
スムーズな導入には早めのシミュレーションがカギとなります。
まずはお問い合わせください。
こちらもおすすめ
クックチルに関する記事一覧
-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!
ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。
-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう
「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。
-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト
給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。
基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。
コストに関する記事一覧
-

クックチルで病院食の悩み解消!もう「物足りない」とは言わせない!
病院食というと、「おいしくない」「量が足りない」といったネガティブなイメージを持たれてしまいがち。もう「物足りない」なんて言わせない!病院食の満足度向上へ導くために、今私たちができることを考えましょう。
今回は、病院食が物足りないと言われてしまう理由や、入院患者さんに喜んでもらうためのポイント、病院食の満足度向上の強い味方となる、ナリコマのクックチルについて詳しくご紹介します。 -

2025年度から処遇改善加算一本化へ!変更点や賃上げに向けた対応方法を解説
介護職員処遇改善加算は、介護職員の賃金や環境の改善などを目的に取り入れられている制度です。利用には事業所が要件を満たす必要がありますが、介護職員の賃上げをはじめ、人手不足の課題解決にもメリットが期待できます。2025年度からは今までの環境が変わり、処遇改善加算一本化制度へと変更になりました。この記事では、主な変更点と共に、賃上げにつなげるための対応方法として取り組みのコツも解説します。
-

BCP策定はひな形の活用がおすすめ!介護施設で効率良く作成するポイント
BCPは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った言葉で、事業継続計画を意味しています。危機的な状況下でも重要な事業を中断させない、または早期復旧させるための計画です。介護施設では、BCPの策定が義務付けられており、感染症用と自然災害用の2つのBCPを策定する必要があります。これらのBCPを策定する際には、ひな形を活用するのも一つの方法です。
この記事では、BCPをスムーズに策定するのに役立つガイドラインやひな形の解説とあわせて、ひな形を使用したBCP策定のポイントを解説します。